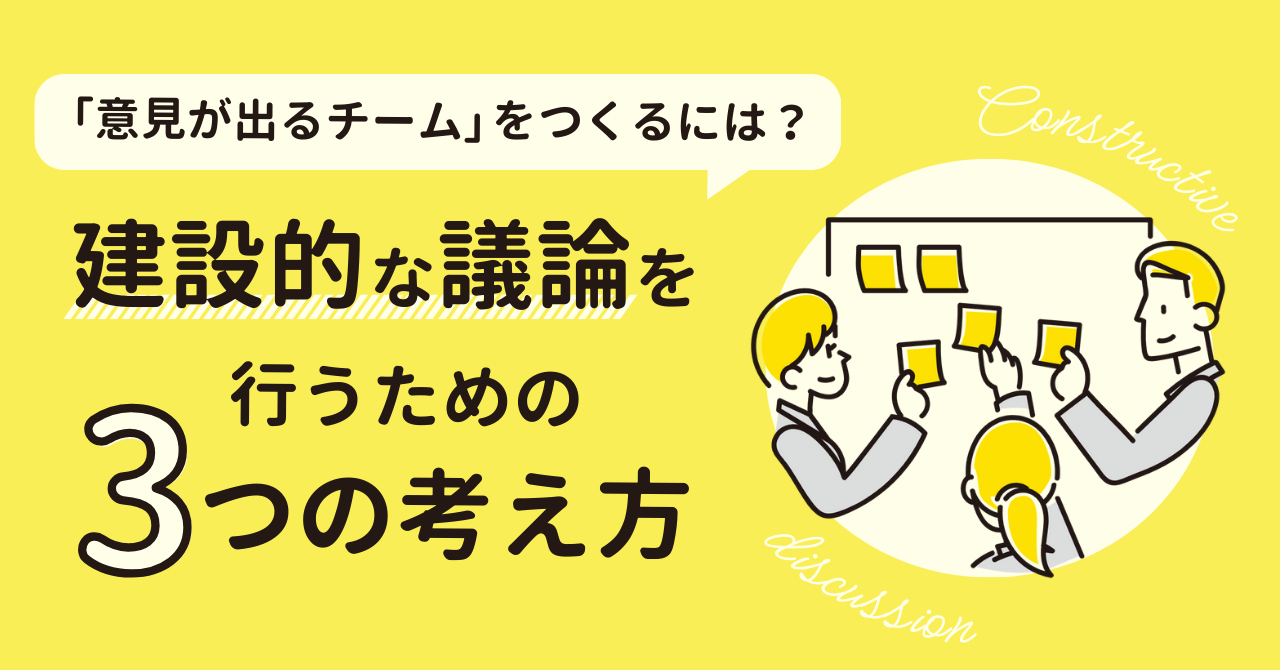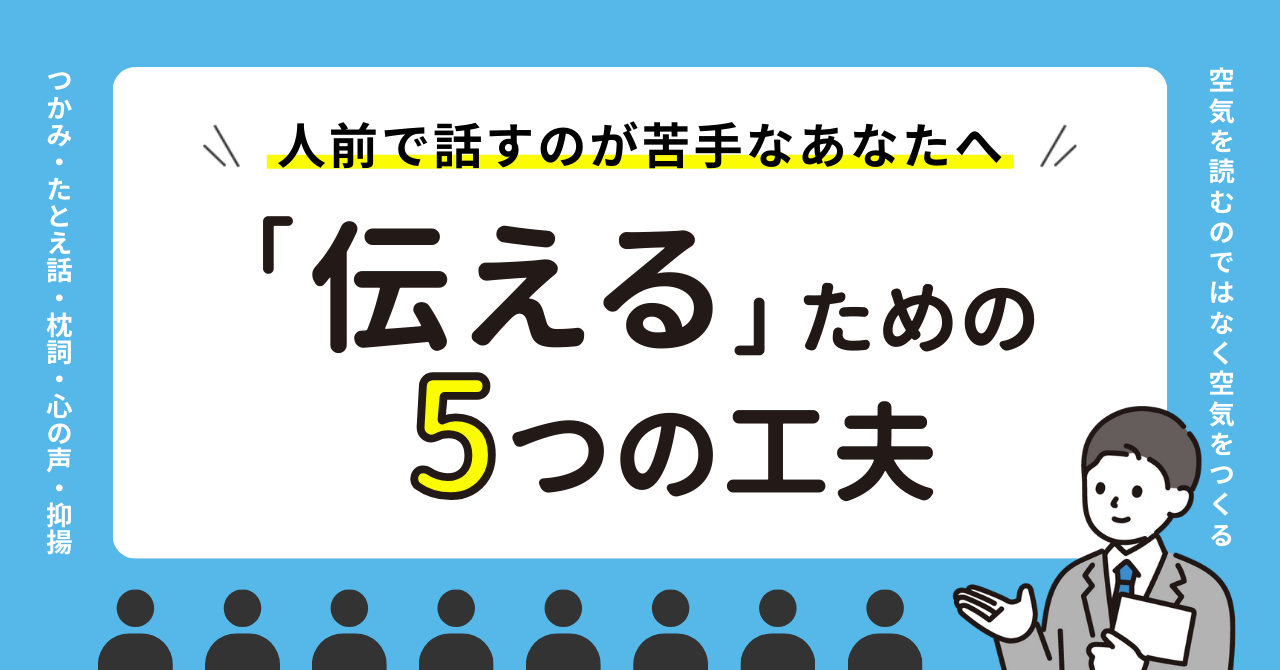数ある広告の中でも、特に運用型広告を扱う人のことを「広告運用者」と呼ぶことがあります。
しかし一口に広告運用者と言っても、事業会社で広告を運用している方や広告代理店に所属している方、フリーランスで活動している方など働き方も仕事内容もさまざまです。
そのため「広告運用者とは◯◯をしていて、こういう人です!」と1つに括って断言することはできませんが、業務範囲や求められるスキルなど、どの働き方でも共通するものを紹介できればと思います。
これから広告運用者を目指す方の参考になれば幸いです。


目次
広告運用者の働き方
まずは、広告運用者の働き方を「広告代理店」「事業会社」「フリーランス」の3つに分けて紹介します。
広告代理店
広告代理店に所属し、クライアント企業の広告運用を代行します。運用体制は主に「分業制」と「一気通貫制」の2つがあり、どちらの体制を取るかは各代理店によって異なります。
分業制の場合、営業窓口・運用担当・レポーティング担当……など1案件に対して複数人が関わっています。メリットとしては、一人一人の業務範囲が限られるため、自分の仕事に集中しやすくチームで多くのクライアントを担当できることです。
一方、一気通貫制は営業から運用まで1社に対して1名の担当者がすべて担っています。広告運用者が直接クライアントと話すことで課題発見に繋がったり、それをすぐに行動に移せるなどのメリットがあります。
ちなみにアナグラムは後者の一気通貫制を採用しています。
事業会社
事業会社に所属し、自社の広告運用を行います。このように広告代理店に委託せず、出稿~改善まで社内で完結するスタイルを「インハウス運用」と言います。
営業や広報、カスタマーサポートなど、さまざまな部署と連携しながら広告施策を行うこともあり、他の働き方に比べて広告運用者以外との関わりが多いのが特徴です。
また、マーケティングチームの規模によってはサイト改善やオウンドメディア運営など、広告以外のマーケティング施策と兼務する場合もあります。
1社のサービスに専念し、マーケティング施策は幅広く携わることができるのが事業会社で広告運用者として働くメリットだと言えるでしょう。
フリーランス
フリーランスの場合、クライアントによって広告運用の一部分だけを依頼されることもあれば、広告運用に加えてマーケティング全般のコンサルティングを担うこともあります。
その時のリソースや自分の望む働き方によって、業務範囲をある程度自由に選択できるのがフリーランスで広告運用者として働くメリットです。
しかしながら広告代理店や事業会社以上に多様な働き方があるため、特徴や業務範囲は一概に言えないというのが本当のところです。
広告運用者の仕事
ここからは、具体的に広告運用者がどんな仕事をしているのかを紹介していきます。
もちろん働き方や担当している企業・サービスによって業務範囲は変わるので、必ずしもこれがすべてというわけではありません。「広告運用を行う上でこんな業務が必要になる」という一例として見ていただければ幸いです。
今回はインハウス運用でもクライアントワークでも共通して必要となる業務を、下記の7つに分けて解説します。
②自社/顧客/競合分析
③広告戦略立案
④ターゲティング/クリエイティブ考案
⑤入稿
⑥分析/改善
⑦レポーティング/報告
①与件整理
まずは、広告を配信したい案件について与件整理をします。
与件整理とは「プロモーション対象である商材は何か?」「現状の課題は?」「予算は?」など、戦略を立てる上で必要となる前提条件を確認することです。
与件整理が十分にできていないと、たとえば以下のような問題が起きる場合があります。
このような聞き逃しや認識の齟齬を防ぐためにも、事前にヒアリングした内容をまとめた与件メモを作成し、関係者間で確認することが重要です。
具体的な与件メモの作り方については、下記記事をご参照ください。
②自社/顧客/競合分析
与件整理をしたら、次は自社・顧客・競合分析(いわゆる3C分析)です。
- 自社(Company):どんな強みをもっている?
- 顧客・市場(Customer):ユーザーが解決したいことは?
- 競合(Competittor):競合のポジション、戦略は?
これら3つの分析をしっかり行うことで、はじめて訴求すべき強みやどんな人に向けて広告を配信するべきかが見えてきます。逆に競合に比べて優位性が低い部分がわかれば、「この施策はやらない」と決めることもできます。
自社/競合分析はこのように1つのシートにまとめることで、強みや弱みが明確になるでしょう。

あまり分析せずに価格訴求ばかりしていたら、実は競合商品に比べて値段が高かったため全然ユーザーが反応してくれなかった……ということも起こりかねません。
予算も時間も有限なので、何をやるべきか・やらないべきかを明確にするためにも配信前にしっかり分析しましょう。
③広告戦略立案
①の与件や②の3C分析結果を踏まえて、広告戦略を考えます。
ここで言う広告戦略とは、具体的なクリエイティブや配信メニューを決める前の全体的な運用方針のことです。以下のような情報を簡潔にまとめることで、関係者全員に今後の方向性を示します。
- 配信目的に合わせて、どのようなターゲットにどの広告媒体を使ってアプローチするか
- 顧客のニーズや競合に対する優位性を踏まえて、何を訴求するか
- 広告予算や目標を踏まえた施策の優先度
例として、とあるファンデーションの広告戦略を考えてみます。
- メインターゲットである20~30代女性の新規獲得のために、InstagramやLINEで美容に興味があるユーザーに向けて広告を配信する。
- 顧客アンケートによると「天然由来の成分で安心して使える」「カバー力が高い」といった声が多い。値段は競合商品に比べると高めなので、価格訴求はせず、肌への優しさや期待できる効果を打ち出す。
- 広告予算が限られているため、はじめは年齢や興味関心軸を絞り込んで配信し、目標獲得単価を下回るようであれば徐々に配信ターゲットを拡大する。
書き方はどんな形でもかまいません。大切なのは具体的な配信メニューやクリエイティブを考える前に、関係者間で認識をすり合わせることです。
もしも広告戦略を決めず、いきなり「TikTok流行ってるんでTikTok広告やりましょう!」といった提案をしても上長やクライアントを納得させることは難しいでしょう。
戦略を決める際どのように媒体を選定すればよいのかは、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
広告戦略は具体的な施策提案に説得力をもたせるだけでなく、広告運用者自身が施策を進める時の旗印としても役に立ちます。
④ターゲティング/クリエイティブ考案
ここまで事前準備をして、ようやく実際に配信する際のターゲティングとクリエイティブを考えるステップです。
③の広告戦略立案では「誰に」「何を」訴求するか概要をざっくりと決めました。それを元に、媒体ごとにどの配信メニューを使ってどんなクリエイティブを用意するか「あとは入稿するだけ」というレベルまで落とし込みます。
ターゲティング
運用型広告は、テレビCMや雑誌広告などのマス広告と違い、オンラインの行動データに基づいて細やかなターゲティングができます。
どんな設定ができるかは媒体によって異なりますが、たとえば年齢・性別・地域といったデモグラフィック情報や、特定の分野に興味関心を持つ人、一度自社サイトに訪れた人……などさまざまなターゲティングが可能です。
また、検索広告であれば特定のキーワードで検索した人、SNS広告であれば「このアカウントをフォローしている人」など、その媒体ならではの配信メニューというのも存在します。
ターゲティングの種類も日々進化しているので、媒体情報のキャッチアップをかかさないことが大切です。
クリエイティブ
運用型広告におけるクリエイティブとは、「広告文」「画像」「動画」「キャッチコピー」「ボタンの文言」などユーザーが広告として目にするすべての素材のことを指します。
いきなりクリエイティブを作成するのは難しいですが、ここまで3C分析や広告戦略立案をしっかり行っていれば、どんなターゲットに向けてどんな強みを訴求するべきかが見えてくるはずです。
それでも、広告運用を始めたばかりだと「センスがないと難しいのでは?」と感じてしまう場合も少なくないですよね。
筆者が新人運用者の方におすすめしているのは、検索画面やSNSで実際に目にして良いと思った広告を保存し、なぜ良いと思ったのか言語化する癖をつけることです。
- 自分好みのデザインで目に止まった
- こんな商品があるんだ!という新たな発見
- 値段にお得感がある
- 今抱えている悩みを代弁するようなコピーが打ち出されていた
- 気になっていたサービスのお試しモニターを募集している
- 前に検討したけど買わなかった商品の広告が出てきた
これを繰り返すことで、今までなんとなく目にしていた広告を見る目が変わり、自身がクリエイティブを考える際もユーザー目線を取り入れて作成することができるようになると考えます。
余談ですが、筆者は事業会社でインハウス運用をしている時にこちらのアナグラムの広告を見て「たしかに今やってる運用型広告の仕事好きだなぁ」とコピーが刺さり、数年後に転職を決めました。
成果を出せる広告文の作り方は、こちらの記事でも紹介しています。
⑤入稿
広告を掲載するために各媒体の管理画面で入稿していきます。
事前に把握しておきたいのがアカウント構造です。媒体ごとに違いはありますが、ほとんどの運用型広告は「アカウント」を起点とした階層構造になっています。
たとえばGoogle広告やYahoo!広告の場合、上図のように「アカウント」「キャンペーン」「広告グループ」という3つの階層で成り立っています。
各媒体のアカウント構造に沿って入稿しますが、この時大事なのが媒体のルールや仕組みを把握した上で、成果を上げやすいアカウント構成は何か?を考え抜くことです。
現在は自動化機能も進化しており、各媒体は「データが分散すると機械学習が進みづらいため、なるべくシンプルなアカウント構成にしましょう」と推奨するようになりました。こうした媒体の仕組みや方針も理解した上で、管理・運用しやすいアカウント設計を目指します。
「このアカウント構成にすればOK」という必勝法があれば良いのですが、扱う商材や事業フェーズによって配信メニューや分析したい粒度なども異なるため、最適なアカウント構成はその都度変わります。
アカウント設計の考え方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
また、広告の掲載開始のタイミングはミスが発生しやすいので、配信前に下記の記事を確認しておくと安心です。
⑥分析/改善
掲載開始したらあとはひたすら分析と改善を繰り返すのですが、分析の基本は「鳥の目」「虫の目」「魚の目」で見ることです。
「虫の目」・・・複数の小さな視点から見る視点
「魚の目」・・・世の流れを掴むための視点
アカウントを局所的に見てしまっていると、微々たるインパクトしか与えないところばかりに注目してしまい、せっかく考えた施策が工数のわりに結果に結びつかなかった……なんてことにもなりかねません。
まずはアカウント全体を俯瞰的に見て、インパクトの大きい箇所から優先的に分析していくことが重要です。
分析の手順が決まったら、改善ポイントは因数分解で考えていきましょう。
たとえばコンバージョン(獲得数)が減ってしまった場合の改善策は、コンバージョン数がどのような要素から成り立っているのかを考えれば導き出せます。
因数分解した構造を把握していれば、すぐにボトルネックを見極め、改善策を投じられるでしょう。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
⑦レポーティング/報告
最後に、レポーティングと関係者への報告です。
せっかく成果を上げていても、運用状況を関係者にきちんと理解してもらえなければ「本当に任せていて大丈夫かな?」「この広告にこれだけの予算を投資すべきだろうか」と疑問を持たれてしまう恐れがあります。
報告の頻度や求められる情報は関係者によってさまざまですが、よくあるのがレポートの作成自体が目的となっているケースです。
あくまでレポートは「現状を可視化して関係者間で次のアクションを決めやすくする」という目的を果たすための手段です。
この目的が果たせて関係者間で合意が取れているのであれば、形式はメールでもパワーポイントでもなんでもかまいません。レポート作成にはあまり時間をかけすぎず、報告する内容と流れをある程度フォーマット化しておくのが良いでしょう。
また、報告の際にどんな順序で話すのかも重要です。
いきなり細かいクリエイティブの相談をしても、相手は「それが全体に対してどのくらい改善インパクトがあるのか」「優先度が高いのか」を判断することができません。
客観的事実→数値の変化→数値変化の要因・分析・対処と上流から話すことで、聞いている側も総合的な判断がしやすくなります。
報告レポートもこのような流れで作成すれば、仮にそのレポートが一人歩きしたとしても見た人に正しく理解してもらえるはずです。
広告運用者に求められるスキル
さて、ここまで読んでくださった方は広告を配信するまでの事前準備がいかに大切か、おわかりいただけたのではないでしょうか。
業務範囲に差はあれど、上記で挙げた仕事やその周辺業務をおこなう上で広告運用者にはさまざまなスキルが求められます。たとえば「大局観」「分析力」「継続力」「提案力」「検索力」「コピーライティング力」など……。
ここで挙げるとキリがないので、どんなスキルを磨くと良いのかをテーマにした記事を2つ紹介します。
これらのスキルを身につけようと思った場合、みなさんは何から始めますか?
関連する記事をネットで探したり、本を読んだり、セミナーに参加したり……共通しているのは「まず情報を集める」ということです。
アップデートの激しい運用型広告界隈において、情報収集は1回おこなったら終わりではなく、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。どうやって情報収集をおこなえば良いかわからないという方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
最後に
「広告運用者になりたい!」というと「AIで自動化が進んでるのに大丈夫?将来不安じゃない?」と周りから心配されることがあります。もしかしたら、この記事を読んでいるあなた自身がそういった不安を持っているかもしれません。
広告運用者の仕事が「クリエイティブを入稿すること」や「報告レポートを作ること」だけであればたしかに将来が不安ですが、これらは「売上を伸ばす」とか「予算内で費用対効果を最大化する」といった最終目的を達成するための手段に過ぎません。
広告運用という手段を用いながら、課題を発見してPDCAを回して最適解を求め続けるという経験は、どの仕事にも活きてくるはずです。
むしろ自動化で作業がラクになった分、市場分析やユーザー理解により時間を割けるようになったので広告運用者にとってはプラスだと考えます。
漠然とした不安を抱えている方は、よろしければこちらの記事も読んでみてくださいね。
個人的には、運用型広告は施策の効果が明確で、どれか1つを極める過程で知識が枝葉のように広がっていき、適切な人に適切なメッセージを届けられた時は「こんなサービスがあったんだ!ありがとう!」と感謝されることもある……とてもやりがいのある仕事だと日々感じています。