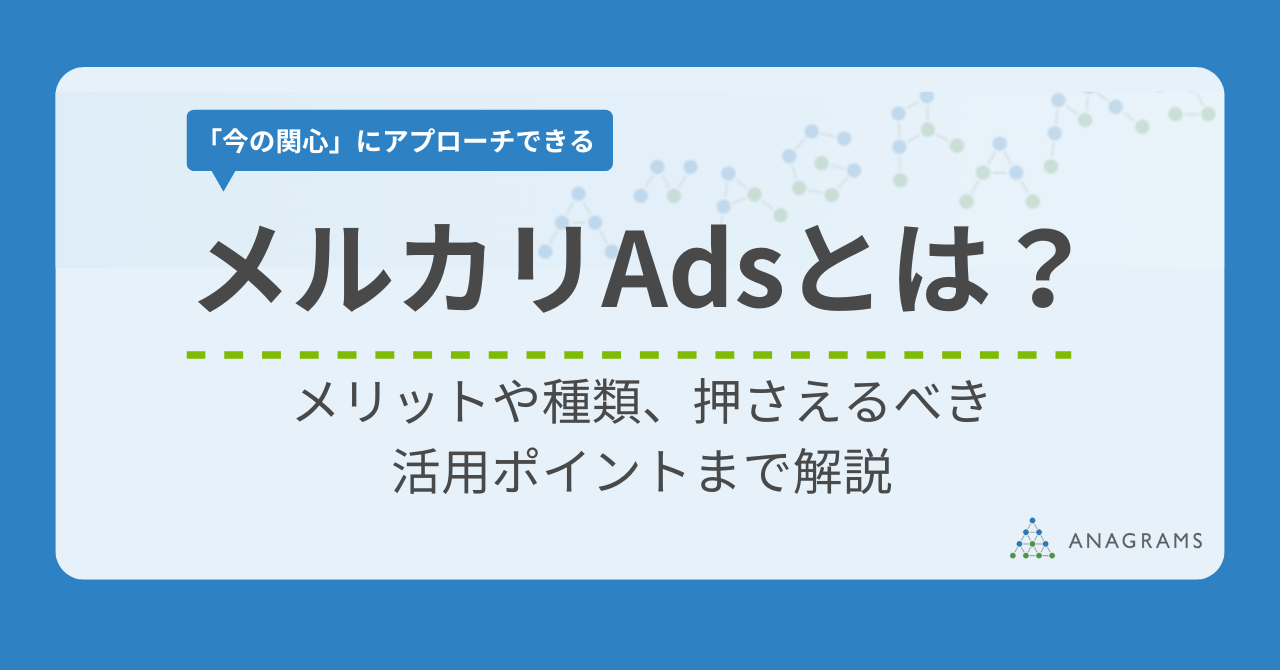- 広告代理店で働き始めた。
- 異動で自社の広告運用をすることになった。
- マーケティング部門で自社のWeb広告を担当することになった。
このような状況にあるみなさんは今、分からないことがたくさんあって混乱しているのではないでしょうか。
たとえば、GDN・YDAといった略語があります。GDNとはGoogle ディスプレイネットワークの略称、YDAとはYahoo! ディスプレイ広告の略称で、どちらもディスプレイ広告を配信するアドネットワークです。
同じディスプレイ広告だけど、GDNとYDAでは何がどう違うのか分かりづらいですよね。この記事ではGDNとYDAの特徴や違いをわかりやすく解説していきます。


ディスプレイ広告とは
まずは実際の掲載イメージを見てみましょう。
ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリ上の広告スペースに掲載される広告のことです。広告の見た目や掲載場所はフォーマットの種類によって様々ですが、画像が表示されるバナー広告は見たことがある人も多いのではないでしょうか。
検索広告と何が違うの?
運用型広告といえば検索広告をイメージする方も多いと思いますが、ディスプレイ広告と次のような違いがあります。
- 掲載されるタイミングが違う
- 目的やニーズが明確でないユーザーにアプローチできる
- 画像や動画を使った視覚的な訴求ができる

ユーザーが検索エンジンで検索をしたときに表示される検索連動型広告と、ユーザーが他のコンテンツを見ている時に表示されるディスプレイ広告とでは、商品の購入など最終的なコンバージョンまでに広告がもたらす効果が異なります。
検索広告(Search)は、すでに商品に興味を持っている・数ある商品からどれを買うか検討しているユーザーの購買(Action)と近くユーザーを後押しする効果が大きいですが、ディスプレイ広告では、商品を知らないユーザーやニーズがはっきりしていないユーザーにまずは商品を知ってもらったり(Attention)、興味(Interest )を持ってもらうことが期待できます(※)。
1つの商品の広告を出す場合でも、アプローチしたいユーザーの状況や特性に合わせて検索連動型広告とディスプレイ広告を使い分けられると効果的です。
※ただし、広告主のサイトに訪問済みのユーザーに向けて広告を配信するリマーケティング・リターゲティング広告は、何かを探しはじめた後のユーザーへの配信となるため、ユーザーの購買に非常に近いところに位置します。「ディスプレイ広告」と一括りにせずに、配信されるユーザーの状況は常に気にしておきたいですね。
ディスプレイ広告と検索広告との違いやディスプレイ広告の基礎の理解を深めたい方はこちらの記事も合わせてご確認ください。
GDNとYDAとは?
冒頭でもご説明した通り、GDNとYDAは、アドネットワークの代表的な2つです。
GDNとYDAは、Google、Yahoo!JAPANそれぞれのサービスおよびディスプレイネットワークに参加しているパートナーサイト内に表示されます。
配信先の違い
GDNとYDA、どちらのネットワークを使って広告を配信するかによって、利用するプラットフォームは「Google ディスプレイ ネットワーク(GDN)」と「Yahoo! ディスプレイ広告(YDA)」とに分かれます。
具体的な配信先の例として、GDNであればライブドアブログや食べログなどのパートナーサイトのほか、YouTubeやGmailなどGoogleが提供するサービスに広告を掲載することができます。
一方YDAは、日本の人口の約7割が利用しているLINEアプリ内の「LINE NEWS」トップ、タブ、記事内の掲載枠に配信ができることが大きな特徴の1つといえます。
もちろん、LINE以外にもクックパッドなどのパートナーサイト他、Yahoo!ニュースやYahoo!知恵袋などYahoo!JAPANが提供するサービスなどへの広告掲載が可能です。
ニュースサイトなど普段使っているサイトによってもユーザー層が異なりますよね。また、広告クリエイティブや商材、サービスによっても配信先との相性もあります。それぞれのネットワークでどこに広告が配信されるか、まずは代表的なものを掴んでおきましょう。
広告のフォーマットの違い
GDN、YDAで掲載可能な広告フォーマットは、いずれもテキスト、画像、動画と利用できる素材の種類こそ同じですが、画像のサイズやテキストの文字数など仕様には違いがあります。
参考:
たとえばGDNの広告素材をYDAにも用いようと思ったら文字数が違うため調整しなおさなければならないなど、2度手間になりやすいところですので、広告作成前にチェックしておくのがオススメです。
ターゲティング方法の違い
ディスプレイ広告のターゲティングには大きく次の2種類があります。
- ユーザーの特徴でターゲティングする方法
- 配信先のコンテンツの特徴でターゲティングする方法
YDA・GDNどちらも、ユーザーと配信先のコンテンツそれぞれをターゲティングすることができます。ですがプラットフォームごとにターゲティングの手法は異なり、それぞれ以下のような種類があります。
ユーザーを軸にターゲティングする
年齢セグメントはGDNとYDAとで年齢の区切りが異なるので注意が必要です。GDNは24歳以上は10歳単位で区分できるのに対し、YDAは20歳以上は5歳単位で区分が可能で、GDNよりも細かい粒度で年齢設定が可能です。
また、GDNは世帯年収のみ設定が可能なのに対し、YDAは個人年収や世帯資産など細かい粒度での設定が可能です。加えて、仕事やライフイベントなどのターゲティング設定は不動産やウエディングなど検討のタイミングでのアプローチが重要になる商材などに活用してみても良さそうですね。
(注1)Google広告にて、2023年5月1日以降類似セグメントの生成ができなくなっております。また、2023年8月1日にはすべての広告グループとキャンペーンから完全に類似セグメントが利用できなくなる予定です。
参照:オーディエンス ターゲティングに関する変更: Google 広告の類似ユーザー機能(別称「類似セグメント」)がサポートされなくなります
(注2)2023年4月19日(水)に顧客データを利用した「オーディエンスリスト(カスタム)」は、新しいリスト種別の「オーディエンスリスト(Yahoo! Audience Discovery)」、または「オーディエンスリスト(顧客データ)」に自動移行が実施されました。
実際の検索履歴を用いたYDAのサーチキーワードターゲティングがヤフー社によって提供されているキーワードリストを選択する方法に対し、GDNは任意のキーワード指定やURLをカスタムインテントを用いて自由に設定が可能です。なお、GDNのカスタムセグメントで指定した語句と検索履歴を利用できるのはGoogle サービスで広告配信をしているキャンペーンのみなので覚えておきましょう。
このように、同様のターゲティング手法でも媒体によって設定方法が異なるため、商材やサービスに合わせてターゲティングを考えることが重要です。
また、媒体の定義したカテゴリだけではなく、広告主の保有する顧客データを利用したGDNのカスタマーマッチ、YDAのオーディエンスリストターゲティングは強力なターゲティングの1つといえます。
掲載面のコンテンツを軸にターゲティングする
両者に大きな違いはないものの、設定方法が少し異なります。
GDNのコンテンツターゲティングは、ページ、キーワード、ターゲットにしたいテーマに関するウェブページ、アプリ、動画などが設定できます。
一方、YDAのコンテンツキーワードターゲティングは、入力したキーワードがYahoo!広告の管理画面に備わっている場合のみトピックの選択が可能になります。
その点、GDNのほうがキーワードの自由度高く設定ができますが、両媒体ともに商材やサービスを加味し、誰に何を売りたいのか?を考え設定に反映することが重要です。
YDAとGDN、どちらを使えばいい?
結論からいえば、予算が許す限り両方の媒体に出稿することをオススメします。
媒体によって配信されるサイトが異なるため、できるかぎり多くのユーザーに商品やサービスを知ってもらうためには、YDA・GDNともに押さえておきたいところです。
ですが、予算の都合やリソースの問題もありますよね。まずはターゲットとなるユーザーが普段どんなサイトを訪れていそうかを考えてみるのがおすすめです。それらのサイトへ広告を配信できるのはどの媒体か、また、それらのユーザーへアプローチするターゲティング方法が用意されているのかどうかから出稿プランを検討してみてはどうでしょうか。
最後に
自分がインターネットを利用する時間のうち、検索をしている時間はどれくらいでしょうか?よほどの検索マニアで無い限り、きっと1割の時間にもみたないのではないかと思います。
ディスプレイ広告の強みは、検索している以外にインターネット利用の多くを占める、コンテンツを閲覧している時間に見込みユーザーと接触できることです。
ディスプレイ広告の仕組みやGDN・YDAの違いを押さえたうえで、適切なユーザーによりよい広告で訴求できるよう、広告フォーマットの細かな規定やターゲティングの設定方法などに学びを進めて、ディスプレイ広告を作成・運用できるようになっていきましょう!