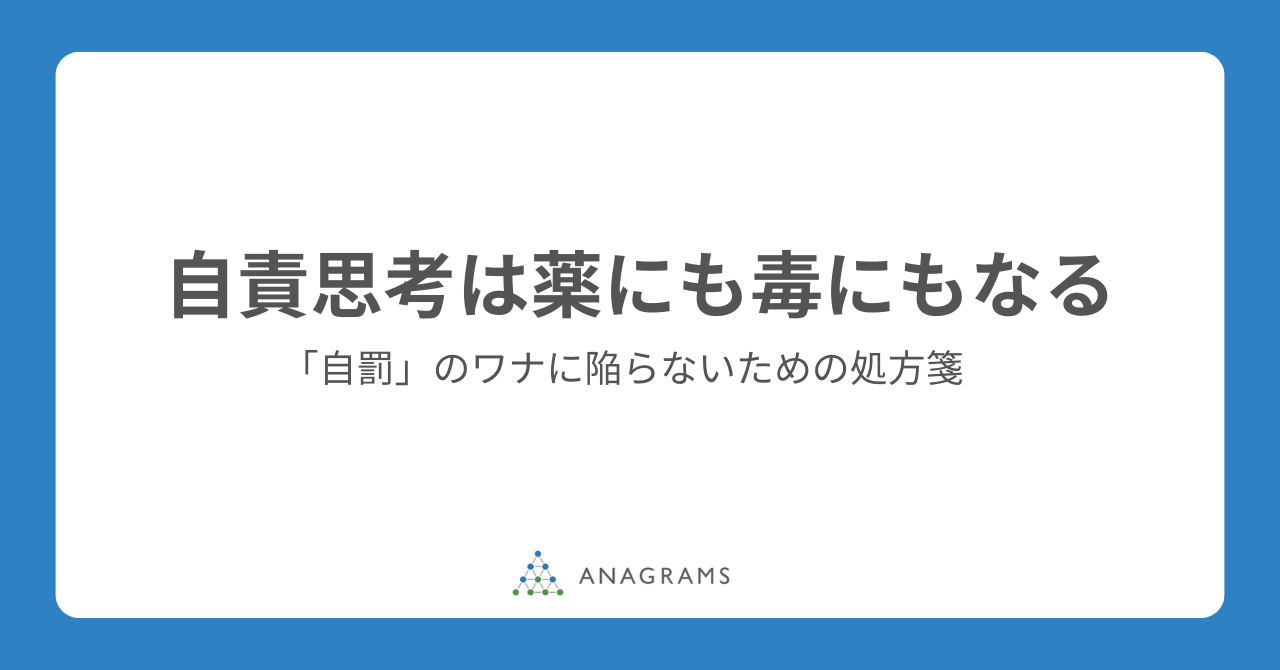あなたは建物を建てたことがありますか?
筆者は興味こそあれど、経験はありません。ありませんが、綿密な思考プロセスというのは、建物を建てることとどこか似ているのではないかと想像します。
細部まで神経が通った誰かの意匠に触れると、奥行きのある思考を感じずにいられないからです。
設計図を元に基礎を固め、骨組みや外壁を設けて内装を施す。そうして築かれた堅牢かつ機能的で美しい建築物は長きにわたって形に残り、人々を魅了し続けます。これは人の思考が具現化したもの全般に言えるかもしれません。
では優れた思考やひらめきは、限られた人だけのものでしょうか。
偶然の産物ではなく着実なプロセスを経る「建築」になぞらえるなら、答えはきっとNOです。もちろん鍛錬は必要ですが、逆に言えば後天的に開拓できるスキルのはずです。
思考力はすべての基盤です。目的を達成するための大きな武器にも、自分と社会を繋ぐ頑丈な橋にもなります。そのために着想をいかに充実させ、積み上げ、発展させるか。この記事ではプロセスを3段階に分け、思考を組み立てる方法を紹介します。


設計図があれば、思考は深められる
深い思考に欠かせないもの、それはプランを持ってゴールに到達するための”設計図”です。設計図があれば方向性がはっきりするだけでなく、途中で立ち返りながら軌道修正もしやすくなります。
とりかかるのが億劫に思えたことも、紙に書き出して眺めてみると意外に新たな糸口が見えた経験はありませんか?要素を一度洗い出すようにアウトプットし、視覚から改めてインプットし直すと、ただ考えるよりもずっと思考が促され深まりやすいですよね。
- 思考によって成し遂げたいゴールは何か?
- そのゴールに到達するためには、いつどんな手順を踏むべきか?
- それぞれのプロセスは、いかに嚙み合わせるか?
まずは目指す場所を明確にすると推進力が生まれ、必要なものも自ずと見えてきます。
規模は違いますが、これは事業の旗を立てるときにも同様です。
例えばアナグラムは、「分業を是とする資本主義のアンチテーゼとして、広告業界に一気通貫で働く選択肢を提示すること」を掲げて出発しています。軸が定まっていれば、ビジネスモデルや組織構成などで肉付けすることによって説得力が増していくのです。
解像度の高い設計図は実行の助けになり、完成度の高いアウトプットにつながりやすくなります。この記事では思考のプロセスを「土台」「骨組み」「内装」として3つの工程に分けて組み立てていきます。
設計図に必要なのはこれらの要素です。
- 土台: 知識の基盤を固め、応用に繋げる
- 目的を明確にし(抽象化)
- 位置づけを整理し(構造化)
- 輪郭を定義する(言語化)
- 骨組み: ロジックや理論で補強する
- 目的から導く戦略に(演繹法)
- 経験やトレンドを反映させ(帰納法)補完し合う
- 内装: 創造性や想像力で充実させる
- 新しいアイデアを生み出し(類推)
- 独自性を引き出す(相対化)

これらの工程は必ずしも一方通行ではありません。何度も行き来することで思考の密度はさらに高まり、ゴールも近づきます。あなたの”設計図”が達成したいゴールは何ですか?
知識の深い理解で築く「土台」
思考の土台や基礎を築くために重要なのは、整頓された知識です。何かを深く理解すれば応用も効きますよね。
土台が揺らいでしまうと建物は立ちません。認識に穴や欠けがないかはこの工程で複数の角度から確認する必要があります。ここで役立つのは「抽象化」「構造化」「言語化」です。
- 抽象化:目に見える具体的な事象から本質を解釈する技術
- 構造化:要素を整理して、シンプルに理解する技術
- 言語化:ものごとを適切に定義して人に伝える技術
それぞれは互いに影響しあっていますが、ここでは便宜を図るため順に見ていきましょう。
抽象化
まずは抽象化。対象をより上位の概念で捉えて、本質を見極める方法です。何かを適切に定義したいときにも役立ちます。信号機など、何らかのアイコンやシンボルを用いて記号化することも抽象化の一種と言えますね。
例えばあなたが最近買ったもの、それを選んだ理由も一緒に思い出してみてください。
食べ物かもしれないし、洋服や家具かもしれません。他のものよりも美味しそうだったから、好みだったから、など理由もさまざまでしょう。ですが買ったものや理由が何であっても、突き詰めると「もっと生活を良くしたい」という同じ想いに行き着くのではないでしょうか?
わたしたちの日常の行動や選択は、抽象化すると、その大半が「よりよく生きる」ためのものと捉えられるのです。
抽象化はもちろん仕事においても役立ちます。ビジョンが定まり、やるべきことの解像度が上がるからです。
例えばアナグラムではアイデンティティを「クライアントの最も身近な相談役になる」としています。だからこそ、わたしたちの仕事は運用型広告に限らず、マーケティング全般ひいては経営のご支援だと考えているのです。
どんな仕事であっても、突き詰めるとその目的は誰かの役に立つことと言えますよね。結果として売上が上がれば利益も増え、新たな事業や雇用が生まれ、増えた税金は社会のために役立てられます。ビジネスとは、抽象化すると「社会に貢献すること」なのです。
目に見える具体的な事象から、核心を突いて多くを学び取るための技術が抽象化です。
構造化
そうして手に入れた知識は、整理するとよりシンプルに理解できます。次の「構造化」はそのための方法です。
要素を洗い出した上で分類すれば、それぞれの重要度に応じた順序立てや重みづけもしやすくなります。頭の中で散らかった情報を、対応する箱に片付けて整頓するイメージでしょうか。
この記事で用いている「土台」「骨組み」「内装」の分類も、実は思考するプロセスを構造化したことで発想されています。記事の構成を考えることもまさに構造化ですね。
複雑に思える問題は、それぞれの要素が大きさも濃度もバラバラな状態だから絡み合って見えます。必要に応じて要素を細かく分解したり、反対に統合したり。情報の粒度を揃えれば状況は理解しやすくなり、解決にも近づきます。
アナグラムでは事業の枠組みに三方良しを反映しているものが多く、これも構造化の為せる技です。クライアント・自社・社会を可能な限り同じウエイトで大切にしつつ、その源を担う社員がいきいきと成果を上げられるように設計しています。
キーワードになるのは逆ピラミッド型での意思決定や挙手性。ピラミッド型のチームを構成しながらも、決定権は現場のメンバーが持っており、上長はそれを阻害しません。担当案件や配属を決めるのも挙手がベースです。
もちろん上長へ相談して判断する局面もありますが、担当者は第一線でクライアントと相対しますから、その分的確な判断につながる情報を誰よりも持ち合わせていると考えています。
そのため倫理と論理に反するものでない限りは、自分の意思でスピーディーに実行できるよう、このような仕組みにしているのです。
構造化によって物事や状況は整理され、問題を解決するヒントも見つけやすくなります。
言語化
最後に土台を固めるのが言語化です。丈夫な物体ほどしっかりとした形を持っていますよね。言語化はちょうど型抜きのように、頭の中の思考や感情にくっきりと輪郭を与え、他者にも渡せる状態にする作業です。
漠然とした不安が襲ってきたとき、その感情に言葉で形を与えてみたらいくらか落ち着いたことはないでしょうか?もやもやとした感情も正体がわかれば対処したり伝達したりできるようになります。
感情に限らず何かを発信したい意思があるなら、体外へのアウトプット、つまり言語化は欠かせません。
一方で、言語化は頭の中で無限に広がる思考の枠を規定してしまいます。言葉にできない感動や溢れて止まらないアイデアは、言語化した途端、陳腐になったり躍動を止めてしまったりするものです。
自分の手で可能性を殺さないためにも、言語化の限界は知っておく必要がありますし、同時に努めて適切な言葉を選ぶことには大いに意味があるのです。
ビジネスにおいての言語化は、ブランディングや広告はもちろん、採用の文脈でもその重要性が際立ちます。特に事業の初期ほどそれは顕著です。なぜなら自社を定義する言葉が人を呼び、そこに集まった人々が未来の組織を形成するからです。当然影響はのちのちに大きく跳ね返ってきます。
言語化は思考の「土台」を築く要でありながら、フィードバックを得るための「扉」でもあるのです。
競合の捉え方は、組織の在り方を定義するようなもの。アナグラムがあえて競合を挙げるならそれは概念としての「ファンド」だと捉えています。
わたしたちは広告の代理運用やコンサルティングなどの機能を持っていますが、目指すことは常に一つ。「預かったお金をより大きくしてクライアントにお返しすること」です。
これに共感する人が集まり、組織は100名を超えて拡大してきました。
言語化は思考や発想に形をあたえ、人に伝播させるための第一歩になるのです。
ロジックで構築する「骨組み」
整頓された知識で土台を築いたら、次はその上の骨組みです。ロジックで補強しながら思考を積み上げていきます。ここでは「演繹法」と「帰納法」によって双方向から補完し合うようにアプローチしましょう。どちらも元々は哲学の用語ですが、知らずとも日常の思考によく登場しているはずです。
- 演繹法:与えられた一般的な前提を具体的なケースに適用する推論方法
- 帰納法:観察した事例から法則性を見出し一般化する推論方法
物事を習得したり発展させたりするプロセスを3段階で表した概念に「守・破・離」がありますよね。どれも欠かせないステップですから、演繹法はそのうち「守」に、帰納法は「破」にそれぞれ相当すると言われると、2つとも大切だとイメージしやすいのではないでしょうか。これらは段階や状況に応じて使い分け、ときに循環させるとより効果を発揮します。
演繹法
「すべての人間は死ぬ。ソクラテスは人間である。ゆえにソクラテスは死ぬ」と言ってしまえば当たり前のこの三段論法ですが、これは演繹法の一例です。
演繹法とは、普遍的な真理から論理的に結論を導く推論の方法です。前提が事実(真)である限り、そこから推定される結論もまた真となります。ある程度間違いないとされるものを指針にしつつ経験や知識を増やしていくスタンスを取る、とも表現できるかもしれません。

ではここで少し想像してみてください。未知のことに取り掛かるとき、あなたは何から始めますか?本を読む、人に聞く、まずやってみるなど方法はいくつかありそうですが、少なからず「基本や全体像は抑えておきたい」と考えるのではないでしょうか。
つまりは方法が何であれ、集めた情報や教訓を参考にまずは基本をインプットし、それを踏襲しながら個々のケースに対応するのです。これは守破離でいう「守」ですが、この体得法には、演繹法のエッセンスが多分に反映されているといえますよね。
あるいは何かを極めた人が全く異なる(と傍目には思える)分野で頭角を現すストーリー、これも演繹法で説明できる部分があります。オリンピックで活躍した選手がビジネスにおいても成功を収めるケースは、一度体得した「ゴールへ着実に到達する型」を、演繹法によって他のものごとに活かした結果ではないでしょうか。
演繹法は論理的な思考プロセスですから、もちろん問題解決や戦略の策定にも役立ちます。
例えばアナグラムでは担当者数を3-5社にあえて制限していますが、これは時間と脳のリソースを1社1社に存分に投下するためです。これを演繹法で説明するとこのようになります。
- 前提:量と質を一度に両立するのは難しい
- 結論:担当社数が多いと1社1社に向き合う難易度は上がる
- 対策:成果が出しやすいよう担当社数を絞る
ある前提から演繹法によって結論を得たら、その対策を仕組みや戦略に落とし込めばよいのです。
いうまでもなく、演繹法においては何を前提とするかが大きな鍵を握ります。ですが思考の主体はいつでも自分であり、身を置いた文化圏や選んできた価値観によって形成されたバイアスから完全に自由になることはできません。となると偏りに気が付くのも簡単ではありませんよね。
そこでその偏りを反対方向から補えるアプローチがあります。それが帰納法です。
帰納法
何かを習得する過程に慣れてきたころ、しばしば出くわすのが、原則にあてはまらない「例外」です。想定していない分戸惑うかもしれませんが、それは認識をアップデートし、より実態に即した本質を抽出するチャンスです。帰納法とはまさにこんな試みを指します。
個別の事例を観察・検証し、より信頼できる原則や法則を導き出す。これは前提を疑い、超えようとする守破離の「破」と同じ姿勢を示していますよね。手元のデータや事実が限定的な場合も、何かを発見したり仮説の設定に役立てたりできるのです。
一方で、取り出した仮説や法則の正しさは、どんなデータや事例を選び、どんな解釈を加えるかによって大きく変わってきます。演繹法は前提が真であれば結論も真ですが、帰納法によって得た法則はあくまで一つの解釈に過ぎず、次に観測されるケースにも必ず当てはまるとは断定できません。
例を挙げてみましょう。
- 観測された事象:健康美を誇る人々が「特に何もしていない」と語っていた
- 解釈の例①:遺伝や体質だったり、神経質になりすぎない健やかなメンタルだったりが健康美の秘訣なのではないか
- 解釈の例②:もはや当たり前すぎて意識の外にあるだけで、規則正しい睡眠や健康的な食生活、十分な運動習慣などの積み重ねが寄与しているのではないか
解釈②であれば自分の生活を顧みるかもしれませんが、解釈①だと数秒後にはこれを見聞きしたことすら忘れていそうです。となると解釈の違いは、正しさ云々の問題でなくその後の行動にも影響してきます。誤った一般化や見せかけの因果関係には注意が必要です。
通常、インプットする具体例の数は多く、幅も広いほうが帰納法に活きてきます。ビジネスに置き換えると市場調査やトレンド分析などがわかりやすいですね。アナグラムの仕組みも、演繹法に帰納法を組み合わせることで成果を最大化しようとしています。
担当数を3-5社に制限していることは演繹法の箇所でお伝えしました。ですが臨場感を持てるビジネスが多ければ多いほど、成果に直結する引き出しが増える。これは紛れもない事実です。
そのため量を補う仕組みとして、他のコンサルタントが担当する案件を分析する勉強会(グロースハック)や、仕事に関連する書籍の費用を全額支給する制度を設けています。
このように演繹法と帰納法は循環する関係にあります。鶏と卵のようなもので、本来どちらが先かというものではありません(遺伝学的には卵が先と結論が出ているようですが)。
両方を組み合わせることで守破離は「離」の段階へ移行し、強度の高い思考を組み立てられるようになっていきます。
創造性や想像力で豊かにする「内装」
土台の上に骨組みを築いたら、最後は内装でさらに充実させましょう。個性を加え、もう1段魅力付けするための工程です。「類推」と「相対化」によって思考にオリジナリティやより深い説得力が加わります。
- 類推:構造上の共通点を見つけ出し、理解を深め発明を生む思考法
- 相対化:主観の一歩外側から批判的な目で再評価し、包括的に思考する方法
ここまでに紹介してきたアプローチは単独のみならず、それぞれ組み合わせることでより効果を発揮します。なかでも特に類推は構造化と、相対化は帰納法と密接に関連しているといえるでしょう。
類推
民泊サービス、マッチングアプリ、就職・転職媒体、不動産サービス、カーシェアリングサービス、フリーランスプラットフォーム。わたしたちの生活を便利にしてきたサービスを挙げてみましたが、さて、これらに共通するものは何でしょうか?
筆者が持つ答えとして、これらは特定市場における需要と供給のマッチングを効率化させることをその基本的な意義としています。
類推とはこのように、表面的には異なるように見えるもの同士に共通する特徴や原理を見出すことに始まります。それを別の事例や状況に適用することで、未知の領域や複雑な問題に対しての理解を深め解決策を発見できるのです。
共通点の発見には構造化が役立ちます。理解を助ける方法の一つに例え話がありますが、わかりやすい例えには条件がありますよね。
- 例えに使われるものが、聞き手にとって完全に既知であること
- 例えに使われるものと、新しく説明したいものに構造上の共通点があること
- その類似性が理解しやすいものであること
対象となるもの同士を骨格まで削ぎ落したとき、その構造が似通っていて初めて、例えは意味をなします。大きさは異なっても形は同じなので、図形でいうところの「相似」の関係といえるかもしれません。この記事の主題である「思考」と「建築」も類推によるものです。
ただし、類推による極端な決めつけには注意しなければなりません。
いくら似ていると感じても、どこまで行ってもそれらは別物。わかった気にならず、目の前の対象をそのまま観察できているか?この心構えは意識してもしすぎることはありません。
適切にバランスをとる必要はありますが、類推による結びつけは、遠い概念であるほど意外性があり、イノベーションも起こりやすくなります。
新商品や新規事業の開発などにおいて、類推思考がもたらす発想は大きなヒントです。一見関係がなさそうに見える分野の歴史や他業界の事例はアイデアの宝庫かもしれません。
アナグラムではクライアントの業界を絞らず、8割以上がそれぞれ異なる業界から未経験で入社し、副業もリモート勤務も禁止していません。相乗効果を生み、アイデア同士が結合するチャンスを最大限に広げています。
既知の情報を足場に、新しいアイデアや解決策にジャンプするための思考法が類推なのです。
相対化
最近強いアウェイ感を覚えたり、自分はマイノリティだと感じたりした一番新しい記憶はいつどんなときのものですか?新鮮さや居心地の悪さがあったなら、それはとりもなおさず自分の感覚や価値観を相対化するきっかけを得た瞬間だったかもしれません。
相対化とはある事象や概念を異なる観点や文脈から捉え直し、当初の見方が一側面に過ぎないと認識する試みです。そうして包括的または多角的な視野にアクセスします。
相対化が帰納法と密接に関連すると説明したのは、どちらも多様な事例を見聞きする必要があるためです。相対化の例は意外と日常に転がっています。
- 作品に対する評価は時代や地域に左右される
- ゴッホは生前ほとんど評価されなかったにもかかわらず、現在では世界的に有名な画家として広く認知されている
- 食習慣は文化によって異なる
- 寿司は多くの日本人にとって「普通」でも、生魚を食べる文化のない人にとっては「普通じゃない」
- 時間の感じ方は経験や寿命によって変わる
- セミにとっての一生は人間にとっての1週間であり、さらに大人になるほど1週間は短く感じられやすい
慣れは感覚を鈍らせ、自分の目に映る世界を絶対的なものと思い込ませます。そんなとき、日常の地続きにない体験は新しい刺激になりますよね。改めて自己を見つめ直す機会も運んできます。
就職・転職や旅先での体験を経て価値観が更新されることがあるのもこのためです。意図して定期的に新しいコミュニティに飛び込むのは、自分のバイアスから可能な限り自由であるために有効なのです。
相対化がもたらす視野は、自社の独自性を発見・創造する助けになります。アナグラムでは、企業が陥りがちなジレンマに対する一つの解決策として、あえて売上のノルマを設けていません。
もちろんノルマがもたらす一定以上の効果や意義については否定の余地がないと考えていますが、わたしたちはノルマという恣意的な指標のためにクライアントと自社の利益が相反しうる状態を作りたくないのです。
代わりに評価項目の一つには顧客満足度を設定しています。
売上は比較がしやすい一方、市場の規模によって少なからず天井が決まってきます。それに対し、人が喜ぶ基準や理由はさまざまで、満足には際限がありません。オーダーメイドで仕事を設計し、凝らせる工夫に終わりがない。そのほうが飽きずに仕事を楽しむことができ、結果としてクライアントへの貢献にもつながりますよね。
人が人を完璧に評価することなどできないと認めた上で、わたしたちは「もっと良い方法があるはずだ」と常にベターな仕組みを模索し続けています。
批判的な思考とは相対化の連続です。だからこそ、思考の旅には終わりがないのです。
揺るがない”思考の建築物”を建てるために
この記事では思考を建築になぞらえ、設計図の充実を図る方法をお伝えしてきました。これらの方法を活用して一度組み立てた思考は、芋づる式にたくさんの示唆を与えてくれます。
- 思考も建築も一貫性が大事。一貫しているからこそメッセージは鮮明に伝わり、強度や波及効果もあがる
- どちらも設計図は書き直しができる。検証を小さく繰り返しながら、工程を行ったり来たりしてもいい
- 思考も建物も一度完成したら終わりではなく、メンテナンスが必要。大幅なリフォームもできるが、建てる段階でできる限り隅々まで考慮しておいたほうがトータルコストは抑えられる
- 土地の選定、土台、骨組みにはなかなかやり直しがきかないと認識する。着手する前に時間が巻き戻ることはない
- 基本を体得すればアレンジが効き、練度が上がれば内装どころか土台から個性を出せる
これは思考や建築に限らず、計画的に階層を積み重ねてゴールへ向かう多くの営みにきっとあてはまることでしょう。
しかしここまで紹介してきたのは、あくまで設計図の書き方に過ぎません。最後にこの記事において最も大切だと伝えたいことがあります。
これは筆者への戒めでもあるのですが、思考はどれだけ深めても地上からは見えず、実行されたときに初めて形や意味を持つようになるということです。どんなに立派な建物も最初のレンガが置かれなければ、積み上がることも完成することもありません。
発信しなければ存在しないのと一緒だから、アナグラムのメンバーはこうしてブログを書いています。
思考を組み立て、実行し、フィードバックから学び、また次の思考に活かす。思考の建築家への道はまっすぐの一本道ではなく、試行錯誤の繰り返しです。
けれど思考と実行を繰り返せば、必ず今より堅牢で機能的で美しい”思考の建築物”が建ちます。
アナグラムにはまさしく、そうやって作成した設計図を手にそれぞれが存分に行動に移し、思考を磨き続けられるだけの土壌があるのです。