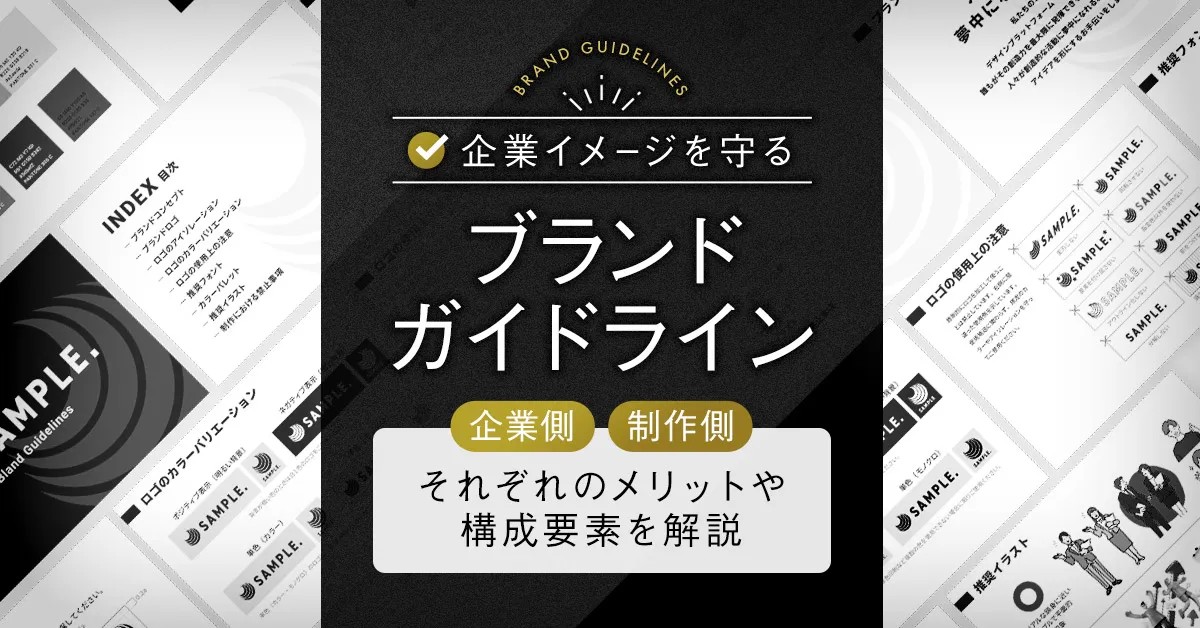バナーを作っていざ配信!でも「最初にどのくらい入稿したらいいんだろう?」「入れ替えるタイミングはいつ?」「クリエイティブを評価する上で見るべきポイントは?」……このように配信後も運用者の悩みはつきません。
広告クリエイティブを作って配信したら終わりにせず、配信結果から次の施策に繋げていくことがクリエイティブの質を高める秘訣です。
今回は「広告クリエイティブのPDCA」をテーマに、制作から改善までのフローをご紹介していきます。


広告クリエイティブのPDCAとは?
今回の記事における「広告クリエイティブ」とは、バナーなどの素材を使った広告全般を指します(一緒に表示される見出しや本文なども含む)。運用型広告は予約型広告やオフライン広告と異なり出稿後のクリエイティブ変更が容易なため、改善を重ねることでパフォーマンスの向上が見込めます。
しかしながらバナー広告を改善するにはデザインの修正作業などが発生するため、都度調整できるテキスト広告と比べると工数がかかります。着実に成果につなげていくためには制作前の準備や運用後の調整など適切に対応しながら進めていくことが大切です。
広告クリエイティブのPDCAの各段階でおさえておきたいポイントを以下にまとめましたので、さっそく順番に見ていきましょう。
Plan:計画
まず最初に広告クリエイティブを準備していきます。制作前のプロセスに力を入れることで最終的な成果にも差がつきます。
制作の目的を確認し情報を整理する
前提としてバナー広告を作る目的を明確にしておく必要があります。
ディスプレイ広告やSNS広告はすべての商材との相性が良いわけではなく、商材によっては費用対効果が見合わないケースがあります。また予算をあまりかけられない状況下で配信をスタートしても、インプレッションがほとんど出ずに思ったような結果が得られない可能性が高いです。取り組みの優先度や制作の必然性が高いことを前提に、適切なタイミングで実施していきましょう。
そして良質なクリエイティブを作るためには商材への深い理解が欠かせません。3C分析やアカウント分析、口コミやアンケート調査の結果などを踏まえて、現状の課題やメインの顧客層、商材独自の強みや特徴を洗い出しておきましょう。これらの情報がターゲットや訴求軸を決める際に役立ちます。
ターゲット・訴求軸・媒体を決める
広告作りにおける肝は「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかということです。
集めた情報を元に「誰に(ターゲット)」「何を(訴求)」の部分を考えていきましょう。ターゲットはペルソナ(年齢や行動パターン、趣味趣向などの人物像)を詳細に決めていくというよりは、実際の顧客層や口コミなどを参考にしながら「この商材を必要とする人はどんな人物なのか?」を逆算して考えていくとイメージしやすいです。訴求軸はターゲットにとって有益な情報や、他社商材と比較したときの独自性や優位性などを打ち出せると良いでしょう。
ターゲットや訴求軸が固まったら、次は「どのように」の部分を考えていきます。ターゲットを踏まえてどんな広告媒体や広告フォーマットを選択するのか、伝えたい内容をどのような表現や見せ方でクリエイティブに落とし込むのかを決めていきます。
媒体ごとにリーチ数やターゲティング精度、クリエイティブの表示フォーマットが異なるため、商材との相性を踏まえて適切なものを選択しましょう。ある媒体では審査落ちしなかった内容でも別媒体ではNGというケースもありますので注意してください。類似ターゲティングや興味・関心ターゲティングなど、実際に入稿するときのターゲティング設定まで想定しておけるとなお良いです。
また実際に広告が出稿される面まで把握しておくことも大切です。バナー広告はたいてい広告の見出しや本文とセットで表示されるため、そこまで含めて1つのクリエイティブだと考えてください。
特にTwitter広告のようにテキストを読まれる媒体の場合は、文体や絵文字などの細部の表現にまでこだわると成果に繋がりやすいです。広告文とバナー上のテキスト内容が重複しないようにするなど、限られたスペースを効率よく使うこともポイントです。
配信媒体の選び方についてはこちらの記事も参考になります。
クリエイティブ案を詰めて制作する
次に具体的なクリエイティブ案を考えていきます。運用型広告においてはPDCAサイクルを上手に早く回していくことが重要であり、渾身のクリエイティブを1つだけ入稿するよりも、複数のクリエイティブを運用しながら成果の良いものを発掘していくやり方が適しています。また広告の点数が少ないと同じユーザーに何度も表示され、飽きられて効果が悪くなることも懸念されます。そのため1つのターゲットや訴求軸につき1案ではなく、複数パターン用意しておくと良いでしょう。
架空の商材を参考に、進め方の例を紹介していきます。
<STEP1>分析を元にターゲットとニーズを明確にする
3C分析などを踏まえて以下のようにメインターゲットとニーズを導き出していきます。
<STEP2>ニーズごとにクリエイティブの具体案を考える
ニーズを元にクリエイティブに落とし込む具体的なテキストなどを考えていきます。
合わせて使用する素材なども考えておきましょう。表現に悩んだときは競合他社のバナーやSNSのオーガニック投稿でリアクションが多いものを見ると参考になります。
<STEP3>デザインやフォーマットでバリエーションを出す
具体案がまとまり、テキストや素材などの必要な材料をそろえたら制作に入ります。
訴求やテキストはそのままでデザインや優先順位を大きく変えてみたり、反対に同じデザインで伝える内容を変えてみるなど、少し工夫するだけでバリエーションを増やすことができます。
静止画バナーで当たった訴求をカルーセル広告や動画広告に展開するなど、別のフォーマットに横展開させていくのも有効です。
工数や費用がかかるカルーセル広告や動画広告の場合、カルーセル広告なら1枚目、動画なら冒頭1シーンのみを変更する形で複数パターン作ると良いでしょう。
その理由としては、カルーセル広告ではスワイプを促す1枚目で興味を持ってもらえないと続きを読んでもらえませんし、動画広告においては冒頭5秒以内にスキップされる確率が高いと言われているためです。後半の作りが同じでも最初の印象を変えるだけで、工数に対するインパクトが大きく結果にも差が現れやすいのでおすすめです。
バナー広告制作については以下の記事も参考になります。
Do:行動
バナーが用意できたら次は入稿を進めていきます。
適切にキャンペーンやターゲティングを設定する
新たに配信を始める場合はキャンペーンや広告セットを作成します。この時気をつけたいのがキャンペーンや広告セットを細かく分けすぎないことです。
入稿サイズごとに広告グループを分けたり、ターゲット設定やリンク先が同じなのに別の広告グループにしているケースがあります。細分化すればするほど1つあたりの広告の表示回数が減り、評価がしづらくなってしまうので、ABテストのように特別な意図がある場合をのぞいては、なるべくまとめるようにしてください。
次にターゲティングを設定していきます。ブロード配信ではターティングが広すぎると本来のターゲットとは違う層にまで広く出てしまう可能性が高く、とはいえターゲティングを絞りすぎると今度は機会損失に繋がる恐れがあります。
潜在層に広げていくフェーズではターゲット設定を狭めすぎず、クリエイティブの表現でターゲットをしぼっていく……そんなイメージを持っておくと良いかもしれません。
広告は一度にたくさん入稿しない
バリエーションが多いに越したことがないとはいえ、1つの広告セットに何十個もバナーを入れるなど、一度にたくさん入稿するのは賢明ではありません。広告の数が多すぎると配信がそれぞれに分散してしまい、機械学習に時間がかかるだけでなくパフォーマンスが安定するまでに余計な予算を消費してしまう恐れがあります。例えばMeta(Facebook)公式では広告セットに対する広告数は6件が推奨されています。他の媒体ではまた異なりますが、あまり多くなりすぎないよう、ひとつの目安にしてみてください。
期間や条件を決めてA/Bテストを行う
設定の変更やクリエイティブの差し替えでパフォーマンスが落ちないか心配なときや、仮説の検証をしたいときにはA/Bテストがおすすめです。A/Bテストをするときは結果に揺れが出ないように必ず条件や期間を設定してから始めるようにしましょう。A/Bテストの代表的なやり方としては、差分の広告セットを作って自分で管理しながらテストしていく方法と、媒体のテストツールを使って集計する方法があります。
A/Bテストに関しては以下の記事も参考になります。
運用しながら適宜調整する
目標CPA(コンバージョン単価)に対して著しく高騰してしまったり、インプレッションは十分出ているのにクリックやコンバージョンがほとんどつかないクリエイティブは停止や差し替えを検討します。考えられる原因の1つとして、ターゲティング設定のズレやミスにより本来のポテンシャルを発揮できていない可能性もあるので、停止の前にまずはターゲティング設定を見直してみましょう。
とはいえ配信スタートしてから日が浅いうちに広告を止めたり、短い期間の中でターゲティング設定をコロコロ変えたりすると、データも溜まりにくく機会損失にも繋がります。明らかに採算が合わないときには停止する必要がありますが、できる限り長期的な目線で様子を見ていくようにしましょう。
またCPAが高めでもコンバージョンが多い広告を停止すると、今まで蓄積してきた機械学習や他の広告のパフォーマンスにも影響が出ることがあるため、慎重に行うようにしてください。
Check:評価
配信スタートから一定期間が経ったら結果を振り返ります。
クリック率やCPAのみにとらわれず総合的に判断する
広告の評価指標としてクリック率やCPAばかりに注目してしまいがちですが、他の指標や観点も意識してみてください。
クリック率が高い=クリックしたくなる広告であることには間違いありませんが、大幅な値下げや無料キャンペーンなどの広告、ゲームやくじ引きなどのギミックを持った広告は特性上クリック率が高めになりやすいです。クリック率が高くてもその後の離脱率も高く、コンバージョンに繋がらなければ結局のところ費用対効果が見合わなくなってしまいます。
またクリック率に対してCVR(コンバージョン率)が低いときは、広告とリンク先のファーストビューに悪い意味でギャップがあったり、ページの内容に違和感を持たれて離脱されている可能性もあります。リンク先まで含めて改善できるところがないかトータルで確認しておくと良いでしょう。
CPAに関しても単純に数値の高低だけで判断するのは危険です。例えばCPAが低くてもサービスの解約率が高い広告Aと、CPAが高くても解約率が低い広告Bを比較すると、LTV(顧客生涯価値)の観点から見ればBの方が質の高い広告という評価になります。
また売上ベースでみると、CPAが許容範囲でコンバージョンが少ない広告よりも、CPAが高騰しつつもコンバージョンが多い広告の方が評価に値することがあります。近視眼的になっているときは課題や目的を見直し、あらゆる視点から指標を見ていくことが大切です。
広告クリエイティブを評価するときに気を付けたいことは、こちらの記事で詳しく解説しています。
結果は振り返りしやすい形式にしてデザイナーにも共有
その都度、広告アカウントを確認して「このバナーの成果が良かった」という漠然とした結果だけを覚えておいても後の学びにはなりません。一覧にして具体的な配信結果を残しておくと振り返りがしやすく、上司やクライアントなど関係者に報告する際にも役立ちます。
配信結果はクリエイティブを制作したデザイナーにも共有すると良いでしょう。結果の良し悪しがわかるとデザイナー側からも新しいアイデアを提案しやすくなりますし、共通の認識を持つことで修正依頼や新規で制作相談をするときにもコミュニケーションが取りやすくなるはずです。
アナグラムではスプレッドシートやExcelを使って配信結果をまとめることが多いです。以下にMeta広告での配信例としてサンプルを貼っていますので参考にしてみてください。※架空の商材です
結果を元に仮説を立てて次の施策に繋げる
配信結果をスプレッドシートなどにまとめ終わったら、成果の良かった(悪かった)広告の要因を分析していきます。
……といったように次のアクションに繋がる仮説を立てていきましょう。
Action:改善
最後に配信結果や仮説を踏まえて次の施策を考えていきます。今回は以下3つの改善策について解説します。
- 仮説を元に新しいクリエイティブを展開する
- 成果の良かったクリエイティブを別媒体や検索広告などに活用する
- 鉄板の訴求の効果が落ちてきたら根本から考え直す
仮説を元に新しいクリエイティブを展開する
成果に繋がったと考えられる要素を残したり反映させていく形で、新しいクリエイティブを展開していきます。架空の商材を例にして以下に4つのケースを挙げてみました。
ケース1:方向性は変えずにパターンを増やす
仮説:リアルな「あるある」ネタがターゲットの共感を生んだのでは?
次のアクション:「あるある」ネタを増やして同じ方向性でパターンを増やす
ケース2:方向性は変えずに表現や見せ方を変える
仮説:コスパ訴求だったら商品写真を使った方が量をアピールできるのでは?
次のアクション:商品写真に差し替えて容量を追記したバナーを作る
ケース3:成果に繋がったとされる要素を取り入れる
仮説:「3分」「今すぐ」「無料」といった手軽さを感じられる文言が良かったのでは?
次のアクション:他のバナーにもCTA「3分で登録完了!今すぐ無料公開中の作品を見る」を反映させる
ケース4:広告のフォーマットを変更する
仮説:実際の操作感や機能の詳細をもっと伝えられると良いのでは?
次のアクション:フォーマットを動画広告に変更し、より詳しく機能を説明する
成果の良かったクリエイティブを別媒体や検索広告などに活用する
たとえばMeta広告で好調だったバナーを同様の属性のユーザーをターゲットとしたGoogleディスプレイ広告でも配信するなど、同じクリエイティブをそのまま別媒体に配信していくのも有効です。ただし入稿サイズが異なったり表示場所や見え方に違いがあるためひと手間かかりますが掲載面に合わせてリサイズしたりデザインの調整を行うことを推奨します。
また成果の良かったクリエイティブに使われていたテキストを検索広告の見出しや説明文に取り入れてみたり、表現や見せ方をLPのファーストビューなどに活用してみるのも効果的です。
鉄板の訴求の効果が落ちてきたら根本から考え直す
安定して成果の良かった鉄板の訴求でさまざまなパターンを試してきたものの、だんだんとユーザーの反応が鈍くなってくると次に何をやるべきかわからなくなってしまうかもしれません。そんなときは「誰に」「何を」の部分に立ち戻り、今までとは異なる軸でターゲティングや訴求を立て直してみてください。根本の軸が変わることで新たなクリエイティブを生み出すことができるでしょう。
まとめ
広告プラットフォームの技術の向上によって、特に「入札」「ターゲティング」で自動化が進む運用型広告ですが、「クリエイティブ」においてはまだまだ人間のサポートが必要です。
機械学習は過去のデータを元に最適な選択をしたり発展させていくことが得意ですが、現状ではゼロベースから何かを生み出すことは得意ではありません。ロボットにはない人間の強みは、新しい仮説を立てたり創意工夫を凝らすことができることです。
運用型広告において効果的なクリエイティブを作るための考察は以下のブログが参考になります。
重要性が高まっている?広告運用におけるクリエイティブの現在地について考えてみた
自動化に頼れるところは頼って上手に活用しつつ、クリエイティブな要素は私たちの頭をフルに使って生み出していきたいですね。広告クリエイティブのPCDAを回して、広告の質や表現力をどんどん高めていきましょう。