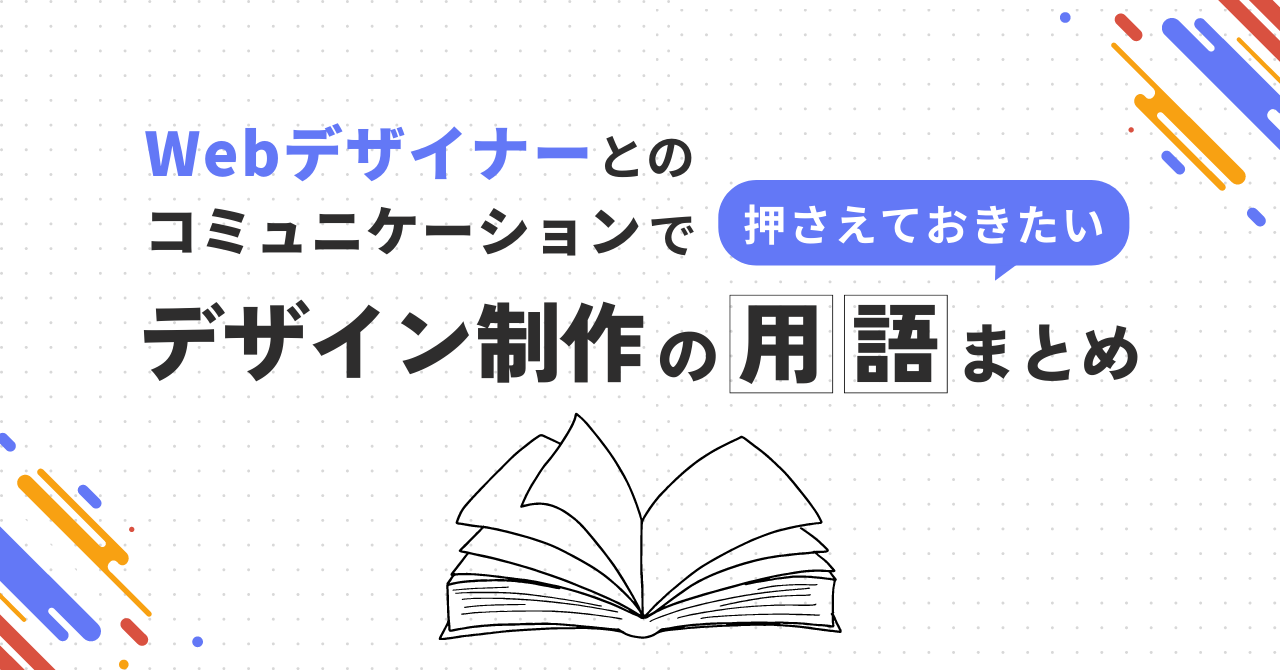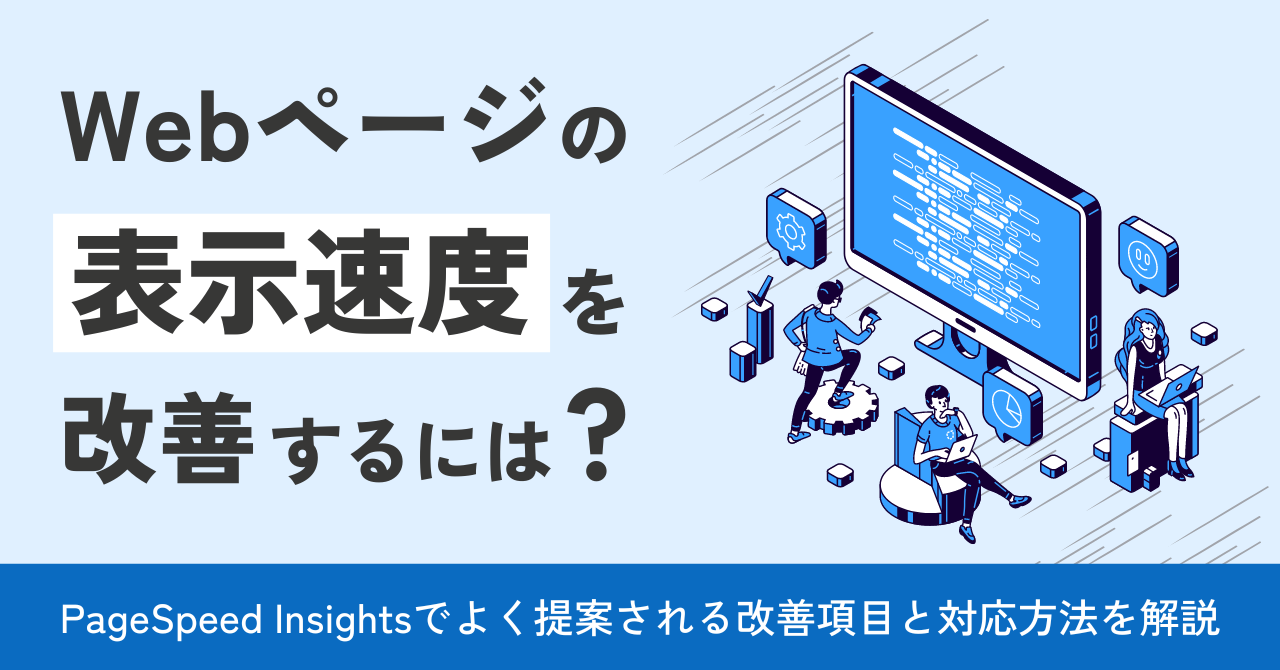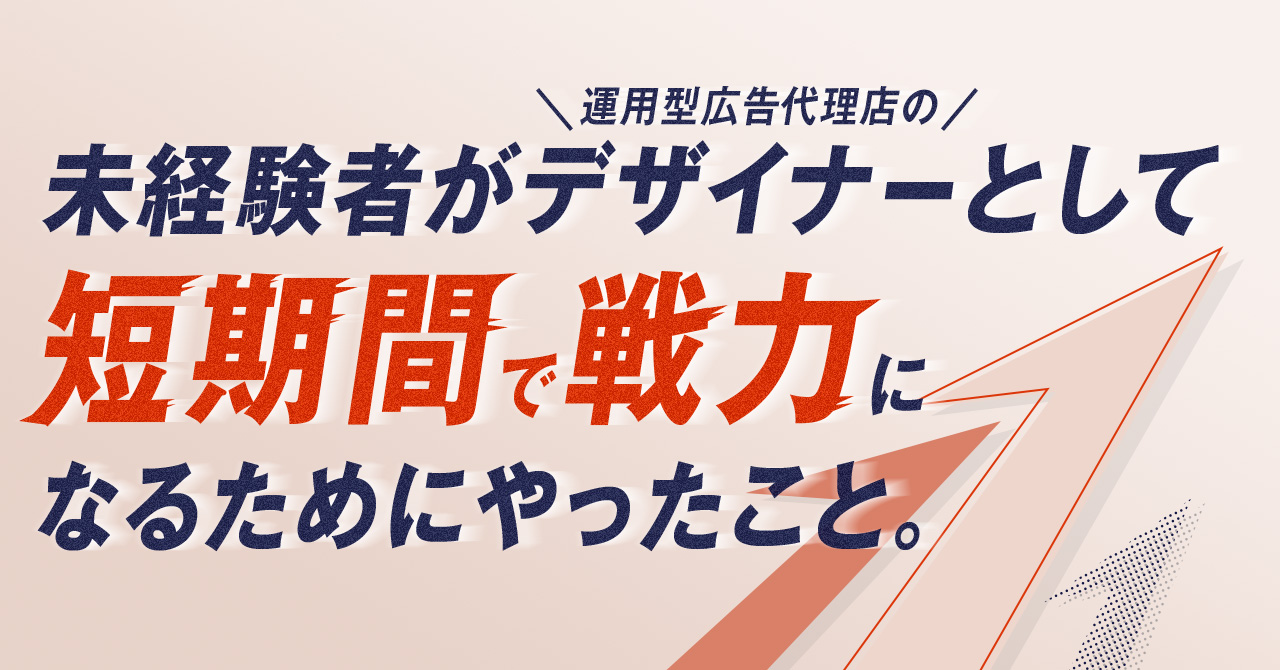広告運用の成否を分ける要素は、入札、ターゲティング、クリエイティブの大きく3つに分類できます。
そのうち入札とターゲティングは、自動化が進んだことで以前ほど成果の差をつけることが難しくなってきました。加えて、運用型広告の媒体が多様化しプラットフォームごとに異なるクリエイティブ戦略が必要となっていることから、クリエイティブ制作の重要性はこれまで以上に増しています。アナグラムでもクリエイティブ制作専門のチームを設けて注力している領域です。
運用型広告で成果を上げるためのバナーや動画、ランディングページといったクリエイティブを制作するために、デザイナーにはどのようなスキルや視点が必要なのでしょうか。
私はWebデザインと広告運用の両方を経験し、現在はクリエイティブチームの責任者を務めています。アナグラムのクリエイティブチームを立ち上げて約2年、多くの試行錯誤や社内外からのフィードバックがありました。
その経験から、現時点で私が考える「運用型広告の現場で必要なデザイナーのスキル」を整理してみました。


目次
成果につながるアクションを判断できる
アナグラムでは広告運用者もデザイナーも「クライアントの成果を上げる」という共通のゴールに向かって日々取り組んでいます。数字と向き合っているのは運用型広告の現場に限ったことではありませんが、運用型広告は施策と振り返りのサイクルが特に早い性質があります。
リソースが限られている中「とりあえず新しいバナーを制作する」といった場当たり的な施策が続いてしまうこともあるため、大局観を持ちながら成果につながるアクションを判断する力が必要です。
具体的には、どのようなスキルが求められるでしょうか?
課題設定に踏み込めるか
いま目の前にあるタスクは、いったい何を解決するための仕事でしょうか。
たとえば「このバナーのデザインは素人感があるから成果が出ない。もっとプロっぽく仕上げてほしい。」というオーダーがあったとします。
実際に成果が出ない理由がデザインの素人感にあれば、課題と打ち手がマッチしているため効果が期待できます。しかし実際はターゲティングとキャッチコピーが合っていないせいかもしれませんし、ランディングページやエントリーフォームにもっと大きな問題があるかもしれません。
適切な課題を設定できているかは、それ以降のアクション全ての判断基準になってくるため、最重要と言っても過言ではないでしょう。何がボトルネックになっていて、デザインを用いてどう解決できるのか。ここにミスマッチがあってはいけません。
オーダーを鵜呑みにするだけではなく、デザイナー自身も施策の意図を理解し、時には意見を交換しながら制作に取り掛かるような関わり方が理想だと考えています。
課題設定の大切さは以下の記事でも紹介しています。
違和感を曖昧にせず意見できるか
何か違和感に気付いたとしても、指摘することでプロジェクトの流れが止まることを嫌がって黙っているという人は意外と多いのではないでしょうか。マーケティングとデザインでお互いの役割に干渉してはいけないと、遠慮してしまう場面もあるかもしれません。
しかし、数値や言語だけでは表現しきれないものごとをカタチにするのはデザイナーの仕事です。違和感があるまま進めてしまうことで、クライアントの期待に答えられなかったり市場に振り向いてもらえないデザインになってしまうかもしれません。
成果を上げるために必要だと思ったのであれば、違和感を曖昧にせず相手の立場も考慮した上で意見を伝えましょう。
広告運用の業務を理解しているか
課題設定に基づいて伝えるべきメッセージを決定したとして、どんな体裁のものを、どのくらいの数、どのくらいの頻度で制作すべきでしょうか。
たとえば広告掲載開始にあたってバナーが1つしか用意されていなかったり、媒体に合わないトンマナだったりすると、広告運用者であれば不安な気持ちになるでしょう。
デザイナーも自分が制作する広告の配信にどんな設定項目があるのかや、媒体が提唱する広告運用のベストプラクティスを把握することで、成果を上げるためには何をどのくらい制作するべきかイメージしやすくなります。効率的に学ぶために、媒体が用意している認定資格に挑戦したりセミナーに参加するのもおすすめです。
広告運用の知識は制作だけでなく振り返りのフェーズでも役立ちます。配信結果はデザイン以外の多くの要素に影響されるため、すべてがデザインに起因する結果だと捉えてしまうと、誤った判断をしてしまうかもしれません。
もし実際の配信結果を確認できる環境であれば自分でもクリエイティブによる配信結果の違いを見てみたり、広告運用者に結果を確認してみると良いでしょう。
デザインで重視するべき要素を見極められるか
その広告クリエイティブの、購買決定に大きく影響する要素は何でしょうか。コピーなのか、商品の見た目なのか、モデル選定なのか、トンマナなのか……。もちろん、どれも大事なのですが、どのように重み付けするかも重要です。
デザイン視点のみで考えると、どうしてもトンマナに意識が向きがちです。しかし実際は「広告クリエイティブの見た目が好きだったから購入した」ケースばかりではありません。にも関わらず、細部の装飾に時間をかけすぎてしまうような場面もあるのではないでしょうか。
運用型広告では渾身のクリエイティブ1つだけを配信するのではなく、多くのバリエーションを試しながら、どのようなクリエイティブであればより良い成果をあげられるかを探ることも必要です。
1つのデザインの細部を必要以上に突き詰める時間で、コピーの異なる別の1案を追加するほうが運用型広告では有意義な場面があることも知っておきましょう。
クリエイティブを納品できる
課題設定とアウトプットのイメージまで練り上げても、頭にあるものをカタチにできなければ意味がありません。制作物が配信されるまでがクリエイティブ制作です。もしかすると、毎回自ら制作しなくてはならないと思い込んでいる人もいるかもしれません。
しかし自身はディレクションに徹して、制作はパートナー企業など他の人にお願いするのも一つの手です。自ら制作する場合も、他の人に任せる場合も持っておきたいスキルを紹介します。
状況に合った選択をできるか
コピーやデザインの案が大量にあったとして、その全てを一斉に配信するのは制作や運用にかかるリソースの面で現実的ではありません。クリエイティブ制作ではたくさんの案を出すだけでなく、その中から実際に取り入れるものを選ぶ工程も重要です。
たとえばプロテインパウダーの広告であれば「価格」「味」「成分」など訴求する要素はいくつもありますが、プロモーションの課題やブランドが目指すもの、競合製品と比べた時の優位性に応じて広告メッセージに何を取り入れるべきか判断は変わってくるでしょう。
そのクリエイティブはどこで掲載され、どんな人に見てもらい、どんな行動を促したいのかを整理することで、適切な選択ができるようになります。
情報を整理する過程でビジネス・顧客の理解が必要になる場面もあるので、3C分析などマーケティングのフレームワークを使って効率よく情報収集するのがおすすめです。
フィードバックを適切に扱えるか
言っていることが矛盾している、デザインのセオリーに当てはまらない、前提条件や価値基準が曖昧である……など、納得できないフィードバックに悩まされた経験はデザイナーであれば誰にでもあるでしょう。
しかし、フィードバックをしている側は課題意識を持っていてもデザインに落とし込むにあたって、上手に言語化できていないだけかもしれません。
そもそも、広告を最終的に評価するのはデザイナーではなく生活者です。デザイナーのためのデザインにならないためにも、様々な意見をむやみに否定せず、適切に扱うことを忘れてはいけません。
意図を確認しないまま否定したり、反対に上司やクライアントの意見だからといって無条件に取り入れるのではなく「この広告クリエイティブが高い成果をあげるためにどうあるべきか」を基準に判断することが求められます。
自ら制作できるか
デザイン制作の実務を行えることは運用型広告の現場ではとても重宝されるスキルです。スピード感の求められる運用型広告の現場では、マーケターやディレクターの想いをスピーディーに形にできれば、それだけ早くビジネスを動かせるのです。もちろん、自身で提案した施策を自ら手早く制作してしまえることは強みになります。
一生のキャリアのうち、ずっとデザイン制作を行う立場で過ごせる人はほんの一握りです。キャリア形成の中で、ディレクターやマネージャーなど、人を動かすことで成果を出す立場になることもあるでしょう。
実際に手を動かせるスキルはそこでも必ず役に立ちます。自ら制作できることは最も確実な方法であると同時に、キャリア形成の基盤にもなるもので、言うまでもなく重要なのです。
イメージ通りのものを発注できるか
では制作の実務が行えないと仕事が務まらないかというと、必ずしも自ら制作できる必要はありません。(制作ができれば有利なことは間違いありませんが)
意外に思うかもしれませんが、Webディレクターという職についていても本人が必ず制作できるとは限らず、デザインができることはディレクターにとっても強みなのです。イメージ通りのものを制作するにあたっての適切な与件設定やフィードバック、人材配置などはデザイン実務のみでは身に付きにくく、重宝されるスキルです。
また、自ら制作するスキルを持っていたとしても、プロジェクトに必要な制作物すべてを自分で制作し続けるのが難しい場面はいつか訪れます。そんな時を見据えて発注側としての経験をしておくことも大切でしょう。
クリエイティブ制作に限りませんが、誰かの力を借りて仕事をする立場であれば、その人たちが気持ちよく引き受けてくれて腕をふるってくれるような仕事の頼み方ができると理想的です。いわゆるコミュニケーションスキルはもちろん、外部パートナーに委託する場合は支払いを遅らせない、値切らない、といったことも信頼を構築する上で大切になることを知っておきましょう。
まとめ
アナグラムでクリエイティブ制作を行うなかで、特に必要だと感じているスキルを並べました。必ずしもこれらをすべて身に付ける必要はなく、自分で制作するのが得意なのか、人を動かしながらカタチづくるのが得意なのかによって、活躍できるフィールドはさまざまです。それだけ広告運用に携わるデザイナーは多様な人材が求められているとも言えます。
この記事で紹介したことは特別な才能やセンスが必要なものではなく、知識と経験で後から習得できるものばかりです。まずは自分の得意分野で活躍しながら、徐々にできることを増やすことで着実にステップアップできるでしょう。