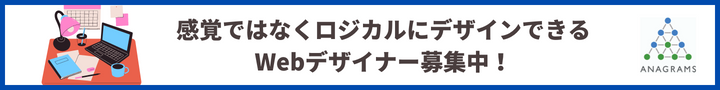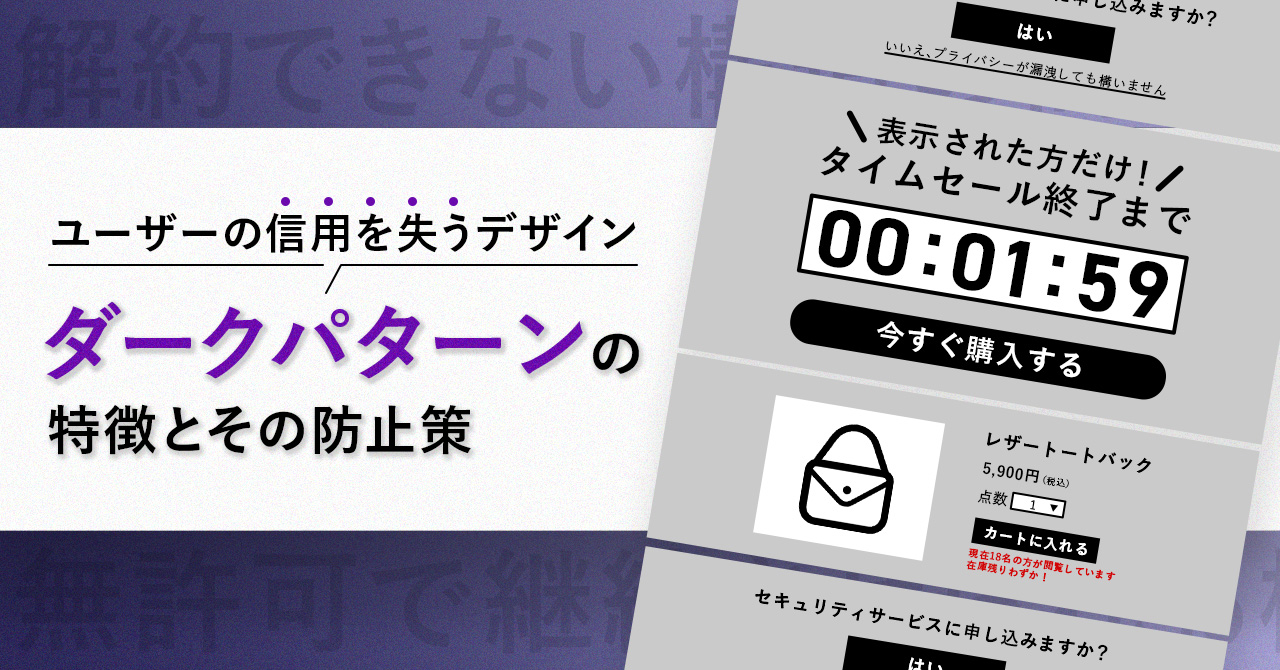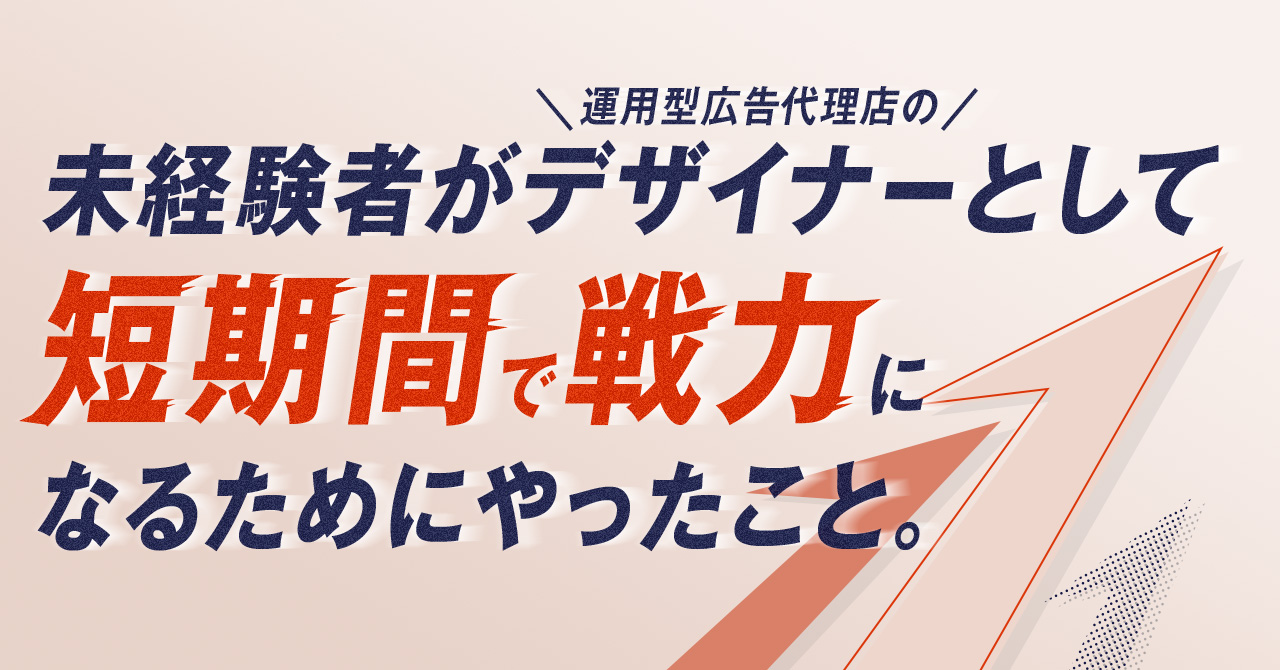
未経験から新しい職種にチャレンジする場合、最初はなかなか成果が出せない状況に焦ってしまいますよね。
私は前職でエンジニアとして働いていましたが、運用型広告代理店にデザイナーとして入社しました。入社までは運用型広告の知識もなくデザイナーとしても未経験でしたが、1年足らずでバナーや動画制作はもちろん、クリエイティブのディレクションや改善提案など、幅広い業務を任されるようになりました。
そんな私が、未経験から運用型広告のデザイナーとして短期間で戦力になるために取り組んだことを紹介します。
未経験からの転身に限らず、デザイナーとして伸び悩んでいたり、成長するための方法を知りたいという方のヒントになれば幸いです。


目次
これまでの経験で活かせることを洗い出す
未経験で転職というと、0からのスタートだと考える方もいるかもしれません。しかし、これまでの経験を振り返ると、必ず今に活きることが見つかるはずです。
たとえば私の場合、前職はエンジニアでしたが、エラーを見つけて修正する業務を何度も経験してきました。その経験から細部にまで注意を払う習慣が身につき、現在は丁寧なデザインを制作したり、ミスを未然に防いだりと、デザイナーの業務にも活かすことができています。
違う業界や職種から転職した場合は、商材理解やターゲット理解に役立てられるのでこれも強みと言えますよね。
未経験だと初めてのことばかりで落ち込むことも多いですが、元々の良さまで無くしてしまっては成長スピードが落ちてしまいます。スキルや知識から強みとなる部分を洗い出すことで、過剰に自信を失ってしまうのを防ぐことができるでしょう。
「〇〇ならあの人」というポジションを作る
デザイナーの中でもバナー制作が得意な人、LP制作が得意な人……など人によってさまざまな強みがあります。
チーム内にすでに強みのある人がいる分野で自分のスキルを磨くことも大切ですが、最速で戦力になるためには、他の人があまり手をつけていない領域を見つけるのも一手です。
私の場合、入社当時は今ほど動画を作れる人が多くなかったため、動画制作を自分の強みにしようと考えました。そのために動画制作が得意な先輩に教えていただいたり、SNSやYouTubeで情報を集めたりしてスキルを高めていったのです。
編集スキルを磨くだけでなく、動画の目的に合わせて構成案から自分で考えていくうちに、徐々に「動画ならあの人」と認知してもらうことができました。
ただし、ここで気をつけたいのが「ポジションを作るだけで満足しない」ということです。今後も成果を上げ続けるためには、常に最新情報をキャッチアップして、別の分野にチャレンジすることも忘れてはいけません。
説明できるデザインをする癖をつける
デザイン初心者だと、感覚的になんとなく見た目が綺麗なデザインをしてしまうことが少なくありません。しかし、漠然と綺麗に装飾するのでは伝えたいことが伝わらず、成果も出しづらくなります。
たとえば「なぜここにロゴを配置したのか」「ボタンはなぜこの色なのか」と質問されたとき、すぐに回答できるでしょうか。
どんなデザインも、ユーザーに何らかの感情を抱かせたり行動を促したりするためには、意図を持ってロジカルに作ることが重要です。
デザインをするときに、「なぜここを強調したのか?」「なぜこの雰囲気のデザインにしたのか?」など、「なぜ」を問いかけながら制作を進めてみてください。
日常で触れるデザインからインプットする
デザインのアイディアは、ただ普通に生きていて突然0から生み出せるものではありません。
例えば、電車に乗っていてもスマホではなく広告や人を観察してみたり、本屋では雑誌のデザインを見てみたり、アンテナを張ってみると日常にもさまざまなヒントが転がっています。
それらすべてをインプットするのは大変という方は、まずは自分が担当している商材に関するデザインを集めることから始めてみましょう。意識的に観察する習慣をつけておくことで、デザイン的な表現や訴求軸、考え方など引き出しを増やすことができます。
私の場合は、SNSやWebサイトを利用しているときに気になったバナー広告を保存して、良いと思ったポイントを言語化することを習慣化しました。
バナーを見る際に意識すべきポイントを知りたい方は、下記記事をご参照ください。
自分の学びをオープンな場でアウトプットする
自分の思考を広げるためには、学んで終わりではなく、アウトプットして理解を深めたり、他の人から意見をもらうことも大切です。
私が働いているアナグラムでは、コミュニケーションツールとしてSlackを使用しています。メンバーごとに「times」という個人チャンネルを作り、独り言や考え事を投稿する文化があったので、私もtimesチャンネルを作成し、日々勉強したことを投稿するようにしました。
もちろんSlackではなくメールでもリアルのミーティングでも方法は何でも良いのですが、他の人が見ることのできるオープンな場でアウトプットするメリットはたくさんあります。
- 人に伝えようとするので、文章構成力が身につく
- アウトプットを見て意見や感想など反応があるため、学びが深まる
- 発信者が何をインプットし、何を得意としているのか他のメンバーから認知されやすくなる
- 発信者の人柄がわかりやすく、ふだんのコミュニケーションが円滑になる
インプットをすること以上に、アウトプットをすることが学習の深度を深めると実感しています。
上司・先輩に聞く/真似する
早く成長したいのであれば、その道の先を行く上司や先輩に聞いたり、真似をすることが効果的で短期成長できる鍵と言えます。
はじめのうちは「そんなこともわからないのか」と思われるのが怖くてなかなか聞きづらいかもしれませんが、現場で実務を遂行してきたからこそ分かる、本やWebには載っていないノウハウを得ることができます。
また、自分にとってお手本となるメンターを決めて、その人の考えや行動を真似てみることも効果的です。ただ、メンターを一人に絞ることはあまりおすすめしません。なぜなら一人に絞ってしまうと、その人からしかインプットできないので思考や行動の幅が狭まってしまうからです。そのため、メンターは複数人決めて、デザイン制作ならAさん、ディレクションならBさん、プレゼンの話し方はCさん……のように、カテゴリ別に設定すると、幅広く網羅的な思考・行動が身につきやすくなります。
自分が広告運用者だったらどうするか?を考える
デザイナーという枠の中でクリエイティブの見た目の部分だけを考えるのでは、作業者と同じであり、替えが利く存在となってしまいます。
競合やターゲットユーザーの分析を行い、仮説を持ってクリエイティブのPDCAを回していくことで、成果に繋がるクリエイティブを考えられるデザイナーへ成長することができます。
とは言え、広告運用者と同じ視点は一朝一夕で身につくものではありません。日頃から広告管理画面を見たり、運用者にクリエイティブの成果を確認したりするなど、日々習慣化し身につけていくことが必要です。
運用型広告の現場で求められている、デザイナーのスキルについてはこちらの記事でまとめています。
最後に
色々と書かせていただきましたが、ひとつひとつは難しいことではないので「なんだそんなことか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。また、上記で挙げたこと全てが誰にでも当てはまる方法ではないと思います。
ですが、いきなり大きな成果を上げようと思っても時間がかかってしまい、なかなか上手くいきません。仕事を任せてもらうには、まずは小さなことでもいいので目の前の仕事で成果を出し、信頼してもらうことが大切です。本日紹介した方法は、そんな最初の成果を出すための手助けになるでしょう。
デザイナーとして成長したいとお考えの方は、もし取り入れられそうなものがあればぜひ試してみてくださいね。