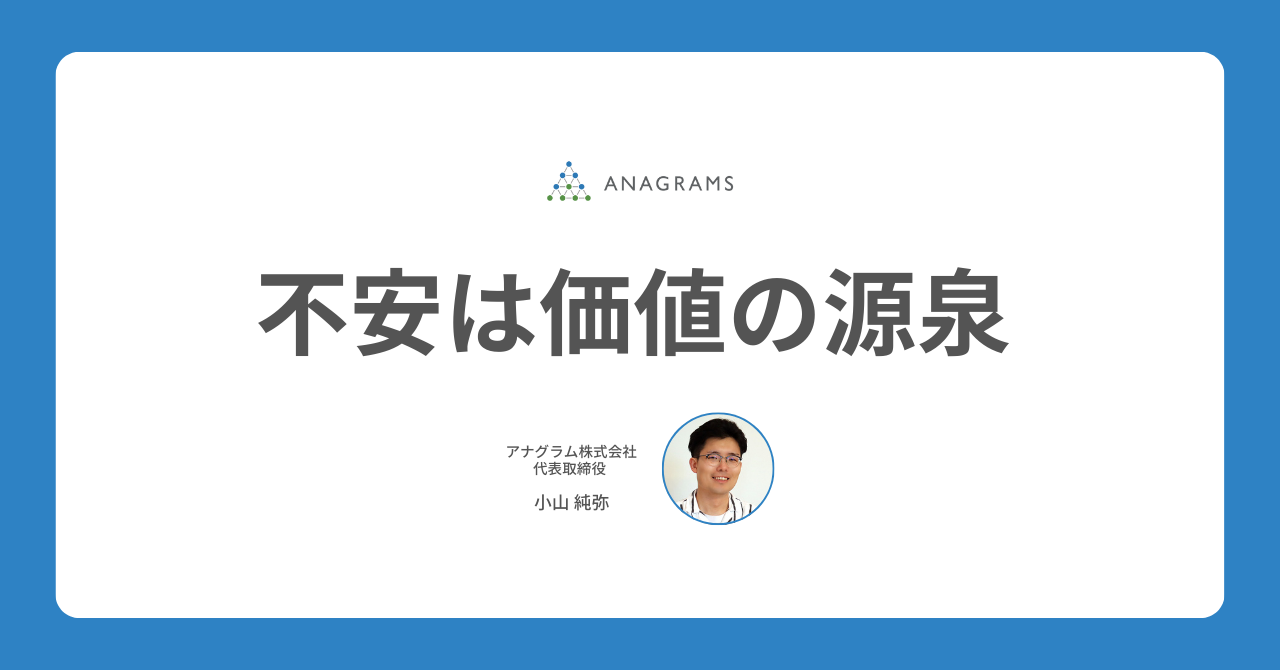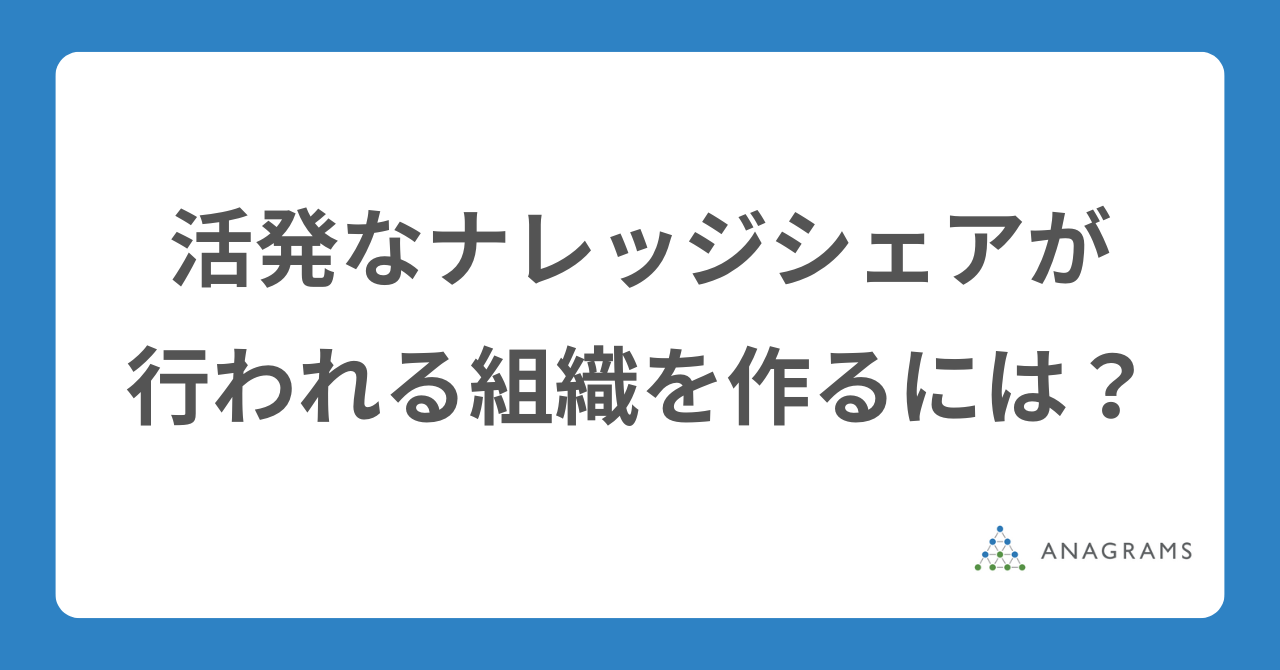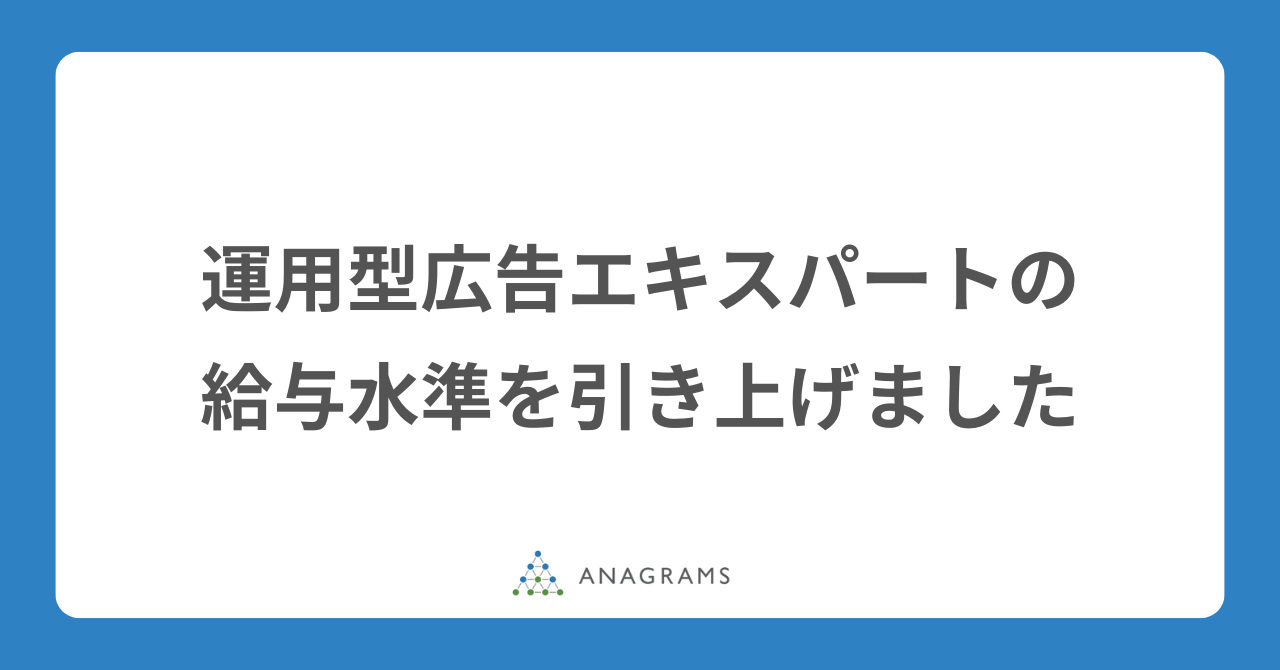
アナグラム代表の小山です。
アナグラムでは、2025年6月から運用型広告エキスパート職の最低保証年収を以下の通り変更しました。
クルー:450万(←400万)
チームリーダー:900万(←700万)
マネージャー:1300万(←1000万)
今後の採用競争激化に備えた先行投資として入口の給与もあげていますが、それだけでなくチームリーダー→マネージャーとポジションが上がる(≒広範囲かつ複雑な仕事を任せられるようになる)につれてしっかりと給与を引き上げることができる構造にもなっています。
今回の決断に至った背景には、広告運用者に求められる能力の多様化や、そのなかでもアナグラムとして大事にしていきたい「一気通貫」というコンセプトがあります。少々脱線しますが、このブログではそういった背景も含めて書いていければと思います。


目次
広告運用者に求められる能力
広告運用は、手を動かすことで確実に貢献できる要素がありつつ、同時に深く思考し、創意工夫を凝らす余白がある仕事です。
マス広告とは異なり、個人でもアカウントを開設し配信することが可能な運用型広告。ただ、実際に広告配信や計測の設定を行い、日々管理画面の成果を見ながら改善していくのには、専門知識や時間を要します。だからこそ、「広告運用を代行してほしい」というニーズは存在し続けているのです。
一方で、ただ広告管理画面上の数値を改善するだけでは、いずれ成果の伸びは頭打ちになってしまいます。
そこからさらに成果を改善していくためには、広告管理画面の改善に留まらず、ビジネス全体を俯瞰し、ボトルネックを解消していくことが必要です。
例えば、広告のクリック率は高くてもコンバージョンにつながらない場合、LP(ランディングページ)の改善が必要かもしれません。あるいは、リード獲得後のインサイドセールスのプロセスに問題がある場合、そのプロセスを改善することで広告において許容できるリード獲得単価は引き上がります。このように、管理画面の成果にとらわれずに視点を広げ、適切な箇所にメスを入れることで、広告自体の成果も飛躍的に向上させることができるのが、この仕事の面白さだと感じます。
ひと昔前は、媒体の仕様も今ほど親切なものではなかったため、「緻密なキーワード設定」「職人技のようなターゲティング」といった管理画面上の工夫に時間を割く必要がありました。しかし、近年それらはAIによって自動化・効率化されてきているため、運用者には「ビジネス全体を見て成果を改善していく力」がより求められるようになっています。
こういった時代の流れも踏まえ、アナグラムは、運用型広告に関する専門知識を持つことで管理画面上の成果改善にもしっかりと貢献しつつ、ここ数年は、ビジネス全体のボトルネックを解消するための幅広いご支援にもより一層踏み込んできました。
運用型広告の領域にとどまらず、幅広い領域をカバーする「クライアントの伴走者」としての働き方は、以下の記事でも紹介しています。
「一気通貫」と「支援領域の拡大」をどう両立するか
ただ、支援の幅が広がれば広がるほど、担当者に求められる知識や経験が増えることになります。
アナグラムは、できる限り分業をせず、広告運用・クライアントワークなどを1人の担当者が意思決定しながら行う「一気通貫」の体制をとっています。
分業をしている会社であれば、支援領域が広がるにつれてLP担当、CRM担当…というように、担当者を細分化していくのがオーソドックスなやり方だと思われますが、アナグラムの根幹である「一気通貫」と「支援領域の拡大」をどう両立していくかという課題には、当然向き合う必要がありました。
実際、採用面接でも「支援の幅が限定されないのは楽しそうだが、実際に機能するものなのか?」と聞かれることも多いのですが、具体的には以下の2つの取り組みによって、「一気通貫」と「支援領域の拡大」の両立を実現しています。
① 広告運用の経験を一切問わず、ポテンシャルを重視する採用戦略
② 知見共有・ヘルプセンターなどでの全社的なフォローアップ体制
① 広告運用の経験を一切問わず、 ポテンシャルを重視する採用戦略
入社時に、広告運用の経験は一切問いません。それ以上に、「幅広い領域を学び成長できるか」「より抽象度の高い課題解決に挑戦できるか」といったポテンシャルを重視します。
なぜならば、このようなポテンシャルを持つ人材は、未経験からでも「一気通貫」で多様な業務をこなし、支援領域を自ら拡大していく原動力となりうるからです。これはそのまま、クライアントの成果に直結します。
直近では8割ほどのメンバーが未経験で入社しており、バックグラウンドも多様です。そして、その多様なバックグラウンドや強みを活かすために、マネジメント層には、型にはまった業務管理ではなく、メンバーが自律的に思考し、行動できるような環境整備が求められます。
② ヘルプセンター・グロースハック・知見共有などでの全社的なフォローアップ体制
アナグラムでは、「自立」よりも「自律」が求められます。つまり、一人ですべての能力を補おうとするのではなく、適切に人に頼りながら物事を前に進められる力こそが重要だということです。
Slackの「ヘルプセンター」というチャンネルでは、自分一人では補いきれない視点をすぐに質問することができます。実際、毎日数件は質問が投げかけられており、それに対して早ければ数分で回答がもらえます。
また、定期的に自分の担当している案件を他のメンバーに見てもらうグロースハックという機会があり、さまざまな視点からの改善案が出てきますし、案件を運用するなかで得た知見を社内のNotionに共有する文化もあります。
これらの取り組みによって、知識や経験が足りない部分を会社としてフォローアップしたり、担当者の盲点をカバーすることができ、「一気通貫」でありながら、クライアントに対して高品質で幅広い支援を提供できる体制を実現しています。
人の可能性を信じ、未来に投資する
なぜここまでしてアナグラムは「一気通貫」にこだわるのか。
それは、私たちが「人の可能性を信じ、人こそがプロダクトだと考える会社」だからです。
意思決定を一部の人が担い、実務は領域ごとに最適化していけば、スケーラビリティは担保されるでしょう。しかしそのやり方は、人が本来持っているはずの「豊かな思考」や「多角的な視点」を制限してしまう危険性もはらんでいます。
「部署ごとのノルマに縛られて、本質的な提案ができない…」
「クライアントではなく、つい上司が喜びそうな提案をしてしまう…」
働くなかで、こんな経験をしたことはないでしょうか。
せっかく面白い発想やユニークな視点を持っていても、それを活かせない。これは個人にとっても組織にとっても大きな損失です。だからこそアナグラムでは、「一気通貫」体制とそれを支える仕組みによって、メンバー1人1人が持つユニークな発想や視点を最大限に尊重し、クライアントへの提供価値に直結させることを目指しています。
ここまで述べてきたように、「運用型広告で日々の調整ができる」レベルと「運用型広告を用いつつ、ビジネスをドライブできる」レベルには大きな開きがあります。
アナグラムの運用型広告エキスパートに求めるのは、後者です。ビジネスの全体像を理解し戦略を構想する抽象度の高い視点から、具体的な施策を実行し成果を出す実行力まで、非常に幅広い能力が求められます。このような広範かつ高度な領域をカバーできるポテンシャルを持った人材を採用し、育成し、そして長く活躍してもらうこと。それこそが、アナグラムの持続的な成長の鍵だと考えています。
今回の給与水準の引き上げは、まさにこのための「未来への投資」なのです。
加えて、「運用型広告を用いつつ、ビジネスをドライブできる」能力を持ち、かつ、複雑性の高いマネジメントによって未経験者を含む多様なメンバーを一人前のエキスパートに育て上げ、チームとして最大の成果を引き出すことができる人材は、市場において極めて希少な存在です。よって、マネジメントを担うチームリーダー、マネージャーの給与水準も大幅に引き上げています。
給与水準の引き上げは、あくまでアナグラムの思想を実現するためのいち手段にすぎません。だからこそ、その背景を知っていただきたいと思い、ここまで書いてきました。
「自分」というプロダクトをもって、クライアントのビジネスに貢献することに面白さを感じる。抽象から具体まで、幅広く経験できる環境で力をつけていきたい。ここまで読んでくださった方のなかに、そんな方がいらっしゃったら、ぜひ応募をご検討ください。