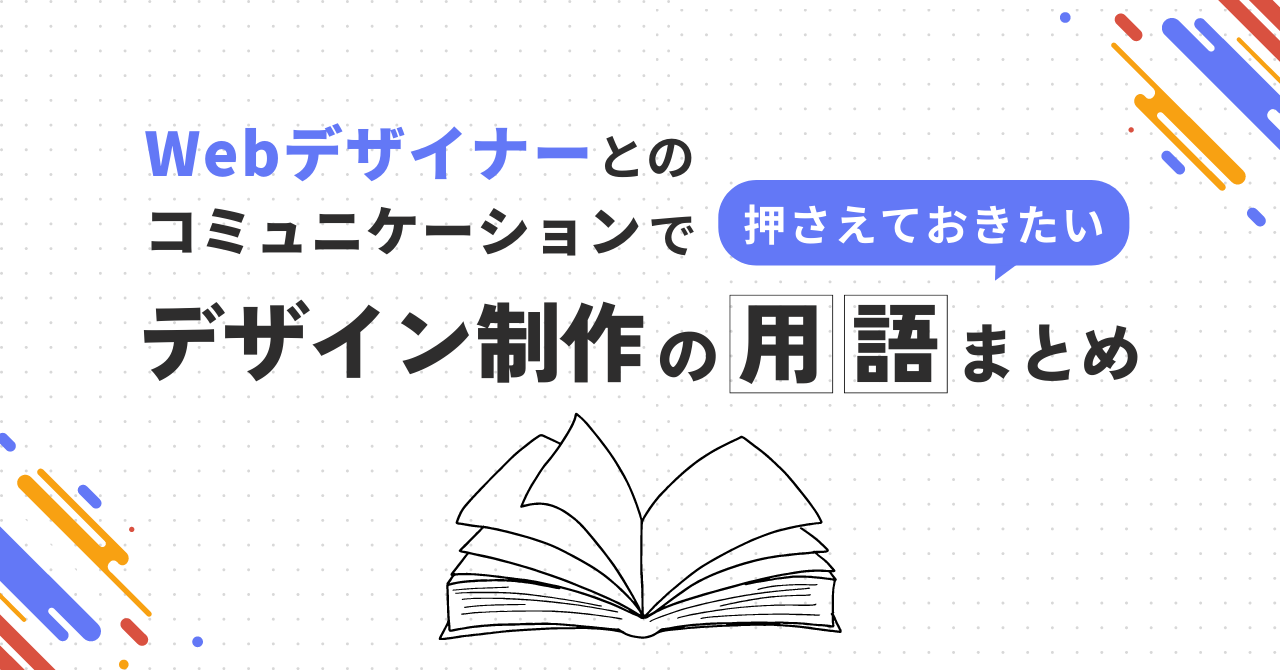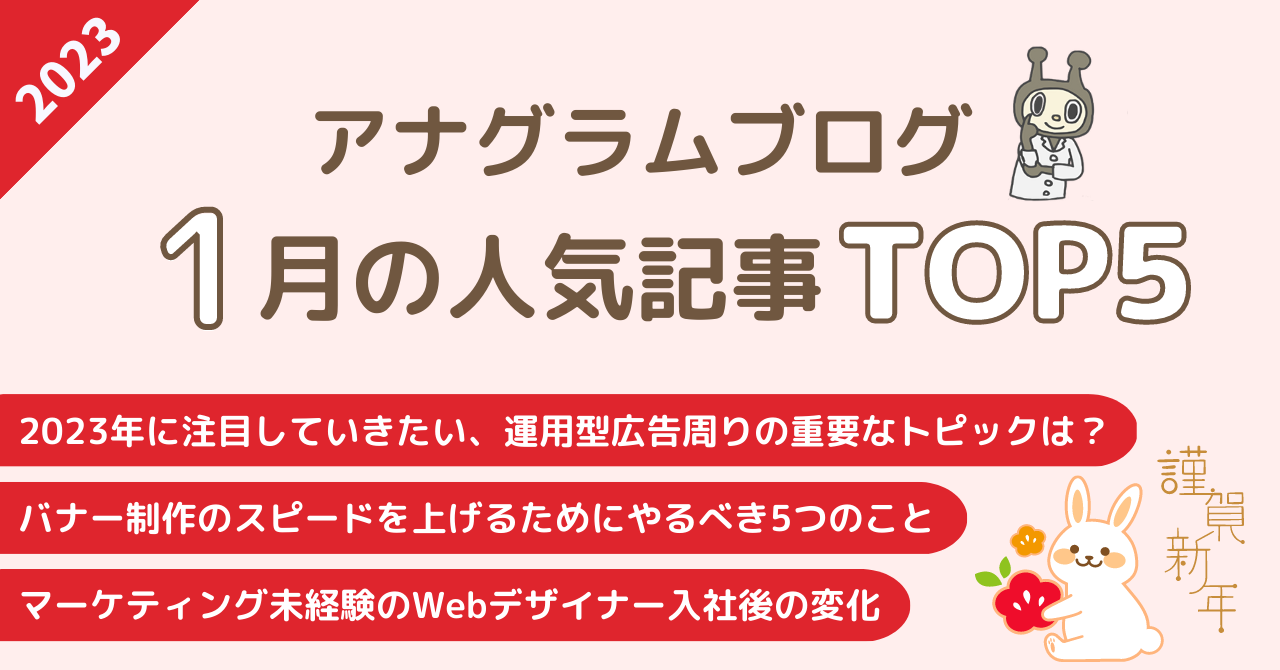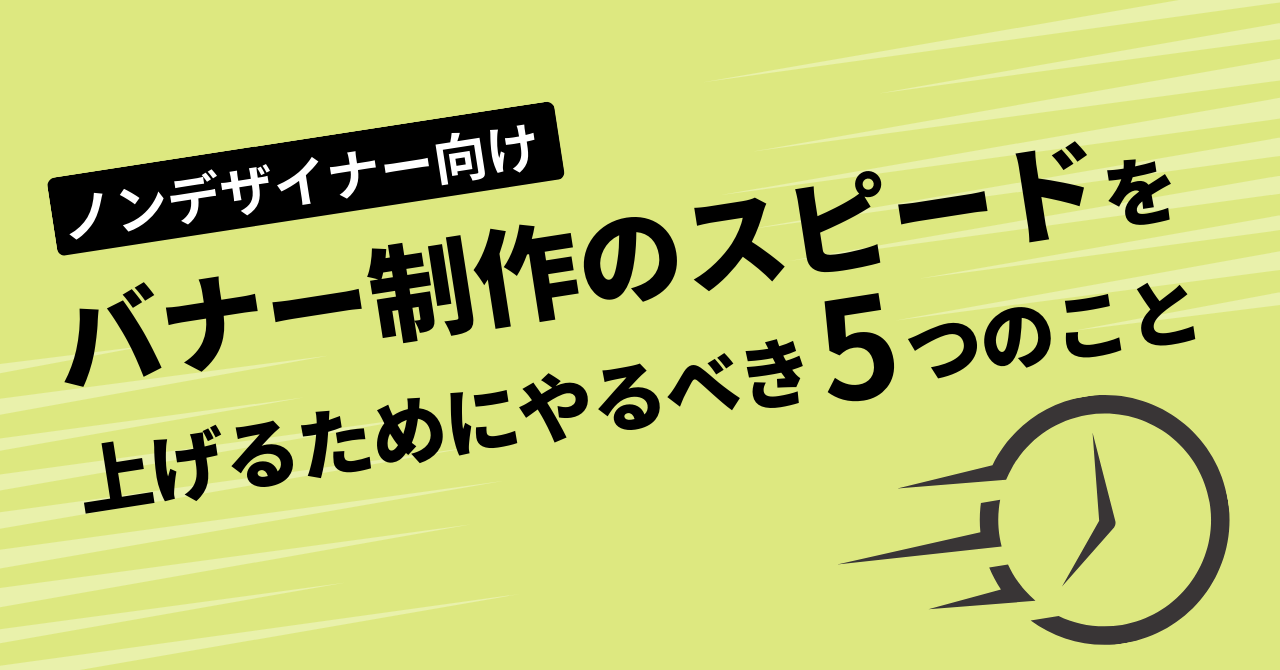
広告運用業務のなかで「自分でもバナーを作れるようになりたい」と考え、バナー制作に挑戦している方もいるのではないでしょうか。
そんな中、バナー制作に時間をかけても思うような仕上がりにならなかったり、どこまで作り込めば完成したと言えるか分らずに想定外に時間がかかってしまうことはありませんか?
デザインを良くすることはもちろん大切ですが、広告運用で成果をあげるためにはバナーの1つ1つに時間をかけすぎてはいられない状況もありますよね。
この記事では、バナー制作のスピードを上げるためのコツや考え方をお伝えします。
※この記事ではデザインを視覚的な表現のことと定義して扱います。


基本のフォントを決めておく
フォントにはたくさんの種類があります。OSに初期からインストールされているもの、無料で商用利用できるもの、デザインツールに盛り込まれているものなど、実にさまざまな選択肢があるため毎度1から吟味していては時間がいくらあっても足りません。
バナーのフォント選びで重視するべきなのは、可読性・読みやすさです。企業が生活者に伝えるべきメッセージがきちんと伝わることが絶対条件です。クセがなく読みやすいフォントを何種類か基本のフォントとして決めておくことで、フォント選びの時間が大幅に短縮できます。
たとえば私は以下のフォントを基本にしながら、より適切なフォントがある・ありそうな場合のみ時間をかけて検討しています。
まずは基本のフォントから選定できないか検討し、別のフォントにすべき理由を明確に説明できる場合だけ、他の選択肢を検討すれば十分です。
もしかすると、毎度同じようなフォントを選んでしまうことに後ろめたさを感じてしまう人もいるかもしれません。たしかにフォントによってデザインの印象は変化しますが、じっくり読まれることの少ない広告の場合は、読みやすさを優先してフォントを選ぶことは決して悪いことではないのです。もし広告に変化を加えたいのなら、キャッチコピーを磨くなど、他にも時間を割くべき選択肢がたくさんあることも忘れてはいけません。
商用利用可能で使い勝手の良いフォントとして、よく紹介されているのが「Noto Fonts」です。OSの初期フォントはデザインに適したものが少ないため、まずはインストールしてみることをお勧めします。
参考:Google フォント
画像素材は要件を決めてから探す
フォントと同じく、画像素材選びも時間をかけてしまいやすいポイントです。私もデザイナーとして経験が浅かった頃は、素材サイトを眺めているだけで気づけば数時間経っていたことがありました。
写真素材サイトから理想どおりの画像を見つけることは難しいです。というより、イメージが細部まで具体化されていないにも関わらず、ピッタリな画像を見つけようとする矛盾した行為によって時間が掛かってしまうのではないでしょうか。(私の体験談でもありますが……)
理想どおりが難しいのなら、及第点にできる条件を決めましょう。たとえば「30歳前後に見える」「日本人女性1人」「自宅のソファーで」「スマホをいじっている」「笑顔」のように、どのような要素が満たされていれば及第点なのかを事前に決めてから画像素材を選び始めることで、使用する画像を決断しやすくなります。
選択肢が複数ある場合は、より重視するポイントを決めて絞り込みます。反対に、複数のストックフォトサービスを横断しても全く見つからない場合は、写真合成・加工やキャッチコピーによる説明でカバーできるよう条件を緩和するか、撮影も視野に入れましょう。
レイアウトの基本を押さえる
情報がスムーズに伝わるレイアウトにはある程度の法則が存在します。
特に広告バナーは、ユーザーに一瞬で興味を持ってもらうために、どこからどの順番で読めばいいのか考えなくても理解できるようになっていることが大切です。基本的に、人の視線は左上から右下にかけて「Z」のカタチで移動します。(文字が横書きの場合)
視線の動きの法則に従って考えると、レイアウトのバリエーションは意外と多くありません。例えば以下のようなレイアウトは汎用性が高く、さまざまな広告バナーに取り入れられていますよね。
つまり、レイアウトはオリジナルのものを無理に考案するよりも世の中にある事例をどんどん参考にしてしまったほうが、短時間で効果的なバナーに近づけられるということです。
上の例からわかるように、他のバナーと同じようなレイアウトであっても、コピーや写真などにオリジナリティがあれば全く違うバナーに仕上がるはずです。
フォントと同じように、自分の中で基本のレイアウトをいくつか決めておくことで時間短縮に繋がると考えます。
細部にこだわりすぎない
デザインの細部まで突き詰めるほど、多くの時間が必要になります。しかし、改善にスピードが求められる運用型広告において、細部に費やした時間に見合うだけのリターンがあるのかはまた別です。
バナーではメッセージが齟齬なく伝わることが大切です。デザインの細部を改良することで、メッセージの伝わりやすさが大きく向上する場合は時間を割く意味があります。
たとえば以下の3枚のバナーであれば、左と中央のバナーは視認性を改善したことで成果にも影響がありそうです。しかし、中央と右の画像は細かい装飾の違いはあるものの、パッと見た時の情報量にほとんど違いがありません。
時間をどこまでかけるべきなのか、工数対効果も意識しましょう。
余白を必要以上に恐れない
バナーの面積は限られているので、少しでも多くの情報を盛り込んだほうが得だと考えるかもしれません。しかし情報が多すぎると1番伝えたいメッセージが曖昧になったり、いかにも広告っぽい雰囲気になってしまって無視されるなど、逆効果になることも考えられます。
余白があるからこそ、残された情報が強調され、効果的にメッセージを伝えられる場合もあることを覚えておきましょう。
まとめ
この記事で紹介した内容は、中堅デザイナーでも気を抜くとつい時間を使いすぎてしまうポイントです。広告運用の現場では、バナー1つあたりの完成度を高くするよりも多くのバリエーションを試し、より良い成果があがる表現を模索することが優先される場面もあります。バナーの見た目で損をしない程度の完成度に短時間で到達できるようになれば、広告運用で成果を改善するにあたって大いに役立つでしょう。
新しいことにチャレンジするとき、最初から自分の頭だけで思考してゼロベースで取り組むと、時間がいくらあっても足りません。バナー制作などのデザイン業務も同じで、まずは世にあるバナー広告を観察し、再現することから始めてみると少しずつ理解が進みます。
なかなか思うようにバナーの制作ができないという方は、今回紹介した内容に心当たりが無いか、1つずつ確かめてみてください。