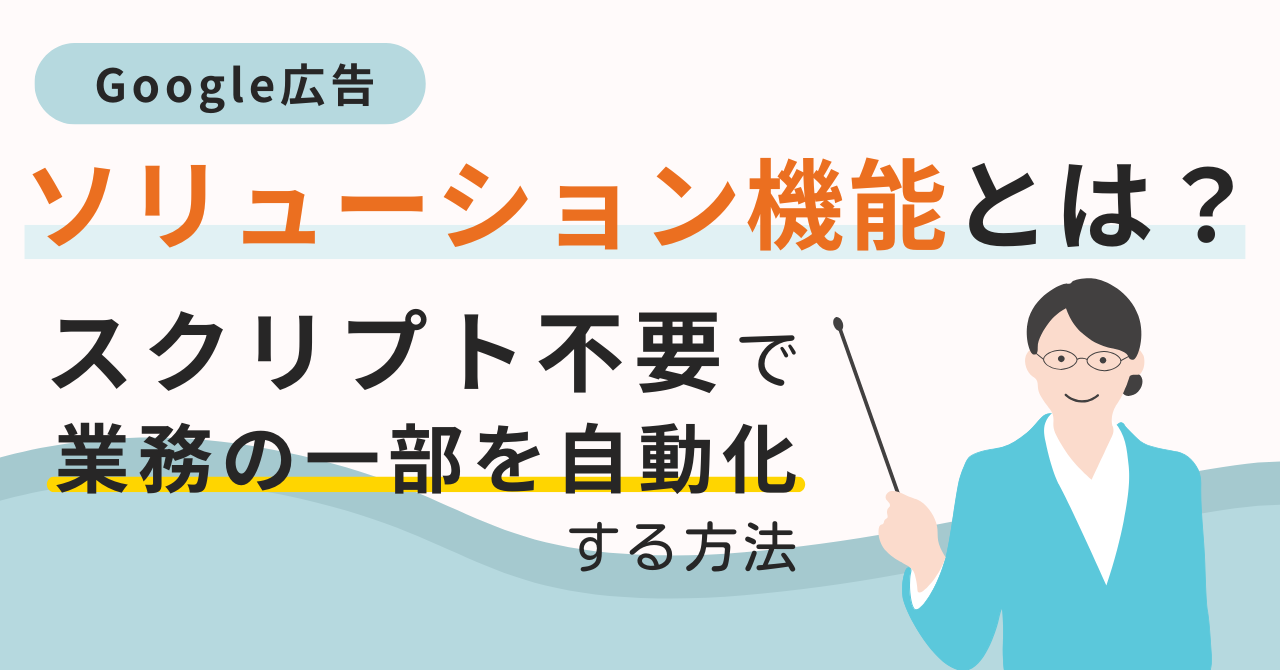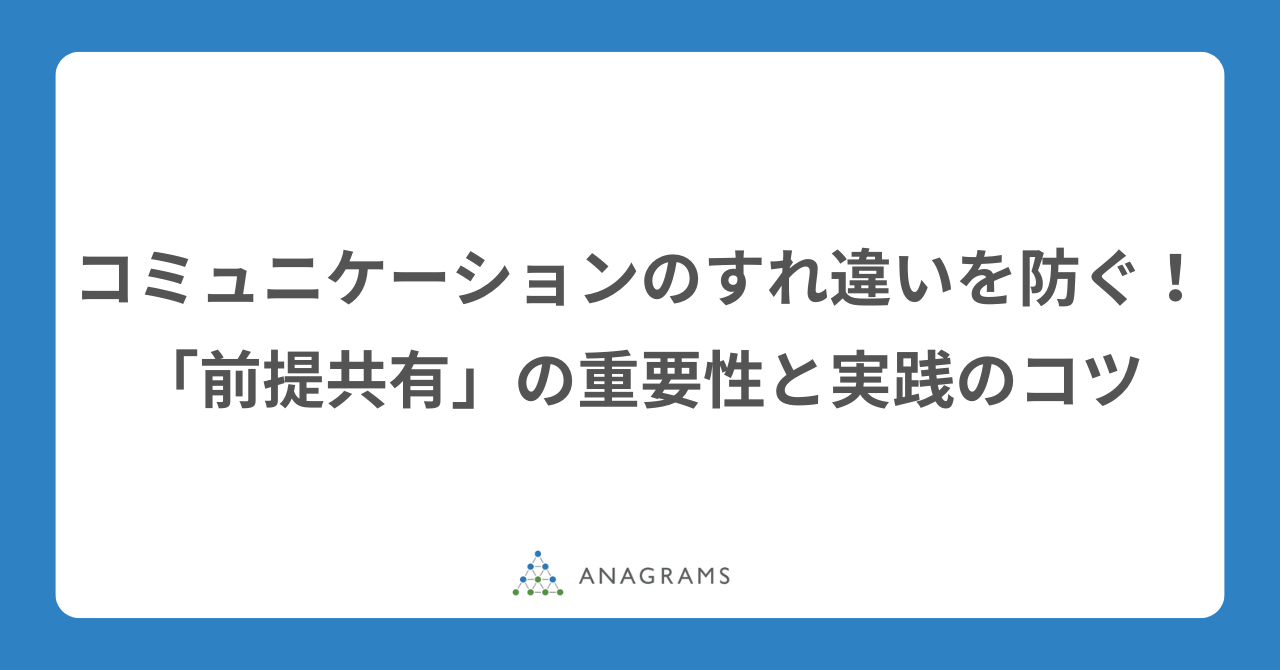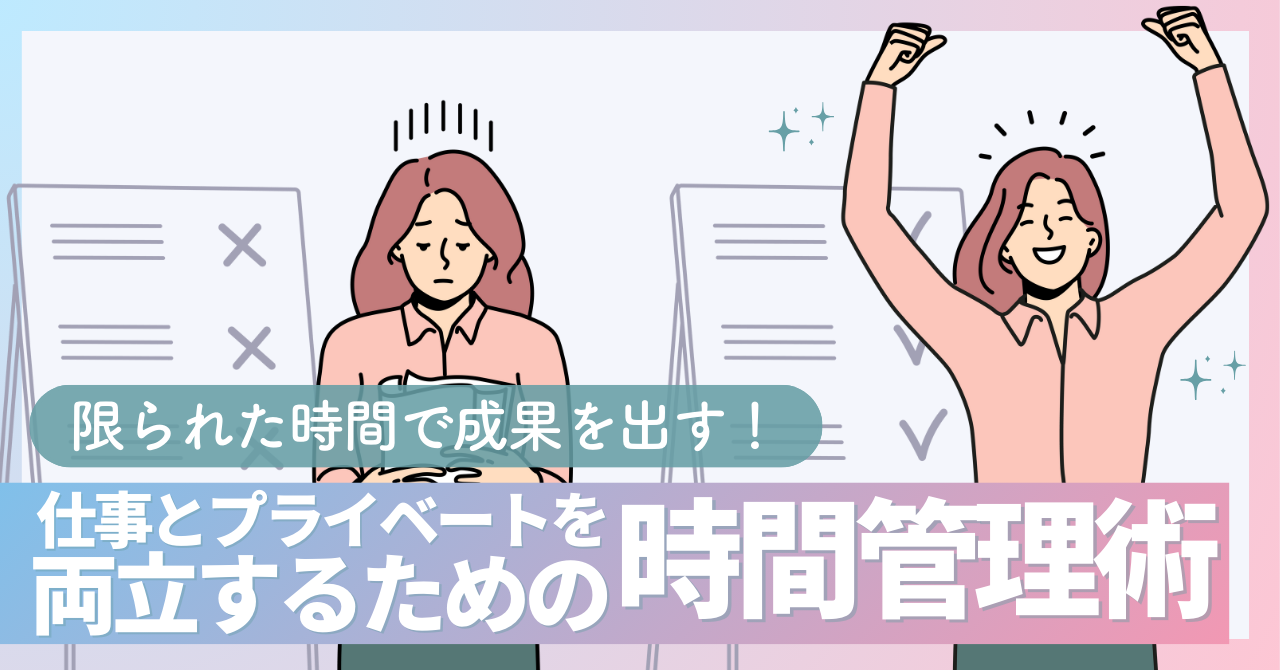Google アドワーズが提供開始となってから15周年のタイミングで発表された、管理画面のリニューアル。まだベータ版の段階ではありますが、いままでの管理画面にはない、さまざまな機能も実装されています。
AdWordsリニューアル版管理画面で改善を目指すもののひとつとして「重要なデータを即座に手に入れられるようにする」を掲げています。
今回は「さまざまな分析情報を浮き彫りにして、より実用的な形式でデータを視覚化できる機能」のひとつであると考えられ、こちらのコンセプトに基づいて随時改善されている「概要ページ」について、概要ページに表示される数多くあるカードの中から、特に有用だと思われる概要カード4つとインサイトカード3つの、合計7つをピックアップしてご紹介します。
参考:モバイル時代を見据えた AdWords 管理画面の改善 - Google 広告主コミュニティ


目次
概要ページとは
AdWordsリニューアル版の管理画面にログインした時、はじめに表示されるページです。
概要ページには、それぞれのアカウントの設定や掲載結果に合わせて Googleが選択したカードと呼ばれるデータが表示されます。なお、キャンペーンや広告グループ単位でも、概要ページが用意されており、そのキャンペーンや広告グループに関するカードが表示されます。
概要ページに表示されるカードには大きく分けて次の2種類です。
- 概要カード
- インサイトカード
「概要カード」にはアカウント、キャンペーン、広告グループごとにまとめられ、選択した期間の掲載結果の全般的な概要が表示されます。全体的な期間を変更すると、概要カードに表示されるデータも変わります。文字通り、アカウントの「概要」を直感的に把握し課題のある箇所にあたりをつけるのに役立ちます。
「インサイトカード」とは、選択した期間に関係なく、掲載結果のデータに何かしら大きな変化・特徴的なパターンが生まれた場合、その測定データを表示してくれるカードの事を指します。広告掲載の成果を最大化するうえで役立つ・見落としやすい指標変化などが表示されることがあります。
確認するには手順が多かった・見落としがちだった指標変化も、インサイトカードが表示してくれるケースがあり、「分析検証~改善までの時短化」といった効果が期待できるカードです。
概要ページの基本的な使い方

概要ページは、アカウント・キャンペーン・広告グループの各単位のページメニューで「概要」タブをクリックすることで確認することができます。

また、特定の期間を指定して比較するには、管理画面右上の期間選択ツールをクリックします。[比較]を有効にすると任意の期間同士を比較することが可能です。
Google アドワーズの公式ヘルプページには、カードの種類は今後も増やしていく予定であると記載があります。
なお、管理画面上の表記とヘルプページの表記が統一されていないカードが見受けられますが、本記事では2018年4月時点のヘルプページの表記を正としております。
便利な概要カード4選
キャンペーンまたは広告グループの大規模な変更(最も変化の大きい要素)

キャンペーンまたは広告グループで掲載状況(費用やクリック数、コンバージョンなど)の変化が大きいものを簡単にチェックすることができます。
キャンペーンやその他の画面でも、期間を指定しての数字の比較は行なえますが、概要カードでは数字だけではなく、横棒グラフで増減が示されているため、優先的に原因を探るべき変化の大きいキャンペーンや広告グループにすぐさまあたりをつけられます。
曜日・時間帯別の掲載結果

曜日・時間帯ごとの掲載結果を確認できるカードですが、筆者のオススメは、曜日×時間のヒートマップ形式での表示です。
「曜日と時間」で表示した場合、選択した指標の数が多い時間・曜日ほど、青色が濃く表示されます。白色に近づくほど、少ない事を表します。
月次や週次で期間ごとにまとまった数字は把握できても、意外と見落としがちなのが曜日と時間の関係です。自身の行動を思い浮かべていただければと思いますが、多くのひとは曜日ごと、時間ごとにある程度の行動パターンが決まっていることは少なくないはずです。
一週間の内、広告がよく見られているタイミングはいつか、コンバージョンにつながるクリックがされているのはいつかなどユーザーの行動を俯瞰して確認する助けになります。
ユーザーはどんな行動をしているのか、その行動に寄り添った広告出稿ができているかなど、現在の広告運用を見つめ直すひとつのデータとして確認してみてください。
オークション分析データ

オークション分析レポートは、同じ広告オークションに参加している他の広告主と検索連動型広告の掲載結果を比較することができるレポート機能です。
通常のオークション分析レポートでは、各指標を横並びの数字で確認できますが、概要カード上では、たとえば「平均掲載順位×インプレッションシェア」のように2つの指標を任意で組み合わせて散布図として表示できます。競合と比べて平均掲載順位にどれだけの差があり、それがインプレッションシェアにどの程度影響しているのかを直感的に把握できます。仮に競合の平均掲載順位が上位でインプレッションシェアが高いようであれば、掲載順位を高めることでインプレッションを増やせる可能性があります。
このように、掲載機会の損失やよりシェアを増やす余地を素早くキャッチアップし、次の対応に活かすことができます。
Google で広告が表示された上位の検索語句

Google 検索で広告の表示につながった検索語句を確認できるカードです。
このカードの「ワード数」のタブは、検索に使われた特定のフレーズごとにデータが集計されたものです。
たとえば、あるフレーズを使った検索からの流入が増えている場合に、キーワードを追加したりそのフレーズにあわせて広告文を変更したりすることが可能です。また、意図しないフレーズを発見できる場合もあるでしょう。
もちろん検索語句レポートを定期的に確認することも大切ですが、より頻度高く目に入れることが新しい発見につながるケースがありますので、ぜひ定期的に確認しておきたいカードです。
参考:最高のキーワード洗い出しツール、検索語句レポ-ト活用術
便利なインサイトカード3選
新しい単語

広告が表示されたGoogle 検索において、最近(過去7日以内)使われた新しい単語を確認できます。
少々古いデータですが、Googleは「過去6ヶ月に検索された事がない、新規検索語句の割合が20%ある」と発表しています。これまでになかった検索の兆候を捉えることで、場合によってはキーワードの追加や広告文の作成などの対応をいち早く準備することも可能です。
参考:「部分一致」でまだまだ広がる!マッチタイプの特性を利用したキーワード拡張による検索連動型広告の可能性
このカードが表示されていたらまずはチェックしてみるのをオススメします。
上部 vs その他

検索結果の上部とその他に表示された広告では、ユーザーからの認知のされ方は大きく変わります。Googleでは、検索結果右側のテキスト広告枠が廃止されてからは、一層その傾向が顕著になっています。
参考:Google、検索結果右側のテキスト広告枠を全世界で廃止へ
たとえば、広告の表示回数は大きく変動していないのに、広告がクリックされなくなってしまったという場合、それまで検索結果の上部に表示されていたのに気がついたらその割合が大幅に減少していたというケースもよくありますよね。一定の期間でクリックが減少している状況を発見してはじめて状況が明るみに出ることも多く、把握するのがなかなか難しい状況です。
このカードによってこのような変化をいち早く知ることで、意図しない掲載順位の降下などにすぐさま対応することができます。
似たカードに「端末シフト」があります。

特定の端末タイプから発生した広告の表示回数の割合が、大幅に変化した場合に表示されることがあるカードです。
要因はさまざまですが、特定の端末のみ大きな変動があったことを意味しており、場合によってはデバイスの入札単価調整比を調整が必要です。
掲載結果のペースを時間単位で確認

その日のクリック数などが、通常の同じ曜日のペースに対して大きく隔たりがある場合に表示されやすいカードです。
当日の掲載状況は翌日に集計して把握されることも多く、「上部 vs その他」と同様にすぐには気が付きにくい情報です。その日の掲載状況がふだんと違うことにいち早く気がつければそれだけ対応も迅速に行えますよね。概要ページにこのカードが出ていたら要チェックです。
最後に
アカウント分析において、構成を網羅的に見るとこも重要ですが、デバイスや検索語句、曜日や時間ごとの成果など、確認ポイントが多岐に渡る日々の広告運用においてはすべてを網羅することは現実的ではありません。また、細部ばかりを見ていると近視眼的になり、大局を見失うことも多いでしょう。
今回ご紹介した概要ページは、カードを表示させる・表示させない、をこちら側でコントロールすることができません。コントロールできないことは比較的ネガティブに捉えられがちですが、人間は基本的に見えていないものや、見ようとしないものは目に入らないため、
概要ページは見るべきデータを自動的に視覚化して提示してくれることに価値があると筆者は考えます。
機械学習による広告運用の自動化が進んでいく中で、何がどう調整されているかわからない時に、概要ページのようなビジュアライズされたデータはその状況を明快に理解するために、これから先ますます需要が高まるでしょう。
また、カードの内容は必ずしも正しいとは限りません。なぜなら数字に現れない個別の事情は加味することができないためです。すぐに鵜呑みにするのではなく、いまの運用方法とカードの内容を照らし合わせて取り入れていくのをオススメします。