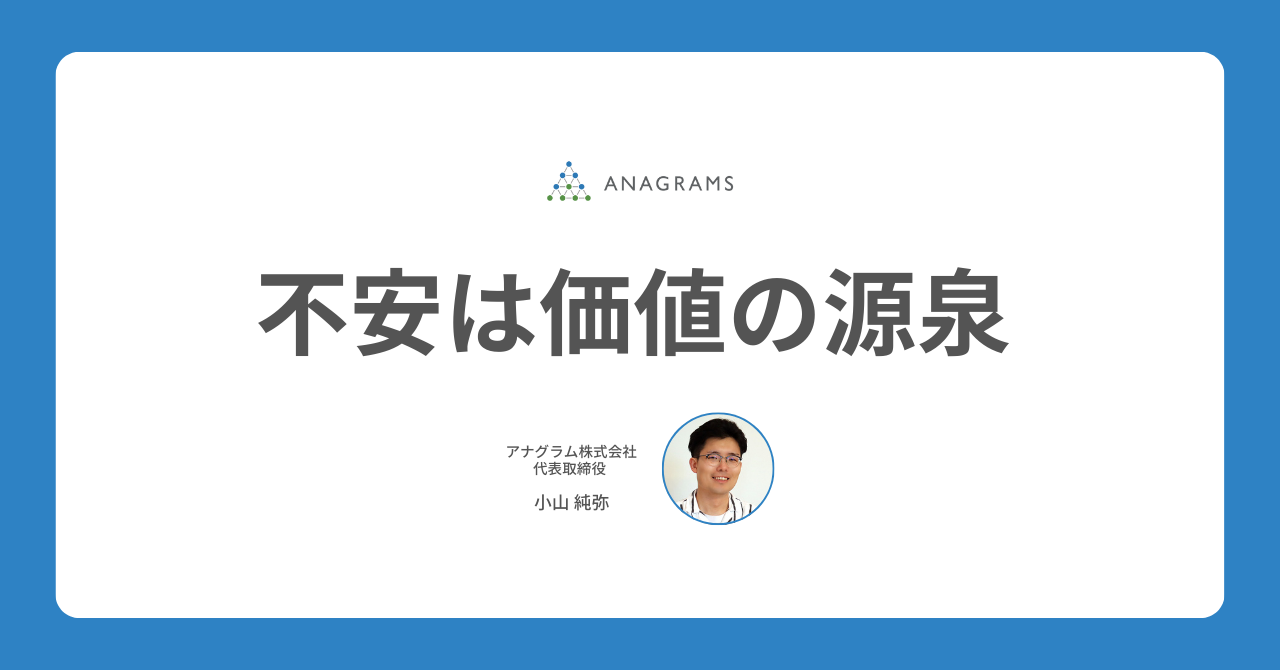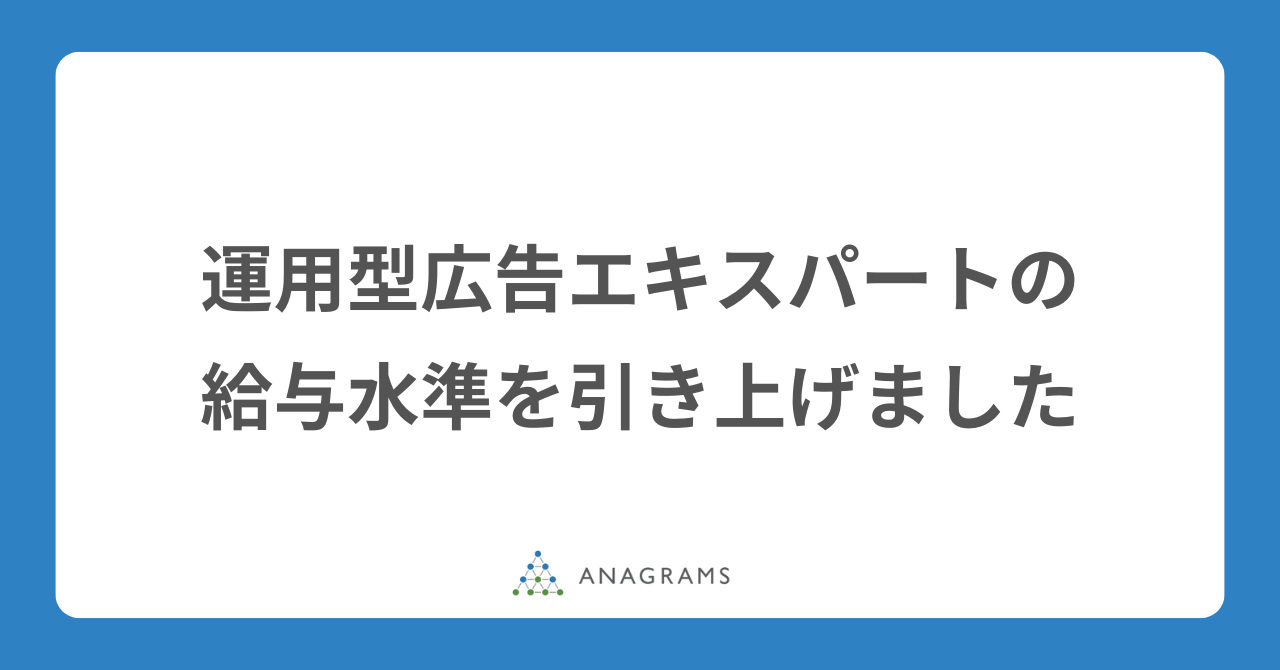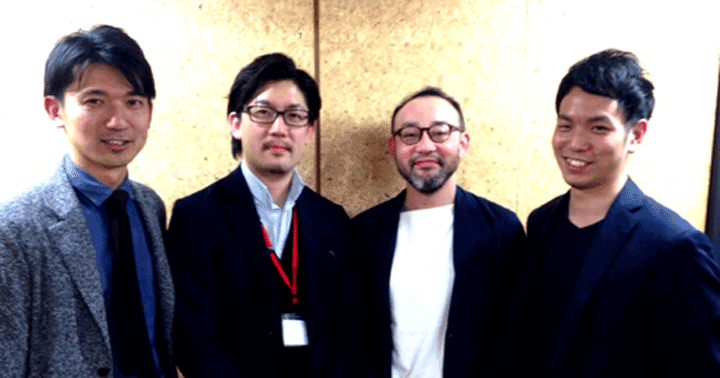アナグラムでは、社内のメンバー総出でのアカウント分析会、通称「グロースハック」を毎週実施しています。
今回はこれまで100社以上のアカウントを分析する中で見えてきた、頻出のアカウント改善ポイントをまとめてみました。


目次
- アカウント分析勉強会「グロースハック」とは?
- アカウント改善11のポイント
- 1.検索連動型広告の設定に過不足がないか?
- 2.ディスプレイ広告ターゲティングを十分に活用できているか?
- 3.費用対効果の悪いセグメントに広告費を投じすぎていないか?
- 4.自動化を過不足なく適切に活用しているか?
- 5.媒体の機能を十分に活用し切れているか?
- 6. リマーケティング・リターゲティングの配信設計がビジネスにマッチしていない
- 7.過去成果が悪くて停止したプロダクトや配信設定、媒体などにもう一度チャレンジできないか?
- 8.表面的な指標に縛られすぎて機会損失が発生していないか?
- 9.広告文やランディングページの切り口や見せ方は適切か?
- 10.選択している広告媒体は適切か?
- 11.そもそもプロダクトやサービスそのものや、戦略・ポジショニングを見なおす余地はないか?
- まとめ
アカウント分析勉強会「グロースハック」とは?
ピックアップした1社の広告アカウントを原則全運用担当メンバー40数名(2019年5月時点)で毎週分析する会で、2014年ごろから連綿と続く取り組みです。
参考:アナグラムの文化、グロースハック(Growthhack)とは?
サービス改善を意味する広義の「グロースハック」よりやや意味が狭く、広告アカウントの改善やその周辺領域にフォーカスしています。
平均1,000文字程度のアウトプットが全社員流れてくるのは内容・流速ともに圧巻です。40数名ともなると、自分だけだと絶対に思いつかない知見や気付きがあります。筆者も5年以上広告運用に携わっていて広告運用の技術に関してはそれなりに自信がありますが、グロースハックを通じていまだに毎回新たな発見が5つ以上はあります。
広告アカウントの改善ポイントは多くがビジネスごとに固有なことも多いため、本記事の内容をそのまま適用して改善を図る、というものではなく、さまざまな案件の参考となるよう一般的な内容に抽象化したり、取り扱っていない商材に置き換えたりしています。
それでは見ていきましょう!
アカウント改善11のポイント
1.検索連動型広告の設定に過不足がないか?
運用型広告は、詳細なターゲティングが可能な分、以下のような機会損失を招いてしまうことがあります。
- ターゲティングなど配信規模を絞りすぎてしまうケース(目に見える機会損失)
- 全く思いつかなかったキーワードでも獲得が見込めるケース(見に見えない機会損失)
検索連動型広告のターゲティングについてよくある改善ポイントをもう少し具体的にケースごとに見ていきましょう。
目に見える機会損失
キーワードが登録してあるものの、ボリュームが大きく重要な検索語句で掲載順位が低すぎて、機会損失を起こしている
すでに登録しているキーワードでも掲載順位が低すぎてほとんど露出できていないケースも要注意です。キーワードが登録されていても、掲載順位が低すぎると登録していないのと同じです。
目に見えない機会損失
新たにキーワードを追加する余地があるケース
現在出稿を意図していない検索語句に出稿を追加すると、新たに獲得が見込めるケースがあります。キーワード追加の余地があるのは以下のケースなどです。
例)「+看護師 +求人」というキーワードが登録されているのに「+看護師 +募集」「+看護師 +応募」が抜けている。
よくあるのが「看護師」(完全一致)が抜けているケースです。「看護師 求人」などと比べて検索意図が読みづらいものの、求人を探す意図も多くを占めます。予算や費用対効果次第ですが、大きな検索ボリュームのキーワードに対しては出稿を検討するべきです。
また、以下のようなキーワードも出稿の対象となってきます。
- 代替品となりうる、別ジャンルのサービスなどのキーワード
- 関連度はそれほど高くないものの、検索ボリュームが大きくかつ競合他社が出稿しづらいキーワード
注意深く想像力を働かせるのが大切です。
想像できるキーワードを「徹底的にキーワードを網羅し登録する」という選択肢もあるにはありますが……次々にこれまでに無い検索語句が生まれる中では現実的ではありません。機会損失を少なくするには次のような対策が有効です。
部分一致のキーワードを上手く活用することで検索語句の幅を広げる
部分一致は、もっとも多くの検索語句を広告表示の対象とします。運用歴が長いと、過去の不用意な拡張で関連性の薄い検索語句への露出のイメージもあると思いますが、現在では自動入札や機械学習が進み、以前に比べ的はずれな配信は比較的抑えられているように感じます。「ユーザーの最近の検索内容も考慮に入れられる」部分一致は、活用次第でこれまで広告を掲載できていなかった検索語句へも幅を大きく広げられるので利用を検討してみてもよいでしょう。
人間が意図して想定できるよりも世の中は複雑です。思いもよらぬところに広告主の商品やサービスを必要としている人がいることも。そのため自分が全く想像できないキーワードでも獲得が見込める可能性は常にあります。
2.ディスプレイ広告ターゲティングを十分に活用できているか?
検索連動型広告と比べディスプレイ広告は商材を選びますが、出稿してみると費用対効果が見合って配信できることも多いです。
各媒体ごとに強力なターゲティングがあるので、類似商材で獲得ができている場合などは追加が検討できます。随時媒体側でターゲティングも追加アップデートされているので、思いがけず商材にピッタリのターゲティングが見つかることも少なくありません。
よくターゲティングの追加提案で出てくる効果の出やすい各媒体のメニューは以下などです。
Google 広告
- コンテンツターゲット
- 購買意向の強いユーザー層
- カスタムインテントオーディエンス
Facebook広告
- 類似オーディエンス
YDN
- サーチターゲティング
- デモグラフィックターゲティング
Twitter広告
- キーワードターゲティング
- フォロワーターゲティング
リマーケティング以外のサイト未訪問ユーザーに向けたディスプレイ広告に新たに取り組むときに優先的に検討してもいいかもしれません。
3.費用対効果の悪いセグメントに広告費を投じすぎていないか?
さまざまな切り口で入札単価の調整が可能です。特定のセグメントだけ費用対効果が悪化してしまっているケースもあります。
入札単価調整が適切ではないケース
たとえばGoogle 広告ではデバイス別、オーディエンスリスト別、性別・年齢別などで入札単価の調整率が調整できます。自動入札を利用していない場合は、データを見て手動で調整するのが有効です。
調整には広告管理画面で分割表示をしたりレポートをダウンロードする手間がかかります。ひと手間かかるため見落としがちな調整項目です。とくに最近広告運用の世界に入ってきて、自動入札にしか接したことが無い担当者等だと、手動で細かく入札単価調整をする視点やスキルが抜けていることもあります。
細かな調整ではありますが、アカウントによっては大きな改善ドライバになるケースもあります。目下の調整に加えて、管理画面を定期的に見に行くよう習慣化・仕組みを作ることが大切です。
4.自動化を過不足なく適切に活用しているか?
多くの運用型広告の媒体では、機械学習を活かした自動化機能が利用可能です。ただし、ただ設定すれば上手くいくというものではありません。
不用意に自動化に頼りすぎて広告効果を損ねていないか?
自動入札は媒体の推奨設定とされているため多くのアカウントで導入がされています。ただ、目標コンバージョン単価の自動入札を導入せず、あえて手動(上限クリック単価および拡張クリック単価)で運用するべきケースもあります。
地域別の店舗ごとの集客を月ごとにコントロールする必要があるケース
店舗によっては多少費用対効果が見合わなくても集客する必要があったりと、効率だけが全てではありません。自動入札だといつの間にか特定店舗の集客がシュリンクすることも・・・。入札の強弱など細やかな調整が必要になる場合には、自動入札が向かないこともあります。
急激な変化が頻発するケース
自動入札は急激な変動に対応するのが苦手と言われています。以下のような状況があるアカウントだと手動入札の方で成果が安定するかもしれません。
- 大規模セール
- 急激なトレンド変化
- 予算が月ごとに大きく変動
コンバージョン数が不足しているケース
目標コンバージョン単価は、過去 30 日間に 30 回以上のコンバージョンを獲得していることが推奨されます(目標広告費用対効果の場合は同期間に 50 回以上)。コンバージョン数がこの水準に届かない場合は、手動での小まめに運用した方がパフォーマンスが上がることもあります。
5.媒体の機能を十分に活用し切れているか?
絶え間なくアップデートされ続けているので、キャッチアップ・対応が遅れている、対応を見落としているケースがあります。
設定が適切ではない、改善の余地がある
たとえば、動的検索広告(以降、DSA)が適切に動くように調整がされていないケースがあります。
- ページフィードの活用
- フィルタ設定の活用、商品が無いページの除外
これらの設定によって、一旦動かして費用対効果が見合わなかったため停止している場合でも、主力の配信に成長することもあります。
設定して損はない箇所の設定漏れなど
長く運用しているキャンペーンだとアップデートの反映が遅れているケースがあります。
- 説明文2行目、広告見出し3行目の入力
- 広告表示オプションの設定
通常の配信先とは異なる広告フォーマットやターゲティングが作り込まれていない
Gmail広告、Instagramのストーリーズ広告など、固有のクリエイティブやターゲティングが活用できる配信先に合わせてもっと作り込んで充実させることで獲得が伸びるケースがあります。
6. リマーケティング・リターゲティングの配信設計がビジネスにマッチしていない
購入完了済みユーザー、リード獲得済みユーザーへ広告配信の余地があるケース
一度申し込み・購入した方からのリピートが業績につながるビジネスの場合は、申し込み・購入完了済みユーザーに対してリマーケティング配信などの施策を実施できます。カスタマーマッチで顧客リストを利用も有効です。
その他以下のような改善策が検討できることもあるでしょう。
- リマーケティングの配信期間が長すぎる・短すぎるケース
- サテライトサイト等の別ドメインの所有サイトにリマーケティングを配信できる余地があるケース
7.過去成果が悪くて停止したプロダクトや配信設定、媒体などにもう一度チャレンジできないか?
獲得を見込んだものの過去に上手くいかず停止した配信について、二度と再開しないのはもったないことがあります。
過去に比べて状況が良くなっている点はないでしょうか?
- 広告文やリンク先のコンテンツが改善されている
- コンバージョンデータが以前に比べて増加している
- 媒体の新機能や機能の改善
こういったアップデートに合わせてもう一度チャレンジする選択肢も持っておきたいです。
8.表面的な指標に縛られすぎて機会損失が発生していないか?
ユーザーの新規性や収益貢献度の違い
たとえば、同じCPAでコンバージョンが獲得できるキーワードでも、新規のお客さまの割合が異なる場合があります。コンバージョンの数を増やしていきたい場合、既に顧客となっていただいているお客さまよりも、新規のお客さまの開拓を行っていったほうが中長期的にはプラスとなりますよね。
管理画面上では同じ1コンバージョンでも、現実には価値が異なるケース
たとえば以下のような場合だと、1コンバージョンあたりの価値が本当に同じか、疑ってみてもいいかもしれません。
また、リソースが限られている場合には、できるだけ収益への貢献度が高いお客さまを手厚くサポートすることで、安定した収益を得ることが重要な場面もあります。
一件のコンバージョンも、ユーザーの新規性や収益貢献度などの違いを指標とすると、価値の違いが立体的に見えてきます。
手法によってアプローチできるユーザーの違い
検索連動型広告はサービス名や課題意識等で自ら検索したユーザーに広告出稿します。営業でいうとプル型・インバウンド型のようなもので、顧客の本気度や問い合わせの質は高い傾向があります。(もちろんキーワードや広告文・ランディングページによっても大きく変動します)
一方、ディスプレイ広告は、SNSやブログ、調べごとやネットサーフィンをしているときに出稿できる広告です。とくにサービスに関心や課題意識を持っているタイミングとは限りません。営業でいうとプッシュ型・アウトバウンド型のようなもので、まだ顧客の本気度が低かったりするため、問い合わせの質がイマイチだったりします。
「問い合わせの質が明らかに悪い・・・」
こういうお困りごとがあれば、検索連動型広告の明らかに本気の顧客が検索しているであろうキーワードに費用を集中させることで良質な問い合わせを増やせるケースもあります。
そもそもコンバージョンの最大化がビジネスの拡大に対して因果関係が薄いケース
コンバージョン地点がビジネスのキャッシュポイントに対して余りにも浅い地点にある場合は注意が必要です。いくらコンバージョンを増やしても売上にまったく繋がらないことが起こりえます。
因果関係の薄いマイクロコンバージョン
以下のようなマイクロコンバージョン(購入や登録など本コンバージョンの手前のボタンタップ等で発火させるコンバージョン)だと、誤タップや単にページをタブで開いている人も含まれてしまい、マイクロコンバージョンを最大化しても成果に繋がらないことも
- ファーストビューにある申し込みボタンタップ
- ページへの滞在時間
マイクロコンバージョンが、本コンバージョンの10倍以上など乖離が大きい場合には要注意です。
必要以上に低いコンバージョンのハードル
本来得たい成果に対して、必要以上に低いハードルを設定してしまうと、広告管理画面のコンバージョン数だけ増えて、肝心の広告主の売上につながらないというケースがあります。動線やフローの整備が急務ですが、広告側でも以下のような対策を行うとよいでしょう。
本気度の高い方を集客できるよう広告配信側で工夫する
たとえば、クリックするハードルを上げるよう広告文の条件を厳しくするなどの方法です。即戦力人材が欲しい求人広告の場合、「経験者優遇」などを広告文に盛り込むことで、ターゲットでないひとの時間も奪わずに済みます。
そもそも目標とするコンバージョン地点を変更する
そのコンバージョンを増やすのが広告主の目的だっけ?と再度目的を明確にしてみましょう。目的を達成するためにどうすればいいかを考えることが重要です。
9.広告文やランディングページの切り口や見せ方は適切か?
前提知識無しにフラットな目線で見返してみると、違和感があるケースも
- LPや商品を見てパッと見で何が魅力かわからない、理解ができないケース。
- 商品にある程度詳しい顧客しか理解ができないケース
はじめて見た顧客が理解できるように補足説明を入れたり見せ方を変えたりで改善できることが多いです。
新たに獲得が見込めそうな広告文の切り口の開発が見込めるケース
ありきたりな自社のサービス名や規格訴求やセールの訴求一辺倒では頭打ちになることもあります。新しい効果的な広告文を見つけられると次の展開のヒントとなるでしょう。いち消費者・当事者としての直感も大事にしたいですね。
「私自身もこういうことで困ったことがあるから」
「友達が同じようなことを話していた」
そういった素朴な感想が次の広告文のヒントにできます。顧客が具体的に何に困って・どういう課題意識で購入・申し込むのか解像度を上げることで、成果の上がる広告文が出てくる可能性も上がるでしょう。
10.選択している広告媒体は適切か?
ある程度特定の媒体を改善し尽くし、そのうえで予算に余裕があるケースがあります。取り組む媒体を増やすことで獲得を伸ばせたり、不必要な費用を削減したりできる可能性があります。
- Amazon 広告に取り組むと売上を増やせそう
- Twitter広告も相性が良さそうだから取り組んで良さそう
- 実施中のFacebookは、ターゲットとしているユーザーとは実は相性が悪いかも
ただし、媒体数が増えると、広告主でも広告代理店でも当然ながら手間も時間も必然的に増えます。インパクトが少なすぎるなら媒体追加をあえて見送る選択肢や、停止してしまう選択肢も常に持っておきたいです。
また広告媒体を考えるとき、そもそも運用型広告以外の集客方法も検討できないか?の視点も重要です。たとえば、店舗系のビジネスであれば、広告に注力する前にGoogle マイビジネスにしっかりと取り組むべきかもしれません。
11.そもそもプロダクトやサービスそのものや、戦略・ポジショニングを見なおす余地はないか?
どうしても運用型広告を多少上手に運用しただけでは状況を打開するのが困難なケースも中にはあります。以下のような状況が多いように思います。
- 法的・社会的なモラルに抵触しており媒体審査等に通らないケース
- 競合に比べ商品競争力が低いケース
- 競合に対して著しく利益が残りづらく広告で費用対効果を合わせるのが困難なケース
そういったケースだと、対処法はさまざまですが、運用型広告以外のボトルネックを改善することに集中すべきかもしれません。
まとめ
広告アカウントはやり切ったと思ってもまだまだやれることは意外とあるものです。みなさんが担当しているアカウントでも役に立つとうれしいです。
ただ本当にクリティカルな改善は、広告アカウントごとの一般論では無く、ビジネス固有の事情にフォーカスしてはじめて出てくることが多いです。ぜひ個別のケースで、ここで得たヒントがどう活きるのか考えるといいのかなと思います。