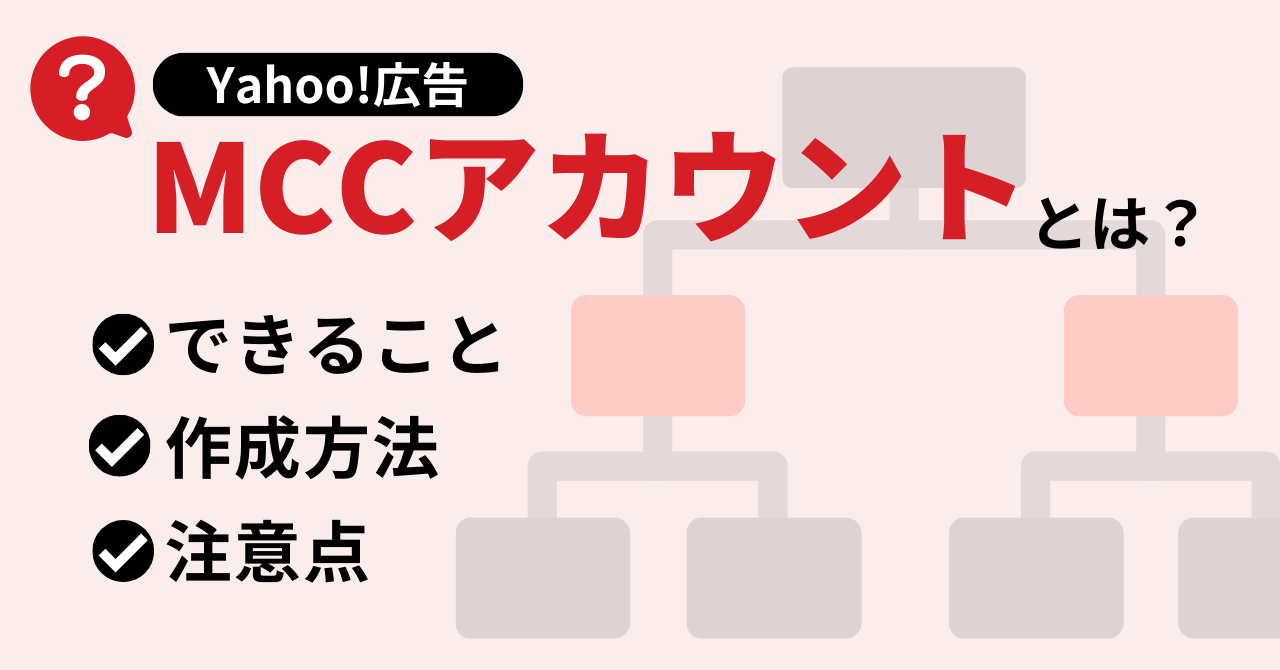メールマガジン(以下、メルマガ)を配信していて、こんな悩みありませんか?
- メルマガ内コンテンツのネタに困る
- メルマガ作成に時間がかかる
- メルマガの効果がわからない
企業のメルマガ担当者ならだれもが一度は通る悩みではないでしょうか。
メルマガは、企業のマーケティング戦略のひとつと頭ではわかっていても、手間がかかるのに効果が分からなくては、続けるのがしんどいなと思ってしまうときもありますよね。
そこで今回は、メルマガ配信が正直しんどくなってきた企業のメルマガ担当の方に向けて、無理なく続けるためのメルマガ配信の心得とクリエイティブ検証で見るべき指標をご紹介したいと思います。


目次
マーケティング戦略におけるメルマガの役割とは?
企業のマーケティング戦略において、メルマガはクーポンやキャンペーン情報、お役立ち情報への案内、問い合わせなどの行動喚起に適したチャネルといえます。
なぜなら、メルマガは特定電子メール法で、承諾を得ている人にしかメールを送ってはいけないと決まっており、基本的にメルマガを送るにはメルマガ登録してもらう必要があります。
このようにメルマガは、顧客自ら承諾をしたうえで配信されるため、企業の情報を能動的に収集している関心の高い顧客にアプローチできる貴重な手段といえます。
参考:メルマガの法律『特定電子メール法』とは?オプトイン・オプトアウトも解説 - 配配メール
メルマガを無理なく配信し続けるためには
メルマガ読者は、自分に合ったタイミングで気になる件名のメールを開封しています。そのため、基本的には単発での配信よりも継続して配信する方が読者との接点を多く持つことができるため開封してもらえる可能性が高まります。だからこそ、継続的に配信できるように体制を整えることが大切なのです。
しかし多くの場合、メルマガ担当者は他業務との兼任でメルマガを配信しています。そのため、なるべく無理のない範囲で行うことが、継続的に配信するための重要なポイントと言えるでしょう。
では、メルマガを無理なく配信し続けるためにはどうしたら良いのでしょうか。今回は、その心得をお話していきたいと思います。
メルマガ配信の目的を持とう
相手が興味のないことを話し続けても一向に関係が築けないのと同様に、メルマガも闇雲に配信し続けても顧客との関係は築けません。どんな顧客に、どんな行動を促したいのか、メルマガ配信の目的を持ちましょう。
たとえば、配信の目的が店舗への来店なのか、セミナー応募なのかでは、メルマガのタイトルもコンテンツも違ってきますよね。まずは、メルマガ配信で促したい行動を、目的として設定しましょう。
設定した目的を促すためのコンテンツとタイトルは何が効果的なのか、顧客がどのタイミングならメルマガを開きやすいか、またはメールを読むタイミングはいつなのかを想像しながら配信時間を考えることが、顧客との関係を築くうえでの第一歩なのではないでしょうか。
メルマガ毎に顧客像を持とう
当たり前かもしれませんが、顧客はすべて同じ人ではありません。それぞれ興味を持つきっかけもタイミングも異なります。一つのメルマガですべての顧客の興味をひこうとするのではなく、メルマガ毎に顧客像を持って取り組むことが大切です。
また、メルマガ毎に顧客像を持つことで、コンテンツの幅も広がり、メルマガのネタに困ることも減ってくると思います。
コンテンツは少なくても大丈夫
メルマガというとある程度まとまった読ませる文章を用意しなくてはならないと考えがちなのがメルマガ作成から足を遠ざける理由の一つになっていないでしょうか。
以前、メールマーケティングサービス「配配メール」の総責任者を務める安藤さんを取材したときに最も衝撃的だったのが、「コンテンツは短くても大丈夫」という事実です。
安藤:
75%の読者がメールを読む時間は「7秒」なんですよ。(※)文字数にすると、1文字ずつきっちり読むとしたら、70文字なんですね。とはいえ、全部を見ているとは思わないので流し読みだと、2倍の速度で見たとしても140文字ですよね。読者は、ツイート1回分しか読んでないです。メルマガのコンテンツは、基本的にはじっくり読まれていないと思った方が良いです。※2019年9月 ラクス株式会社 自社調べ
悲しいことに、たくさん書いたからといって読まれるわけではないのです。
でも、7秒しか読まれなことをポジティブに捉えれば、メルマガひとつにつき、7秒=140文字だけ書けばよいのです。もしも、じっくり読んでもらわないと伝わらないモノを促進したいのであれば、ランディングページへのリンクを案内するなどして、メルマガ内コンテンツは140文字前後でまとめましょう。
140文字は、ツイート1回分です。それなら時間をかけずに作れそうですよね。
まずは週1回の配信からはじめてみよう
顧客は企業の情報を知りたいからメルマガを登録しています。しかし、せっかく登録したのにあまり情報が届かなかったら、がっかりしてしまいますよね。その企業への関心も下がってしまうかもしれません。では、どのくらいの頻度で配信するのが良いのでしょうか。
以下は、Mail Marketing Labの記事をもとにまとめた、ビジネスモデルとメルマガの目的ごとに適した配信頻度です。
| ビジネスモデル | メルマガの目的 | 配信頻度 |
|---|---|---|
| BtoB | 販売促進 | 月1~2回 |
| BtoC | 販売促進(セールやキャンペーン通知など) | 毎日~週数回 |
| BtoB・BtoC | 顧客との関係づくり | 毎日~週数回 |
参考:メルマガの頻度ってどれくらいがベスト?自社の配信頻度を見つけるための3つのポイントとは|Mail Marketing Lab(記事内容を元にアナグラムで加工)
メルマガは、読者がメールを読もうとしたときに接点を持ちます。商品を購入するタイミングではないため、基本的には顧客との長期的な関係づくりをすることで、商品やサービスの販売や問い合わせの促進につながることが多いです。
一方で、BtoCのように購入までの検討期間が短く、安価で衝動買いも見込める商品やサービスの場合は、セールやキャンペーン通知などを定期的に行うことで購入率の高いチャネルにもなりえます。このようにBtoBとBtoCでは購入までの検討期間が違うため、「販売促進」という同じ目的であっても適した配信頻度が異なります。
また、これからメルマガをはじめる場合や、販売促進を目的としたメルマガであまり効果を感じていない場合は、顧客との関係づくりを目的としたメルマガ配信を、週1回からはじめてみるのをおすすめします。なぜなら、配信頻度が低いメルマガはコンテンツの質を担保できる一方で、読者との接点が少ないが故に、開封してもらえない可能性が高まるからです。
「週1回は、なかなかリソース確保が難しいな」と思ってしまった方もいるでしょう。でも、思い出してください。顧客がメールを読む時間は7秒、文字数にすると140文字程度です。今まで複数コンテンツでひとつのメルマガを配信していたのならば、コンテンツごとにメルマガを作成すれば、週に1回以上の配信も現実的なのではないでしょうか。
最低限のKPIを押さえよう
メルマガ配信を継続できない理由のひとつに、効果がよくわからないという悩みが挙げられます。その場合は、以下の最低限のKPI(指標)を押さえておくこと良いでしょう。
さらに、各指標の目標値も押さえておくと良いですね。開封率が低いなら、タイトルを開封したくなるような表現に変えようとか、クリック率が低いならクリックしたくなるようにコンテンツやCTAを改善するなどの対応がとれるようになり、メルマガの効果が分からない状態からは脱することができます。
指標とその基準となる数字(目標値)を押さえておくことで、継続的な改善が行えるようになりますね。
メールのクリエイティブの効果はどう評価するのか?
メルマガの成果を決める要素は、配信リスト(ターゲット)はもちろんのこと、クリエイティブが重要です。ここでは、クリエイティブに注目してお話したいと思います。
メールクリエイティブを構成する要素
まず、メルマガにおけるクリエイティブとは何なのでしょうか。クリエイティブを構成する要素は以下になります。
② タイトル(件名)
③ プリヘッダー(一部メール受信ボックスのみ表示)
④ CTA
⑤ 本文
⑥ コンテンツ
実際の画面に合わせて見ていきましょう。
メールのプレビュー画面

「① 差出人」や「② タイトル(件名)」は馴染みがあると思いますが、「③ プリヘッダー」は知らなかったという方もいるのではないでしょうか。プリヘッダーとは、Gmailなど一部のメールサービスのプレビュー画面で表示される、件名の次に続いているテキスト部分です。メール本文の冒頭が表示される場合もありますが、メール配信ツールによっては、本文とは異なるテキストを設定することもできます。
メールを開いたあとの画面

メールを開いたあとに最初に目に入るのが「⑤ 本文」です。メルマガで促したい行動が「④ CTA」です。CTAは、URLリンク式とボタン式では効果が8倍くらい違うとも言われています。詳しくは、次の記事をご参考ください。
参考:4.HTMLメールは嫌われる|メールマーケティングとは?効果を上げるために知っておきたい7つの誤り
クリエイティブ検証で見るべき指標
クリエイティブ検証でおもに見るべき指標は、開封率・反応率・クリック率になります。ざっくり分けると、「タイトル」の評価は開封率、メルマガ内「コンテンツ」の評価は反応率とクリック率を見ます。
反応率は、開封されたメールのうち文中のURLがクリックされた割合なので、コンテンツが態度変容(クリック)を促したかどうかを判断するために見ておきたい指標です。ただし、特定の狭い顧客層を狙ったタイトルでは反応率は高くなるがクリック率は低くなるため、一概にも反応率だけを見ておけば良いとは言えません。ですので「コンテンツ」の評価は、反応率とクリック率の両方を見て判断をした方が良いでしょう。
改善指標ごとに見るべき要素
次の表は、クリエイティブにおける改善指標ごとの見るべき要素をまとめたものです。

それぞれ上から順番に改善への影響度が高いため、上から順番に見直していきましょう。
開封率が目標値よりも下回っている場合は、タイトル(件名)>プリヘッダーの順番で、クリック率や反応率が目標値よりも下回っている場合は、CTA>ファーストビュー>本文の順番で改善していきます。「差出人」は定期的に改善を加えるものでもないので、たとえば、企業メルマガなのに差出人名が「個人」になっている場合は「社名+個人名」にするなど、個人メールだと誤認されないような修正はしたいです。差出人が意図どおり読者に伝わっているかはいま一度見直しておきたいですね。
まとめ
さて、ここまでメルマガを無理なく続けるための心得と、クリエイティブ検証で見るべき指標をご紹介してきました。
メルマガは不特定多数の人に同じ内容を送るものなので、ついついユーザーをひとまとめに捉えて施策をたててしまいがちですが、読者はそれぞれ興味を持つきっかけもタイミングも異なります。メルマガ毎に目的や顧客像を明確にし、基準となる指標をもって評価していくことがメルマガを改善していくうえで重要なのではないでしょうか。
また、本記事を読んで、今までメルマガ作成がしんどかった方も、これからメルマガをはじめる方も、気軽にメルマガ配信ができそうと思ってもらえたら幸いです。