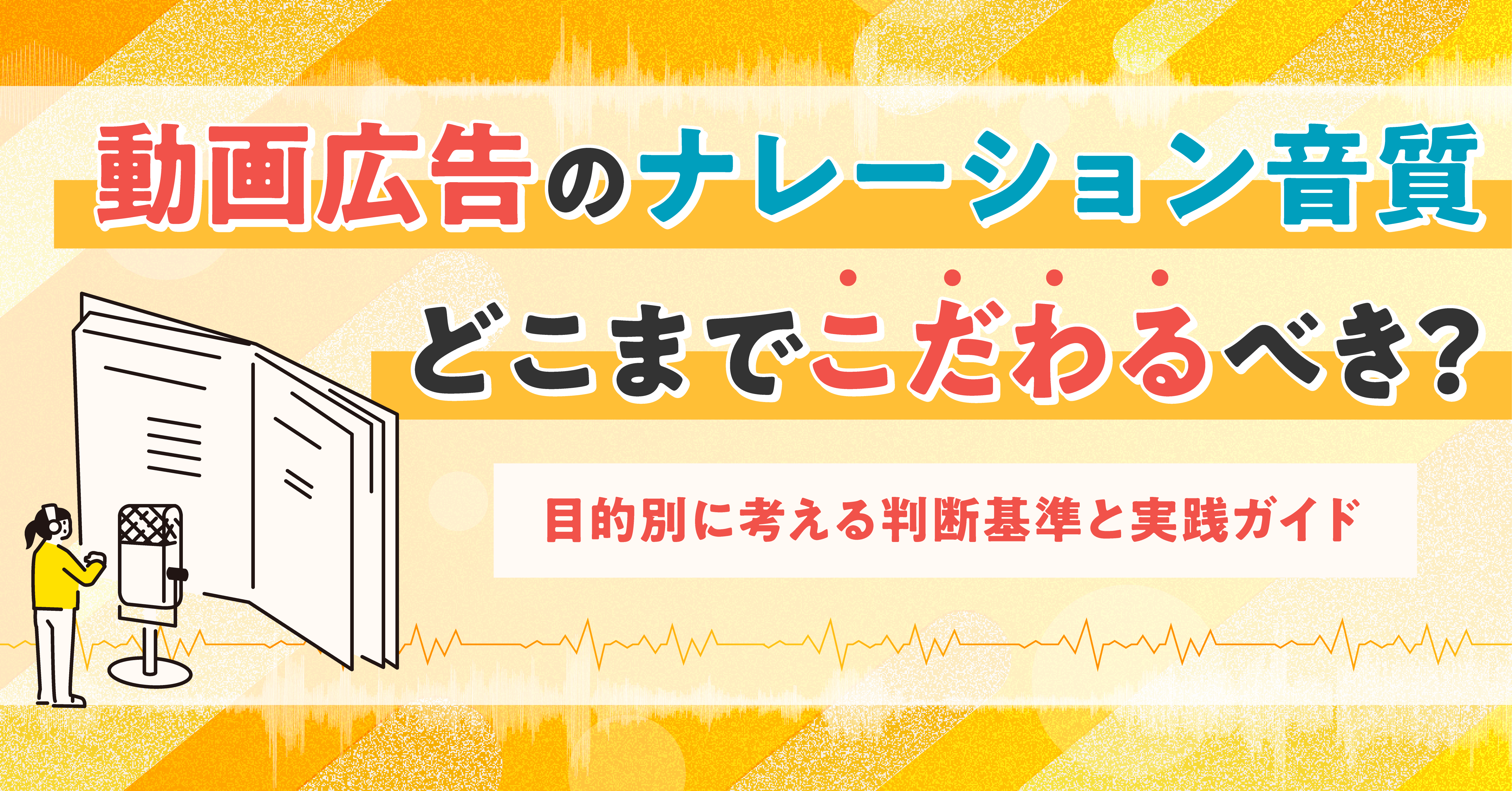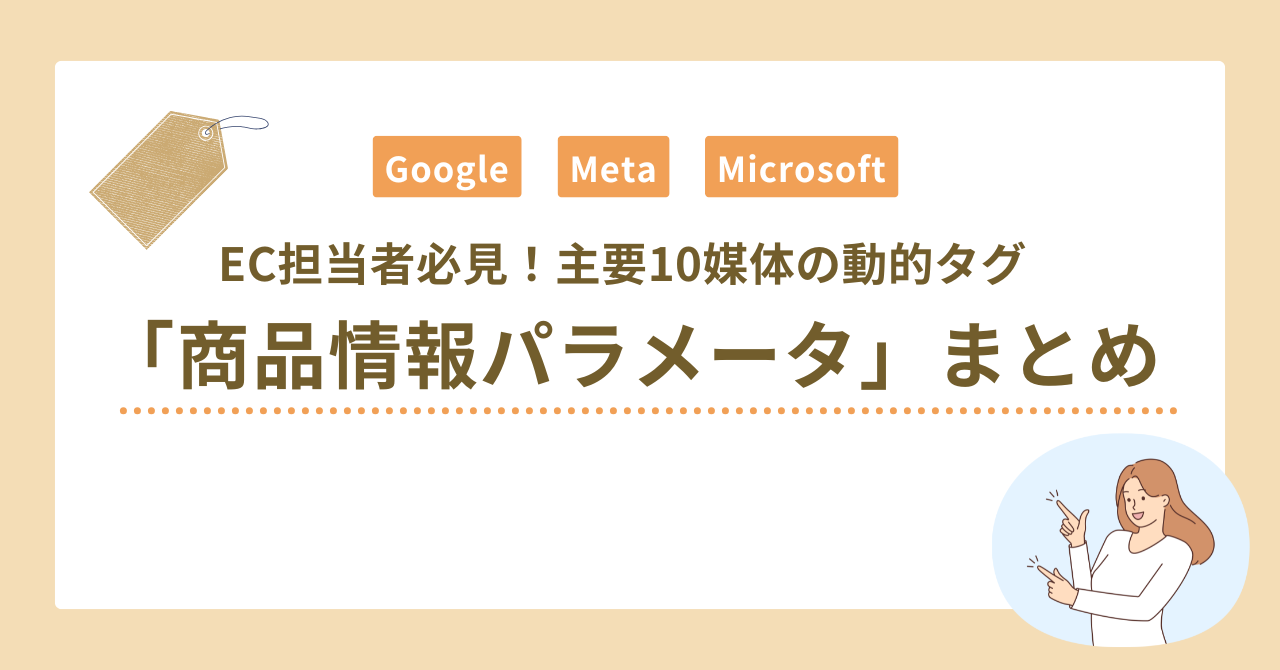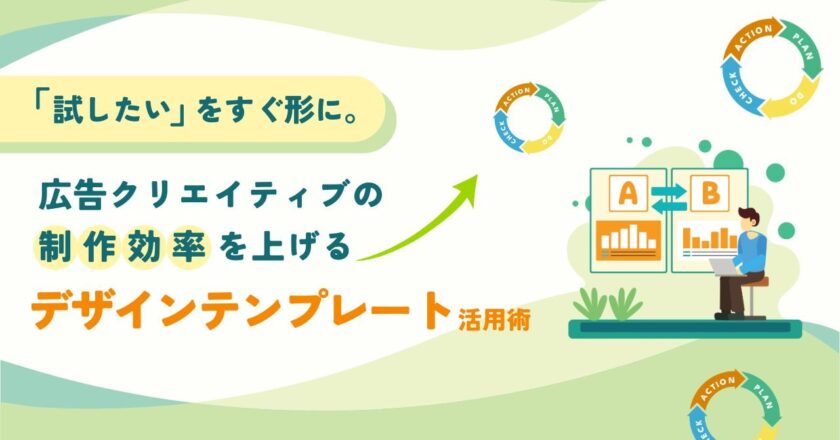※2019年12月25日:最新の情報をもとに更新
年々伸び続けるネットショップ市場(EC市場)。経済産業省の発表によると、2015年の国内EC市場規模は13.8兆円(前年比7.6%増)まで拡大しているとされています。
▼日本のBtoC-EC市場規模の推移

引用元:電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました~国内BtoC-EC市場規模は13.8兆円に成長~
もちろん一口にネットショップと言っても、その業態は実にさまざま。一つの商品だけを販売する単品通販、数万点を扱う多品目メガストアに、オーダーメイドの受注生産などなど。実店舗来店を促すO2Oプロモーションも、広義な意味ではネットショップと言えるかもしれません。
そんな多角化するネットショップ市場で、適切なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標。目標の達成度を測るための指標)を設けることは、広告に限らずプロモーションを行う土台となる部分です。ネットショップのKPIは、慣例的にまだCPAが用いられることが多いように思いますが、各サイトの取扱商品増に伴い、ROASでの運用が必要になるシーンも増えています。
今日はそんなネットショップを中心としたビジネスのリスティング広告を運用する際の、ちょっとしたコツを書いてみようと思います。


目次
ROASってなに?
ROASとは、Return On Advertising Spendの略で、投資回収率とも言われます。読み方はロアス。ざっくり言うと、「広告経由であがった売上」を「広告費」で割った数値のことで、下記の式で求めます。

例えば、売上が100万円で、その売上をあげるのにかかった広告費が20万円だったとすると、売上100万円÷広告費20万円×100で、この場合のROASは500(単位は%)ですね。1円の広告費が5円の売上を生んだ、投資額が5倍になった、と見ても良いと思います。
どんなときにROASを指標として運用するといいの?
一般にKPIにされることが多いCPAと比較してみましょう。

上表のように、お客さんがカートに入れる金額がほぼ全員同じ場合はCPA、お客さんごとに異なる場合はROASでの計測が適しています。10万円のパソコンを買う人もいれば1,000円のスマホケースを買う人もいる、みたいなお店はROASですね。単品通販はCPA、多品目通販はROASが基本ですが、単品通販でもキャンペーンやセールによって不定期&頻繁に金額が変動する場合は、CPAよりROAS計測の方が向いているかもしれませんね。
続いて計算式の登場人物に目を向けると、CPAが広告費とコンバージョン数をカップリングしているのに対し、ROASは売上が広告費のパートナーとなっています。コンバージョンか売上か、CPAとROASの大きな違いはここにあります。
なお、仮に多品目通販でも顧客数を増やすことが最重要ミッションであるなら、KPIをCPAにすることで、コンバージョン数の推移を把握しやすくなるメリットが得られます。この場合、1売上あたりの平均粗利(平均顧客単価-平均原価)を目標CPA(上限CPA)とするのが一般的です。
リピートが見込める商品であれば、LTV(顧客生涯価値)、リピート率も加味することでさらに適切なCPA設定が可能です。プロモーションの選択肢も広がりますね。
参考:もう迷わない、適正なリスティング広告の予算とCPAの決め方
目標ROASの算出式と考え方
では、目標ROASはどのように算出するのがよいのでしょう。
基本的には下記のように、1売上(平均顧客単価)を粗利(平均顧客単価-平均原価)で割った値が、目標ROAS(下限ROAS)となります。平均原価には、商品の原価に配送費やその他のコストなどを含めるのが一般的です。

文字だけだとあまりピンと来ないかもしれません。いくつか例をあげてみましょう。
1売上あたりの平均顧客単価¥10,000、平均原価¥3,000の場合
[wc_box color="inverse" text_align="left"]
【例1】下限ROAS。この値を割ると赤字になる最低限死守すべきライン
目標ROAS 143% = ¥10,000÷(¥10,000-¥3,000)
【例2】ちょっと余裕をもたせたROAS。粗利の半分50%を広告費とし、もう半分の50%を利益にしたい場合:
目標ROAS 285% = ¥10,000÷{(¥10,000-¥3,000)×50%}
【例3】利益重視ROAS。粗利の30%だけを広告費とし、残り70%を利益にしたい場合:
目標ROAS 476% = ¥10,000÷{(¥10,000-¥3,000)×30%}
注意として、あまり利益を重視しすぎたROASにすると、プロモーションで行える範囲、選択肢が狭くなり、ビジネスの機会損失を起こす可能性もありますので、ある程度許容する幅をもっておくことも大切です。
ROAS運用の考え方
以上のように算出した目標ROASに対し、どのように運用していくのがよさそうでしょうか。当然CPAとROASでは、扱う指標が違うため、運用の考え方もそれぞれに適したアプローチを行わなければ、パフォーマンスの継続的な向上、素早い改善は困難です。
ここでは入札単価の決め方を例にとって、CPA運用とROAS運用の違いを見ていきましょう。
▼CPA運用の入札単価の決め方
[wc_box color="inverse" text_align="left"]
目標CPA ×コンバージョン率
<解説>目標CPA ¥10,000でコンバージョン率が1%なら、¥10,000×1%で、入札単価の目安は¥100となります。
[/wc_box]
仮に1クリック¥100で100人お店に来たとしたら、¥100×100人で、かかった広告費は¥10,000。コンバージョン率1%なので、お店に来た100人中1人が購入する。よって入札単価を¥100としておけば、目標CPA¥10,000以内で1件の購入が計算できる、とおおまかにこんなロジックです。
▼ROAS運用の入札単価の決め方
[wc_box color="inverse" text_align="left"]
(売上単価×コンバージョン率)÷目標ROAS
<解説>1売上(平均顧客単価)あたりの売上単価¥30,000でコンバージョン率が1%、目標ROAS 300%なら、(¥30,000×1%)÷300%で、入札単価の目安は¥100となります。
[/wc_box]
ちょっとややこしく感じるかもしれませんが、ひとつずつ要素を分解していけば大丈夫です。(売上単価×コンバージョン率)は、1売上(¥30,000)をROAS 100%で取るために、入札単価をいくらにすればよいかを算出しています。先ほどの目標CPAが売上単価に変わったものだと置き換えて考えるとわかりやすいかもしれません。
今回の例だと¥30,000×1%で、ROAS 100%になる入札単価は¥300ですね。この入札単価¥300を目標ROAS 300%(または3)で割ってあげることで、ROAS 300%以上にするための入札単価は¥100、という数値が求められます。
ROAS運用の注意点
ROAS運用を行う際の注意点としては、CPAを過度に意識しないことですね。
重点的に見るべきはROAS、続いて売上額と売上単価、特殊なケースを除いて、CPAは判断材料のひとつとしてチラ見するぐらいで十分かと思います。少し乱暴ですが、CPAがいくら高騰しようとROASが目標ラインを維持していれば大きな問題はないためです。下記はその一例です。
[wc_box color="inverse" text_align="left"]
例)
【CPA¥3,000】売上額1,500万円、広告費300万円、コンバージョン1,000件
(ROAS:500%|売上単価:15,000円)
↓
【CPA¥5,000】売上額1,600万円、広告費300万円、コンバージョン600件
(ROAS:533%|売上単価:20,000円)
CPAが1.7倍弱になっていますが、売上額は+100万円。ROASも33ポイント上昇。みなさん、思わずにっこりするパターンですね。
また、ROASのキーマンとなる売上単価は、さまざまな要因で大きく変動する可能性を含んでいるので、できれば固定の数値ではなく、媒体の管理画面で直近のフレッシュな売上単価を採用するのがお勧めです。
年末に福袋を販売予定のネットショップを例にして考えてみましょう。このお店の売上単価は通常2万円ほどですが、福袋の販売時期は5万円を超えます。このように、キャンペーンやセット売りなど、平均顧客単価が上がりそうな時期が読めている場合。前もって上昇後の想定売上単価をベースに入札単価をあげておくことで、機会損失を最小限にし、チャンスを生かす運用ができると思います。
ちなみに、売上単価の変動があまりないのであれば、「現在のROAS ÷ 目標ROAS」で出した掛け率を、現在の入札単価に掛ける手段もあります。
現在のROASが240%、目標ROASが300%なら、240÷300=掛け率0.8。これを現在の入札単価に掛けると20%低い入札単価にしていくイメージですね。現在のROASが目標ROASよりかなり良い場合も同様の式で掛け率が求められるので、例えば掛け率2.0なら、入札単価を2倍にしても採算が取れる見込みが立つ計算です。
※上記の入札単価はあくまで目安で、実践では機会損失を防ぐため10~20%高い単価で入札したり、拡張CPCを導入したり、入札戦略を入れたり、状況・変数を加味して立ち回る必要があります。
媒体画面での売上の測り方
ROASを指標とした運用を行うには、媒体管理画面で売上金額を取得するのがお勧めです。ただ、通常のコンバージョン計測タグをそのまま設置しただけでは、顧客ごとに異なる売上を取得することはできません。
カート内の売上金額を動的に取得する必要があるため、サイトごとに設定は異なりますが、各媒体ごとに以下の方法で売上の取得が可能です。
ROAS指標の見方と設定方法
広告管理画面でのROAS指標の見方
広告管理画面で以下の項目を表示しておくと、ROAS運用が行いやすくなります。
Google 広告

Yahoo!広告の検索広告(旧:スポンサードサーチ)
![]()
Yahoo!広告のディスプレイ広告(旧:Yahoo!ディスプレイアドネットワーク)
![]()
各項目の内容は次の表でご確認ください。
| Google 広告 | Yahoo!検索広告 | Yahoo!ディスプレイ広告 | 内容 |
| コンバージョン値 | コンバージョン価値 | コンバージョンの価値(クリック経由) | 売上です。 |
| コンバージョン値 / 費用 | コンバージョンの価値/コスト | コンバージョンの価値(クリック経由)/コスト | 売上 ÷ 広告費。ROASです。ここの表示が「3.51」ならROASは351%になります。 |
| 値 / コンバージョン | 価値/コンバージョン数 | コンバージョンの価値(クリック経由)/コンバージョン数(クリック経由) | 売上 ÷ 購入件数。売上単価です。 |
自動入札の目標にROASを設定する方法
小見出し通りで恐縮ですが、Google 広告やYahoo!検索広告の自動入札で、当然ROASも目標に指定可能です。
設定手順をそれぞれ解説していきます。
Google 広告

- 管理画面右上の「ツールと設定」をクリック
- 共有ライブラリで「入札戦略」をクリック
- 左上の「+」ボタンをクリックで開いたプルダウン内「目標広告費用対効果」を選択
- 青枠内の項目を入力し、「保存」をクリックで入札戦略の目標にROASを設定完了です。


Yahoo!検索広告
※今回は、ポートフォリオ入札で設定する方法を解説します。

- 管理画面上部タブの「ツール」をクリックでプルダウンを開き、「ポートフォリオ入札ツール」を選択
- 左上の「+ポートフォリオ入札設定の作成」をクリック
- プルダウン内「広告費用対効果の目標値」を選択
- 青枠内の項目を入力し、「作成」をクリック
- 入札方法の「▼」をクリックし、「自動入札:広告費用対効果の目標値」を選択
- 「ポートフォリオ入札設定」を選択
- 設定したい自動入札名を選択
- 「編集内容を保存」をクリックで入札方法にROASを設定完了です。


次に「ポートフォリオ入札設定」を設定したいキャンペーンの「キャンペーン設定情報」をクリックしてキャンペーン編集画面を開きます。



以上が自動入札の目標にROASを設定する方法になります。
目標ROASを設定すれば、さまざまなシグナルを参照し、設定したROASを維持しながら売上を最大化できるよう働いてくれます。
個人的な体感では、しっかり組まれたコンテンツターゲットと非常に相性が良く、精度も高い印象です。もちろんリマーケティングでも超オススメ。
ただ、あまり細かく広告グループが分かれているとポテンシャルを最大限に生かせない場合も。月間で0件~数件のコンバージョンしか生まない広告グループが無数にあるキャンペーンなどですね。細かく分かれていることで各広告グループの母数がたまるスピードが鈍り、直近のまとまったデータが見えづらくなるため、自動入札を導入する場合は、初期設計・構築時に細かくし過ぎないのが肝要です。
月間30件以上の売上件数があり、不定期なセールやキャンペーンが少なく、売上単価が大きく動かないものだと、自動入札の適用で飛躍的に売上が伸びるケースも多々あるので、適用しない理由を探す方が難しいと思います。
参考:「目標広告費用対効果」に基づく入札について - Google 広告 ヘルプ
最後に
本日はROAS運用についてまとめてみました。
施策や訴求の刺さり度、外的要因で生き物のように変動する売上を「鳥の目」「虫の目」「魚の目」で眺めながら、流入経路ごとの売上単価を分析したり、さらなる仮説や検証を試していける楽しさは、ROAS運用ならではの魅力でもあります。
ただ、しっかりROASに寄り添った運用をしていても、そもそも目標としている下限ROASがズレているケースもちらほら目にします。厳しすぎる、緩すぎる、細かすぎる、などですね。指標がブレたプロモーションは、改善のためのアプローチが遠回り且つ的外れになりがちで、そう遠くない将来に停滞・縮小していくリスクが高まってしまいます。
大事なのはやはり、ビジネスのミッション達成に最も適した指標を正しく見定めること。そして、その指標を達成、ないしは超越する成果をたたき出すためにどう運用していくか、素早く思考し、今取れる最良のアクションを実行し続けることです。
適切な目標の上に、正しい方向へ向かうためのアプローチをのせて、少しの勇気と情熱、誠実さをふりかければ、プロモーションの成功確率が大きく上昇することは間違いありません。
市場・環境の変化、プロダクトライフサイクルに応じて、目標や指標の正当性を見直しつつ、その時一番フィットするものを選択していきたいですね。