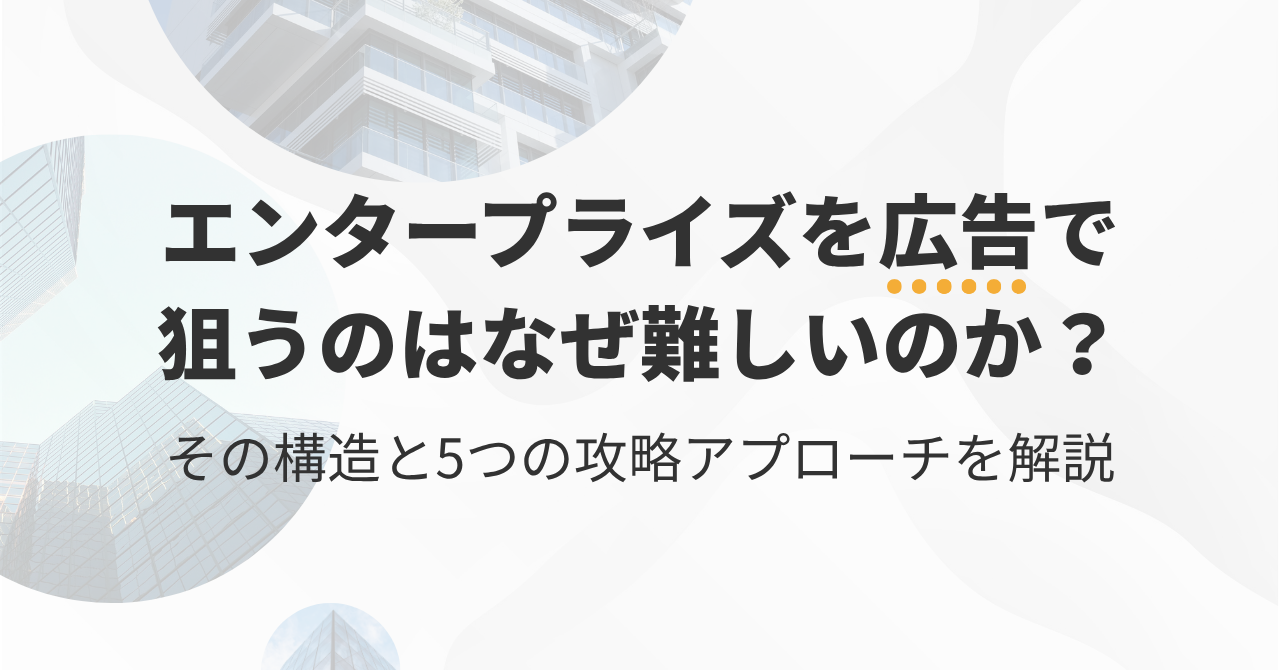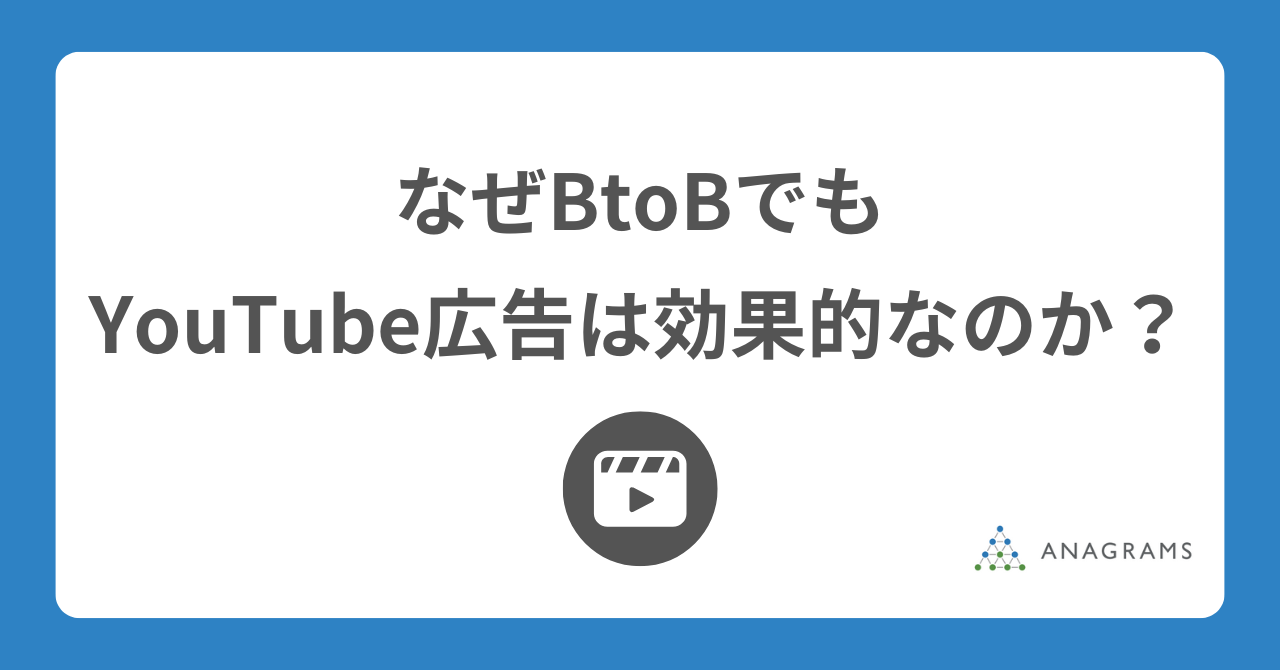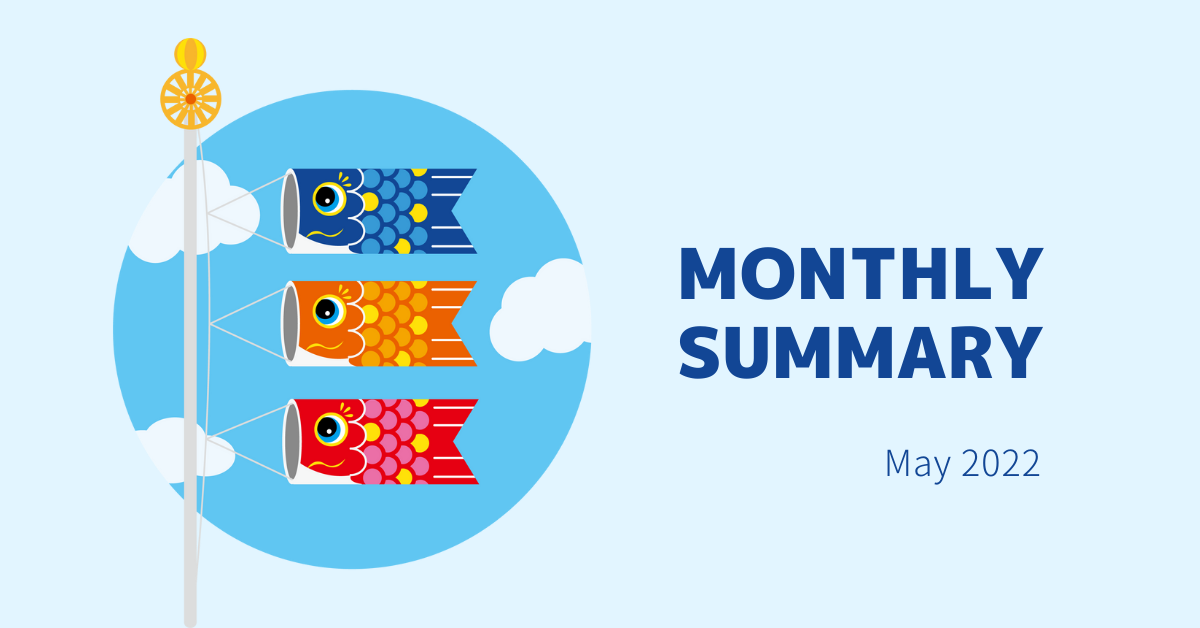お役立ち資料やサービス資料、お問い合わせなどWebサイト上で複数のコンバージョンポイントを設けている方でこんなお悩みはありませんか?
- 商談や申し込みに繋がらない、確度の低いコンバージョン件数が多くなってしまう
- 問い合わせなどの商談や受注につながるコンバージョン件数を増やしたい
- コンバージョンポイントごとに優先度を決めて自動入札を最適化したい
このようなお悩みは、コンバージョン値を各コンバージョンポイントごとに割振り自動入札を活用することで解決する可能性があります。コンバージョン値とは、コンバージョンの価値や売上を指しています。例えばECなどを運営している方だと売れた商品ごとにコンバージョン値を取得して広告管理画面上にて売上を把握し、売上が最大化されるように運用調整をされている方もいるかと思います。
主にコンバージョン値を活用した運用方法はECなどを運営されている方向けの手法だと思われていますが、他の業種業態でも活用できます。今回はEC以外でも活用できるコンバージョン値を利用した広告運用について紹介します。


目次
コンバージョンポイントごとにコンバージョン値を変えて重みづけをする
上記の図のような形でコンバージョンポイントが複数あるビジネスがあります。家族向けの注文住宅やBtoB向けのSaaSツールなど、個人法人向け問わずWeb上で完結しないビジネスだと複数のコンバージョンポイントを設けることが多いのではないでしょうか。具体的にはSaaSツールなどであれば資料請求→問い合わせ→商談→受注のように、資料請求と問い合わせはWebで獲得し、その後は営業が対応して成約する形になります。
このSaaSツールのWebマーケティングで追うべき指標は、大半が資料請求と問い合わせ数になるかと思います。ただ、ここで考えてもらいたいのは、Web上で発生する資料請求と問い合わせは同じ価値があるのでしょうか?
wacul社が調査したサービス概要を説明した資料VSお役立ち資料などのホワイトペーパーはどちらの方が売上に繋がるか?というデータによると、資料請求からは3割が受注に繋がり、ホワイトペーパーからは1割が受注につながったということでした。
参考:サービス資料vsホワイトペーパー。売上につながるのはどちらか?B2BサイトにおけるCVポイントのベストプラクティス研究
ここで伝えたいことは、資料請求、ホワイトペーパー、問い合わせなどによって商談化率や受注率が変わってくるため、コンバージョンポイントごとに価値が変わってくるということです。問い合わせからの受注率が高ければ問い合わせの価値は他のコンバージョンポイントより高く、もっと数を増やせれば売上の最大化に繋がるのではないでしょうか。
自動入札を活用し、費用対効果重視の運用に切り替える
より価値の高いコンバージョンを増やすことに利用できるのがコンバージョン値を活用した運用方法です。まずは、ECなどのビジネスで活用されている運用方法から紐解いて、EC以外の業種での活用方法について考えてみましょう。
ECなどであれば上記図のように商品ごとで売上単価が分かれており、その売上単価がコンバージョン値と等しくなります。バッグが1個売れればコンバージョン値が20,000円になる形ですね。
このようなECではコンバージョン単価(以下、CPA)で目標を管理するよりも費用対効果(以下、ROAS)で管理していることが多いです。ROASについての細かな説明はここでは簡単に言うと「広告経由の売上」を「広告費」で割った数値のことを指します。先のECの例を出すのであれば広告経由で単価20,000円のバッグが1個売れ、かかった広告費は10,000円。そうするとROASは200%になります。ROASの細かな説明などは以下の記事を参考にしてみてください。
もっと知りたい、ネットショップを中心としたビジネスにおけるリスティング広告のROAS運用のこと
ROAS運用のメリットはコンバージョン値が最大化されるように調整可能になることです。さらにGoogle 広告などの自動入札にある目標費用対効果やコンバージョン値の最大化などと組み合わせるとコンバージョン値が高いコンバージョンを優先的に取れるように自動入札が調整をしてくれます。上記のバッグなどの図で考えるのであれば、コンバージョン値の高い、バッグAや指輪Bのコンバージョン件数が増えるでしょう。
一方、目標コンバージョン単価(以下、tCPA ※targetCPAの略)の場合だと、コンバージョン値を考慮せずに目標CPA内で獲得数が最大化されるように動くことが多いので、コンバージョンが取りやすくCPAが安い商品に配信が寄ってしまうケースがあります。
上記の図で考えるのであれば、CPAが安く獲得できるネックレスCのコンバージョン件数が増えてしまいます。安いCPAで獲得は出来ますが、コンバージョン値が低いため、売上が伸びづらくなります。
一方、コンバージョン単価は高いですが、コンバージョン値が高いバッグAや指輪Bのコンバージョン数が増えた方が売上の最大化に繋がります。そのため、ECなどではCPAではなく、ROASで目標を追い、ROASを最大化させるような自動入札を活用するのが有効です。
このようなコンバージョン値を活用した運用方法は主にECだけかと思うかもしれないですが、コンバージョンポイントが複数あるビジネスでも、コンバージョンポイントごとに値を割振れば、ROAS運用を活用できます。
質の高いコンバージョン件数が最大化する可能性がある
コンバージョンポイントが複数あるビジネスでもコンバージョン値を取得できるようして「コンバージョン値が高い=コンバージョンの質が高い」ということを広告媒体に学習させることが出来ます。
例えば、上記の図のように問い合わせを資料請求やホワイトペーパーなどより値を高く設定していれば、広告媒体側では価値が高いと判断します。自動入札と組み合わせると、価値の高いコンバージョンである問い合わせや商談が最大化されるように動きます。
一方、前の見出しでも述べたかもしれないですが、tCPAだと、コンバージョン値を考慮せずに目標CPA内で数が最大化されるように挙動します。そのためコンバージョンポイントが複数あるビジネスだと、安くコンバージョンが取れる、ホワイトペーパーなどに配信が寄ってしまう可能性があります。数よりも質を上げていきたいのであれば、コンバージョン値を取得できるようにし、費用対効果を最大化させる入札戦略の活用を検討してみるといいかもしれません。
コンバージョン値を活用したROAS運用をする上で気を付けること
コンバージョン値を活用した運用方法やメリットについて説明してきましたが、ここからは導入に向けての注意点などを紹介します。
最終目的により近いアクションが最大化されるようにコンバージョン値にグラデーションを
ECなどであればそのまま売上金額を入れればいいですが、EC以外のビジネスだとコンバージョン値をどんな基準で設定すればいいの?と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。そこで値を設定する上での考え方をお伝えします。
最終成約金額から商談化率や受注率を加味して逆算する

上記の図のように受注金額から受注率、商談化率などの数値で逆算して出します。受注単価が20万、商談からの受注率が30%であれば、20万×0.3=商談の価値は6万円となります。商談の価値に問い合わせからの商談化率を掛け算して、このような流れで各コンバージョンポイントごとの価値を算出していきます。
既存のCPAから考える
- ホワイトペーパー|5,000円
- 資料請求|15,000円
- 問い合わせ|50,000円
- 商談|200,000円
- 受注|600,000円
- 直近の資料請求CPA15,000円
既存の配信でホワイトペーパー、資料請求、問い合わせの3つのコンバージョンポイントがあるとしましょう。一番コンバージョン件数のボリュームが多い資料請求が直近CPAが15,000円だとします。直近のCPAを元に資料請求の価値は15,000円と設定。そして自動入札の目標ROASで運用し目標をROAS100%にすると直近のCPAである15,000円を目指して自動入札が働いてくれます。ROAS100%以上(120%とか)で設定するとCPAを低く取りに行く動きやROAS100%以下(90%とか)だとCPAを上げてコンバージョン値を増やすように自動入札が挙動します。
資料請求15,000円という価値をベースにホワイトペーパーや問い合わせのコンバージョン値にグラデーションをつけていきます。
具体的にはホワイトペーパーは資料請求より価値が低いので5,000円以下で設定。一方、問い合わせは資料請求より価値が高いので50,000円。次の見出しで説明するオフラインコンバージョンを活用できるのであれば商談や受注などにも値を割振っていいですね。受注には実際の受注単価も記載してもいいです。受注単価にばらつきがあるものは平均値を入れることを推奨します。
また、受注単価の額がとても高いのであれば、商談などその前の数値からの遷移率で入れることをおすすめします。例えば受注金額が1,000万で月に1件、オフラインコンバージョンで入ってくるとして、問い合わせの価値が5万、商談が20万程度だと、受注との差がありすぎて、自動入札に影響を与える可能性もあるかもしれません。また、受注の数が少ないと自動入札が働かないのでコンスタントにデータが入ってくる商談やアポ確定などのフェーズをオフラインコンバージョンで取りこむことをおすすめするケースが多いです。
いずれにせよここで伝えたいのは、コンバージョンポイントごとに値のグラデーションをつけ、問い合わせや資料請求など受注に近いコンバージョン件数が最大化されるように機械学習を働かせるよう設定してもらいたいということです。価値の高いコンバージョンポイントの値は高く、価値の低いコンバージョンポイントの値は低くすることをおすすめします。
オフラインコンバージョンを活用することも検討
オフラインコンバージョンとは、オフライン上でコンバージョンしたデータを各種広告管理画面に差し戻してカウントすることを指します。イメージが湧きづらいと思うので具体例を出して説明します。BtoBの場合だと資料請求→商談→受注といった流れが受注までの流れかと思いますが、広告管理画面上で計測できるコンバージョンは資料請求までになります。
そこでオフラインコンバージョンを活用して、商談や受注に至ったデータを各種広告のクリックIDや顧客データと紐づけて管理画面上でカウントできるようにします。そうすると、検索広告であれば商談や受注に至った広告グループやキャンペーンを把握することが出来たり、商談や受注までを意識した運用調整が可能となります。
また、このオフラインコンバージョンに値を割り振りすれば、資料請求より値が高い商談や受注数を最大化するように調整することも可能です。
オフラインコンバージョンについては以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。
Google 広告は「コンバージョン値のルール」も検討を
Google 広告で計測されるコンバージョン値を、コンバージョンしたユーザーの属性によって、調整できる機能「コンバージョン値のルール」が登場しました。
こちらはユーザーの属性に基づいてコンバージョン値の処理に関するルールを事前設定し、コンバージョンに至った際に計測されるコンバージョン値をそのルールによって、入札戦略とレポーティングで重み付けできる機能です。
例えば1件当たりのリードの価値が10,000円のビジネスがあるとしましょう。
首都圏からのリードは商談に繋がりやすいため、価値を12,000円に。
四国地方からのリードは商談化率が低いから価値を8,000円に。
といったように地域、オーディエンス、デバイスごとに条件を満たすリードの値にルールを設けて変更することができます。
より、リードの値に現状のビジネス状況を踏まえて重みづけができるようになっています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
Google 広告であれば導入までに最低でも約2か月ほどかかる
コンバージョン値を設定していない場合、まずは値を設定しましょう。主に活用することの多いであろうGoogle 広告の自動入札は過去30日間のコンバージョンの傾向を加味して調整が実施されるため設定してからすぐに自動入札をONにするのは避けましょう。
これまでコンバージョン件数のデータはアカウント上に残っているかもしれませんが、コンバージョン値のデータについてはまだ取得できていない状況になりますので、コンバージョン値を活用した自動入札を実施する上で十分なデータが溜まっていない状況になります。そのため、コンバージョン値を設定してから最低でも30日間ほど様子を見ることをおすすめします。
目標広告費用対効果に基づく入札をキャンペーンで使用するには、過去 30 日間にコンバージョンを 15 件以上獲得している必要があります。この条件は、ほとんどのキャンペーン タイプに適用されます。
Google 広告の自動入札である目標広告費用対効果を活用するのであれば上記のコンバージョン件数が最低でもある状況が好ましいです。
さらに、自動入札を入れてからも学習期間がかかり、成果が安定するまで1週間~2週間ほどの期間がかかることが多いので、値の割り出しや設定、データ取得し自動入札を導入、パフォーマンスが安定まで、おおよそ2ヶ月くらいを目安に見た方がいいかなと考えています。
Google 広告以外の媒体でもコンバージョン値を入れてからすぐに自動入札を入れずに、各媒体ごとの学習期間を考慮してから費用対効果を最大化させる入札戦略の活用することをおすすめします。
ROAS導入前後の数値を確認して効果測定しよう
ROAS運用の一番の目的は価値の高いコンバージョン件数の最大化です。価値の高いコンバージョンである資料請求や問い合わせは、ホワイトペーパーなどの価値の低いコンバージョンに比べてCPAが高くなる傾向にあります。そのため、ROAS運用導入直後はCPAが高く見えることが多いですが、目的である価値が高いコンバージョン件数が増加していることに焦点を置いて施策の判断をする必要があります。
施策の目的から考えて成果の判断を考えていきましょう。
数よりも質が求められるフェーズなどで活用できる
近年、運用型広告の進化によりリード獲得がしやすくなってきました。しかし、その影響で量は集まるが、商談や受注に繋がらない質の低いリードも増えた。という問題もよく聞きます。今回紹介した方法はリードの質を高めてくれる可能性があるので、フェーズや状況によっては一度、チャレンジしてみる価値があるのではないでしょうか。