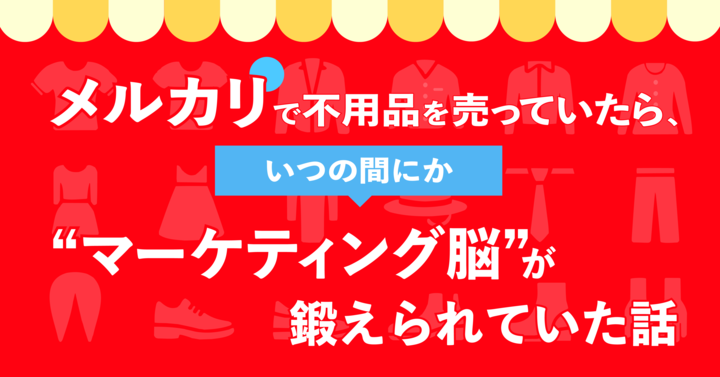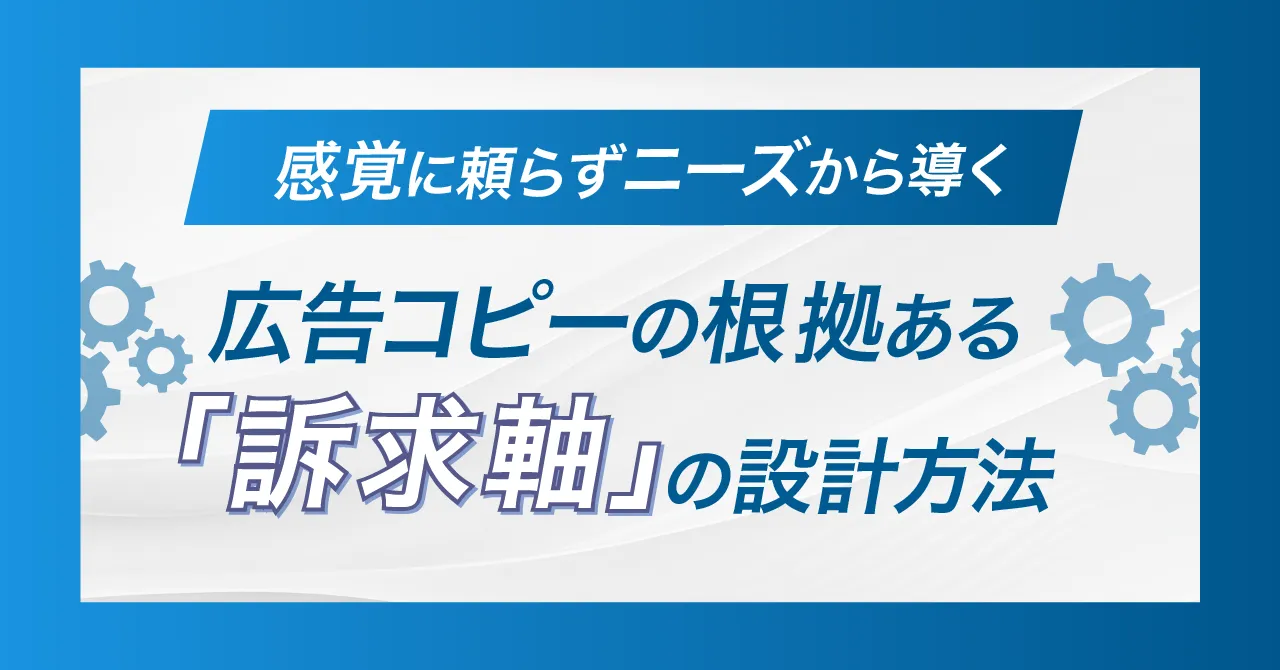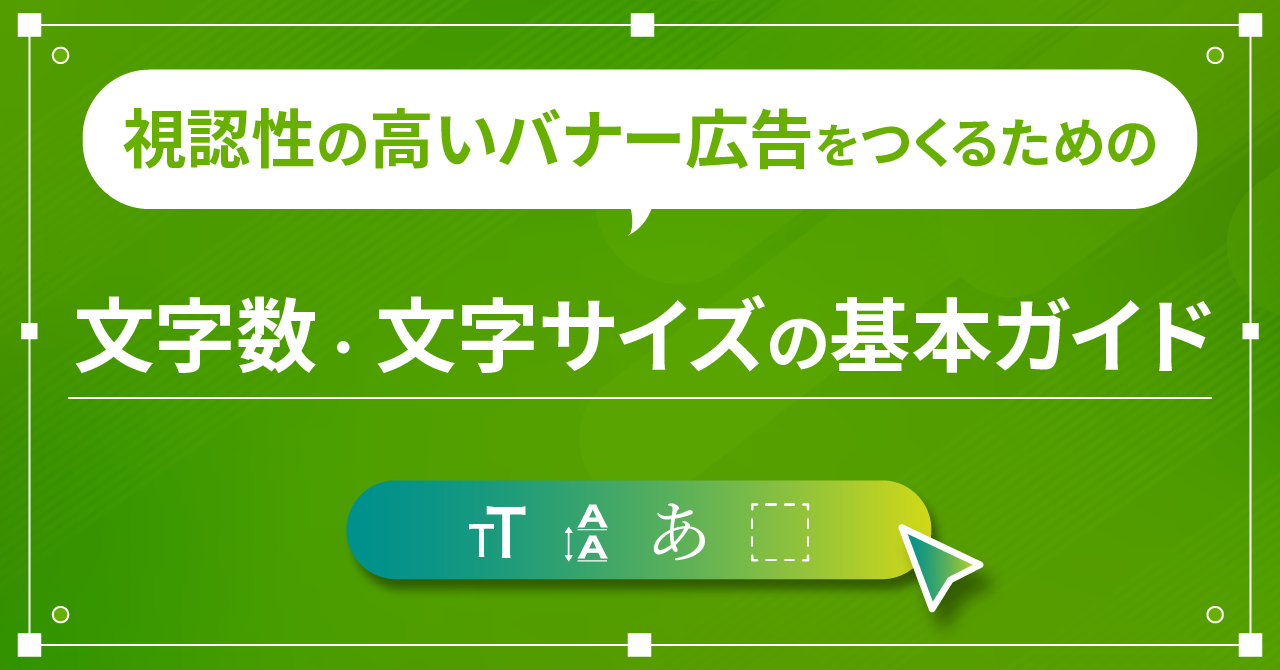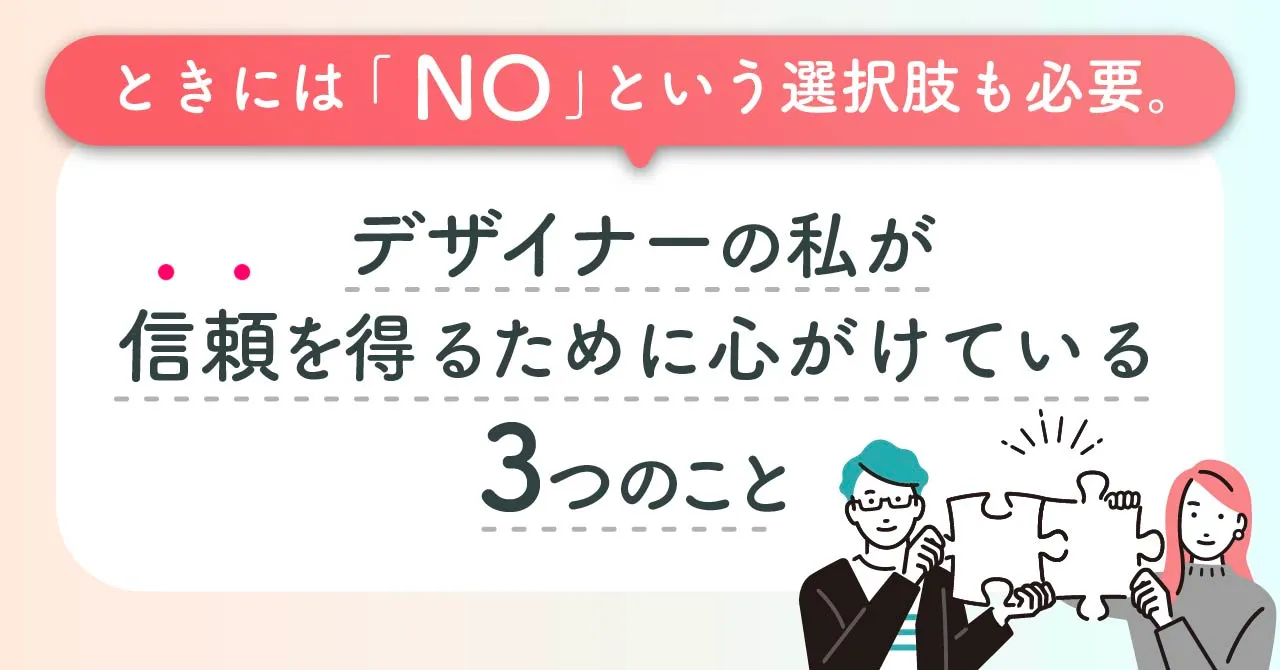
デザイナーとして仕事をしていると、「依頼主の言った通りのクリエイティブを制作するだけで本当にいいのかな」「もっと自分から積極的に提案したいけど、何から始めれば良いのかわからない」と悩むことがあります。
依頼主の期待に沿ったクリエイティブを作ることはもちろん重要です。しかし、「どんなクリエイティブなら成果が出るのか」「そもそも成果向上のために何が必要なのか」といった上流の段階からデザイナーが携わることで、アウトプットはより良いものになります。また、発注者と受注者の関係ではなくチームの一員として、より欠かせない存在になれるでしょう。
今回は、マーケティング支援会社でデザイナーとして働く私が、周囲から信頼を得るために心がけている3つのことをご紹介します。
「デザイナーとして一歩前進したい」と考えている方のヒントになれば幸いです。


根拠ある提案のためにまずは定量・定性データの分析をする
きちんと成果を出し事業成長に寄与するために、クリエイティブは「感覚」ではなく「根拠ある仮説」に基づき制作を行います。
仮に同じ提案をするとしても、「この提案はどんな根拠に基づいているのか」によって相手の受け取り方は大きく変わるでしょう。
<例>
根拠の薄い提案:
「動画広告にナレーションをつけましょう。他の広告もナレーションがついているものが多いので、同じようにするときっと成果が伸びますよ」
根拠のある提案:
「動画広告にナレーションをつけましょう。ターゲットであるZ世代は、別の作業をしながら映像を見る”ながら見”をする人が8割という調査結果があります。どんな状況でも情報が伝わるようにするには、映像やテロップなどの視覚情報だけでなく、聴覚で情報を伝えることができるナレーションも入れると効果的です。」
実際のデータをもとに根拠をお伝えすることで、説得力は段違いになりますよね。
提案にあたっては、以下のようなデータをもとに分析しています。
- 総務省などから発信されている定量データ:市場のボリュームからセグメント分析をする場合に有効。
- 競合と比較した際の優位点:事業のポジショニングの見直しを行う場合に有効。
- ヒアリングで得た情報:会社や依頼者の実情を加味して、施策の優先度を検討する場合に有効。
- 各種アンケート、SNS、通販サイトなどの口コミ:消費者のインサイトを正確に把握した上で施策を練る場合に有効。
結果報告と次のステップをセットで提案する
たとえば広告用のバナーやLP(ランディングページ)制作を行った後は、成果の報告だけでなく、次の施策の提案もセットで行います。
配信しているクリエイティブの成果が良くても悪くても、「今回の成果はこんな感じでした」の一言で終わる報告では、「この人に任せていて大丈夫なんだろうか」と不安になりますよね。
依頼主としては先回りで提案があることで安心できますし、施策の方向性を共有することでお互いの認識のズレを防ぐことにもつながります。
<例>
成果のみ報告する場合:
今回のバナーは、コンバージョン率が低かったです。クリック率は高かったので、訴求内容には興味を持ってくれていると思います。
成果報告と提案をセットで行う場合:
今回のバナーは、クリック率は高かったもののコンバージョン率が低かったです。「訴求内容に興味を持ちリンクをクリックしたものの、バナーで抱いた印象とLPの内容にズレがあり、離脱してしまった」という仮説が立てられます。
まずはLPのどこで離脱したのかを分析し、分析結果を踏まえて改めて〇月〇日までにバナーやLPの改善提案を行います。
このように、配信結果に基づいた仮説と次のアクションを繰り返しています。
クリエイティブのPDCAの回し方について詳しく知りたい方は、下記記事をご参照ください。
すべての要望に応えること=信頼を得ることではない
依頼主からの依頼に「YES」と答え続けることは可能かもしれません。
しかし、成果が見込めない場合や実行が現実的でない場合など、依頼主にとって不利益になる可能性がある依頼に対しては、ときには「NO」という選択も必要です。
例えば、分析や仮説を立てる時間を確保することができないほどのペースでクリエイティブの制作依頼が来たとします。
このような依頼を熱量だけで引き受けてしまうと、多忙のあまり「成果を出す」という本質を見失ってしまい、「納期に間に合わせること」に目的がすり替わってしまうかもしれません。これでは、依頼主にとっても自分自身にとってもマイナスになってしまいますよね。
単に「NO」と言うだけでなく、「要望に応える場合の懸念点」「懸念点を回避するために現実的に可能な納期や代わりのアクション」を提示することを心がけています。
<伝え方の例>
「いただいた納期だと、分析に時間を割けず、納得のいく検証ができない可能性があります。過去の配信結果や既存ユーザーの口コミ分析を行った上で訴求内容の提案をしたく、〇月〇日までお時間をいただくことは可能でしょうか?」
闇雲にお断りするのではなく、このようにYESの判断をできない理由と、代わりの改善案を添えることが、依頼主との信頼関係を築く上でとても大切です。
まとめ
デザインは単なる見た目の良さではなく、ビジネスを成長させるための重要な手段です。
デザイナーが信頼を得るためには、根拠のある提案、先を見据えた報告、そして関係者の意向を尊重しつつも、新たな選択肢を提示する姿勢が大切だと考えています。
こちらの記事では、未経験から運用型広告のデザイナーとして短期間で戦力になるために実際に取り組んだことを紹介しています。デザイナーとして成長したいとお考えの方は、こちらも併せて参考にしてみてくださいね。