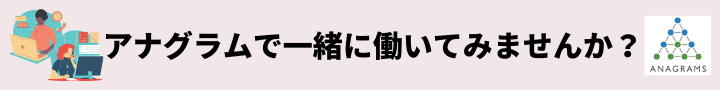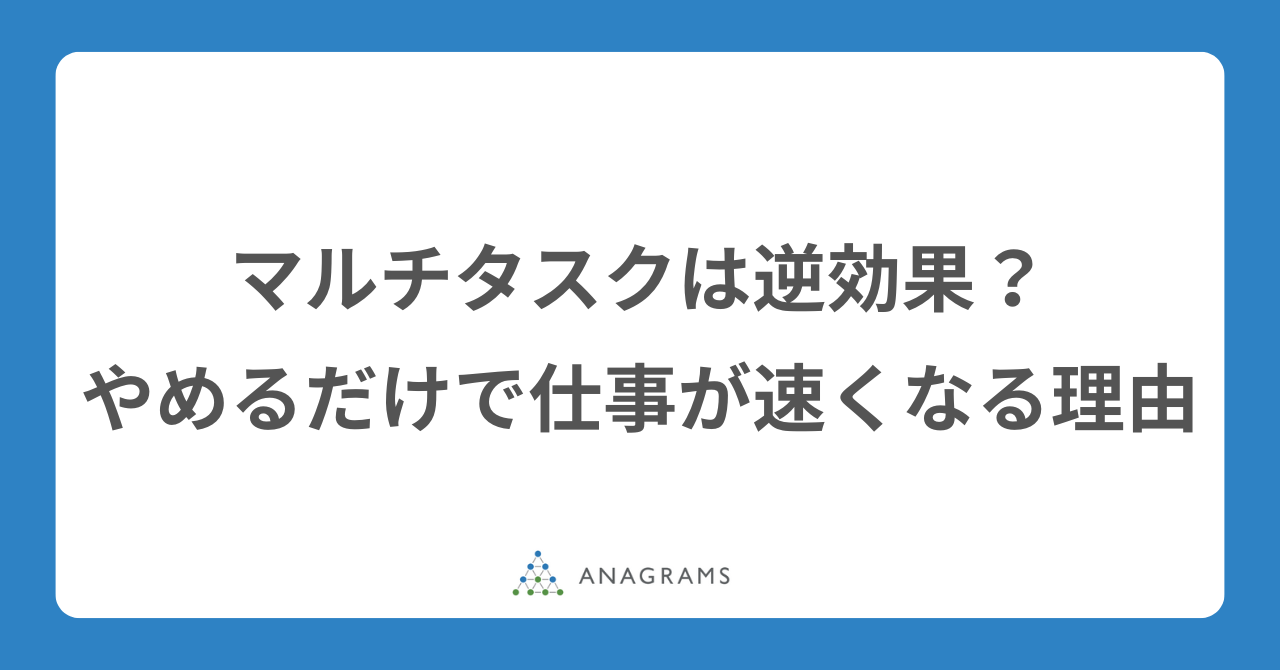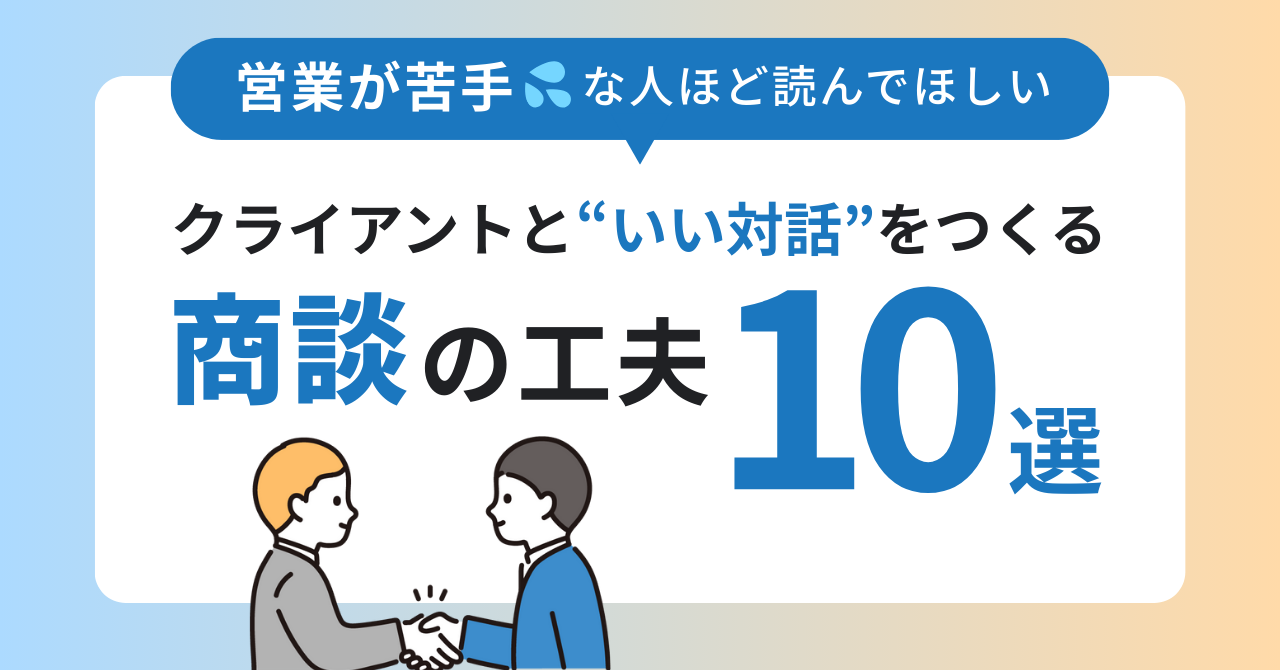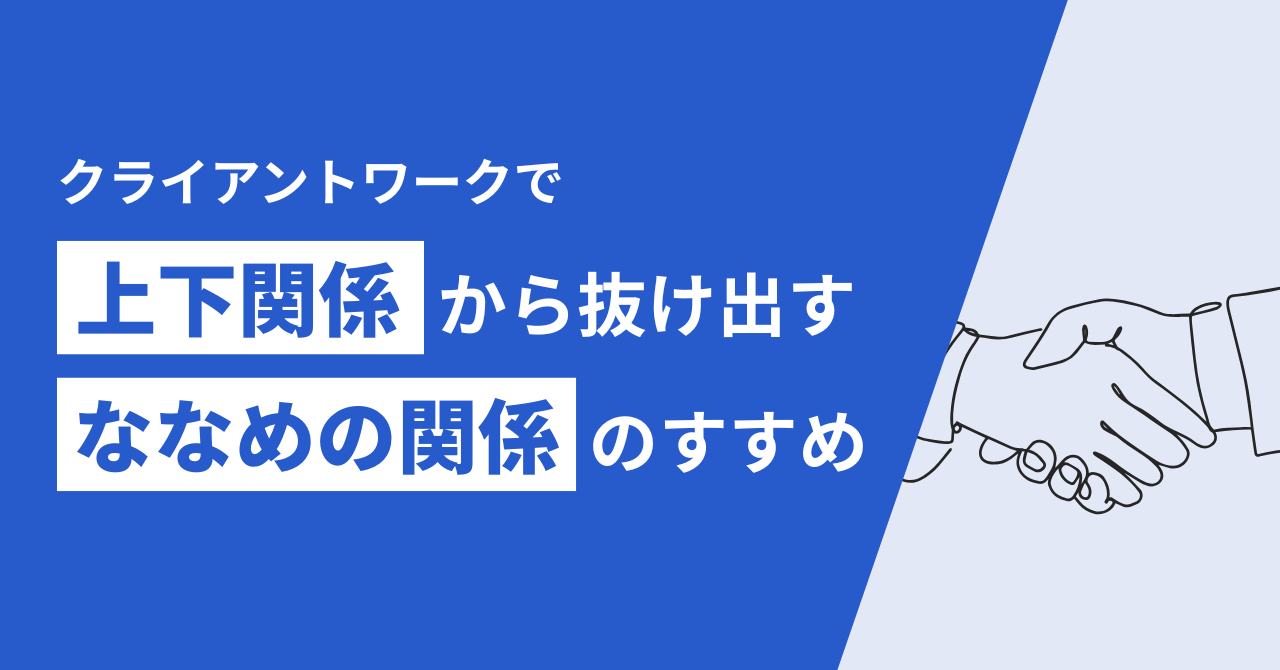
広告代理店やコンサルティングの現場では、「クライアントとどう距離を縮めるか」が成果に直結する場面が多くあります。
しかし、「対等な立場で話したい」と思っていても、いざ話す場面になると相手の反応を気にしすぎて、本音をうまく引き出せず、結果としてこちらの考えだけを伝える一方的な提案になってしまうことも……。
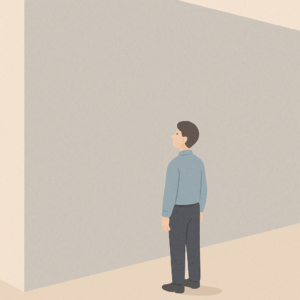
私自身、まさにそんな悩みを抱えていました。当時は「コミュニケーションが苦手だから仕方ないのかも」と諦めそうになっていたのですが、あるとき、ふとしたきっかけでその感覚が変わったんです。
ヒントになったのは、社内で定期的に1on1をしていた、別部署の上司や役員——いわゆる「ななめの上司」とのやりとりでした。
この記事では、「視点の持ち方ひとつで、関係性はこんなにも変わるのか」という私自身の体験をお伝えします。クライアントとのコミュニケーションで、悩んでいる方のヒントになれば幸いです。


目次
なぜクライアントに対して身構えてしまうのか?
クライアントとの距離が縮まらない原因は、コミュニケーションスキルの不足ではなく、無意識に上下関係を作ってしまっていることかもしれません。
私自身、クライアントワークを始めたばかりの頃は、毎回の打ち合わせに緊張しすぎて、言葉が硬くなってしまっていました。
頭のどこかで「クライアントは評価する側」「お金を払っている人=正しい側」という意識が強くあり、「ちゃんとしなきゃ」「完璧に提案しなきゃ」と力が入ってしまっていたのだと思います。
その感覚の原点を振り返ると、大学時代の飲食店のアルバイト経験に行き着きます。「お客様は神様」というマインドが体に染みついていて、「外部の人には失礼があってはいけない」という思い込みが自然と根付いていたのです。
さらに、社会人になってからは「自分はプロであるべき」という意識が加わり、「失敗してはいけない」「不確かなことは言ってはいけない」と、自分自身に過剰なプレッシャーをかけていました。
その結果、クライアントと接するときは常に試されているような感覚があり、本音で話せず、会話も一方通行に。当たり障りのない言葉しか出てこなくなり、距離を縮めるどころか、むしろ壁をつくってしまっていたのです。
“ななめの上司”という視点がくれた気づき
それまでの私は、クライアントとうまく話せない理由を「コミュニケーションが苦手だから」だと思っていました。でも、あるときふとした違和感を覚えたのです。
当時の私は社内の別部署の上司や役員にお願いして、頻繁に1on1をしてもらっていました。直上司ではなく、いわゆる“ななめの上司”との時間です。
不思議なことに、その1on1では、構えることなく自然に話せていたんですよね。
ななめの上司は、直接的に業務に関わるわけではないけれど、課題や悩みに耳を傾けて必要な支援や助言をくれる存在。加えて、自分と違う部署や役職の視点を持っているからこそ、「それってこういう見方もできるんじゃない?」と視野を広げてもらえることも多く、毎回の会話が前向きに終わる感覚がありました。
この「気兼ねなく相談できて、異なる視点ももらえる」という関係性は、よく考えてみるとクライアントにも通じるものがあるなと気づいたんです。
クライアントもまた、日常的に密に接しているわけではないけれど、必要な背景情報の共有や社内調整などを通して、こちらの働きをサポートしてくださる存在です。
それに気づいたとき、「相手の捉え方を変えれば、クライアントに対して必要以上に身構えず、対話ができるのでは?」とハッとしました。
そこで試してみたのが、「クライアントを“ななめの上司”だと思って話す」というマインドセットの切り替えです。
上下関係ではなく、“ななめの関係”と捉えてから変化した3つのこと
クライアントを“ななめの上司”と捉えるようになってから、こちらのふるまいが少しずつ変化し、結果として相手の反応も変わっていきました。

①提案は「完璧に答えを出さなきゃ」から「一緒に考えよう」へ
当時の私は、「曖昧なことを言ってはいけない」「自分が答えを出さなければいけない」と思い込んでいたため、「これが良いと思います」と一方的な提案になってしまっていました。
でも「ななめの関係」だと思ってみると、むしろ目標達成のために相談し合う仲間のような気持ちで話せるようになり、分からないことや判断が分かれる点も素直に共有できるように。
「私の中ではこう考えたのですが、御社の視点からはどう見えますか?」と聞けるようになり、会話が一方通行ではなくなっていきました。
②質問は「失礼のないように」から「相手を知るために」へ
クライアントとの会話では、相手に失礼のないようにと気を配るあまり、つい遠回しな聞き方になってしまうことがよくありました。
「なぜこの依頼がきたのか」「社内でどんな意思決定があったのか」といったことも、本当は聞きたいのに踏み込めずに終わってしまう。
でも、ななめの関係だと思って接してみると、相手を“評価する立場”ではなく“協力してくれる相手”として見られるようになり、率直に聞けるようになったんです。
実際に、「この方針になった背景って、なにか社内で動きがあったんですか?」と少し踏み込んで聞いてみると、社内の状況を丁寧に共有していただけました。結果的に、単に依頼に応えるだけではなく、別部署の意向も汲んだ提案をして、喜んでいただけたのをよく覚えています。
「聞く=失礼」ではなく、「知ろうとする=信頼の第一歩」なのだと、改めて実感した出来事でした。
③関係性は「専門家」から「信頼される相手」へ
以前は、クライアントから相談されるのは、自分の専門領域である運用型広告に関することだけでした。
しかし、自分だけでは答えが出ないことを素直に伝えたり、組織やサービスについてどんどん質問するようになったことで「この人は背景までちゃんと理解しようとしてくれる」と感じてもらえたのか、ある時からSNS運用や顧客管理システムの課題などについても、声をかけてもらえるようになったんです。
もちろん、すべて自分で解決できるわけではありません。しかし、「この人なら話しても大丈夫かも」「まずは相談してみよう」と思ってもらえるようになったこと自体が、自分にとっては大きな変化でした。
「頼られる関係性」は、専門知識だけでなく、どう向き合ってきたかによって築かれていくのだと思います。
「関係性」は、捉え方から変えられる
クライアントとの関係性を変えるのに、特別なスキルやテクニックは必要ありません。「どう捉えるか」たったそれだけで、ふるまいも、相手の反応も変わっていきます。
私は今、広告支援の現場で日々クライアントと関わっていますが、各社のマーケティングチームの一員になった気持ちで取り組んでいます。
もちろん、人によって心地よい距離感は違いますが、私の場合は「少し距離のあるななめの上司」と捉えることで、必要以上に構えず、等身大で接することができるようになりました。
もし、今この記事を読んでいるあなたが「クライアントと壁を感じてしまう」「緊張してうまく話せない」と思っているなら、次の打ち合わせの前に、そっと心の中で唱えてみてください。
「この人は、ななめの上司だ」と。
きっと、少しだけ会話がラクになり、これまでとは違う時間を過ごせるはずです。