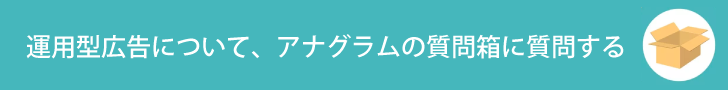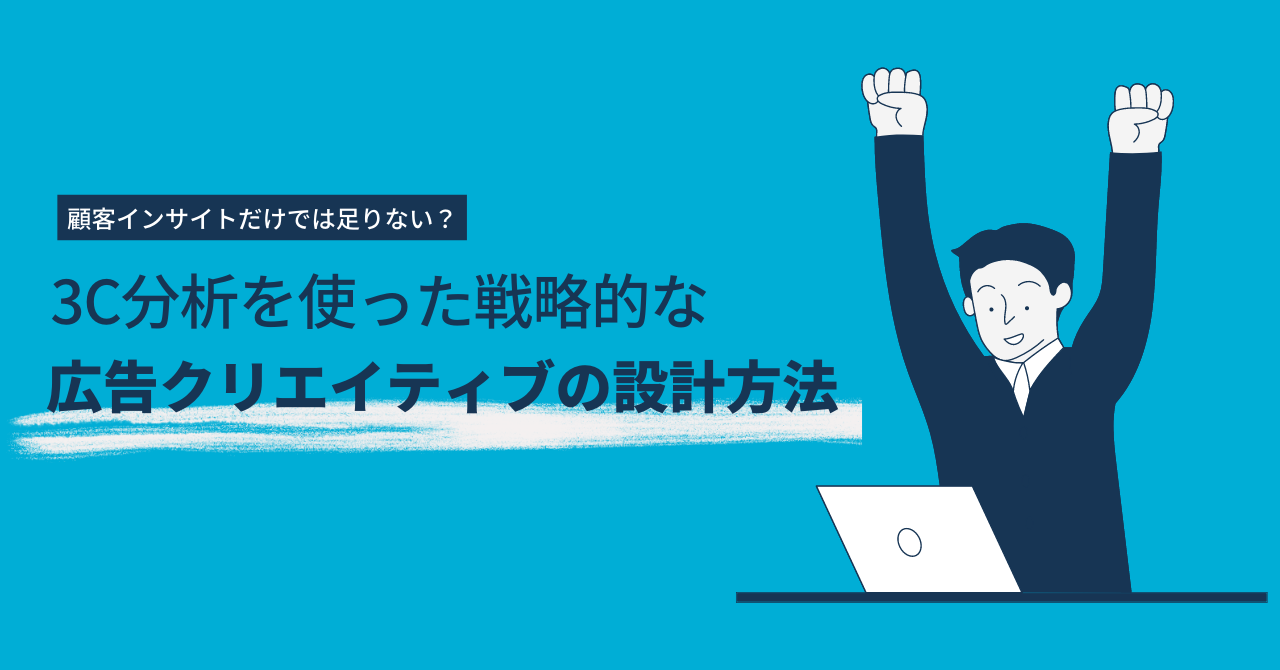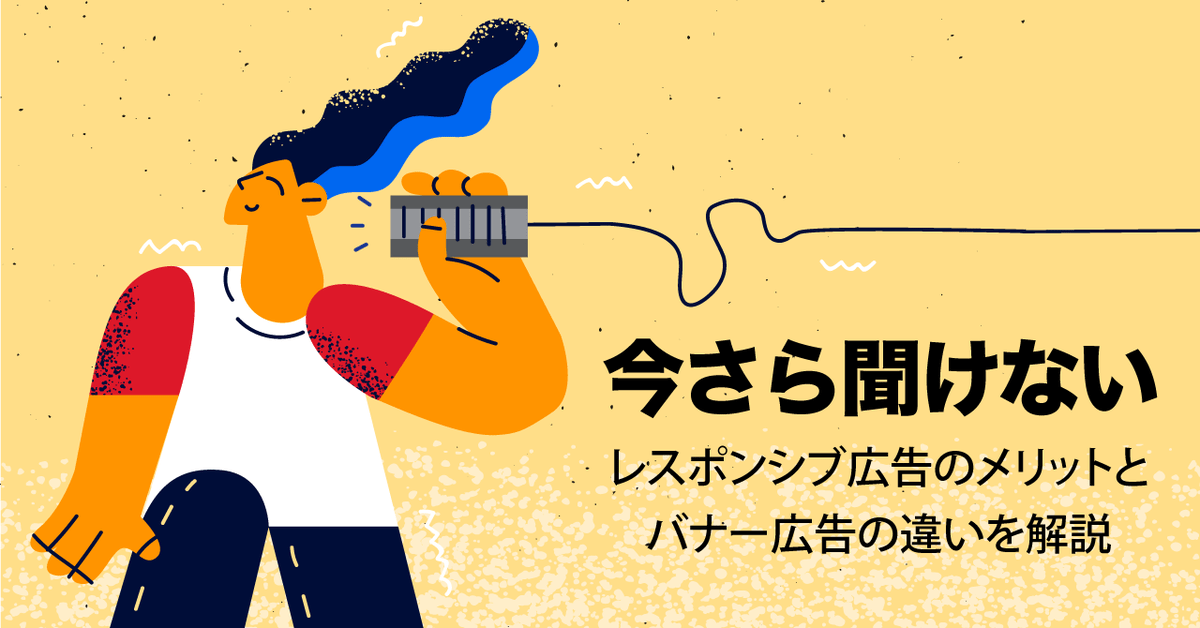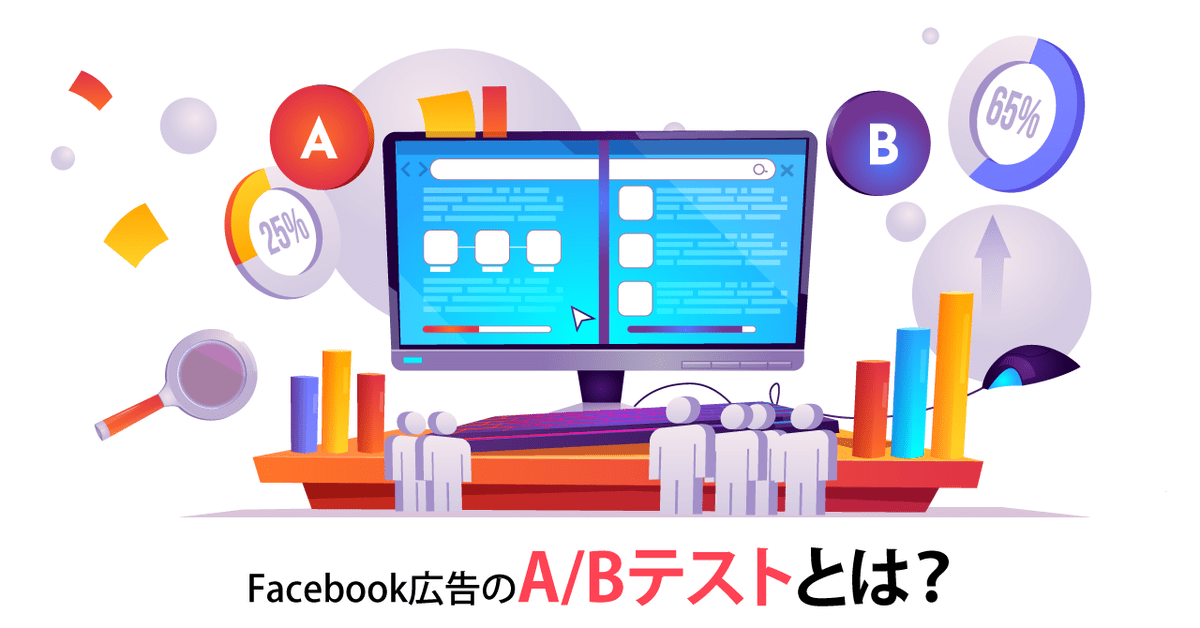※2019年10月11日:最新の情報をもとに更新
運用型広告媒体のコンバージョントラッキングは、次の2つの理由から不可欠な機能です。
- 広告配信の成果を可視化できる
- 配信セグメントごとの成果を比べながら最適化をかけられる
ただ、いざコンバージョン数をみると、「実際の売れた数と合わない…」となることがよくあります。実はこのコンバージョン数と実際の広告効果との乖離、コンバージョン計測の仕組み上どうしても起こってしまうものなのです。運用型広告を運用していると必ずぶち当たるこの乖離の原因について解説します!


目次
乖離が発生する8つの要因
1. 広告媒体ごとの重複
ユーザーは自然検索や検索連動型広告・ディスプレイ広告、SNS広告など、様々なメディアを経由してコンバージョンに至ることがあります。複数の広告媒体の広告をクリックしてコンバージョンに至った場合、コンバージョン経路上にあった広告媒体の管理画面レポートそれぞれにコンバージョンがカウントされます。

・「Googleの検索連動型広告」と「Google ディスプレイ広告」は同じGoogle 広告アカウントの広告とします。
・同じデバイスの同じブラウザを用いた場合とします。
・Google 広告のアトビリューションモデルはラストクリックの場合とします。
・例中のGoogle 広告の検索連動型広告をクリックしてからコンバージョンまでの日数は30日以内とします。
上記の場合、広告管理画面上のコンバージョン数は次の通りになります。
- Google ディスプレイ広告:1件
- Criteo:1件
- Facebook広告:1件
合計すると3件ですが、実際は1件しかコンバージョンしていませんね。複数の広告媒体で広告配信を行っていると重複はどうしても起こってしまうもので、特に検討期間の長い商材ではユーザーが複数のメディアに触れてコンバージョンに至りやすいため重複率が高い傾向があります。
また、Google 広告は検索連動型広告とディスプレイ広告とで2回クリックされていますが、広告管理画面上で見ると最後にクリックされたディスプレイ広告のみにコンバージョンが付きます。
2. 直接的でないコンバージョンが合算されている
広告が表示されたユーザーがコンバージョンに至った場合、それを広告の成果としてコンバージョンにカウントする計測が「ビュースルーコンバージョン」です。ビュー(広告表示)スルー(経由)で付くコンバージョンですから、その性質上、ビュースルーコンバージョンはクリックスルーコンバージョンよりも多く計上されやすい傾向があります。
そのため、もし実際の広告効果よりもコンバージョン数の方が多いと感じていて、かつビュースルーコンバージョンをコンバージョンに含めている場合は、ビュースルーコンバージョンをコンバージョンに含めることが実際のコンバージョンへの貢献度に見合っているか、念のため確認することをおすすめします。
Facebook広告では、デフォルトの設定でクリックスルーコンバージョンに加えて「広告表示から1日以内のコンバージョン」、つまりビュースルーコンバージョンをコンバージョンとしてカウントする設定になっています。
設定を変えれば、広告表示から1日以内のビュースルーコンバージョンを含めず、クリックスルーコンバージョンのみでコンバージョン計測することもできますが、仕様を理解していないとなかなか気が付きませんよね。
また、Twitter広告でも、リンクのクリックだけでなく、インプレッションや、広告からのエンゲージメント(リツイート、いいねなど)によって発生したコンバージョントラッキングとなっています。またFacebook広告と同様に1日以内のビュースルーコンバージョンもデフォルトではコンバージョンに含めています。
このように広告プラットフォームによってもコンバージョンの定義はさまざまで、数字の乖離の理由のひとつとなっているのです。
3. コンバージョンタグがきれいに読み込まれていない
広告のトラッキングはコンバージョン トラッキング タグ(コード)をウェブサイトの特定のページで読み込ませることによって可能にしています。そのため、何らかのトラブルで、コンバージョンタグが読み込まれなかったり、過剰に読み込んでしまったりすることがあると正常に計測ができません。以下のようなトラブルが起こっていないでしょうか?
そもそもコンバージョンタグの設定が間違っていないか?
- コンバージョンタグが全てのコンバージョンページに埋まっていない
- コンバージョンタグが、広告媒体の指定するページの設置個所に正しく設置されておらず、読み込まれていない
- タグのコードが間違っている(コードのコピペミス、不要な改行コードなど)
- タグマネージャーの設定が間違っている(コンバージョンページのURLを指定する正規表現の間違い)
これらの設定面の不備で、コンバージョンが正しく計測できていないケースもあります。コンバージョンタグがすべてのコンバージョンページに正しく設置され動作しているか再度確認してみましょう。
参考:リスティング広告の「コンバージョンが計測されない」を解決する4つの問いとチェック方法
トラブル的な要因で、コンバージョンタグが読み込まれていないか?
- ユーザーがコンバージョンページを開いた状態で、ブラウザの「更新」ボタンや、「戻る」「進む」ボタンを押してしまう
- ユーザーがコンバージョンページを開いた状態でブラウザを閉じ、再度開いた際にコンバージョンタグが読み込まれてしまう
- サイトの管理者が、広告クリックしたブラウザでコンバージョンページまわりの改修などを行いコンバージョンタグが読み込まれてしまう
これらのトラブル的な要因で、コンバージョンが広告管理画面上で多く計上されるケースがあります。Google 広告やYahoo!プロモーション広告のスポンサードサーチ(以下、スポンサードサーチ)、Yahoo!ディスプレイアドネットワーク(以下、YDN)であれば、コンバージョンの計測方法を「初回のみ」に設定することで、同じブラウザで何回コンバージョンしてもコンバージョンは1件とカウントされるため、重複を減らすことができます。
4. コンバージョンのカウント方法が違う
1人のユーザーが3回コンバージョンに至った場合、そのコンバージョンを1回とカウントするか、3回とカウントするかは広告管理画面で設定が可能です。しかし、その計測仕様を知らずに本来は「総コンバージョン」で計測すべきものを広告管理画面において「ユニークコンバージョン」で計測していたら、それは乖離が生まれますよね。
1回の広告クリックで2回コンバージョンが発生したら、カウントも2回とする計測方法です。例えば、総合通販サイトのように商品を複数回「購入」する可能性があるサービスの場合はこちらの計測方法をおすすめします。例えば、Google 広告では「全件」、スポンサードサーチとYDNでは「毎回」がそれにあたります。
ユニークコンバージョン:
1回の広告クリックで2回コンバージョンが発生しても、カウントは1回とする計測方法です。1人のユーザーが複数回コンバージョンすることがない「会員登録数」などをコンバージョンとする場合はユニークコンバージョンで計測した方が良いでしょう。例えば、Google 広告やスポンサードサーチ、YDNの「初回のみ」がそれにあたります。
一部の媒体では、そもそも総コンバージョンのみしか計測できない仕様の広告プラットフォームもあります。「コンバージョン」と一口にいってもこの2つは計測対象が大きく異なりますので、まずは計測仕様をきちんと把握しておきましょう。
5. 広告管理画面上のコンバージョン日と実売日がズレている
Google 広告・スポンサードサーチ・YDN・Facebook広告・Twitter広告の広告管理画面上のコンバージョンは、広告が最後にクリックされた日(Twitter広告の場合はエンゲージメント日)に計上されます。つまり、2週間前に広告クリックしたユーザーがコンバージョン(商品購入)した場合、売上として記録するのはもちろん当日ですが、広告管理画面上では2週間前の過去レポートにコンバージョンが1件増えます。
例えば、2月23日に広告クリックして3月2日に商品を購入してコンバージョンした場合は、以下のようになります。
広告管理画面:2月23日 1件
実売数:3月2日 1件
前月にコンバージョンが付いてしまいますね。特に、検討期間が長い商材では、集計期間を跨いで広告の成果がズレ込んでいないか注意が必要です。
Googleアナリティクスや一部のDSP・アドネットワークのレポートでは、クリック日では無くコンバージョン発生日にコンバージョンが計上されます。また、Google 広告でもアトリビューションモデルの変更が可能となっているため、必ずしもラストクリックとはならないため、注意しておきましょう。
参考:アトリビューションとは:5分でわかる意味と5つの基本モデル
6. 実売数にウェブサイト上で完結しない売上が入ってしまっている
コンバージョンが付いていなくても、ウェブサイト内に載っている電話やファックスから注文が入っているケースもあります。ウェブサイト内に大きく電話番号を載せている場合は注意が必要です。
ただしGoogle 広告やスポンサードサーチであれば、電話発信コンバージョンの設定をすることで、スマートフォンやタブレット端末で電話番号を直接タップした回数(電話発信コンバージョン)の計測が可能です。それにより、実売数との乖離を軽減できます。
しかし実際に電話がつながったタイミングではなく、クリックしたタイミングをコンバージョンとして計測されるため、誤って電話番号のリンクをクリックして、つながる前に電話を切った場合なども電話発信コンバージョンとして計測されます。そのため、必ずしも正確なコンバージョン数を計測できる訳ではありませんが、電話発信コンバージョンの割合を図ることで、それらを踏まえた運用が可能になります。
参考:Google 広告・Yahoo!スポンサードサーチ、電話発信コンバージョンの基本と設定方法
参考:Google タグマネージャー(GTM)で電話発信タップを計測する方法
7. クロスデバイスコンバージョンの計上の違い
クロスデバイスコンバージョンとは、異なるデバイスで発生した広告クリックとコンバージョンが同一ユーザーだと判断された際、広告クリックしたデバイスにコンバージョンがカウントされることです。媒体ごとに同一ユーザーと判断する情報は異なりますが、Google 広告、スポンサードサーチ、YDNでは、cookie情報とログイン情報を元に、Facebook広告はログイン情報を元に判断しています。
実売数をGoogle アナリティクスや独自の広告効果測定ツールで計測している場合、広告管理画面上のコンバージョン数が実売数よりも多くカウントされることがあります。
8. Cookie情報の遮断によりトラッキングができない
コンバージョントラッキングの大半はまだまだブラウザに保存されるcookieデータに依存しています。そのため、iOSのWebブラウザのSafariで提供されているITP(Intelligent Tracking Prevention)と呼ばれる機能により、Cookie情報がトラッキングに利用できないケースがあります。
各媒体でこれに対する対策をとっていますが、さらにApple社による対策が講じられ、正直イタチごっことなっているのが現状です。
参照:Google アドワーズ、SafariのITP機能の影響下でも、より正確に計測できる3つのコンバージョン計測方法を発表
どうすればいいのか
広告管理画面上のコンバージョン数と実売数の乖離は、広告運用者に対する不信感を煽りがちな部分だと思います。乖離が無視できないほど大きくなっているとき、広告運用者側としてどのように動けばいいのでしょうか?
まず乖離の原因を究明したうえで設定面に問題が無いようなら、広告主(インハウスであれば上司)側に「どうしても乖離は起こってしまう」という事情を説明しましょう。コンバージョン数の乖離が起こる事情は、よほど運用型広告に詳しくないと知らない部分なので、まずは広告主側にしっかり説明することが大切です。
また一方で、広告運用側から見ると、実際の広告効果というのはどうしても見えづらいところです。そのため、広告主側にしっかりヒアリングし実際の広告効果を調べてもらったうえで、以下のような流れで与件を整理できればベストです。
- コンバージョン数と実際の広告効果がどのぐらい乖離しているのか、ザックリでも良いので把握する。
- コンバージョン数と実際の広告効果の乖離まで見越して、広告媒体レポート上で見たコンバージョン単価の目標を決める。
広告媒体レポート上の目標まで落とし込めることができれば、その目標を目安に配信のセグメントごとの細かいチューニングまでかけていけるので、改善の延びしろが大きくなります。
まとめ
広告主は、売上・利益を上げて世の中を変えていくこと、ブランドイメージを定着させることなど様々な思いから、お金を費やして広告を打っています。 コンバージョントラッキングは、あくまでこの大きな目標に対して広告費用対効果を高めるための手段にすぎません。広告管理画面上のコンバージョンだけに捕らわれず、大きな目標に向かうためにはどうすればいいのかを常に考えながら、広告配信を行っていきたいですね!