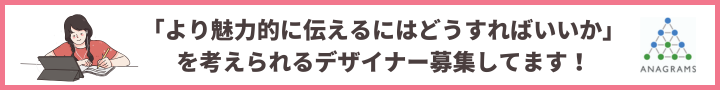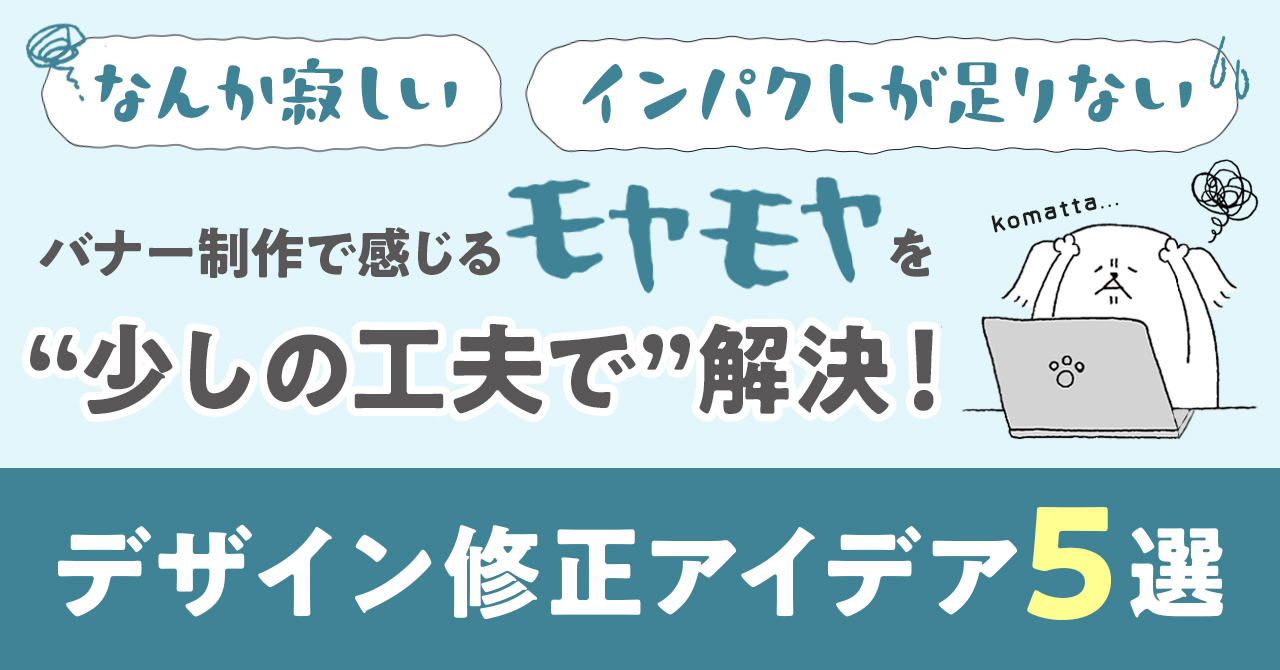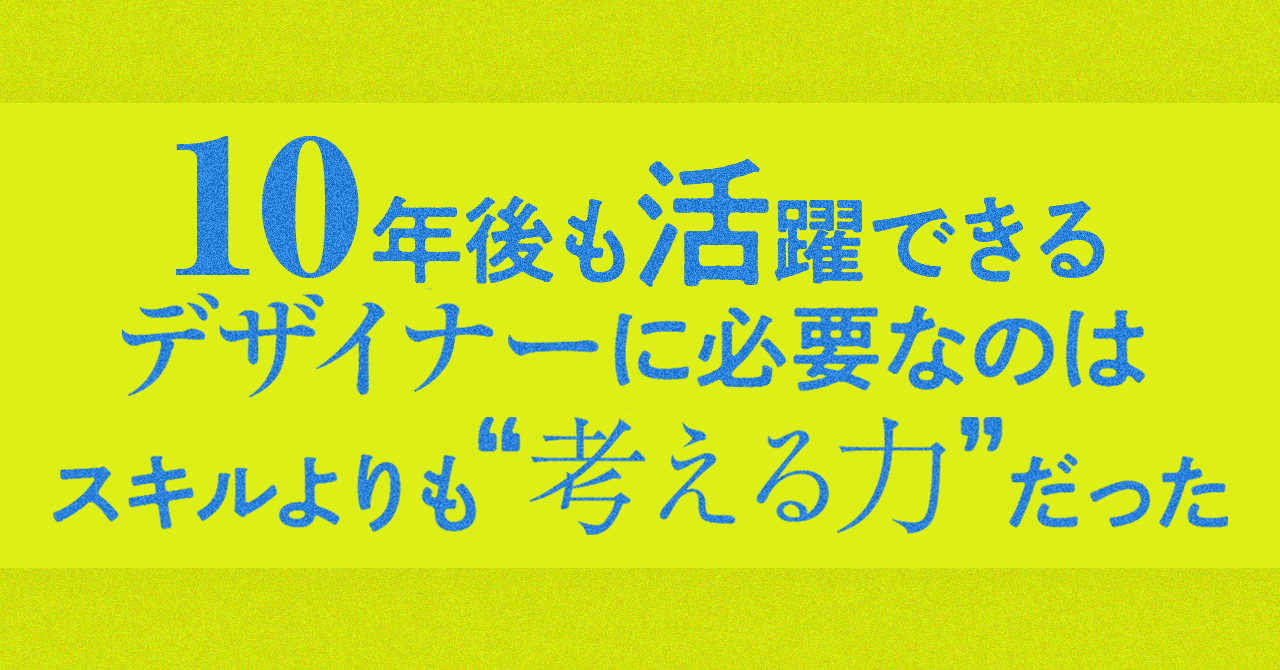
「今のスキルだけで、10年後もやっていけるのかな……」
デザイナーとして働く中で、こんな不安を感じたことはありませんか?
Web・UI/UX・動画、さらにAIの活用など、デザインを取り巻く環境は驚くほどの速さで変化しています。私も「このままでは通用しなくなるかもしれない」という不安から、紙媒体からWeb広告業界へ転職しました。
当時は、「新しいスキルを追い続けていればなんとかなる」と思っていました。しかし、Web広告の世界では、デザインの成果がクリック率やコンバージョン率(サイトを訪れた人のうち、購入や申込といった目標を達成した人の割合)といった「数字」として現れます。
この「成果を出す」ことがゴールの環境に身を置いたことで、スキルはあくまで“手段”にすぎないことを痛感しました。では、何が必要なのか?私が行き着いた答えは、「考える力」でした。
この記事では、なぜスキル以上に「考える力」が重要なのかを、私の実体験からお話しします。デザイナーとしてのキャリアに悩む方のヒントになれば幸いです。


目次
スキルだけでは越えられない壁にぶつかった瞬間
前職では、週刊発行のフリーペーパーのデザインを担当していました。掲載枠や締切はあらかじめ決まっていて、短い制作期間の中でミスなく納品することが求められる環境。だからこそ、「依頼を素早く形にするスキル」こそがデザイナーにとって一番重要だと考えてました。
実際、そのスキルは転職後も活きました。
たとえば、最初に任されたバナー制作。広い紙面に比べれば、小さな枠内で作るバナーは正直ラクですぐにコツを掴めました。制作物を素早く仕上げられることから、社内ではスピード面で評価されることも多かったです。
しかし、案件に深く関わり、自分の制作物がクリックや購入にどれだけつながったのかを数字で追うようになると、それまでのやり方では通用しない場面が増えていきました。
- 依頼通り作ったはずなのに、成果につながらない
- 情報を分かりやすく伝えたはずなのに、クリックや購入を促せない
- 結果を見ても、次は何をどう改善すればいいのか分からない
そんな経験を重ねるうちに、「自分は“作ること”に意識が向き過ぎていた」と気づいたのです。そして、「デザインスキルだけを磨くだけでは、成果にはつながらない」ということを痛感しました。
この気づきは、私の中で“デザインとの向き合い方”を根本から見直すきっかけになりました。
では、そこからどんなふうに変わっていったのか。次の章では、その変化を3つの視点からお伝えします。
1. 「依頼を形にする」から「課題を解決する」へ
以前の私は、「デザイナーの仕事は与件を形にすること」だと思っていました。
そのため、依頼者とのやりとりも「この写真の方が雰囲気に合うかも」「文字数が多すぎるから削りたい」といった、デザインの話に終始していたんです。
最低限必要な情報を確認し、依頼内容をデザインに落とし込む。そうすれば滞りなく納品できるし、依頼者の意図通りのものを作れば広告の成果もついてくるだろうと考えていました。
しかし、「依頼通りに仕上げたのに、思ったような成果につながらない」という場面がありました。
それは、「ずっと配信していて成果が良かったバナーの成果が落ちてきたので、動画形式に変えてクリック率を上げたい」という依頼を受けたときのことです。私は「動きをつければ目を引きやすくなり、反応も上がるはず」と考え、すぐに動画制作を進めました。
ところが、実際に動画を配信してみると、期待したような成果は出ませんでした。
後日、結果を振り返っていたとき、上司が「フリークエンシー(同じ広告が1人のユーザーに何度表示されたか)」を見ながら、こう言いました。
「成果が落ちた原因、動画じゃなくて“バナーの内容自体が飽きられてた”からじゃない? もしそうなら、動画で動きをつけても反応は変わらないよね」
そのとき、初めて気づきました。私は「クリック率を上げたい=動画化すればいい」と思い込んでいましたが、そもそも前提の課題設定がズレていたのです。
依頼が来たら、まずは「背景」と「目的」を聞く
この経験以降、依頼がきたらまずは以下のような内容を確認するようになりました。
- どんな背景があってこの依頼が発生したのか
- 現状どんな課題があり、どこにボトルネックがあるのか
- この制作物で、どんな行動をユーザーに促してどこにゴールを置くのか
もし必要を感じれば、訴求や構成そのものを見直す提案もします。
たとえばある案件で、「バナーの数値部分だけ差し替えてほしい」と依頼されたとき。目的やターゲットを確認したところ、コピーも変えたほうがクリックされやすそうだと感じました。
そこでコピーも提案した結果、デザイン自体は大きく変えなくても、既存バナーよりクリック数や購入率が上がり、「磯村さんに相談してよかった!」と感謝されたんです。
こうした経験から、ただ言われた通りに作るのではなく、本当に必要な打ち手は何かを一緒に考え、提案すること。そこにデザイナーとしての価値があるのだと実感しました。
依頼の「裏側」を考える重要さは以下の記事でも分かります。ぜひ参考に。
2. 「どう伝えるか」から「どう動いてもらうか」へ
前職で求人広告の紙面デザインをしていたときは、手に取ってもらった人に、どれほどわかりやすく情報を伝えられるかが重要でした。その延長でWeb広告を作るときも、「文字の視認性を高める」「重要な情報は強調する」といった、“伝えるための工夫”ばかりに目が向いていたと思います。
でも、いざ制作したバナーや動画広告を配信してみると、自分としては自信のあった制作物でも全然クリックされなかったり、動画の冒頭で9割以上がスキップされていたり……。そんな経験を何度もしました。
後々考えれば当然で、紙の広告は“興味のある人が自ら見る”ものですが、Web広告は“興味がない人の目にも否応なく入る”もの。どれだけ情報を整えても、受け手が「これは自分に関係がある」と思ってもらえなければ意味がありません。
つまり、「相手にどう映り、どう感じてもらえるか」の視点が欠けていたんです。
こういった経験を通じて、見た目をただ整え、一方的に伝えたいことを強調するだけでは、ユーザーは動いてくれないということに気づきました。
「ユーザーからどう見えるか?」を徹底的に想像する
そこからは、少しでもユーザーを理解するための行動を意識するようになりました。
たとえば、広告の配信先となるSNSを実際に使ってみる。あるいは、ターゲットに近い層の人に話を聞いてみる。そうして、「このデザインを見るのはどんな人、どんな状況なのか?」を想像したうえで設計するように変わっていきました。
ある商材のX広告のバナー制作では、仕事終わりに疲れてタイムラインを眺めるユーザーを想定。Xの「会話が生まれやすい」という特性も踏まえて、思わずツッコミたくなるコピーを添え、流し見でも目に留まるようなインパクトのあるデザインに仕上げました。
その結果、広告のクリック数や好意的なコメント数が増えただけでなく、購入者も増え、売上アップにつながったんです。
この経験を通じて実感したのは、「受け手にどう伝えるか」だけでなく、「どうすれば動いてくれるか」までを考え抜くことの大切さです。
完璧に理解するのは難しくても、想像し、寄り添い続ける姿勢こそが、成果につながるデザインをつくる第一歩だと感じるようになりました。
3. 「結果の良し悪し」から「結果から何を得るか」へ
転職して間もない頃、私はマーケティングやWeb広告の知識がほとんどなく、常に手探りの状態でした。そのため、書籍や社内で紹介されていた成功事例などを参考にしながら、良さそうだと思った施策を次々と試していました。
そんなある時、「実写よりイラストのほうがクリック率が高かった」というバナーの成功事例を見かけました。試しに担当案件のバナーを実写からイラストに変えてみたところ、クリック率が大きく改善。そこで、他のバナーでも同じようにイラストへ差し替えました。しかし、今度は思ったような成果は出ませんでした。
その結果を他のデザイナーと共有したところ、「なぜ上手くいかなかったのか?」と聞かれ、私は言葉に詰まりました。「前はうまくいったから」以外の仮説がなかったので、成功した理由も、失敗した理由も分からず、改善策も見つかりませんでした。
このとき初めて、「うまくいった/いかなかった」だけで一喜一憂していても、次に活かせず、成果を継続的に出せないことに気づきました。
やって終わりにせず、次につなげる視点を持つ
それ以降、施策を実施する前に「なぜこれが効果的だと思うのか?」という仮説を持つようになりました。結果を振り返るときも、「結果が良かった/悪かった」ではなく、「次にどう活かせるのか?」という視点で考えるようにしています。
たとえば、ランディングページ(広告から遷移して最初に表示されるページ)の改善に取り組んだときのこと。
まずは仮説を立てるために、ヒートマップ(ユーザーがページ上のどこを注視したかがわかるツール)を確認したところ、ユーザーにとって重要だと思われる情報がほとんど見られていないことがわかりました。
そこで、「重要な情報を視覚的にわかりやすくすることで、情報がきちんと届き、申込率が改善するのでは?」と考え、文字中心だった構成を、アイコンを取り入れた視覚的に伝わるデザインへ変更しました。
結果、申込率は大きく改善しませんでした。ですが、詳細に分析してみると、該当エリアがより注視され、ページ全体を最後まで読んだ人の割合や滞在時間が向上していました。
このことから、「視覚的にわかりやすくすること」は興味喚起につながる一方、「申込を促すには情報そのものを見直す必要がある」という、次の施策につながる発見がありました。
もちろん理想は、一発で成果を出しそれを継続できることです。ですが、効果的なデザインの「勝ちパターン」は常に変化します。だからこそ、一つひとつの結果と向き合い、成功も失敗も次に活かす力が重要だと考えています。
スキル以上に、自分の“考える力”が大切
もちろん、デザイナーにとってスキルは大切です。でもそれは、「成果を支える要素のひとつ」にすぎません。
デザインのトレンドや求められる技術は常に変化します。しかし、課題を整理しユーザーの行動を想像し、施策の結果を振り返る。こうした思考の流れは、どんな時代や環境でも活かせるはずです。
私自身、「考えること」を意識してから、目の前の制作物だけでなく、その先の成果まで視野が広がりました。商材や媒体、制作物が変わっても、自分なりの“軸”を持って進められる感覚があります。
もし、すべての制作プロセスに関われない環境にいても、まずはどれか一つだけでも意識することから始めてみてください。
- なぜこのデザインを作るのか?
- このデザインを見たユーザーはどう感じ、どう動くのか?
- デザインの結果を、次にどう活かすのか?
こうした問いを持ちながらデザインと向き合うことが、10年後、20年後もデザイナーとして活躍するために必要な力を育ててくれるのだと思います。