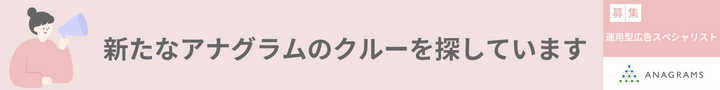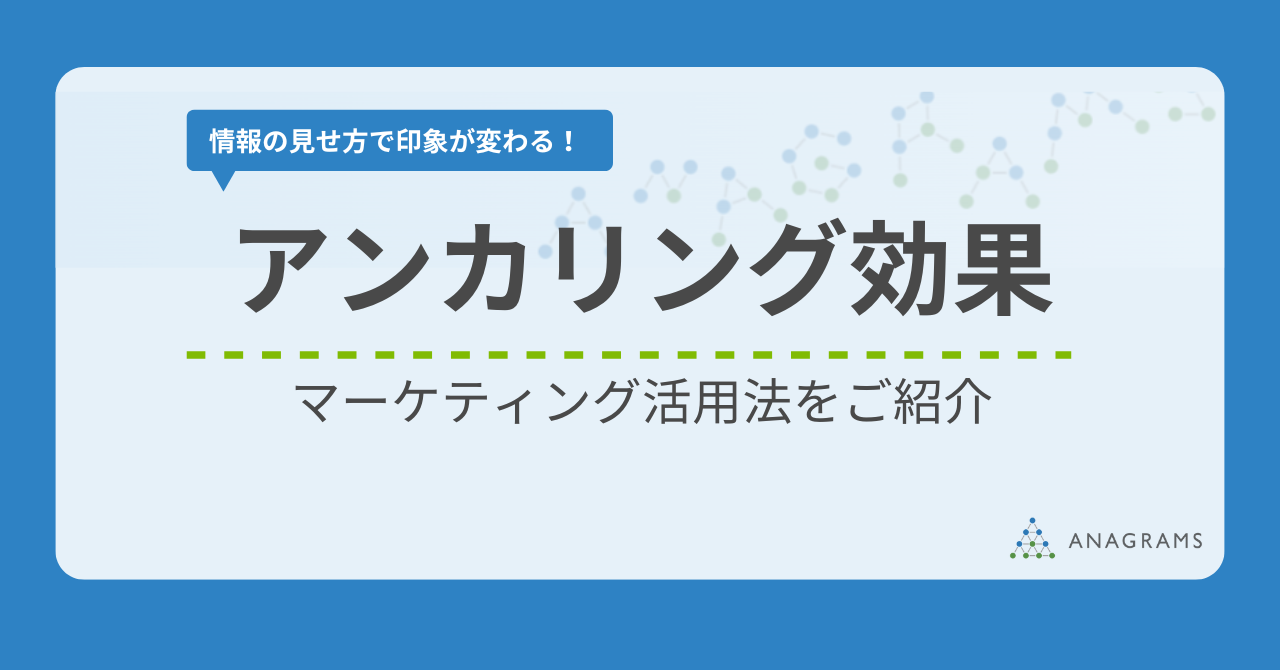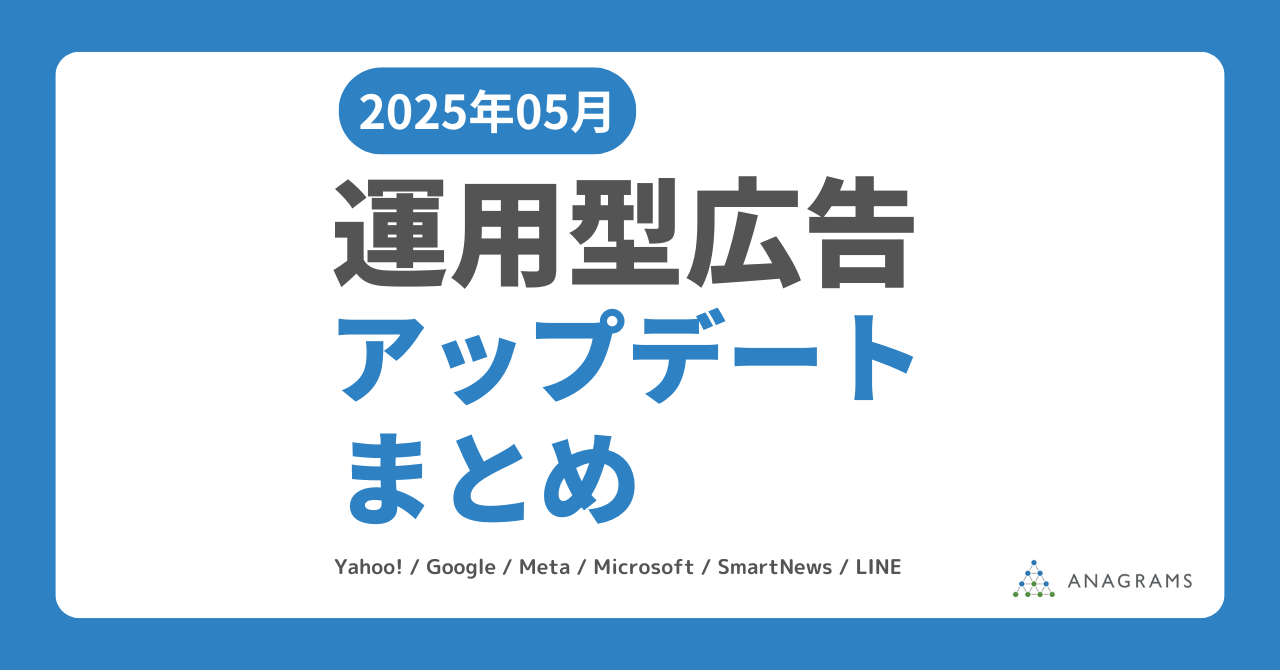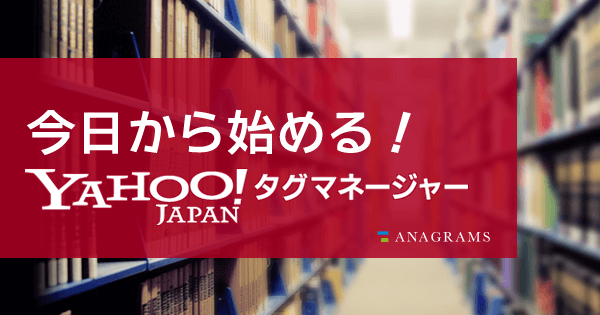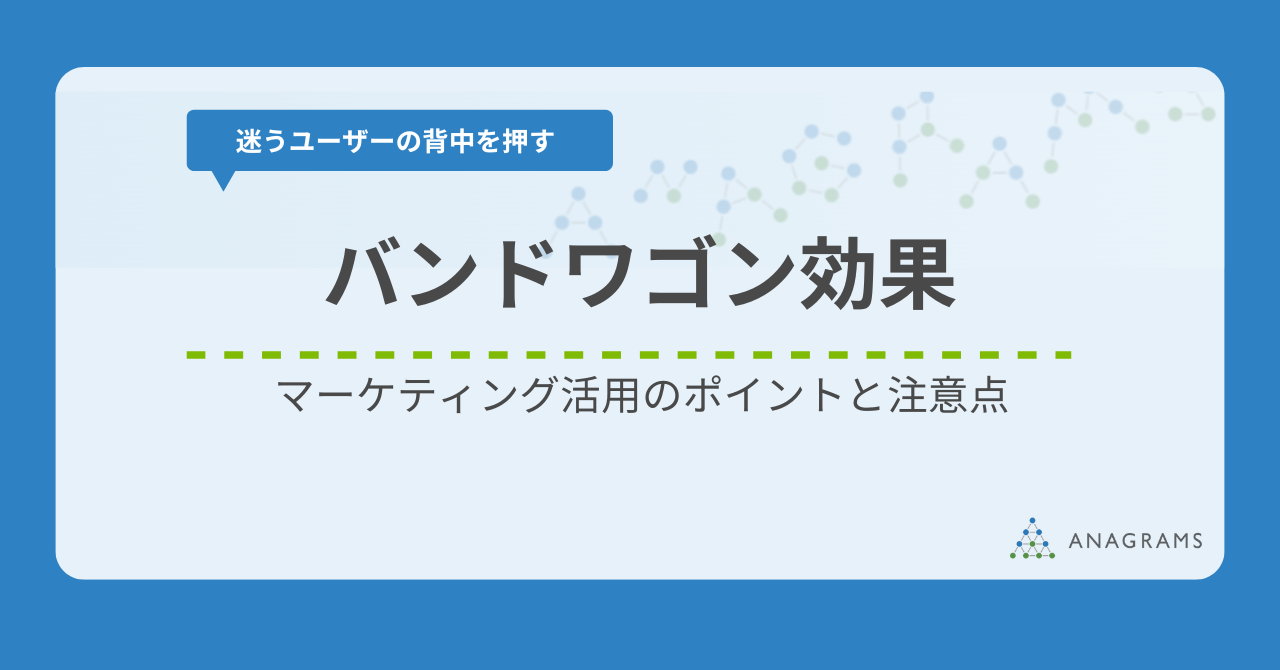
「累計販売実績〇〇個達成!」「○○万人が利用中!」
こういった文言を目にして、”自分も試してみようかな” と思った経験はありませんか?
実は、この “みんなが使っているなら、自分も使ってみよう” という心理には、「バンドワゴン効果」が深く関係しています。
特に認知度が低いブランドや競合の多い商品・サービスを扱っている場合、ランディングページやECサイトの訪問者数は多いのに「本当にこれを選んでいいの?」とユーザーが迷い、購入や申し込みに至らないことが少なくありません。
そのようなユーザーの背中を押し、最終的な意思決定をサポートする方法のひとつとしてバンドワゴン効果は有効です。
この記事では、バンドワゴン効果の概要や具体的な活用事例を紹介します。


目次
バンドワゴン効果の活用例
まずはバンドワゴン効果がどのように活用されているか、例をみてみましょう。自社の商品やサービスに応用できるヒントを探しながら、イメージを膨らませてみてください。
実績をビジュアル化して訴求
冒頭で触れた「○○万人が利用中」「累計販売数○○個」といった数値を、読み手がひと目で理解できるようなグラフなどで見せるのも効果的です。
また具体的な数字だけでなく「○○が特徴的」なども合わせて視覚的に示すと、商品・サービスの良さが伝わりやすくなります。
もしも競合との比較データがあれば、グラフや表で示すのも手段の一つです。
“多くの人に支持されている”という根拠があれば、バンドワゴン効果をより強化できるでしょう。
参加者数のリアルタイム表示
例えば旅行サイトやECサイトなどをみている時に、「いま〇人が閲覧中」「残り〇席」といったリアルタイムの数値が表示されることがありますよね。これらも、バンドワゴン効果のひとつです。
「他の人がすでに検討している=人気がある」という理解につながり、購入や申し込みの意思決定を後押しします。
特にオンライン上では、人の動きが見えにくいので、数値(人数や残数など)を可視化することでバンドワゴン効果をより高められるでしょう。
口コミやSNSの「高評価数」「フォロワー数」の提示
「SNSフォロワー10万人突破!」などの実績を広告やサイト内に載せると、多くの人が支持している印象を与えやすくなります。
同じように、レビュー数や口コミ評価も可視化すると、「こんなに多くの人が高評価をつけている」という安心感が得られ、購入や申し込みを後押ししてくれるでしょう。
これらのように、知らず知らずのうちにバンドワゴン効果を活かしたコピーや機能を目にしていることと思います。
バンドワゴン効果とは
バンドワゴン効果とは、何か行動を起こしたり購入する際、自分の判断に自信を持てなかったり失敗したくない状況下で、多くの人が支持しているモノや選択を参考に意思決定する心理的傾向(※)を指します。
(※)
1960年、アメリカの経済学者ハーヴェイ・ライベンシュタインが発表した論文「Bandwagon, Snob, and Veblen Effects」で提唱
“みんなが選んでいる商品・サービス”を選択することで「これを選べば間違いないんだな」と感じ、購入や申し込みまでの背中を押してくれます。
店舗の行列を見て「ここは美味しそうだ」と思ったりするのも、バンドワゴン効果が働いている典型的な例です。
バンドワゴン効果を活かすためのポイント
バンドワゴン効果を高めるためには “多くの人に支持されている”ということにくわえて、その裏付けとなる根拠や比較が重要です。
実際にマーケティングや広告運用に活用するために、以下を意識すると良いでしょう
客観的な数値や事実を提示する
主観的な「人気です!」という表現よりも、客観的な数値や声を示す方が、利用者の多さを直感的に理解してもらえます。
例えば販売実績やレビュー・口コミ件数など、他社と比較して強調できる客観的な数値がないか探してみましょう。
ユーザーインタビューやアンケート結果を活用し、「購入者が評価している点は何か?」「どのような理由で選ばれているのか?」といったポイントを整理するのもおすすめです。
数字に信頼性を持たせる
単に「累計販売数○○個」と伝えるだけでは、読み手にとって説得力が弱くなることがあります。「なぜその数字が出せたのか?」という理由や根拠を示すことで、数字の信頼性が高まり、より強い訴求が可能になるでしょう。
例えば次のような補足を加えると、数字の意味が伝わりやすくなります。
- 「品質の高さからリピーターが70%以上」
- 「口コミ評価4.8の高評価で支持を集めています」
- 「初回購入者の90%が再購入!」
数字を示すだけでなく、「その数字の裏にある理由」を一緒に伝えることで、読み手に安心感や納得感を与えられます。
顧客にとって意味のある数字を提示する
相対的な”量”や”数字”が多いことが重要ですが、背景や文脈を無視してはいけません。
例えば「累計販売個数1万個」と提示しても、市場規模や同じカテゴリ商品の価格帯によってはその数字が多いか少ないかの判断は難しいですよね。
競合との比較や市場の平均を踏まえつつ、顧客にとって意味のある数字を提示しましょう。
また、単に数や量が多いだけでなく、満足度やリピート率のような質的要素も合わせると、より説得力が増します。
以上のように、客観的な数値を示しつつ「なぜ多くの人が支持しているのか」を裏付ける理由や比較データを提示することが大切です。
また競合よりも優位性があることをわかりやすく伝えることで、バンドワゴン効果はより効果を発揮するでしょう。
バンドワゴン効果の注意点
バンドワゴン効果はユーザーの意思決定を後押しする手段でありながら、正しく扱わないと信頼を損ねたり逆効果を招いたりする恐れがあります。
ここでは、そのようなリスクを回避しつつ成果につなげるために押さえておきたい注意点をご紹介します。
誇張や虚偽表示はNG
虚偽の実績や数字の水増しは絶対にやってはいけません。
一時的に効果が得られることがあっても、中長期的には商品やサービスだけでなく、企業そのものの信頼を深刻に損ないます。
信頼を失った企業は、顧客離れや売上減少に直面するだけでなく、社内の倫理観低下や従業員のモチベーション低下を招き、組織全体に悪影響を及ぼすでしょう。
特に、「No.1」などの表記は目を引きやすい一方で、根拠が不明確であれば景品表示法などの法律に違反するリスクがあります。
誠実さは顧客との信頼関係を築く上での基本です。
短期的な利益を優先して虚偽や誇張に手を出すのではなく、正しい情報で勝負しましょう。
広告やLPに公開する前に、社内で数値や文言の事実確認は怠らないように注意してください。
広告媒体のガイドラインも要チェック
バンドワゴン効果を活用する際は、ユーザーの意思決定を後押しできる魅力的な表現を使いたくなりますが、広告媒体や業界ごとのガイドラインを遵守することが絶対に必要です。特に、最上級表現や比較表現は規制が厳しく、無意識のうちに違反してしまうリスクもあります。
たとえば、Yahoo!広告では「No.1」「最高」「最安」などの最上級表現を使う場合、その根拠となるデータや出典のクリエイティブ内とランディングページでの提示が求められます。
また、医療や健康関連の広告では特に注意が必要です。「日本一の実績」などの最上級表現は医療広告ガイドラインで禁止されています。医療・健康分野の広告を制作する際は、事前に業界特有のルールを確認しましょう。
商品特性によっては逆効果の場合も
バンドワゴン効果は多くの商品・サービスで有効ですが、商品特性やターゲット心理によっては逆効果を招くことがあります。特に、以下の心理効果と組み合わさる場面では注意が必要です。
- ヴェブレン効果(Veblen Effect):高価格の商品を「ステータスの象徴」として購入する心理。
- スノッブ効果(Snob Effect):他人が持っているものを避け、希少性や独自性を求める心理。
「値段が高いから価値がある」「誰も持っていないレア感が魅力」のような商品やサービスの場合、”みんなが使っている”という訴求はブランドイメージと乖離する可能性があります。商品特性を理解し、バンドワゴン効果を使うべきか慎重に判断しましょう。
なによりも重要なのは「優れた顧客体験」
どんなにうまく訴求しても、商品やサービス自体の価値や品質がしっかりしていないと意味がありません。
「みんなが使っているから」と購入しても、実際に使って満足できなければ、それっきりで終わってしまいます。 リピートや口コミで広がることもなく、せっかくの機会を逃してしまうでしょう。
バンドワゴン効果はあくまで「後押し」なので、核となる商品力が伴わないと長期的には成果が期待できません。
バンドワゴン効果を活かす具体的なステップ
これまでの内容を踏まえて、「実際にどうやって施策に取り入れればいいの?」と思っている方も多いでしょう。
以下の手順を参考に、成果を伸ばすための具体的なアイデアを考えてみてください。
1.ターゲットと解決したい課題を明確化
ターゲットと解決したい課題が不明確なまま、ただ「数字をアピール」しても効果は得られません。
そのためにも 、”何が課題か”、”どのユーザーに何を見せる方が良いのか”を整理しておきましょう。
ECサイトのとある商品の場合:
例1:閲覧数は多いが、購入率が低い
→ 累計販売数・人気ランキングの表示
「累計販売数50,000個突破!多くのお客様に選ばれています。」
「今週の人気商品ランキング TOP5」
例2:カート投入率は高いが購入完了率が低い
→購入者のリアルタイム通知を表示
「この商品は過去24時間で125人が購入しました!」
→在庫残数や閲覧数の表示
「現在12人がこの商品を閲覧中です!」
上記のように、まずは広告主が抱える課題を明確にし、それに合った施策や表現を考えてみてください。
2.活用できる数値や事例を整理
累計販売数、定期購入者数、予約数など、自社が持つ数値を洗い出します。
このとき、データが最新かどうか、出典や根拠が明示的かをしっかりチェックしましょう。
3.見せる場所とタイミングを考慮
ユーザーが購入や申し込みを考えるときに、最も迷いやすいシーンやタイミングで実績などをアピールすると効果的です。
例えばWebサイト上のファーストビューで訴求するのか、もしくはフォーム入力画面で訴求するのか、など「ユーザーの背中を押すタイミングはいつがベストか」を考えましょう。
4.ターゲットに合わせた表現を用いる
BtoB向け と BtoC向けのように、ターゲットによって魅力を感じる表現は異なります。
| ターゲット | 効果的な表現 | 具体例 |
|---|---|---|
| BtoB向け | 信頼や専門性業界内での実績 | 導入企業数○○社 / 利用企業の95%が効果を実感 / 導入後3カ月で生産性が○○%向上 |
| BtoC向け | わかりやすい数字人気の高さ | 累計購入実績〇〇個売上/ランキングNo.1 / SNSフォロワー○○万人突破 |
例えばBtoB向けは導入実績や専門性など “信頼” や”実績” を重視する一方で、BtoC向けは累計販売数やSNSフォロワー数など “わかりやすい数字” が有効です。
上記のように自社商品やサービスに見合ったターゲットを整理しましょう。
実績や事例の更新頻度をキープ
数字は「最新」であるほど信ぴょう性やリアリティが高まります。
古いままでは「今の状況とは違うかも」と不安に思われたり、管理能力を疑われることもあるので注意です。
訴求している数値やデータは定期的に更新し、不信感を抱かれないようにしましょう。
まとめ
本記事では、バンドワゴン効果の事例や注意点など、具体的なアイデアを紹介しました。
バンドワゴン効果は“多くの人に支持されている”を参考に、意思決定を後押ししてくれますがあくまでも補助的な要素として効果が発揮されるので、バンドワゴン効果自体が商品価値を生み出すわけではないことに注意しましょう。
商品・サービスの体験が良くないと、せっかく興味を持ってもらってもリピートや口コミなど、継続性が伴わないことも少なくありません。
訴求や表現には細心の注意を払いながら、自社の状況や商品特性に合わせてバンドワゴン効果を取り入れ、成果向上を目指してみてください。