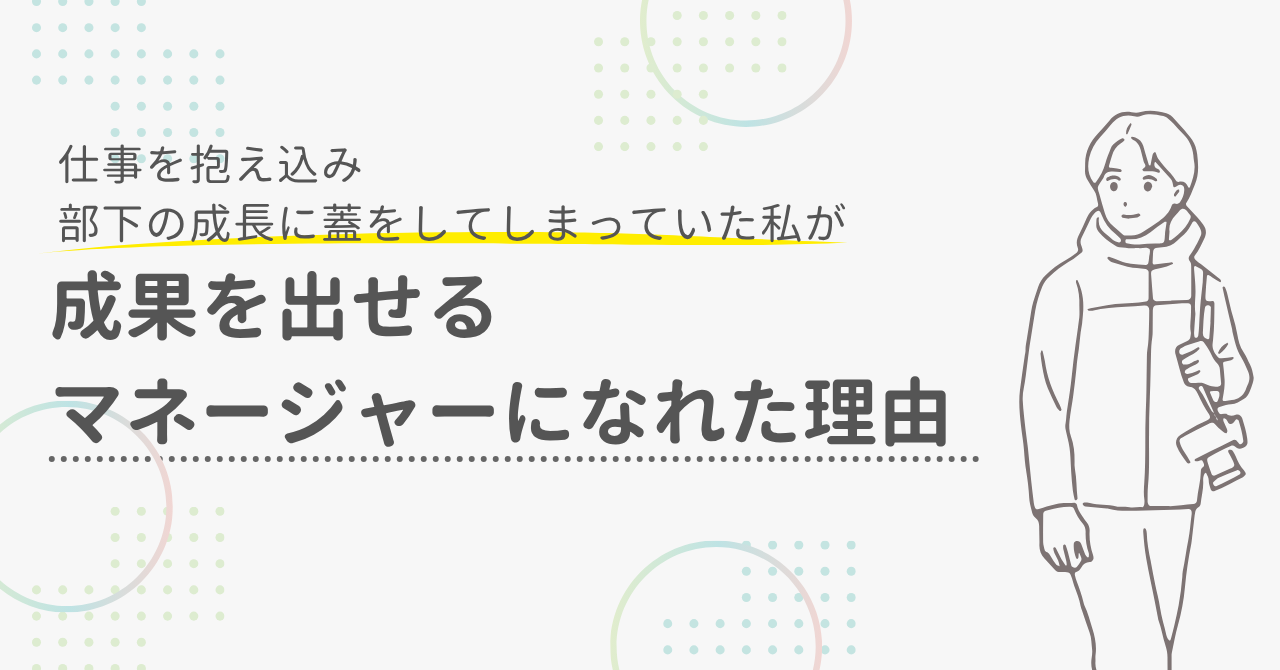
運用型広告の成果を改善することや、そこに付随する関係者との日々のコミュニケーション。私たちの仕事は、良くも悪くも属人的です。いわゆる職人芸や阿吽の呼吸のようなもので成り立っている場面も少なくありません。
だからこそ私は、「このクオリティは自分じゃないと担保できない」「このまま任せたらきっと上手くいかない」という思いに囚われ、自分のキャパシティを越えていることに気付きながらも、部下に仕事を任せきれずにいました。それは、部下の成長機会を奪い、仕事の進行においても周囲を不安にさせる、不健全な仕事の進め方でした。
しかし、そんな私もチームが拡大していく過程で自分を変えざるを得なくなり、今では「周囲に頼りきり」と胸を張って言える状態です。時には、他の管理職メンバーから「チームのことを教えてほしい」と相談されるようにもなりました。
今回は、かつて仕事を抱え込み、部下の成長にも蓋をしてしまっていた私が、どのようにその考えを改め、チームに頼れるようになっていったのか。その過程で大切にしてきたことを、自身の失敗談も交えながら、正直にお話ししたいと思います。


目次
なぜ、私たちは仕事を抱えすぎてしまうのか
部下に仕事を任せられない管理職は、決して怠惰なのでも、意地悪なのでもありません。むしろ、責任感が強く、真面目な人ほど当てはまるのではないでしょうか。では、なぜ私たちは、それほどまでに仕事を抱え込んでしまうのでしょう。
任せられない3つの理由
「自分がやったほうが早い」「部下に失敗されたら困る」「忙しそうな部下に、これ以上仕事を振るのは気が引ける」…そうした考えが頭をよぎり、結局すべて自分で抱え込んでしまう。
しかし、その結果、チーム全体の生産性は低下し、部下の成長機会も失われてしまいます。なぜ私たちは、これほどまでに仕事を抱え込んでしまうのでしょう。その背景には、3つの主な理由があると考えられます。
「自分がやったほうが早い」という“成果重視”の焦り
多くの会社では、プレイヤーとして高い成果を上げた人が管理職に昇進します。クライアントと共に難題を乗り越え、高い成果と厚い信頼を生み出し、その実績が評価されて昇進する。だからこそ、部下のアウトプットを見ると、つい「自分ならもっとうまくやれるのに」と思ってしまう。そして、手や口を出してしまうのです。
自分がプレイヤーだった頃のやり方が「正解」だと信じ、部下にもそれを押し付けてしまう。本人は良かれと思ってアドバイスしているつもりが、いつの間にか細かな指示になり、部下の成長の機会や仕事の楽しみを奪っていることに気づきません。
管理職になった瞬間、自分に求められる役割、いわば「ゲームのルール」が変わったことを頭で理解し、心で受け入れなくてはならないのです。プレイングマネージャーという立場は、そのことを難しくさせる原因の1つでしょう。
「失敗されたら困る」という“責任の過剰な引き受け”
「会社の看板を背負っているんだから、絶対に失敗は許されない」
「ここは重要な局面だから、細部までフィードバックしなくては」
部下と仕事を進めるなかで、こうしたプレッシャーを感じることもありますよね。しかし、これが過剰になると「部下に任せて失敗するくらいなら、自分でやった方が早いし確実だ」という思考に直結します。
でも、よく考えてみてください。その「失敗」とは、具体的に何を指すのでしょうか。契約の終了や、売上の大幅な減少でしょうか。もちろん、それらは避けなければなりません。しかし、私たちが権限委譲をためらうときに恐れている「失敗」の多くは、もっと些細なことかもしれません。
たとえば、「クライアントに少しでもネガティブな顔をされること」「完璧ではないアウトプットを出すこと」「部下が傷ついたり、自信を失ったりすること」ではないでしょうか。
これらは本当の意味でのビジネス上の失敗ではなく、ただ私自身が「見たくない未来」にすぎません。つまり、会社の損失を恐れているようで、実は「周囲の期待に応えられず、自分が傷つくこと」を極度に恐れていただけなのかもしれません。この勝手な気負いが、部下から挑戦の機会を奪い、成長を妨げてしまうのです。
「こんな仕事、やりたくないだろうな」という“過剰な忖度”
「この作業、地味でつまらないから、自分がやった方がいいよな」
「このハードな状況で、部下を一人にはできない」
これらは一見すると、部下への優しさや配慮に見えます。しかし、これもまた、危険な思い込みです。
私自身が「地味でつまらない」と感じる仕事でも、部下にとっては新しい知識を得る貴重な機会かもしれません。私が「ハードで大変だ」と感じる状況も、乗り越えた先には私の想像を超える大きな達成感と自信が待っているかもしれません。
「この仕事は、この部下にとってどんな成長の機会になるだろうか?」という視点を持たず、「自分だったらやりたいか?」という自分本位のモノサシで判断してしまう。これは、部下の可能性に蓋をする、無意識の傲慢でした。
すべての根底にある「一つの強迫観念」
ここまで見てきたように、真面目な管理職ほど仕事を抱えてしまう原因は、仕事の品質への“強すぎる”責任感、失敗に対する“勝手な”気負い、部下への“自分本位な”配慮にありました。
そして、これらの根底には、ある一つの強迫観念が潜んでいたのです。それは、「上司は、部下よりもプレイヤーとして優れていなければならない」という考えです。この考えは、「部下は、自分より仕事ができない存在だ」という無意識の侮りと表裏一体です。
この考えに囚われている限り、任せた仕事が自分のやり方と少しでも違えば「間違い」に見え、部下のアウトプットは常に「未熟」に見えてしまいます。これでは、本当の意味で部下を信頼し、仕事を任せることはできません。
さらに厄介なのは、マイクロマネジメントは、短期的には「自分がチームやプロジェクトを動かしている」という自己効力感を得やすいため、依存性が高いということです。この承認欲求を意識的に手放さない限り、私たちは仕事を抱えることから抜け出せないのです。
仕事を任せるための「リーダーのマインドセット」
チームが5人、10人……と増えていく中で、私は物理的にすべての仕事を見ることが不可能になりました。自分自身がボトルネックとなり、チーム全体のスピードが落ち、周囲の不満も溜まっていく。
何かを変えなくてはならないことは分かっているけど、それが何なのかは分からない。正直、余裕のない時期もありました。そんな中で出会い、今も大切にしている3つの考え方を紹介します。
① チームの成長によって、プロジェクトを成功させる
リーダーの役割は、部下に成果を出してもらうこと。頭では、そう理解していました。しかし、当時の私は「そのためには、まず目の前のプロジェクトで絶対に失敗できない。だからこそ、自分がリードしなくては」という思いを優先するあまり、部下の成長の優先度が下がっていました。そして、重要な場面ほど、私は自分の意見を押し付けようとしてしまっていたのです。
私が介入すればするほど、「本当に私にしかできない仕事」がどんどん増えていく。そんな悪循環でした。私は「プロジェクトの成功」と「チームの成長」を天秤にかけ、無意識に前者を選んでいました。でも、本当は順番が逆だったのです。
私の本当の仕事は、部下を成長させ、私が居なくても成功できるチームを作ることだったのです。
リーダーの仕事は、自分をクビにすること
理屈では分かっていた「部下に成果を出してもらう」を本当に理解したきっかけは、「リーダーの仕事は、自分をクビにすることだ」という言葉です。これはアナグラムのリーダーを対象に開催されたマネジメント研修の場で、当時の代表であり、研修を担当した阿部から教わったものです。
最初は少し戸惑いましたが、この言葉は、私が重要な場面ほど部下に仕事を任せられない原因であった「上司は部下より優れていなければならない」という強迫観念から、私を解放してくれました。
「自分をクビにする」とは、「今は自分にしかできない業務を、他の誰かでもできるようにして、手放していくこと」です。そして、空いた時間で「今のチームメンバーにはまだできない、新しい価値を生み出す仕事」に取り組む。このサイクルを回し続けることこそが、リーダーにとって、マイクロマネジメントよりもよほど重要な仕事だったのです。
この考え方が腹落ちしたことで、現場の仕事を手放すことへの恐怖が薄れました。「自分がやらなければ」ではなく、「これを部下に任せられるようになれば、チームはもっと強くなるし、自分は別の仕事に挑戦できる」と、未来志向で考えられるようになったのです。
② 助けてもらっていることを自覚する
仕事を任せられないのは、部下のアウトプットが、いつまでも良くならないからだ。もし常にそう感じているのなら、原因は部下ではなく、私たち上司の「物事の見方」にあるのかもしれません。
かつての私が、まさにそうでした。私自身のプレイヤーとしての強みは、広告施策やクリエイティブの結果を深く考察し、データから独自の解釈を見つけ出すことだと考えていました。そして、部下のアウトプットを評価するときも、真っ先に自分の得意なモノサシで「この考察は浅い」「その解釈にはこの視点が足りていない」のようなフィードバックばかりしていたのです。
恥ずかしい話ですが、チームで議論するためのミーティングも、今になって思えば「仙波さんのありがたい話コーナー」のようになってしまった時期もあったと思います。
そんな私の目を覚ましてくれたのが、コマースデザイン株式会社の坂本氏による、あるコラムの一節でした。
思い返してみると、以前の私は自分の得意分野である「文章」とか「工夫すること」を使って、相手の苦手分野を攻撃するようなことをしていました。
(中略)
「自分の得意分野を使って、部下の不得意分野を指摘する」というのは、上司の典型的な挙動です。でも、そんなことをしていると、相手が自分をサポートしてくれていることに対する感知が遅れてしまう。
まるで、自分のことが書いてあるような気持ちになりました。
減点方式のフィードバックではなく、加点から始まるディスカッションへ
そもそも私は、制作のスピードや、トレンドを捉えた表現を生み出す技術では、明らかに部下に助けられていました。
それなのに、私は、自分の得意分野を使って、相手のできていない点を指摘してばかりいました。私が口を挟まずに部下に任せていれば、もっとオリジナリティのある見解を出せたかもしれないのに、私が先に「正解はこうだ」とばかりに語ってしまうことで、その機会すら奪っていたのです。
この気づきから、私は部下のアウトプットを見る目を意識的に変えました。「足りない点」を探すのではなく、まず「自分が助けられた点」「自分の能力を超えている点」を探し、具体的に伝えるようにしたのです。
「このデザイン、自分には絶対作れない!ありがとう!」
「この工夫があったからこそ成果につながったよね!すごい!」
「この視点は自分にはなかった!面白い!」
このように、感謝や敬意をまず伝えた上で、「ここから、さらにもう一段良くするために、どんな可能性があるだろう?」というスタンスで自分の意見を伝えることで、部下とのやり取りはフィードバックではなくディスカッションへと変化しました。こうしたコミュニケーションを重ねるうちに、部下のアウトプットは自然と良くなっていきましたし、何より、私自身が、そう信じられるようになったのです。
「仕事を任せる」とは、不安を押し殺して手放すギャンブルではありません。部下の能力や貢献を正しく評価し、リスペクトすることから始まります。そして、自分がいかに部下に助けられているかを自覚することが、その第一歩なのです。
③ "自分のコピー"を量産しないマネジメントへ
私はもともとデザインのバックグラウンドを持ちながら、運用型広告のコンサルタントとしてキャリアを積んできました。この二つの領域を越境できることが、自分だけのユニークな強みという自負がありました。
だからこそ、私が率いるチームも、そんな「広告運用もデザインもわかるハイブリッドなプレイヤー」を増やしていくことが、組織としての競争力になると、信じていたのです。
その結果、私は知らず知らずのうちに、自分と同じ考え方を持つ、いわば「自分のコピー」を育てようとしていました。
それは短期的には、とても安定して見えます。自分と同じ思考のメンバーがいれば、レビューも意思疎通もスムーズに進むからです。しかしある時、ふと、そのやり方に危うさを感じたのです。
「全員が同じ方向しか見ていないチームで、本当にいいのだろうか?」
チームの全員が似たような思考の枠組みで物事を捉えていては、変化への対応力や、新たな気づきを得る力を失っていきます。それは、安定ではなく、緩やかな停滞の始まりだったのかもしれません。
任せることはチームの力を引き出すこと
あるメンバーは、私が思いつかない切り口でクリエイティブを制作する。またあるメンバーは、自然体のコミュニケーションで信頼関係を築く。
以前の私なら直したくなったこれらのやり方も、今では「面白い」「自分にはできない」と素直に感じられます。大切なのは、「違うこと」を問題と見なさず、「違うからこそ価値がある」と受け入れる視点です。
今でも、自分と異なる意見に対し、つい「それは違う」と言いそうになることがあります。そんなときは、こう問い直します。
「これは間違いか? それとも、別の解か?」
マネジメントとは、自分の正解を押し広げることではありません。自分にない視点やスキルを持つ人を迎え入れ、チーム全体の可能性を広げていくこと。
だからこそ、「自分に似た人」を量産するのではなく、「自分にはないものを持った人」を信じて任せていく。多様な意見が交わり、互いの違いを強みに変えられる環境を整えることも、チームの力を引き出すためのマネージャーの大切な役割なのだと、今では考えています。
「丸投げ」にしない、適切な任せ方
「よし、仕事を任せるぞ!」と決意したマネージャーが、次にぶつかる壁。それは「どうやって任せるか」です。やり方を間違えれば、それは「良い委譲」ではなく、ただの「丸投げ」になってしまいます。
では、「丸投げ」と「良い委譲」の違いは、一体どこにあるのでしょうか。
「勇者」ではなく「ゲームクリエイター」であれ
プレイヤー時代の私は「何でも出来る勇者」であることを仕事観にしていました。
少し昔話をさせてもらうと、アナグラムの門を叩いた当時の私は、Webデザイナーでありながら、クライアントの売り上げに貢献するために必要なことを幅広く支援する環境に身を置いていました。この、良く言えばジェネラリスト、悪く言えば器用貧乏というスキルセットに、キャリアの不安を抱えていました。
面接をしてくれた当時の代表である阿部との会話の中で、自分の器用貧乏に対する不安を伝えたところ「何でも出来る勇者になればいいじゃん」と返してもらったことで、とても勇気づけられたのです。この言葉はプレイヤー時代の私を支える仕事観でした。
実際に、持ち前の幅広いスキルは多くの場面で役立ち、仕事が評価されて昇進したり、デザイナーの経験を買われてクリエイティブチームの立ち上げという大役を任されることにもなりました。
しかし、プレイヤー時代に私を支えた「勇者」という仕事観は、マネジメントにおいてはそのまま弱みに反転しました。自分自身が幅広く対応できてしまうがゆえに、どこまでもマイクロマネジメントができてしまうのです。加えて「自分がみんなを守らないと」という意識も、結果的に部下の成長を奪っていました。
そんな状態を自覚するきっかけになったのは、アナグラム代表の小山によるnoteの一節でした。
マネージャーは、あくまで「ゲームクリエイター」であって「勇者」ではありません。
この前提が崩れる関与は極力避けて、間接的なサポートに徹したほうがいいと思います。
バグ技とか見えざる力が働くことは、真面目にやってるプレイヤーにとってはサムいです。ゲーム性を損ねます。
衝撃でした。やるべきことは、「勇者」として直接介入し問題を解決することではなく、「ゲームクリエイター」として、部下が自力でクリアできる絶妙な難易度に課題を調整し、それを仕事として渡すことだったのです。
良い委譲とは「成功体験までを設計する」こと
この「ゲームクリエイター」としての視点がなかった頃、私は今でも自戒している、いくつかの「危険なアサイン」をしがちでした。
例えば、「このキーマンは難しいけど、彼のコミュニケーション能力なら何とかできるかも…」と、何の防波堤も用意せずに、人間関係の難しい案件を任せてしまったこと。
またある時は、「自分には無理だったけど、彼のセンスなら何か変えてくれるかも…」と、自分でも勝ち筋が見えない案件を、希望的観測だけで丸投げしてしまったこと。
今思えば、それらは期待などではなく、リーダーとしての甘えであり、責任放棄でした。「大変だとは思うけど、君なら…」と心の中で言い訳をしながら、部下を送り出してしまっていたのです。
こうしたアサインの最も罪深い点は、メンバー本人の意欲や工夫では、どうにもならない状況に彼らを追い込んでしまうことです。
「何をしても無駄だ」という無力感は、人の心を折る最大の敵です。そんな状況に部下をアサインすることは、成長機会の提供どころか、仕事そのものが嫌いになってしまうほどの傷を与えかねない行為なのです。
この過ちに気づいてから、私は「良い委譲」を行う上で、自分に二つの絶対的な条件を課しています。
一つは、部下の力では動かせない「障害物」を特定し、撤去しておくこと。それは、厄介な人間関係かもしれませんし、組織の構造的な問題かもしれません。部下が自分の仕事に集中できるよう、上司が先にそのボトルネックを特定し、取り除いておく。あるいは、その障害物をうまく回避できるルートを用意しておく。これは、部下を地雷原に送り込まないための、最低限の責任です。
もう一つは、その仕事をその部下に任せた場合の勝ち筋が具体的に見据えられていること。「このプロジェクトの勘所はここで、君の〇〇という強みや経験を活かせば、きっと突破できるはずだ」。このように、上司が成功への見通しをある程度描けていることが重要です。この確信があるからこそ、部下は「自分ならできるかもしれない」と安心して挑戦できますし、壁にぶつかった時も、上司は的確な助言ができます。
この二つが整って初めて、部下は自分の工夫や頑張り次第で状況を好転させられる手応えと、仕事が面白いという感覚を味わうことができ、さらなる成長や挑戦に向けて自走していくのではないでしょうか。
この舞台設定を怠っておきながら「部下が自発的に行動しない」と嘆くことは、舗装もされていない道に人を立たせておいて「なぜ前に進まないんだ」と言っているのと同じくらい、無責任なことなのかもしれません。
部下本人は気づいていない「少し先の可能性」を見出し、後押しする
それでも、チャレンジングな仕事を打診したとき、部下の口から「自分にできるでしょうか…」と不安がこぼれることもあるでしょう。
しかし、その不安にリーダーが同調し、「じゃあサポートするね」と安易に引き下がってしまうと、どうなるでしょうか。それは一見優しいようで、実は部下の貴重な成長機会も、リーダーが本来使うべきだった時間も、同時に失う行為になってしまいます。
もちろん、無謀な挑戦をさせるのとは違います。先ほどの「ゲームクリエイター」の視点で、「成長のための挑戦」を設計できていれば、リーダーは自信を持って「君なら出来るよ、なぜなら……」と部下の背中を押す言葉が言えるはずです。
人は、自分自身の本当の強みや得意なことに、意外と無自覚なものです。だからこそ、リーダーの重要な役割の一つは、部下自身も気づいていない、少し先の可能性を映し出す「鏡」になることなのだと思います。
「前の案件で見せた君の〇〇という力は、この挑戦でこそ活きるはずだ」
「君が当たり前にやっている〇〇は、実は誰もができることじゃない。すごい武器なんだよ」
こうした具体的なフィードバックを伴ったチャレンジの提案が、部下自身が無意識に設けていた限界の蓋を外し、新たな可能性を拓いていく鍵になるのです。
部下が成果を上げるための条件を冷静に見極め、その上で、自分と部下の可能性を信じ抜く。リーダーシップとは、そんな冷静な分析と、熱い信頼の両輪で成り立つものなのかもしれません。
頼ることは、弱さではなく「勇気」である
かつての私は、「上司は、部下よりもプレイヤーとして優れていなければならない」という強迫観念に囚われ、部下に仕事を任せきることにどこか抵抗を感じ、結果的にチームのパフォーマンスを下げるようなリーダーでした。
しかし、今は違います。私一人でできることなど、たかが知れています。チームメンバーそれぞれの強みに目を向け、信頼して任せることで、チームの影響力は私一人では到底不可能だった大きさになりました。今、チームの皆が進めている仕事は、私一人が頑張ってカバーできる範囲をとっくに超えて、様々な挑戦と失敗、そして成果と成長を生み出しています。もし、私が「いざとなったら自分がフォローできる範囲」にこだわりすぎていたら、これらの仕事は生まれていなかったものだと、強く思います。
もちろん、「プレイヤーとしての自分をクビにする」のは、怖いことかもしれません。「もう最前線には戻れないのでは」「市場価値が下がってしまうのでは」「自分が出来ないことを指示して反発されないか」といった不安がよぎることもあるでしょう。
だからこそ、頼ることは、決して弱さではありません。それは、自分の仕事観や価値提供のあり方を変えることもいとわない「強さ」や「勇気」の証なのだと、今ではそう思います。
もしあなたが、かつての私のように一人で多くを抱えて苦しんでいるとしたら。それはあなたの能力が低いからではありません。むしろ、責任感が強く、プレイヤーとして優秀だからこそ陥ってしまっている罠なのかもしれません。
今回のコラムは、当時の自分の至らなさを思い出しながら、少しだけ複雑な気持ちで仕上げました。当時の私が様々な情報に触れて自分の考え方や行動を少しずつ改めていったように、このコラムが他の誰かの、何かを変えるきっかけになれば、嬉しく思います。







