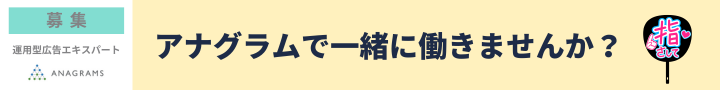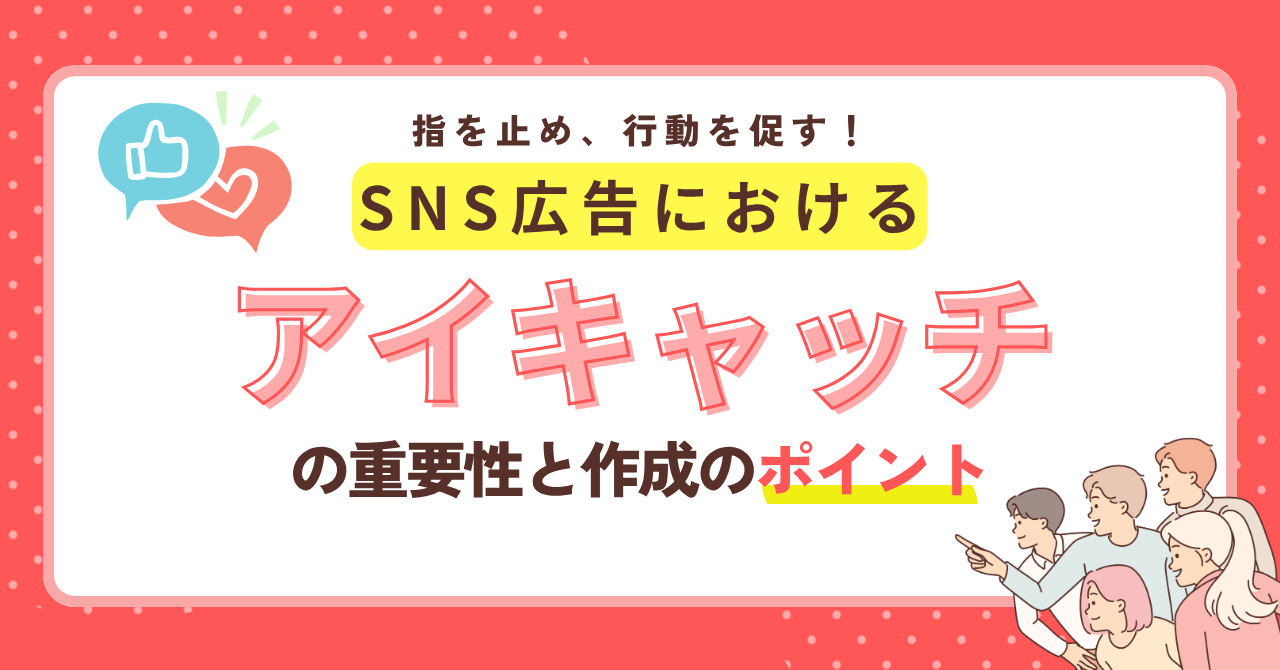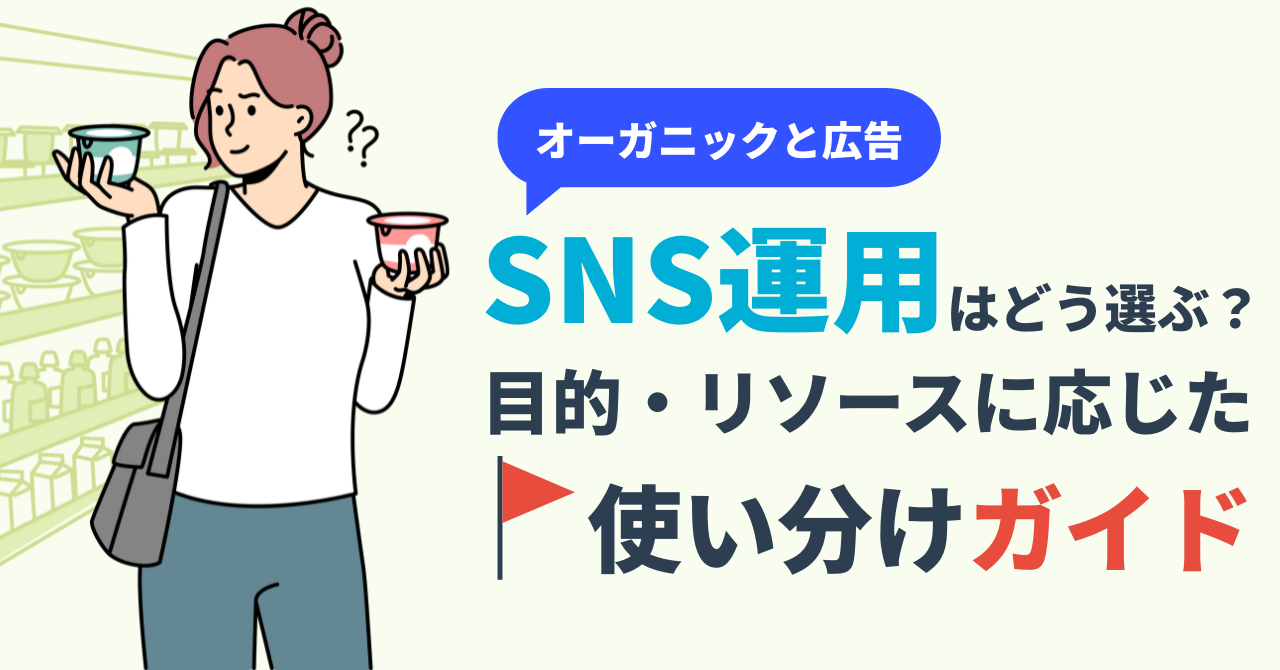「あれ、この商品バズってる!?」
「え、この言葉が流行ってるの?知らなかった…」
SNSで急に広まるブームや、いつの間にか主流になっている価値観。
現代のトレンドは移り変わりが速く、年齢や性別といった従来の属性分析だけでは捉えきれないほどに多様化・流動化しています。
特に、SNSを中心に形成される“界隈”と呼ばれる緩やかなコミュニティの中では、共通の興味関心や文化的文脈に基づいて、情報が独自のスピードと熱量で広がっています。
このような領域においては、外部から観察するだけではなく、“当事者として”その空間に入り込み、数字に表れにくい“価値観”や“行動”などに着目する必要があります。
この記事では「界隈憑依」というアプローチで“当事者としての視点”を持って数値化されない兆しやニーズを発見する方法をご紹介します。


目次
「界隈」とは?
そもそも「界隈(かいわい)」とは何なのでしょうか?
一般的には「ある場所の周辺地域」や「近くのあたり」を意味する日本語ですが、近年では単なる物理的な場所ではなく、「特定の関心・価値観・文脈を共有する人々の集合体」として使われることが増えています。
たとえば、「推し活界隈」「ガジェット界隈」「美容医療界隈」「ビジネス自己啓発界隈」 といった具合で、特にSNSの中では、共通の「好き」や価値観を持つ人々が自然発生的に集まり、言語・行動・文化様式を共有する“文化圏”のような存在が生まれています。
実際、博報堂とSHIBUYA109 lab.が共同で公開したレポート『Future Evangelist Report vol.3 界隈消費』(2024年11月)でも、「界隈」はZ世代を中心に、SNSのアルゴリズムによって形成されるゆるやかなつながりとして定義されており、特定の趣味や価値観を共有する人々のあいだで、独自の文化・言語・消費行動が生まれる様子が詳細に分析されています。
このレポートでは、界隈とは単なるファンコミュニティにとどまらず、ファッション・職業・思想・ライフスタイルなど多様な軸で構成され、複数の界隈にまたがる生活者が自然と情報の受発信を行っていることが示されています。
参考:博報堂/SHIBUYA109 lab.『Future Evangelist Report vol.3 界隈消費』
「誰に届けるか」から「どの界隈に、どんな空気感で語りかけるか」へ
博報堂とSHIBUYA109 lab.が共同で発表したレポートでも示されている通り、いわゆる「界隈」は、単なる年齢や性別といった属性情報では把握しきれない、独自の空気感や行動様式を備えた集団として注目されつつあります。そこには共通の価値観が根付き、特有の言葉づかいや美意識、リアクションの仕方までが半ば暗黙のルールとして存在しています。
このような界隈を理解するというのは、表面的な関心ごとを知るというよりも、その背後にある感性や振る舞いのパターンを読み取る行為に近いと言えるでしょう。
とはいえ、それは外から見ているだけではなかなか掴めません。界隈が持つ“空気感”や“行動様式”は、数値や定量データでは可視化しにくいものだからです。だからこそ、自らその界隈に入り込み、当事者の視点で感じることが重要になってきます。
私はこのアプローチを「界隈憑依」と呼んでいます。単なる観察ではなく、感情や行動まで“なりきってみる”ことで、初めてその界隈に共鳴する表現が見えてくるのです。
「界隈憑依」を実践する6つのステップ
「界隈憑依」とは言っても、具体的に何をすればいいのでしょうか?ここでは、「界隈憑依」の具体的な方法を6つのステップで解説します。
1. ターゲットとなる界隈を定義する
最初に取り組むべきは、「誰に」ではなく「どの界隈に」アプローチすべきかを定義することです。
界隈とは、単なる属性で切れるものではなく、ある価値観・テーマ・スタンスを共有して形成された“文化圏”です。そのため、明確な境界があるわけではなく、マーケティングの目的に応じて、どこに注目するかを設計していく必要があります。
その際に使えるのが、以下の3つの視点です。
▶︎ 界隈の洗い出しに使える3つの軸
- 商品カテゴリ × 関心軸
- 同じ商品でも、購入・支持の理由は人によって異なります。たとえば健康食品の場合、「美容のため」「ダイエットのため」「アレルギー対策」「オーガニック志向」など、関心軸によって界隈が分かれます。
→ 商品そのものよりも「なぜそれを選ぶのか」に注目することで、界隈の地図が見えてきます。
- 同じ商品でも、購入・支持の理由は人によって異なります。たとえば健康食品の場合、「美容のため」「ダイエットのため」「アレルギー対策」「オーガニック志向」など、関心軸によって界隈が分かれます。
- プラットフォームとの相性
- 界隈の主戦場(発言・発信が活発な場所)は、プラットフォームによって異なります。若年層はTikTokやInstagram、ビジネス層はX(旧Twitter)やLinkedInに集まる傾向があります。
→ 同じ話題でも、語られ方や熱量が変わるため、適切な観測場所の見極めが必要です。
- 界隈の主戦場(発言・発信が活発な場所)は、プラットフォームによって異なります。若年層はTikTokやInstagram、ビジネス層はX(旧Twitter)やLinkedInに集まる傾向があります。
- “語られ方”からの逆算
- ブランドやカテゴリに対して、人々がどんな言葉で語っているかに注目すると、その背後にある界隈が浮かび上がってきます。
→ 例:「高コスパ」「映え」「ガチ勢向け」「中毒性あり」などの言葉が頻出している場合、それに共鳴する文脈をもった界隈が存在していると考えられます。
- ブランドやカテゴリに対して、人々がどんな言葉で語っているかに注目すると、その背後にある界隈が浮かび上がってきます。
なお、数字(フォロワー数、投稿量)だけで界隈の価値を判断しないことが大切です。大きく見える界隈でも、実際には購買につながる熱量が低いこともあります。“濃さ”と“接点の深さ”がカギになります。
2. 該当する界隈を発見する
界隈の仮説ができたら、次はそれが実在するかどうかをSNSやオンライン上で検証していきます。
このフェーズでは「その価値観・スタンスで語っている人たちは、どこに集まり、何を話しているのか?」を可視化することが目的です。
▶︎ プラットフォーム別の探索視点
- X(旧Twitter)
- ハッシュタグ検索やユーザーリストから、投稿の連鎖やキーパーソンを発見できます。リプライ(返信)や引用リプライの文脈にも注目。
- Instagram
- リールやストーリーズで、共通するビジュアルトーン・ライフスタイルを観察する。フォロワー同士のつながりも手がかりに。
- TikTok
- トレンド音源や人気チャレンジから、界隈内の熱量の高い文化やノリを把握。おすすめ欄に出る投稿から“無意識的共通点”が見えることも。
- YouTube
- 長尺コンテンツやライブ配信のコメント欄から、価値観やリアルな声、界隈の「内輪ネタ」やノリを抽出する。
なお、短期的なバズや流行タグに飛びつきたくなりますが、要注意です。表面的には盛り上がっていても、それが一過性で終わる場合があります。“継続的に語られている”テーマや人が存在するかどうかを見極めるのが、本質的な界隈を見つけるコツです。
3. 観察・参加する
界隈を特定したら、すぐに発信やアプローチに移るのではなく、まずは静かに観察することから始めましょう。これは“ROM専”(見る専)としてふるまい、その空気に慣れる段階です。
▼ 具体的な観察・参加の方法
- 言葉・表現・テンションを観察する
- 語彙の選び方、絵文字の使い方、ポストの温度感などが、界隈特有の文化を表します。
- コメント欄・引用RT・スレッドを読む
- 投稿の表よりも、反応の裏に本音や価値観が隠れています。
- オフラインで体感する
- 美容ならコスメ売り場へ、ゲームならイベント会場へ。現場にしかない肌感があります。
- アカウントを使い分ける
- 観察専用と、コミュニケーション用を分けることで、距離感をコントロールできます。
あくまでマーケターの視点を持ちながら、共感できる部分を見つけていくことがポイントです。「界隈に混ざること」と「界隈に染まりきること」は異なります。没入と客観性のバランスを意識してみましょう。
なお、界隈は日々変化します。一度の観察で終わらず、継続的に見続けることで変化の“兆し”に気づくことができます。
例:「毎月このタグを1時間チェック」「主要インフルエンサーの投稿を月1レビュー」などルーティン化。
4. 観察ポイント
界隈に入り込み、共通言語やノリが把握できたら、次はより深く、“内的文脈”を理解することが重要です。
- 内的文脈とは?
- 彼らが何を大切にして、何を嫌うのか
- 表立っては語られない「前提」や「ルール」
- 語られない言葉の裏にある感情や本音
- 内的文脈を理解する方法
- キーパーソンへのインタビュー、グループインタビュー
- 関連書籍や動画を参考に、歴史や思想的背景を探る
- 「なぜ?」「どうして?」を5回繰り返し、思考を掘り下げる
彼らの行動原理や価値観を言語化することで、より深いレベルで「解像度の高い」理解が得られます。
特に、キーパーソンを見つけるのは効果的です。界隈の中で発信力や共感を集めている人の言葉や反応は、界隈全体のトーンを象徴することが多く、トレンドの見極めに役立ちます。
5. 情報を分析する
観察で集めた情報から、トレンドの兆しや消費者心理を読み解きましょう。
界隈で頻繁に使われているキーワードや表現を分析し、写真や動画から、消費者のライフスタイルや価値観を推測することで再現性が高まり、新たな発見が見つかります。
具体的には、テキストマイニングでキーワードの頻出度を分析したり、写真・動画から生活感や世界観を推察したり、SNS分析ツール(BuzzSumo、Social Insightなど)でトレンドの変遷を見るなどの方法があります。
ただし、データの「量」だけでなく、「文脈」を読み取る力が重要です。大量のデータから有益な情報を抽出するためには、界隈の文脈や背景にある意味を理解し、解釈する必要があります。
分析結果を基に、どのようなマーケティング施策に活用するか方針を立てることで、より効果的な戦略を立てることができます。
6. 分析の視点:本質を見抜く
表面的な流行に流されず、次の一手に繋がる洞察を導くためには、以下の問いを常に意識することが重要です。
- なぜこの文脈が共感されているのか?
- どんな“未充足のニーズ”を満たしているのか?
- 今後、この価値観はどう変化していく可能性があるか?
たとえば、「サウナ界隈」で流行している“ととのう”という表現は、単なる言葉の流行ではなく、「情報過多な社会で無になる瞬間を求めている」というニーズの表出である可能性があります。
このように、表面的な流行の背後にある人々の心理やニーズを深く理解することで、より本質的なマーケティング戦略を立案することができます。
これらのステップを経ることで、あなたは単に情報を収集するだけでなく、界隈の深層心理に迫り、そこから生まれるトレンドの兆しを掴むことができるでしょう。それは、単に「流行に乗る」のではなく、「流行を創り出す」マーケティングへの進化を意味します。
なお、界隈で得た発見は、マーケ部門だけに留めず、商品開発や広報などと共有することで、より立体的な戦略に活かせます。
例:企画会議で“界隈インサイト共有タイム”を設け、他部門に持ち込む習慣を作る。など
以上が、「界隈憑依」を実務で実践するための6ステップです。
「界隈憑依」は、従来の属性分析を超え、顧客の感情や価値観を深く理解するための強力なツールです。
このプロセスを通じ、界隈特有の言葉や文化を把握することで、顧客との信頼関係を築き、共感を呼ぶメッセージを発信できます。
また、表層的な流行の背後にあるニーズを捉え、市場の変化に先駆けた戦略立案を可能にします。顧客を「消費者」ではなく「仲間」として捉え、より人間的な繋がりを築く、これからのマーケティングに不可欠なアプローチになってきます。
「界隈憑依」を実践する際の注意点と成功のヒント
界隈憑依は、ユーザーの価値観や文脈に深く入り込み、共感される発信や施策をつくるための有効な手法です。ただし、その効果を最大限に発揮するには、いくつかの落とし穴を避けることも重要です。以下では、よくある3つの注意点と、それを回避するためのヒントをご紹介します。
「界隈憑依」の注意点
先ほどの6ステップはユーザーの価値観や文脈に深く入り込み、共感される発信や施策をつくるための有効な手法ですが、同時にいくつかの注意点も存在します。これらの注意点を意識することで、「界隈憑依」の効果を最大限に引き出し、より良い成果に繋げることができます。
【その1】“憑依しすぎて”客観性を失ってしまう
界隈の空気感に共鳴し、没入すること自体は「憑依」において必要不可欠です。しかしあまりにその文化圏に浸かりすぎると、マーケターとしての俯瞰的な視点を見失い、「なんとなくノリで選んだ施策」が増え、本質を見誤る危険があります。
次のポイントに注意して対処していきましょう。
- 憑依する時間帯・環境と、俯瞰して考える時間を意識的に切り分ける
- SNSなどで観察・没入した後は、社内のミーティングや別アカウントで視点を整理
- 「自分は今、観察者か? 分析者か?」と視点のポジションを都度確認する
感情移入や共感が強くなりすぎると、“ユーザーっぽく考えること”が目的化してしまうことがあります。あくまで目的は「生活者理解を通じて、適切な表現や戦略をつくること」であることを忘れずにいましょう。
【注意点2】プライバシーと倫理に配慮する
界隈の会話に参加する際、無意識に個人情報を記録・引用してしまったり、スクリーンショットを誤用してしまうリスクがあります。これは、界隈の人々との信頼関係を損なうだけでなく、法的な問題に発展する可能性もあります。
つまり、情報の取り扱いには細心の注意を払う必要があるということです。
- 観察・共有の際には常に「本人の文脈や意図を尊重しているか」「企業としての倫理に反していないか」を意識する
- スクショを社内共有する場合でも、アカウント名を伏せる/コンテンツの引用範囲を限定する
その界隈で発信している熱をオープンにしている人は多くない可能性が高いです。だからこそ意図を汲み取る・プライバシーに慎重になることは忘れず意識しましょう。
【その3】界隈の文脈を表層的に消費してしまう
「それっぽい」言葉やノリを安易に使ってプロモーションすると、界隈から「わかってない」「雑に扱われた」と受け取られる可能性があります。これは、安易な模倣は界隈からの信頼を失い、逆効果になることがあるということです。
つまり、界隈特有の言葉や表現は、背景にある価値観・感情まで理解したうえで使う必要があるということです。
- 界隈特有の言葉や表現は、背景にある価値観・感情まで理解したうえで使う
- “沼”“ガチ恋”“オタ活”などは、単なる言葉遊びではなく、その人たちの人生観・愛情表現でもあることを理解する
この記事を読んでいる人も、人生で一度は「運営がわかっていない」「今回の実写化はファンが求めているものと全然違う」「こんなテイストが好きなんだろ感が滲み出ていて何か嫌だ」という感情を抱いたことがあるのではないでしょうか。
そんな感情が生まれることを防ぎ「わかってるじゃん」という雰囲気にすることも、需要に合ったコンテンツ・サービスをつくるのに重要になってくるのです。
まとめ
「界隈憑依」は、数字や属性では捉えきれない“今”の空気を掴む、消費者心理を深く理解するための強力なツールとなります。
「誰に届けるか?」ではなく、「どの界隈に、どんな空気感で語りかけるか?」という視点が、これからのマーケティングの鍵になるはずです。
ぜひ本記事の内容を参考に、「界隈」に入り込み、「憑依」することで見えてくるリアルなインサイトをマーケティングやPR・広告・企画などに活かしてみてください。