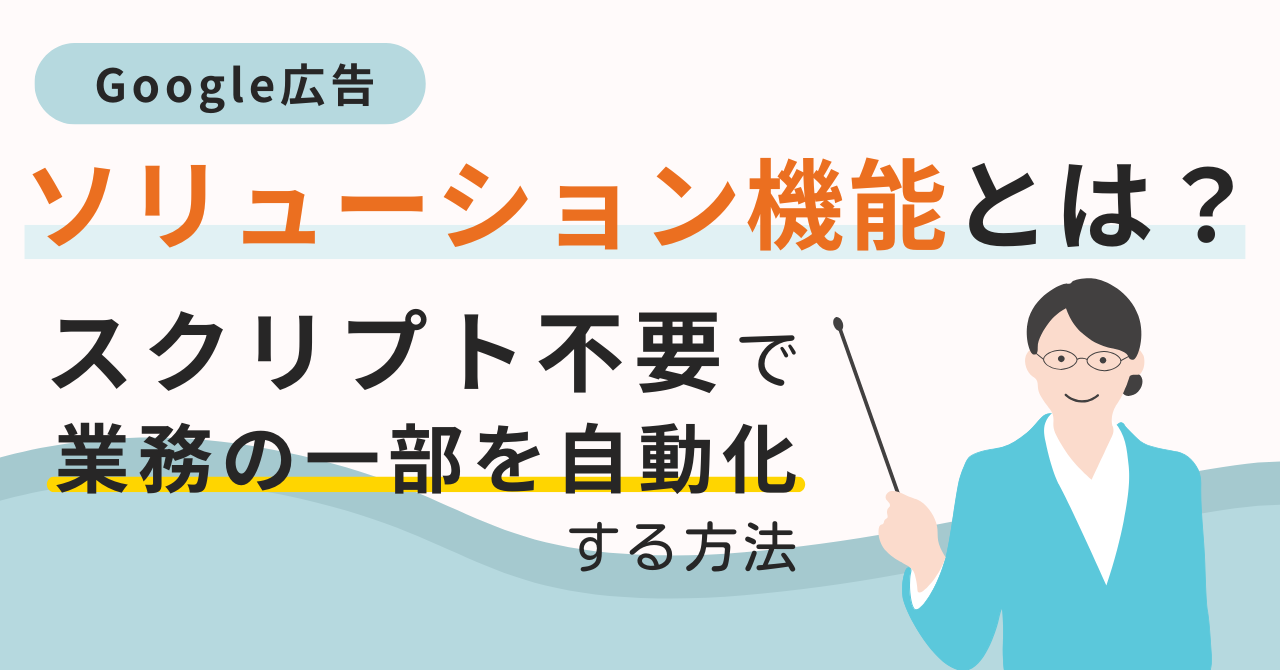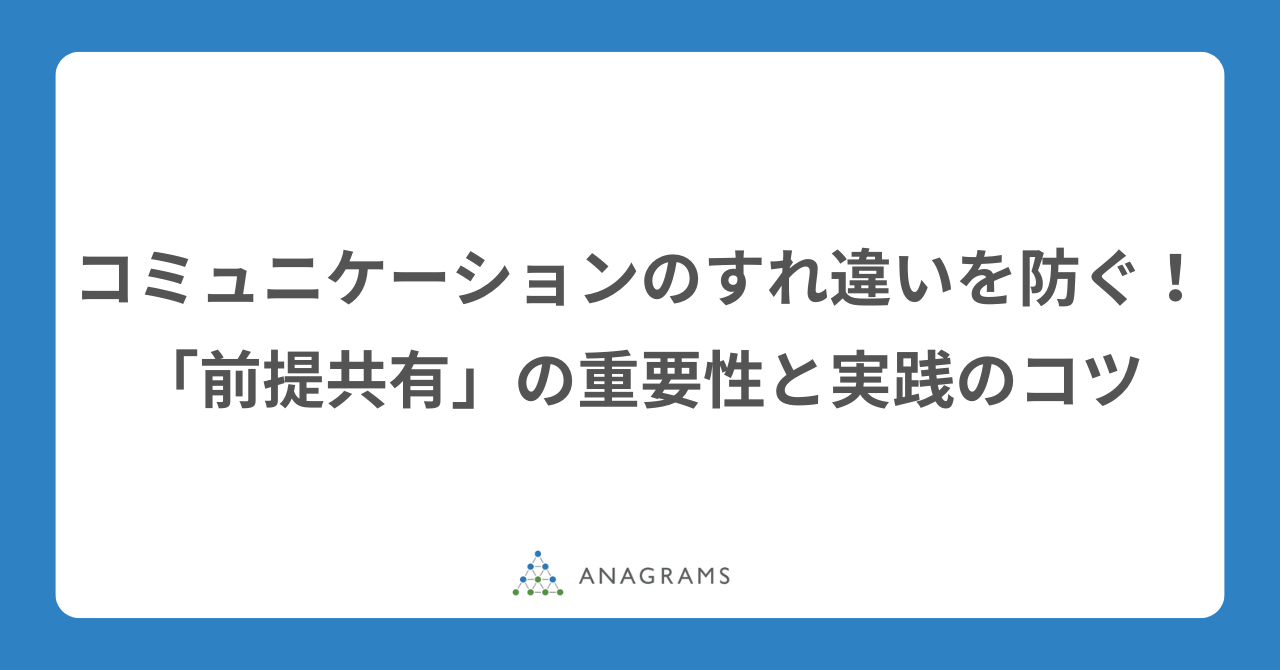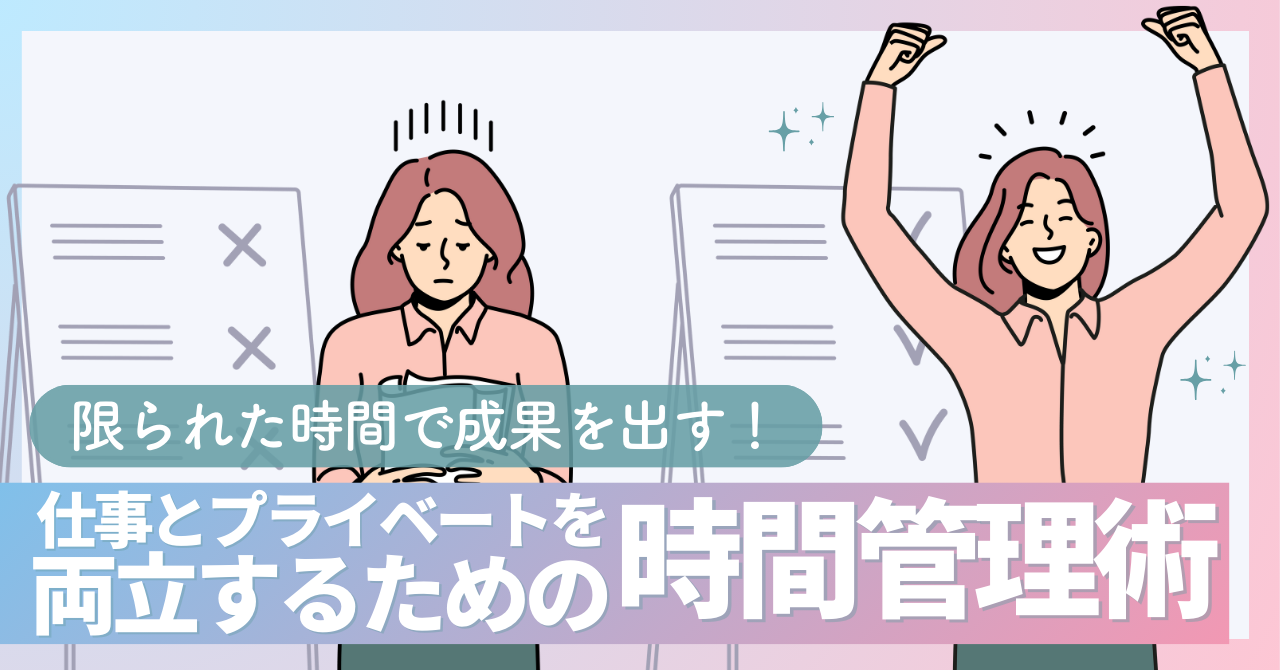スマートフォンでニュースアプリやSNSを使っているとき、タイムライン上に「広告」と表示されるコンテンツを見かけたことありますか?それ、モバイル広告市場の成長株でひときわ注目されている「インフィード広告」です。
「インフィード広告が伸びているって聞くけど、どうしてなの?」、「普通のバナー広告とどう違うの?」というあなたに、インフィード広告で抑えておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
Yahoo!JAPANトップページのタイムライン化が大きな転機に

サイバーエージェントとデジタルインファクトとが共同で実施した、国内のインフィード広告に関する市場動向調査によれば、2017年のインフィード広告市場は前年比36%増の1,903億円、スマートフォン比率が98%と、モバイル広告における大きな成長領域となっています。
参考:サイバーエージェント、インフィード広告市場調査を実施 | 株式会社サイバーエージェント
インフィード広告を出稿できるおもな運用型広告の媒体
- Yahoo!プロモーション広告・YDN(インフィード広告)
- Facebook広告
- Instagram広告
- Twitter広告
- LINE Ads Platform
- SmartNews Ads
- Gunosy Ads
- Google 広告(ディスプレイキャンペーン)
※掲載先のサイトがフィード型を採用している一部の場合のみ
※インフィード形式だけではない媒体がほとんどで、多くは別の広告フォーマットも用意されています。
タイムラインやニュースフィード形式のサービスはFacebookやTwitterといったモバイルを主体としたSNSでは一般的でしたが、当時はスマートフォンのトラフィックがどんどん伸びてはいましたが、デスクトップが主体の時代から続くサービスは、デスクトップの内容をスマートフォンの画面に形だけ収めたものも少なくなく、スマートフォンへの対応は不十分でした。

大きな転換となったのが、Yahoo! JAPANのスマートフォン版およびアプリのトップページのタイムライン化です。
参考:生まれ変わったスマートフォン版Yahoo! JAPANトップページと「Yahoo! JAPAN」アプリを本日より正式公開! - プレスルーム - ヤフー株式会社

画像元:「インフィード広告」でスマホ版Yahoo! JAPANトップページに広告掲載 - Yahoo!プロモーション広告 公式 ラーニングポータル
これに伴って提供を開始されたのが、Yahoo!プロモーション広告のYDNの広告フォーマットである「インフィード広告」です。少なくとも日本においては国内最大規模のポータルサイトのスマートフォンへの最適化にタイムラインが用いられたのがインフィード広告の普及に大きく影響したといっても過言ではないでしょう。
インフィード広告のメリット
いまではインフィード型の広告フォーマットが多くのメディアに採用されており、モバイル広告における大きな成長領域となっている理由には次の2つが挙げられます。
フィード型のサイトに馴染む広告フォーマット
スマートフォンはPCより画面が小さく、1枚のページ内に収まるコンテンツの量にも限りがあります。そのため、スマートフォンでは画面を流れる形でコンテンツを次々に表示できるフィード型は相性がよかったのでしょう。

画像元:「インフィード広告」でスマホ版Yahoo! JAPANトップページに広告掲載 - Yahoo!プロモーション広告 公式 ラーニングポータル
インフィード広告の多くは、多くが「画像(または動画)とテキスト」の要素から成り、掲載面の形式にあわせて広告フォーマットの形式が自動で調整されます。フィードに流れるコンテンツと非常に近い広告フォーマットであるため、サイトのコンテンツと馴染みやすくユーザー体験を極力阻害しないよう設計されています。
従来のバナー広告にくらべ視認、反応されやすい
また、従来のいわゆるバナー形式のものは、広告フォーマットがコンテンツと大きく異なり、仮にフィード上に流れれば大きな違和感がありネガティブな目立ち方をしていたかと思いますが、サイトに馴染んだ広告フォーマットであれば自然な形で視認されやすいという特徴もあります。

もちろん、広告クリエイティブの内容次第ではありますが、まずサイトを閲覧しているユーザーの邪魔をせずに目に止まるという最初のハードルを超えられやすいのが大きなメリットです。
Yahoo!JAPANの調査では、新たなユーザーからのクリック獲得がありユーザーの興味を引きつけやすい特性を示す調査結果も出ています。
参考:画像元:「インフィード広告」でスマホ版Yahoo! JAPANトップページに広告掲載 - Yahoo!プロモーション広告 公式 ラーニングポータル
これらの理由から、とくにモバイル広告においてはインフィード広告が積極的に採用されているのです。
インフィード広告の注意点
一方で、スマートフォンユーザーにアプローチができるといっても、ただ掲載するだけでは期待するような効果は得られないのがインフィード広告です。より成果を上げるために次の点に注意して取り組んでいくのをおすすめします。
検索連動型広告や通常のバナーとは違うアプローチが必要
インフィード広告は視認性が高い一方で、よくも悪くも従来よりも人の目に多く触れる可能性が高まります。コンテンツに馴染んでいると言っても、「今すぐ登録」「50%引き」「限定」などのいわゆる広告的なフレーズばかりが目につけば広告はスルーされてしまいます。場合によっては鬱陶しさを感じさせてしまうこともあるでしょう。広告の訴求や広告を誰に見せるかには、これまで以上に気をつける必要があります。
一方で、広告の訴求がコンテンツに馴染んでいたとしても、広告をクリックして行き着いた先に、求めていた情報がなければ読者はがっかりすることになります。場合によっては騙されたと感じさせてしまい、広告主体のブランドイメージにネガティブな印象を与えてしまうことさえありえます。
能動的に情報を求めているユーザーをターゲットとすることの多い、検索連動型広告とは異なるアプローチが必要です。
インフィード広告で成果を出すための3つのポイント
1.注意を引くのではなく関心を引く
インフィード広告に使う画像とテキストの構成は、広告が表示される周りのコンテンツに馴染むように作成する必要があります。

とくに広告テキストは、広告的なフレーズを極力排除し、続きの内容が読みたくなるように作成するとより反応が得られやすい傾向があります。広告が表示される周りのニュース記事がどういう風な内容でタイトルを出しているのかを参考にしてみるのもオススメです。
2.広告の表示からリンク先までユーザーの気持ちを想像する
インフィード広告では、情報コンテンツを盛り込んだリンク先ページにユーザーを誘導する必要があります。

インフィード広告を見かけてクリックするユーザーは、最新トレンドやニュースなどの情報を求めてコンテンツを見ているユーザーで広告の内容に興味・関心を持ち、続きの内容を気にしているユーザーです。クリックした先のページに関連しているコンテンツが不十分だったり、販促内容だらけだったりすると、そういった広告へユーザーにアクションを期待することは難しいです。
広告フォーマットが従来のバナー広告などにくらべて、ユーザーにストレスを与えにくいものだからこそ、いっそうリンク先ページには気を使う必要があります。まずは広告をクリックしたユーザーが期待するコンテンツは何か、広告からリンク先ページまでのユーザーの気持ちを想像するのが第一歩です。
3.さまざまなクリエイティブのパターンを試し続ける
インフィード広告はSNSアプリやニュースアプリなど、毎日あるいは習慣的に目にする場所に表示されるので、広告の表示頻度、つまり「フリークエンシー」の高まりによって広告訴求への「飽き」も従来のバナー広告に比べて早い傾向があります。そのため、広告の効果検証をよりスピーディーに行う必要があります。
「テキスト」「画像」「リンク先ページ」の3つの要素を活用して複数の広告パターンを用意し、クリエイティブを試し続けることでより成果に繋げられる広告を展開することができます。リスティング広告でも同様ですが、効果検証のために広告を複数パターンに作るときにはより短期間で優劣を判断するために、例えば「見出しのテキストのみ変更」のようになるべく変数を少なくし、パターンごとの差異を大きくすることのがおすすめです。なお、個人的な経験では、情報取得が目的のユーザーが多いためか、テキストの変更によるパフォーマンスの変動は他の要素にくらべて比較的高いケースが多い傾向です。
まとめ
インフィード広告は、その成長性の高さに注目が集まることが多いですが、単に広告を出稿すれば高い効果が期待できる広告フォーマットではありません。
本記事で紹介している、従来とは異なる広告フォーマットのメリットやユーザーのモバイル体験、他の広告とは一味違ったアプローチの方法など、そのメリットを活かすのには抑えるべきポイントがあります。これらを理解した上で、さまざまな仮説をもちインフィード広告に取り組んでいくことが、成果につながるのではないでしょうか。