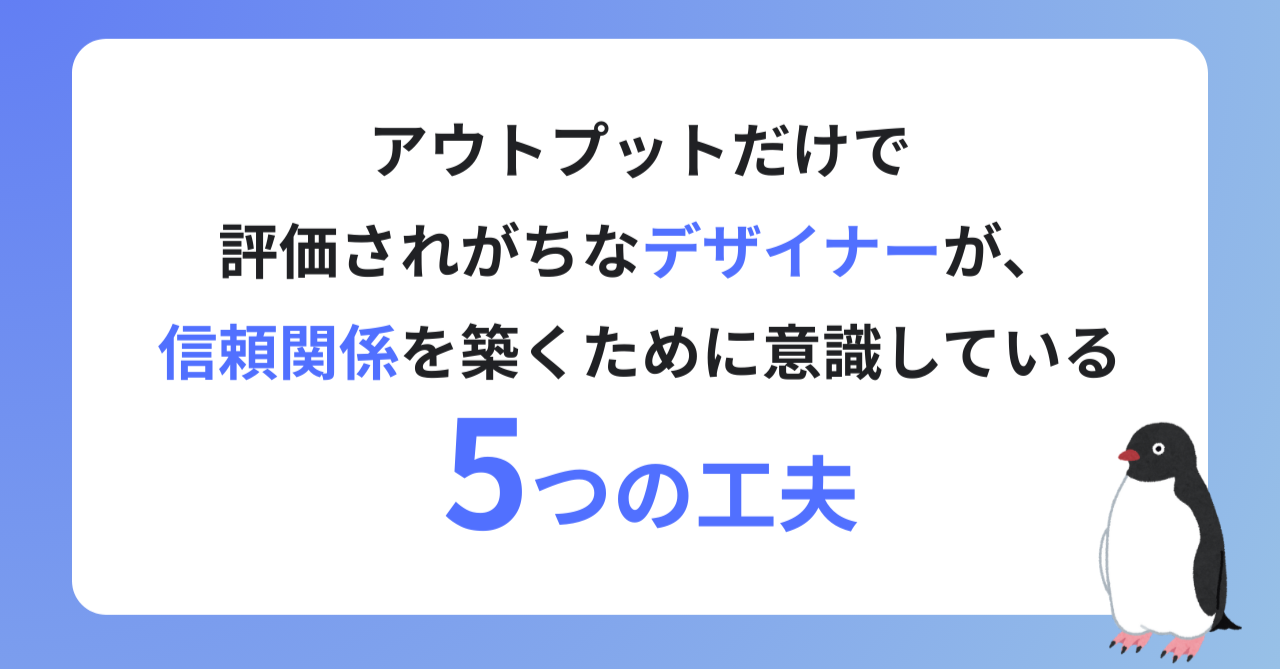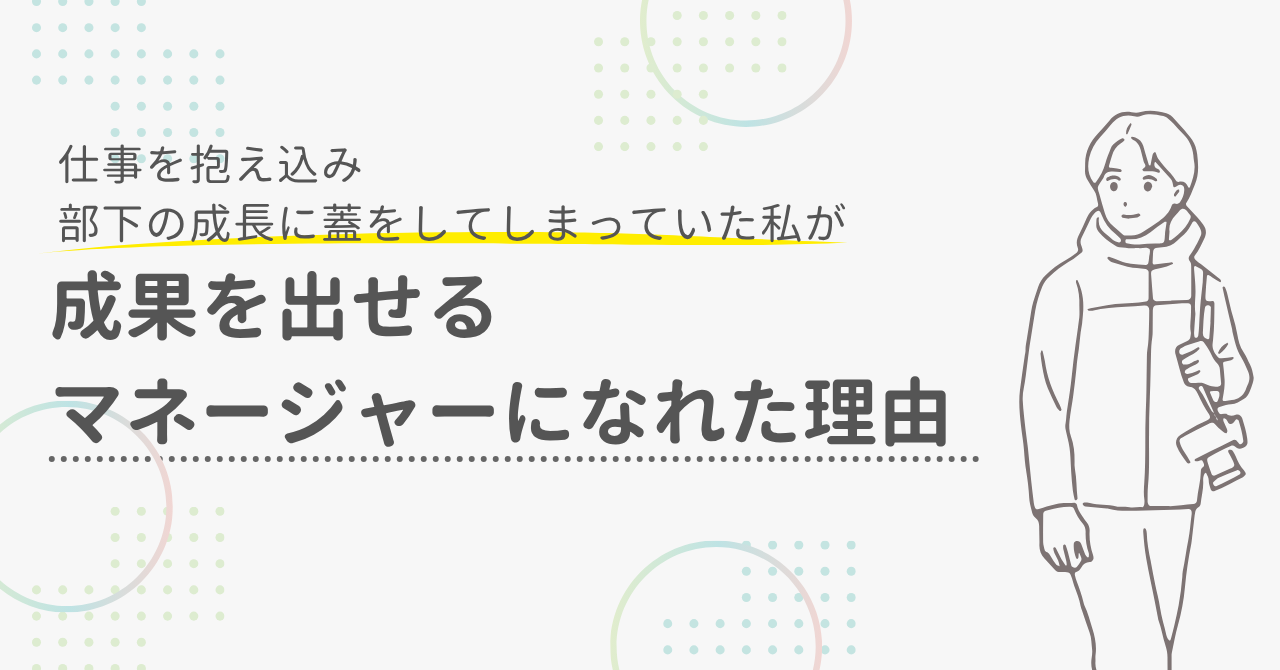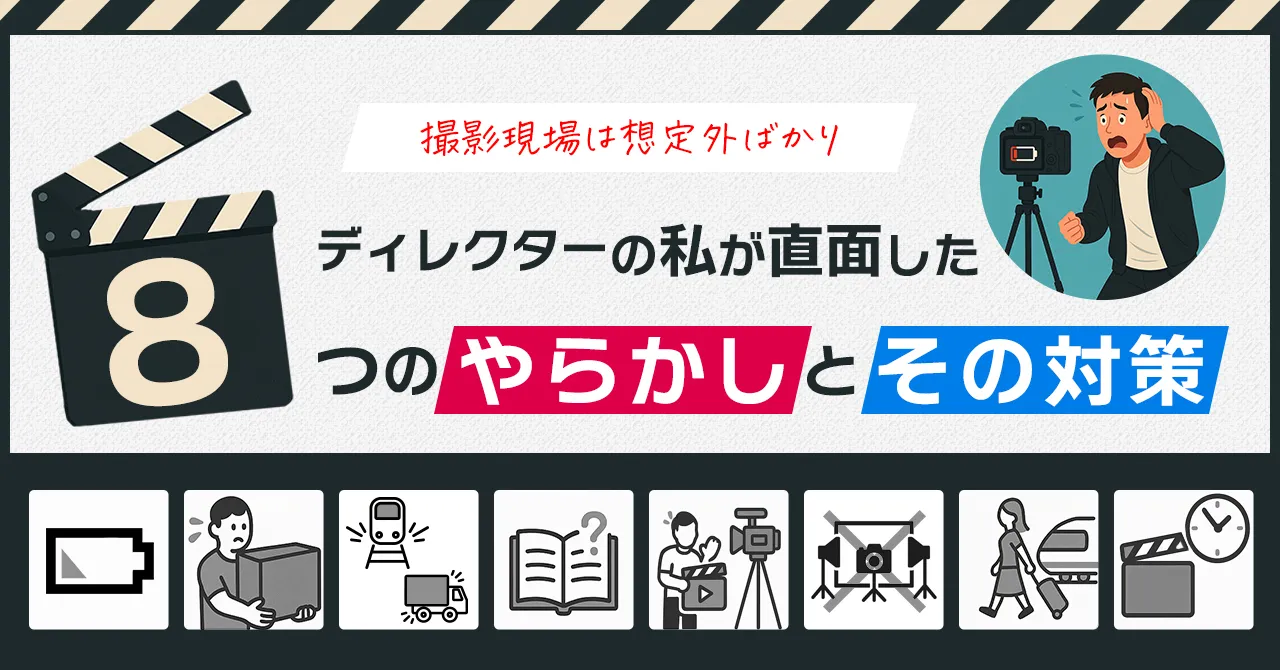
「これで準備は完璧。あとは撮るだけ!」
そう思ったはずなのに、なぜか撮影当日に限って起こる想定外のトラブル。
広告やブランディング目的で、写真や動画の撮影をする機会は増えています。だからこそ、「撮影慣れしていないと気づきにくいポイント」が、意外な落とし穴になることも。
とくに、モデルを起用した撮影やスタジオを借りての撮影は、オフィスや社員を撮る場合と違ってやり直しがしづらいものです。私自身、撮影現場に立つ中で、想定外のトラブルに何度も直面し、冷や汗をかいた経験があります。
この記事では、私が実際に体験した失敗談をもとに、「撮影で見落としがちな注意点」と「次に活かすための対策」をまとめました。


目次
物品準備編
撮影機材や小道具の準備は、基本中の基本。しかし、チェックが甘かったり、運搬手段まで想定できていないと、当日に大きな負担となってしまいます。ここでは、物品に関わる準備不足によって発生したトラブルとその対策をご紹介します。
現場でバッテリー切れに気づく
撮影当日、カメラを回していると画面に赤く点滅するバッテリーマークが目に飛び込んできました。「まさか……充電してなかった?」瞬時に血の気が引き、頭の中が真っ白になったのを覚えています。
前日の準備では、撮影に必要な小道具や台本、スケジュールなどを一通り確認していたのですが、肝心のバッテリーの残量チェックだけがすっぽり抜けていたようでした。
幸いにも予備バッテリーを持っていたため撮影は継続できましたが、もし持っていなければ、関係者全員のスケジュールに影響が出る大きなトラブルになっていた可能性があります。
撮影では、準備万端のつもりでもこうした「うっかり」が意外と起こりがちです。特にバッテリー関連は使用頻度が高く、放置しているうちに自然放電してしまうこともあるため、前日の確認は必須です。
【対策】
バッテリー残量の確認は「当日朝」だけでなく「前日」の時点で行うようにしましょう。あわせて予備バッテリーを複数持参し、「充電済みかどうか」も含めたチェックリストを作っておくことで、ミスの予防になります。
人員不足で荷物運搬が大変に
機材も小道具も一通り揃えて、「これで準備は完璧!」と思っていたのですが、撮影当日に予定していたメンバーが急遽来られなくなり、荷物の運搬がまさかの人手不足に。スタジオまでは駅から徒歩10分以上。しかも、当日は台車の手配もしておらず、重たい機材を二人がかりで手運びすることになってしまいました。
両手はふさがり、腕はプルプル。電車を乗り継ぎ汗だくでスタジオに到着した頃には、若干の疲れが……。撮影備品の準備には、しっかり目が行っていたつもりでしたが、「それをどう現地まで運ぶのか?」までを視野に入れておけば良かったと思います。
【対策】
搬入がある日は、それに見合う人数を確保しましょう。荷物の量は1週間ほど前から洗い出しておき、台車やタクシーの手配も視野に入れておくと安心です。「誰が運ぶのか」まで含めて準備の一部として設計しておくことが、当日のスムーズな進行に繋がります。
レンタルスタジオ編
商品撮影やサービス紹介の動画、プロフィール用のポートレートなど、クオリティを求める撮影ではレンタルスタジオを使うことがあります。スタジオは撮影機材や背景が整っている反面、現地に行ってみないとわからない事情がトラブルの原因になることもしばしば。
音の入りやすさや機材の配置制限など、事前の確認が欠かせません。ここでは、スタジオ利用で見落としがちなポイントとその対策を紹介します。
騒音が入ってしまい録り直し
レンタルスタジオでの動画撮影中、何度も車や電車の音が入り、録り直しが続いてしまったことがありました。内装やレイアウトの雰囲気ばかりに気を取られ、周辺の騒音環境までチェックできていなかったのが原因です。
静かな環境だと思っていたのに、実際には大通りや線路が近く、音声収録には不向きな立地でした。ロケーション選びでは「中」だけでなく「外」の情報も大切だと、身をもって学んだ経験です。
【対策】
ロケハンが難しい場合でも、Googleマップや口コミなどで周辺環境を確認しておきましょう。音声を録る予定がある場合は、マイク機材や遮音対策も事前に検討しておくと安心です。
機材が動かせず想定していた撮影ができない
レンタルスタジオを仮予約した時の話です。「このレイアウトなら大丈夫そう!」と思っていたのですが、後日オーナーさんから「定期利用の機材があるので、配置は変更できません」と言われ、予定していた撮影ができなくなってしまいました。結局、急遽別のスタジオを探して予約し直すことに。
見た目や広さだけで判断してしまい、「何がどこまで自由に動かせるのか?」を確認していなかったことが原因でした。
【対策】
スタジオ予約前には、レイアウト図や写真を確認するだけでなく、オーナーに直接現在のスタジオの様子などヒアリングすると良いでしょう。特に定期利用可や共有設備があるスタジオでは、掲載されているスタジオ情報と異なる場合があるため、事前の確認がトラブル防止に繋がります。
モデル・役者とのコミュニケーション編
採用サイトのイメージカットや、商品の利用イメージを伝える動画広告など、撮影にモデルさん・役者さんを起用するケースがあります。現場で初めて顔を合わせることも多く、関係性ができていない中で、演出のニュアンスまで汲み取ってもらうのは簡単ではありません。
さらに、撮影には時間的な制約もつきもの。短時間で的確な指示を出し、スムーズに進行することが求められます。
ここでは、そうしたモデルさん・役者さんとの撮影で気を付けたいポイントをご紹介します。
台本にセリフのみ載せていて、演出の指示が足りなかった
役者さんにセリフを話してもらったり、演技をしてもらう場合、台本は欠かせません。
私はこの撮影のために渾身の台本を用意し、「これで完璧!」と意気込んで本番に臨みました。ところが、いざ撮影が始まろうとした瞬間、役者さんからこんな質問を受けて、思わずドキッとしてしまいました。
「どんなテンションで話せばいいですか?」
「どういう動きが欲しいですか?」
たしかに、自分の中ではイメージができていたものの、文章だけの台本では演出のニュアンスまでは伝わっていなかったのです。その瞬間、「あ、台本ってセリフだけじゃ足りないんだな」と気づかされました。
【対策】
セリフだけでなく、「この場面ではどういう感情で話すのか」「どの程度の動き・ジェスチャーを求めるのか」といった、演出面の指示も台本に書いておくようにしましょう。可能であれば、事前に参考資料を共有したり、当日ディレクター自らセリフを読んだり、動きを演じて見せることで、イメージの共有がしやすくなります。
「念のためもう一回撮っておきましょう」は失礼になることも
役者さんにセリフを話してもらう動画撮影中のことです。
撮影時間に少し余裕があったので、「このカット、念のためもう一回撮ってもいいですか?」と声をかけたところ、役者さんから「さっきのが全力だったので……まず確認しません?」と言われ、ハッとしました。
私にとっては“念のため”でも、役者さんにとっては一回一回が本番。確認もせずにリテイクをお願いするのは、たしかに無神経だったなと深く反省しました。
ディレクションでは、演出や進行だけでなく、相手の気持ちへの配慮も欠かせないと改めて感じた出来事です。
【対策】
撮影中は、可能な限りこまめにデータを確認する時間を確保しましょう。撮り直しをお願いする場合は、「なぜ必要なのか」をきちんと伝えたうえで、役者さんへの敬意ある声かけをすることが、スムーズな撮影に繋がります。
起用したモデルがまさかの遠方から参加
Web上でキャスティングしたモデルさんを起用した時の話です。
「スタジオが都内だから、モデルさんも都内在住だろう」と、なんとなく思い込んでいた私。ところが、出演確定後にモデルさんから届いた一言で状況は一変。
「新幹線で向かいますね!」
そう、まさかの地方在住だったのです。移動費や拘束時間の調整を慌てて行うことになり、「もっと早く確認しておけばよかった……」と申し訳ない気持ちになりました。
【対策】
モデルさんがどこから来るか、出演確定前に必ず確認しましょう。移動手段や拘束時間の調整も含めて、「県外から来る可能性」を前提にアクセスやスケジュールを設計しておくと安心です。Webキャスティングならではの“距離感の把握ミス”を防ぐためにも、事前のヒアリングと情報共有は丁寧に行いたいところです。
集合時間の伝えミスで待機が発生
2名の役者さんを起用した撮影でのことです。映像としては1名ずつ順番に撮る予定だったのですが、全員に同じ集合時間を伝えてしまい、2人同時にスタジオに到着。結果、1人の役者さんを長時間待機させてしまうことになりました。
スケジュールはしっかり組んでいたつもりでも、「伝え方」が曖昧だと、現場のテンポや役者さんのコンディションにも影響が出てしまいます。
撮影順や集合時間は、事前に明確に共有しておく大切さを実感した出来事でした。
【対策】
撮影順ごとに集合時間を個別に設定・共有しましょう。タイムテーブルへの記載はもちろん、台本にも撮影時間を反映させておくと安心です。
撮影現場は想定外の連続。でも学びの宝庫
撮影現場は、いくら準備していても完璧はありません。
むしろ、予期せぬことが起こる前提で臨むこと、そして、想定外を想定内に変えていく思考のクセをつけることが、現場での柔軟な対応力に繋がっていくと感じています。
そのためにも、
- 撮影当日の流れを細かくシミュレーションしておく
- 自分の頭の中だけで完結させず、「誰が、いつ、何をするか」を言語化して共有する
- 先輩ディレクターに話を聞いて「こういったミスが起こりがち」と知っておく
といった準備やチーム連携が、トラブルの深刻化を防いでくれるはずです。
撮影ディレクションの一連の流れ知りたい方は、こちらの記事もぜひ読んでみてくださいね。