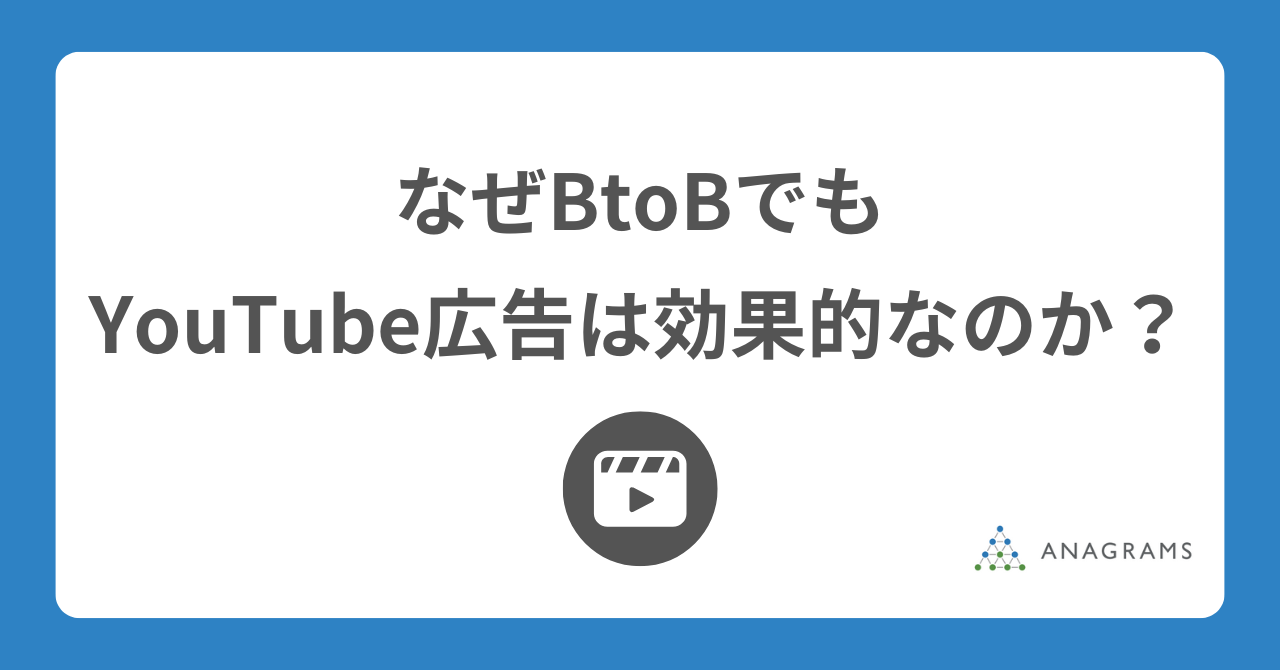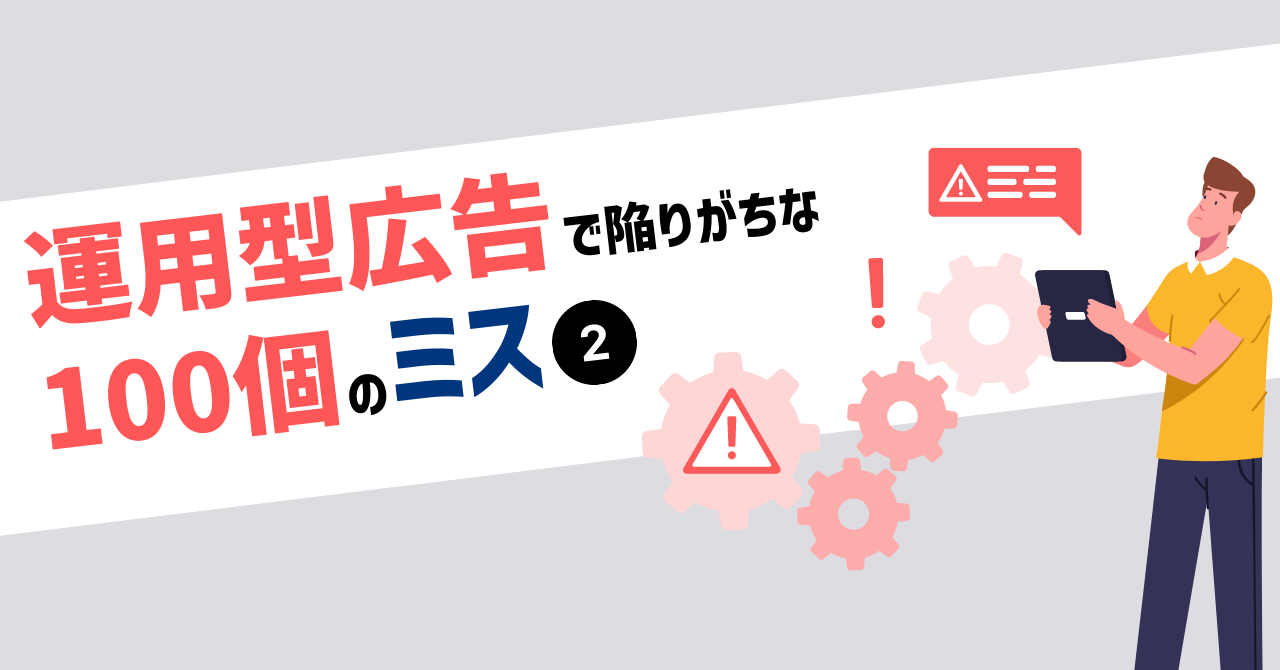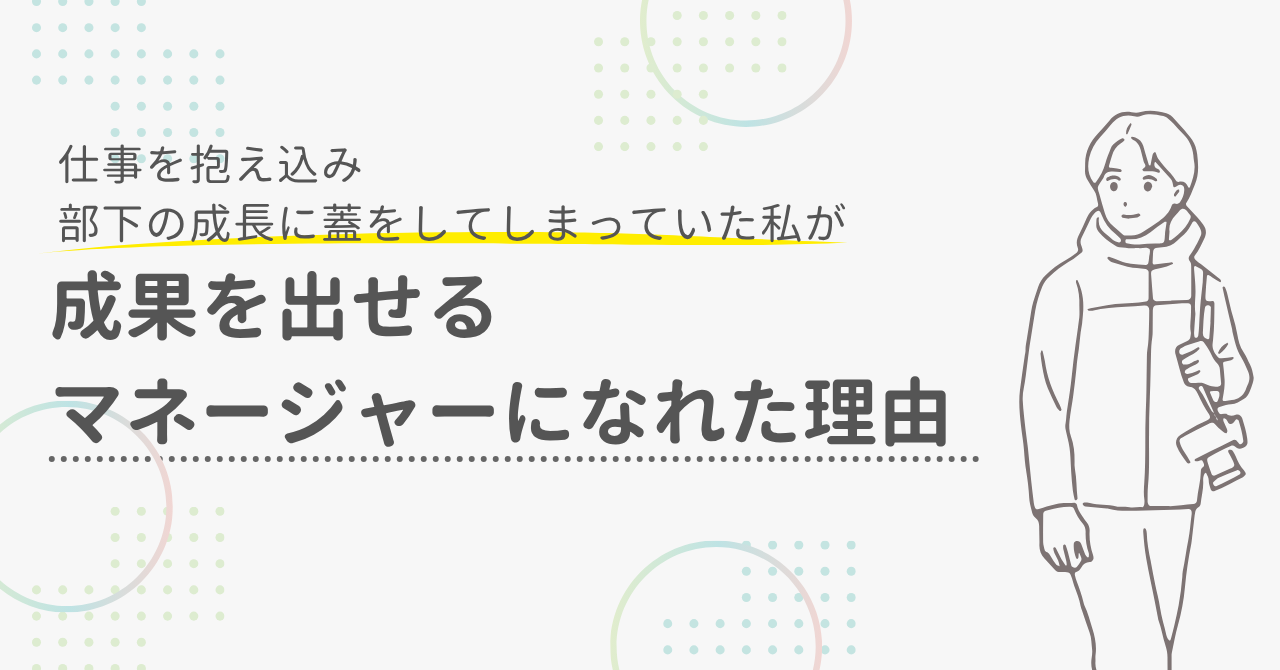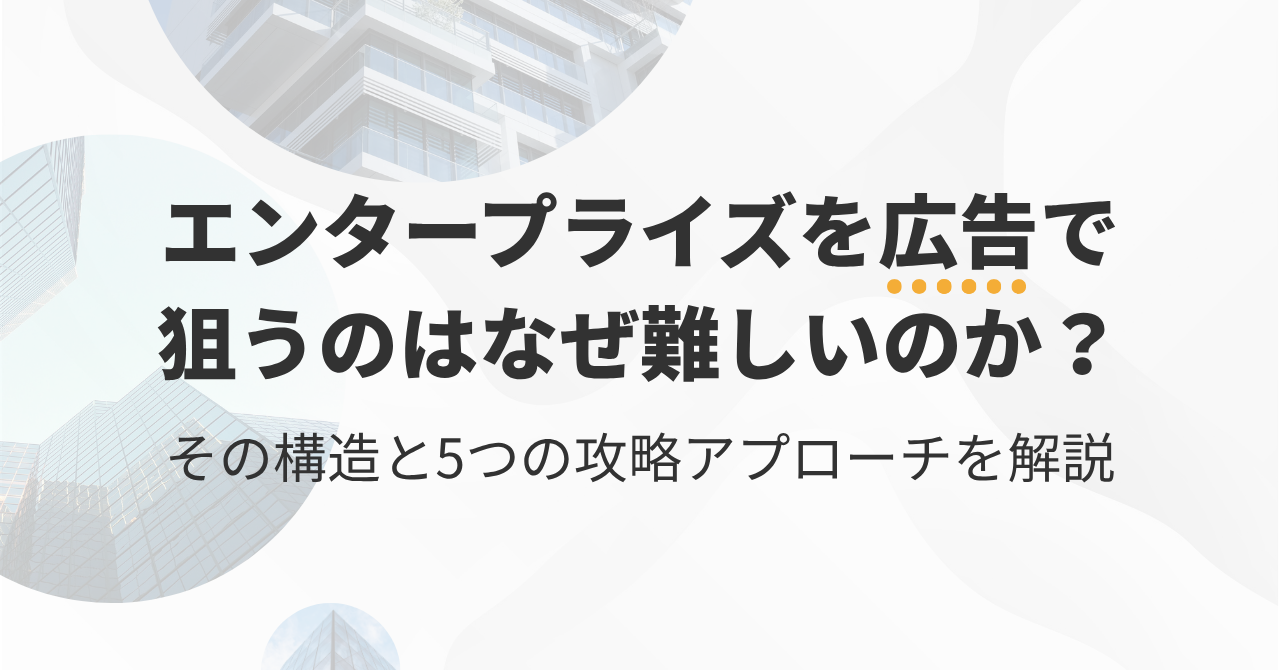
近年、「エンタープライズ企業※」や特定業界の企業をピンポイントで獲得したいというご相談をいただく機会が増えています。しかし、実際に運用している企業の方に話を伺うと、「なかなかうまくいかない…」という声が少なくありません。
多くの企業が採用しているBtoB向けWebマーケティングの手法は、どちらかというと「※SMB向け」に広く展開するやり方が中心です。一方、特定業界やエンタープライズのように対象企業が限られるケースに特化した情報は、まだまだ少ない印象を受けます。
本記事ではまず、「エンタープライズ攻略がなぜ難しいのか」という構造的な背景を明らかにした上で、広告運用において実践できる5つの打ち手を整理して紹介します。
エンタープライズ獲得を本気で狙いたい広告運用者・マーケターの方に、現場でそのまま使えるヒントをお届けします。
※SMB(Small and Medium-sized Business): 中小企業を意味します


目次
エンタープライズ向けの広告が難しい理由
エンタープライズ企業をターゲットに広告を展開する際、多くの運用者が「リードが取れない」「商談につながらない」といった壁にぶつかります。これは単に施策の打ち方が悪いのではなく、そもそもエンタープライズ市場が持つ構造的な難しさに起因するものです。以下に、主な4つの理由を整理します
① 対象企業が極端に少ない
まず前提として、日本国内における従業員1,000名以上の大企業は、全企業の0.3%未満というごく限られた存在です。仮に母数が5,000社だった場合、リード獲得を目的とする広告施策では、その中のごく一部にしか届かないのが現実です。
このような“点”の市場を相手にする場合、「どれだけ多く集められるか」ではなく、「いかに狙った企業にピンポイントで届けられるか」が成否を分ける鍵となります。
② 決裁に関与する人数・階層が多い
エンタープライズでは、商品・サービスの導入において複数の部署や役職者が意思決定に関与します。情報収集をする実務担当、比較検討するミドルマネジメント、最終決裁を下す経営層――それぞれが異なる視点と関心を持っており、単一の訴求だけでは刺さりません。
広告も、「誰に」「どのタイミングで」「どんな情報を」届けるのかを踏まえて設計する必要があり、属人的なリード獲得では対応しきれなくなります。
③ 購入までの検討期間が長い
一般的に、エンタープライズ企業では導入までに数ヶ月から1年以上を要することも珍しくありません。短期的なCVを追うだけでは刈り取りきれず、途中で「このリードは失注だ」と判断してしまうリスクもあります。
ケーススタディ:人事部門向けSaaS
- Meta広告:資料ダウンロード(ホワイトペーパー)のCPAが低く、一見効率的
- YDA(Yahoo!ディスプレイ広告):企業規模100名以上+人事部門向けターゲティングで配信
- リード獲得のCPA自体はMetaの方が安かった
- しかし実際の商談化や受注率はYDAが優れており、総合的にはYDAの方が費用対効果が高かった
このケースでは、「リード獲得CPA」だけでなく「ターゲット属性に合ったリードが獲得できたか」「CV後の商談・受注につながったか」が評価のポイントでした。SMBよりも導入までの期間が長いエンタープライズ企業がメインターゲットなら、まずは狙った企業からCVを取るところに注力することが必要です。
そのため、広告施策も単発で終わらせるのではなく、ナーチャリング前提の多段設計が求められます。複数チャネルでの継続的な接触、段階に応じたメッセージの出し分けが、検討テーブルに乗る確率を高めるカギになります。
④ “企業単位”でのスコアリングや評価が必要
中小企業向けの広告では、「担当者1名との接点」から商談・受注につながるケースが多く見られます。しかしエンタープライズの場合、1件の問い合わせ=1社全体への到達ではありません。
広告を通じて接点を持てるのは、あくまで“組織の中の1人”に過ぎません。その1人だけを最適化しても、案件が動く保証はないのです。だからこそ、“企業単位”でのスコアリングや評価、複数人への接触戦略が必要になります。
エンタープライズ攻略において、「広告でリードが取れない」のは施策の良し悪しだけではありません。“広告の届け方”以前に、“相手の構造”を理解していなかったことが原因であることが多いのです。
次章では、これらの構造的な難しさを前提にしたうえで、実際に広告運用で押さえるべき5つの具体的なアプローチを紹介していきます。
エンタープライズに届く広告設計の5つの打ち手
前章では、エンタープライズ企業を広告で狙うことがいかに難しく、その背景には市場構造や組織特性といった根深い要因があることを整理しました。
では、そうした構造的なハードルを前提にした上で、私たちは何をどう変えればよいのでしょうか?
ここからは、広告運用の現場で実践できる「5つの打ち手」を紹介します。いずれも「特定の企業に、適切な情報を、適切なタイミングで届ける」ための設計であり、リード獲得から商談化・受注までを見据えたアプローチです。
単発のノウハウではなく、戦略的な“勝ちパターン”を構築する視点で、順に見ていきましょう。
アプローチ①|リード獲得前から“理想顧客”を定義する
エンタープライズ向け広告の成否は、施策を打つ前の“設計段階”でほぼ決まると言っても過言ではありません。特に重要なのが、「理想の顧客像=誰に届けたいのか」を明確にし、営業部門とすり合わせたMQL(Marketing Qualified Lead)定義を共有することです。
多くのBtoB企業では、マーケティング側が“リード”を集め、営業側が“リードの質が低い”と嘆く。そんな分断が起こりがちです。これを防ぐには、ターゲット企業の業種・規模・部署・役職といった属性情報に基づいて、MQLを定義し直す必要があります。
さらに、商材の性質に応じて、企業を以下のように整理することも有効です。
(例:ホリゾンタル×バーティカルの分類)
- ホリゾンタル × 標準型:会計ソフト、勤怠管理
- バーティカル × 標準型:医療SaaS、物流管理システム
- ホリゾンタル × カスタム型:データ統合基盤、BIツール
- バーティカル × カスタム型:官公庁向けシステム、病院経営支援
「自社の商材がどの象限に属し、どの業界・規模・職種に刺さるのか」を明確にした上で、広告のターゲティング設計に落とし込むことが、成果のある運用の出発点になります。
アプローチ②|リード単位ではなく“企業単位”でトラッキング
エンタープライズ攻略において、1リード=1チャンスという発想は通用しません。大企業では、1人の行動だけで導入が決まることはなく、複数部署・複数人物が関与する「組織」としての検討が進みます。
この前提に立てば、広告やサイト流入を“企業単位”で把握する視点=ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)が必要不可欠になります。具体的には以下のような設計が鍵となります。
- Webアクセス時に企業IDを判定し、同一企業の行動を束ねて分析(例:IPリバース/データ連携)
- MA/CRMツールで複数リードの活動履歴を統合し、組織全体の“温度感”を可視化
- SFA(営業支援ツール)との連動により、営業活動と広告接触を接続
特定の担当者の反応だけで判断するのではなく、その企業全体が動いているか?を把握できる構造を作ることが、無駄打ちを減らす広告設計につながります。
アプローチ③|態度変容を促す“複数CVポイント”の設計
中小企業を相手にする場合と違い、エンタープライズでは1回の広告接触で商談が始まることはほぼありません。そのため、「資料請求」だけに依存せず、検討段階に応じた複数のCV(コンバージョン)ポイントを設計することが重要です。
たとえば、以下のように段階的なCV設計を行います。
- 初期接触:ホワイトペーパーDL、業界別記事閲覧、広告動画再生
- 中間接触:ウェビナー申込、サービス比較ページ閲覧、業界事例のダウンロード
- 後期接触:個別相談申込、デモ依頼、トライアル申し込み
このように、「今すぐ商談」ではない行動もCVとして定義し、ナーチャリング(育成)を前提とした構成を作ることで、広告による接触が中長期的な商談化へとつながっていきます。
アプローチ④|媒体ごとの役割を“ファネルと属性精度”で見極める
エンタープライズ攻略では、「どの媒体が最も安いか」ではなく、「どのファネルで何を期待するか」の視点で媒体を選ぶ必要があります。
たとえば、以下のように媒体ごとに役割を分けて考えると整理しやすくなります。
- LinkedIn:精緻な属性指定(業種・職種・役職)/決裁層・IT部門への直接訴求
- Meta広告:回遊力・動画との親和性/若手担当者や複数部門への同時接触
- YDA(Yahoo!広告):企業ID連携/法人指名配信や業界別接触
- Google検索:顕在層のニーズ回収/比較検討層の問い合わせ・資料請求誘導
広告は「点」で見るのではなく、「ファネル全体の流れ」の中で媒体をどう組み合わせるかが問われます。
アプローチ⑤|検索広告では“商材理解度別”のキーワードを設計
エンタープライズ向けの検索広告では、「指名検索」や「サービス名」だけで成果が出ないケースが多くあります。なぜなら、検索行動が「課題」や「業界」から始まることが多いからです。
以下のように、商材理解度(=検討段階)に応じてキーワードとLPを出し分ける設計が必要です。
- 初期:SaaS 導入課題、業務効率化とは → 業界課題を掘る記事・DL資料
- 中期:会計ソフト 比較、競合名+評判 → 比較チャート、導入事例
- 後期:freee 導入事例、導入費用 → ROIシミュレーション、相談CTA
広告文・LP・計測の全てを“検索意図に応じた構成”にすることで、CVRだけでなく商談化率の向上が見込めます。
型を持って構造に挑もう
ここまで紹介した5つのアプローチは、いずれもエンタープライズ市場の「構造的な難しさ」を乗り越えるための戦術です。
単にクリック率やリード数を追うのではなく、「誰に届けて、どんな態度変容を起こし、最終的にどこまで案件が進むか」を設計することが、広告施策の成否を分けます。
エンタープライズ攻略においては、「成果が出ない理由」が広告の運用手法にあるとは限りません。むしろ、ターゲティングの設計・営業との連携・媒体の使い分け・KPIの再定義など、広告の“外側”にこそ改善すべきポイントが隠れています。
ぜひ今回紹介したアプローチをベースに、御社ならではの“勝ち筋”を設計し、狙った企業との確実な接点構築につなげていただければと思います。