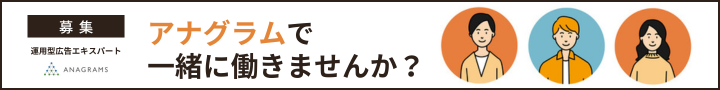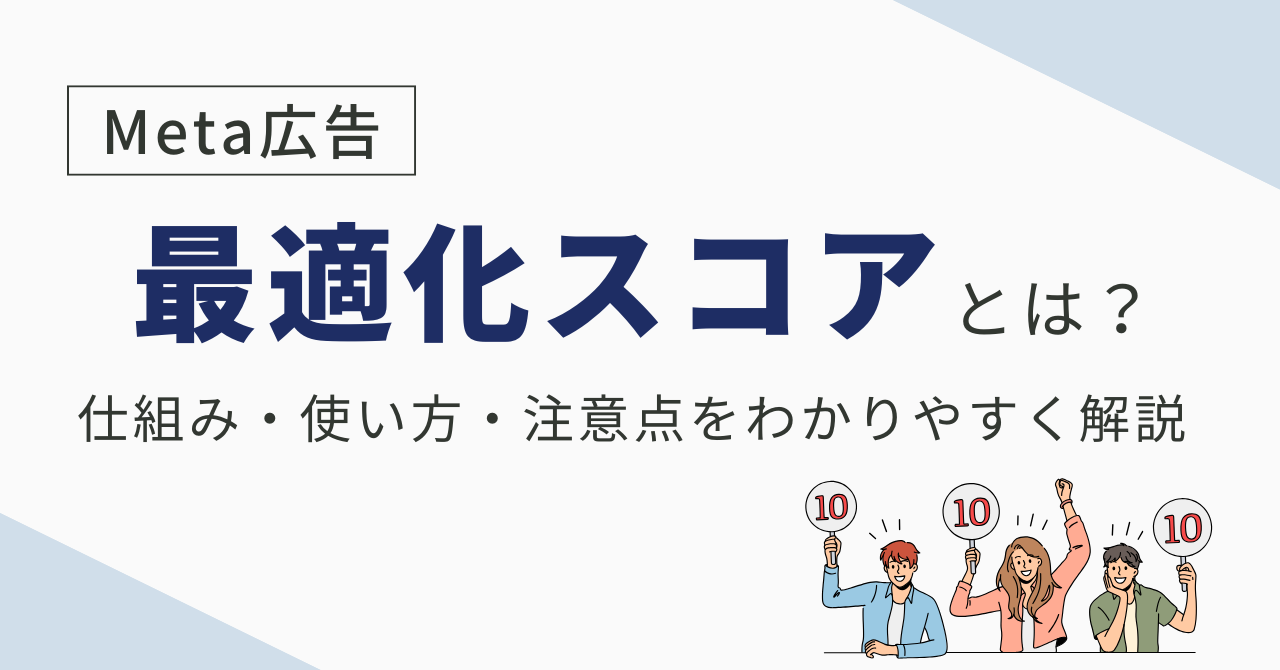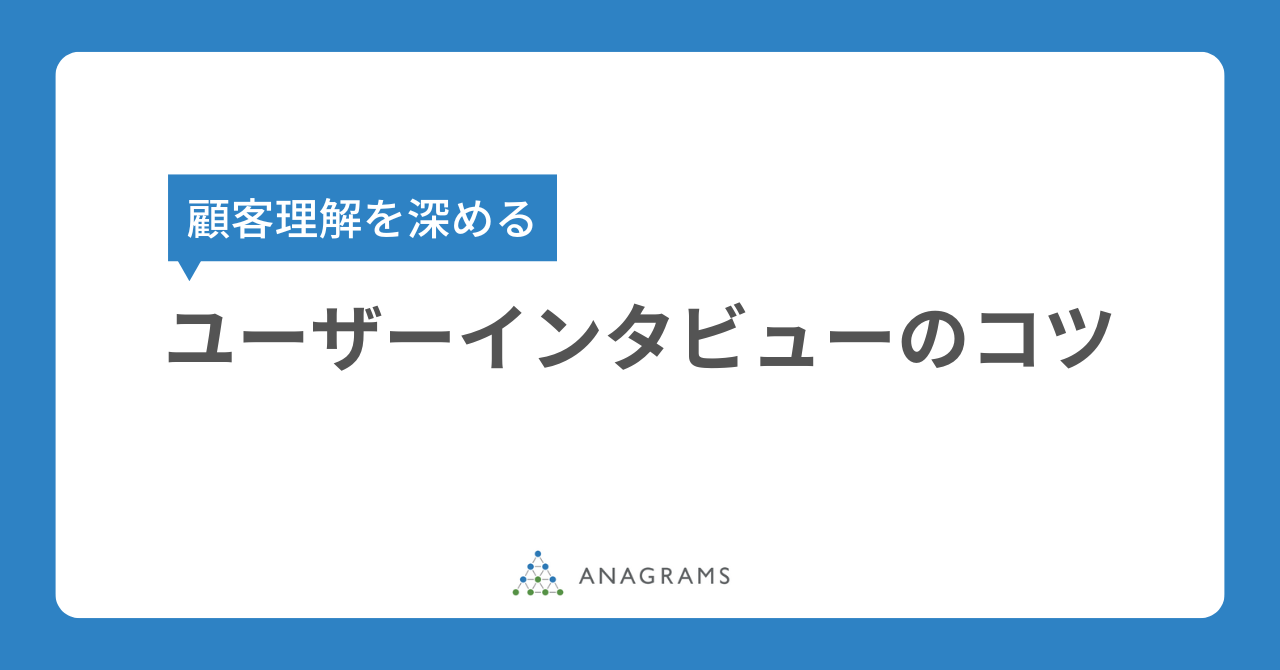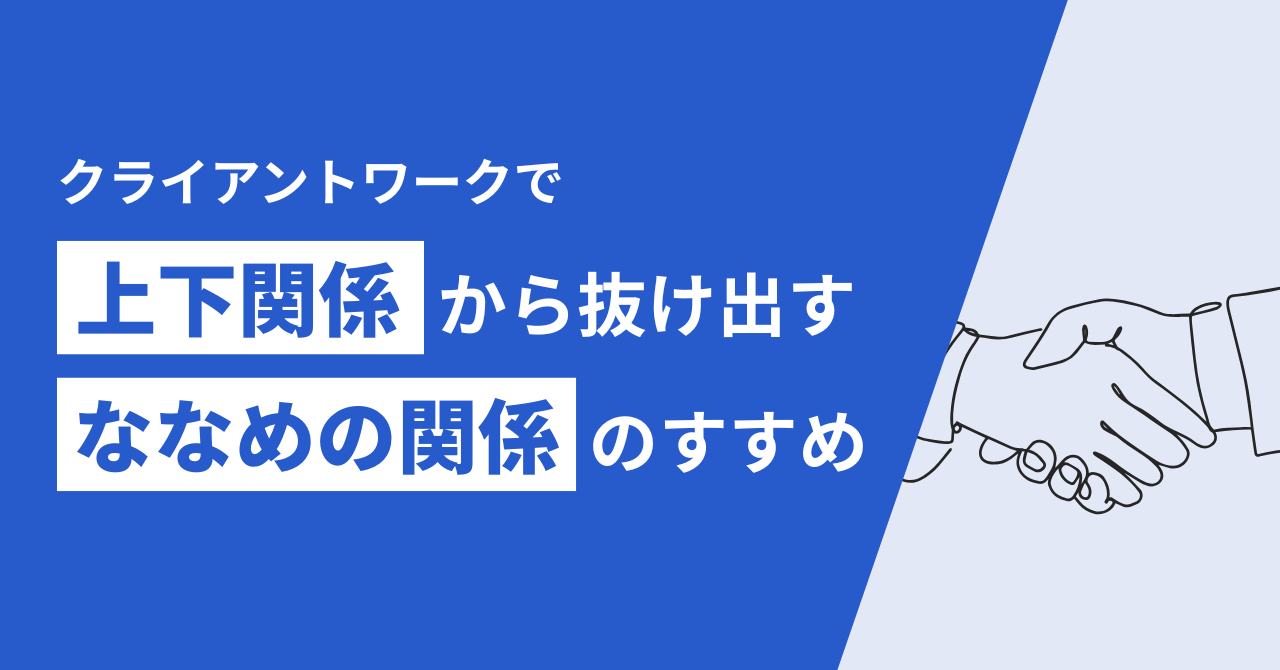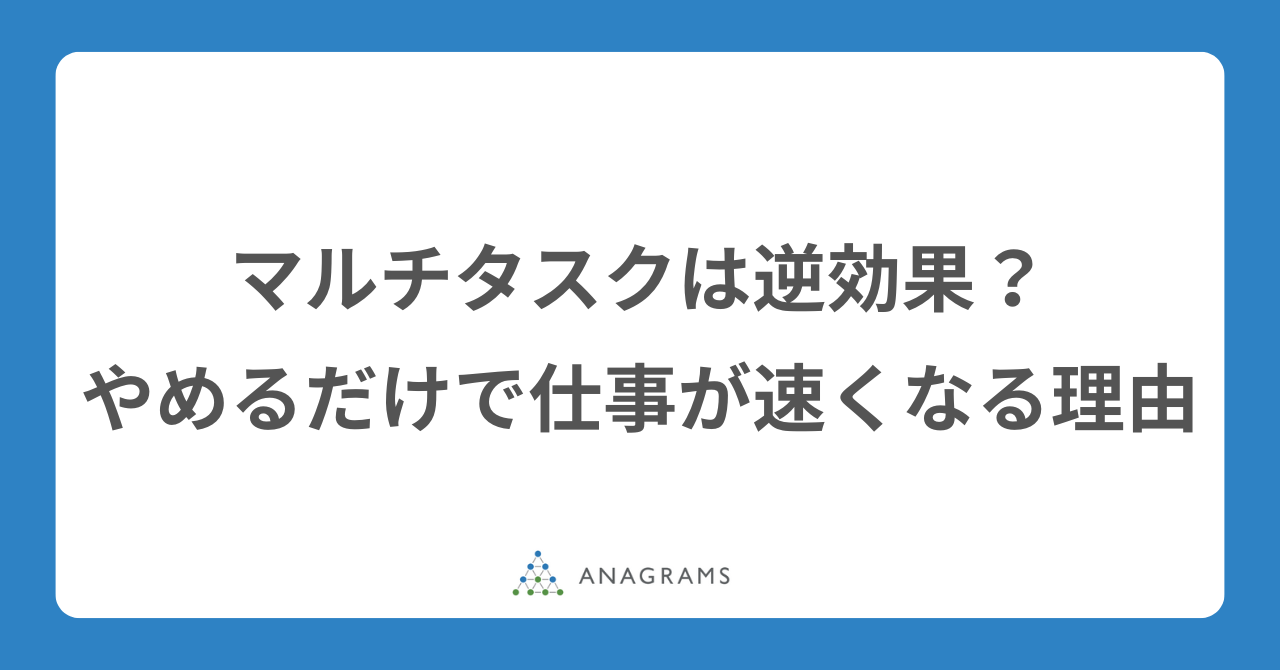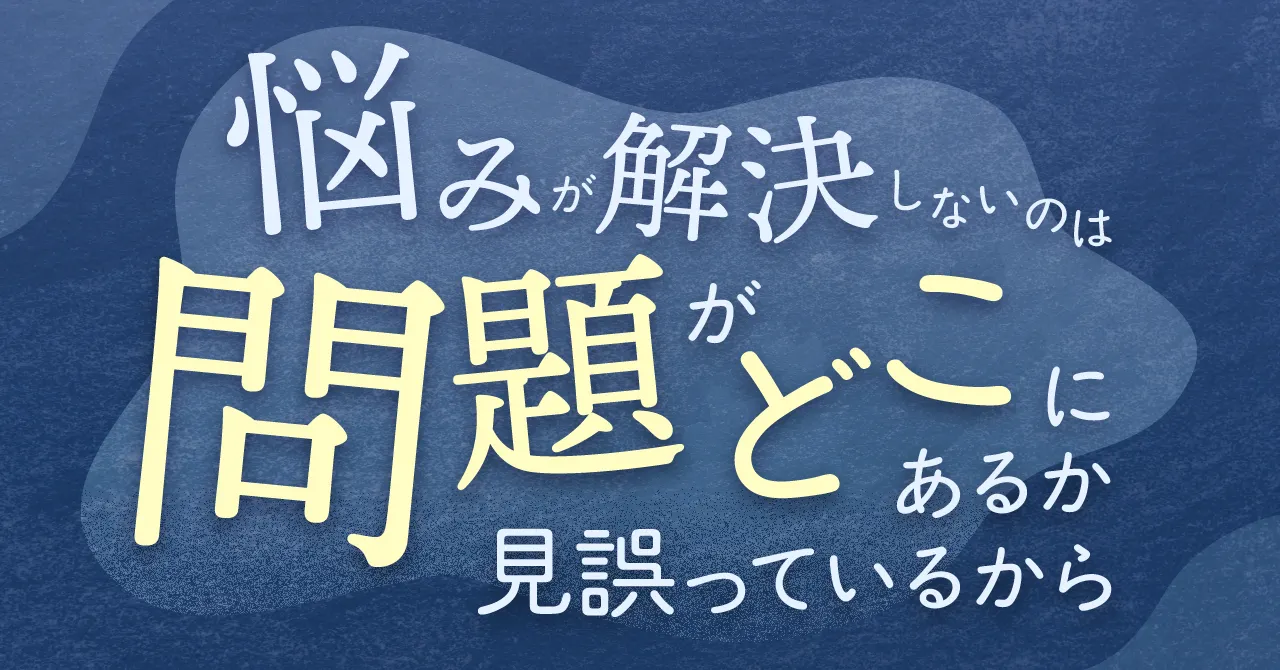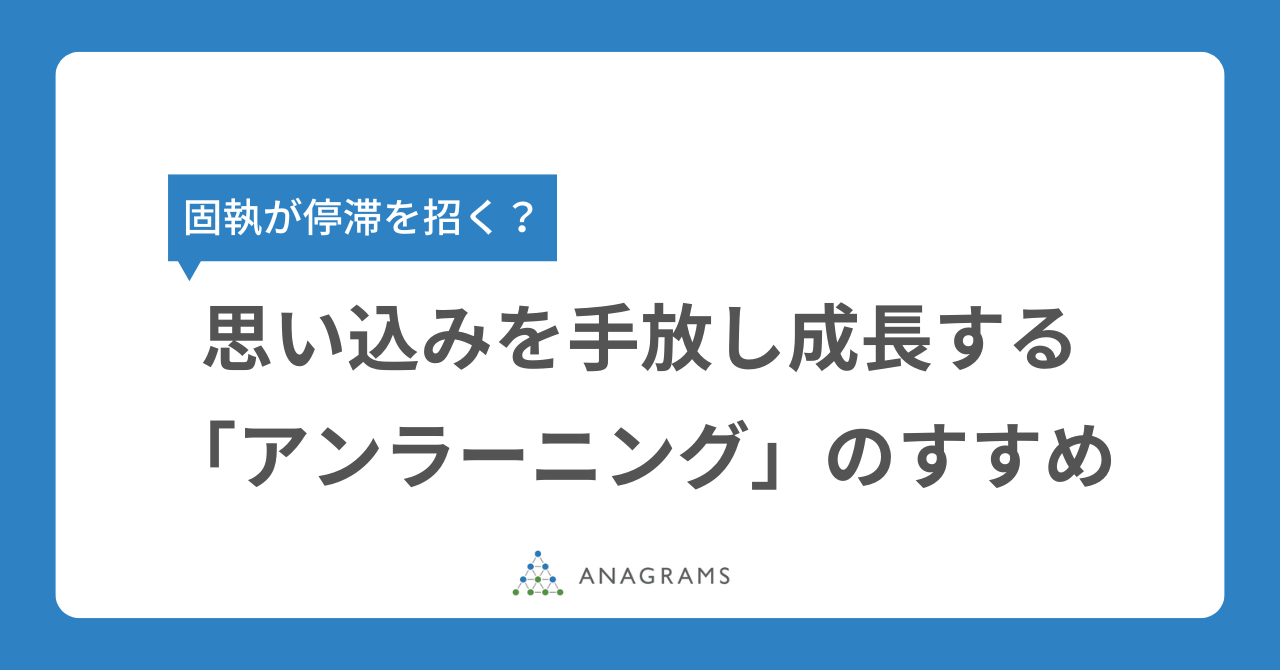
知識や経験は増えているはずなのに、なぜか以前のように結果が出せない……そんなもどかしさを感じていませんか? もしかしたら、その原因は「固執」にあるかもしれません。
変化のスピードが速い広告業界では、過去の成功体験がいつの間にか足かせになったり、新しい知識を学ぶことで、過去の知識を置き去りにしてしまったりすることがあります。
過去の成功体験に「固執」し、変化に対応できなくなる。 あるいは、新しい知識に「固執」し、過去の経験を活かせなくなる。 どちらにしても、「固執」は成長を阻害する要因となり得るのです。
本記事では、広告運用者が陥りやすいこれらの「固執」の原因を深掘りし、それを打破し、常に成長し続けるための「アンラーニング」という考え方と、具体的な実践方法を事例とともにご紹介します。


目次
成長の停滞は「固執」から始まる
なぜ、知識も経験もあるはずの広告運用者が、成長の壁にぶつかってしまうのでしょうか?その原因の一つとして考えられるのが「固執」です。
どんな固執があるのか、陥りがちな2つを紹介します。
「過去」へ固執し、変化に対応できない
変化のスピードが速い広告業界では、過去の成功体験は、時に通用しなくなるだけでなく、むしろ成長の妨げになることさえあります。
しかし、人間の脳は、過去の経験や知識に囚われやすいという特性があります。これは、効率的に情報処理を行うための脳の働きによるものですが、時には判断を誤らせる原因にもなります。
具体的には、以下のケースが考えられます。
- 過去に失敗した施策を、成果が出ないと思い込み、媒体仕様や環境が変わっても試さない
- 過去に成功したクリエイティブの成果が落ちても、たまたまだと考えて対処しない
- 過去の仕事の進め方や、ルーティンを疑わず、変化を起こさない
これらの例に共通しているのは、過去の成功体験や、慣れ親しんだやり方に固執し、変化に対応することを避けてしまっている点です。
広告業界は常に変化しているため、過去の成功施策がタイミングや媒体の変化で上手くいかなくなることもあれば、逆に失敗した施策がタイミングや媒体の変化で上手くいくことなども多くあります。
「トレンド」へ固執し、視野が狭くなる
一方で、固執は過去の成功体験だけに生まれるものではありません。一見、重要に見える最新技術や新しい手法といった『トレンド』にも、私たちは意外と簡単に固執してしまうものです。
なぜなら、人間の脳は、複雑な情報を処理するよりも、分かりやすい概念やシンプルな法則に頼ろうとする傾向があるからです。そのため、従来の常識を覆すような斬新な概念は、私たちの目に留まりやすく、強く印象に残ります。
例えば、あなたも、生成AIのような最先端の技術や、最新のマーケティングフレームワーク〇〇といった情報を目にした際、「これを学べば、きっと成果が向上するはず」と感じたことがあるのではないでしょうか。
しかし、技術やフレームワークは、すべてのケースで有効とは限りません。活用自体が目的になってしまい、本当に解決すべき課題を見失ってしまっては、期待した成果につながりませんよね。
結局のところ、過去の成功体験であっても、最新の情報であっても、1つの考えに固執すること自体が問題なのです。
知識を手放す「アンラーニング」のすすめ
そこで重要なのが、あえて知識を手放すことです。
知識や経験が増えるほど、それに固執してしまい柔軟な意思決定ができなくなってしまう可能性が増えてしまうのであれば、それらを敢えて手放すことが、停滞を打破する鍵になります。
どんな知識も絶対的な正解はない
知識を手放す上で、まず理解しておきたいのが、「どんな知識も、全ての状況において通用するわけではない」ということです。
例えば、「広告文は短く、簡潔にまとめるのが効果的だ」という知識は、多くの場面で有効です。 しかし、商品やサービスの複雑さを伝えたい場合や、ターゲット層に合わせた表現をしたい場合には、必ずしも短い文章が良いとは限りません。
そのことが理解できると、今の知識がこの場面で正しいとは限らないと手放すことができるようになります。
学び続ける姿勢を持つ
このように知識を手放し、新しい知識を学ぶ習慣としてヒントになるのが、アンラーニングという考え方です。
青山学院大学教授の松尾睦氏は、著書『仕事のアンラーニング』において、アンラーニングを「個人が、自身の知識・スキルを意図的に棄却しながら、新しい知識・スキルを取り入れるプロセス」と定義しています。
このように、知識を手放し、学び直す習慣を継続し、固執から逃れて柔軟な思考を続けることが、成長の停滞を打破し、成長し続ける鍵になるのです。
アンラーニングで成長し続けるための3つの習慣
ここからは上記のアンラーニングの習慣を手に入れるための具体的な方法を、3つのプロセスに分けて紹介します。
思い込みを手放そう
まず大切なのは、先入観を持たずに現実をありのままに見ることです。 私たちが持っている知識や経験は、必ずしも現実と一致するとは限りません。
人間の脳は、どうしても過去の経験に基づいて物事を判断しがちですが、現実世界は常に変化しています。 そのため、固定観念にとらわれず、現実を注意深く観察することで、これまで気づかなかった新しい発見があるはずです。
例えば、「価格が安ければ安いほど売れやすい」と思い込んでいたとしても、スーパーで商品を選ぶ際、少し値段の高いものを選んでいたことに気づくかもしれません。「なぜ高い方を選んだのだろう?」と考えてみると、「安いものより、少し高くても品質が良い方が安心できる」という心理が働いていることに気づき、「価格が安ければ安いほど売れやすい」という思い込みから解放されることがあります。
ありのままの現実を見つめる訓練として、以下の2つの方法を試してみましょう。
日々の気づきを言語化する
日々の生活や業務の中で、自分の知識や予想とは異なる出来事に遭遇した際に、その気づきを言葉で表現する習慣をつけましょう。 言語化することで、無意識の思い込みに気づき、新たな視点を得ることができます。
アナグラムでは、一部のチームで、日々の気づきを抽象化して共有する取り組みを行っています。
他者の行動や、意見を参考にする
自分以外の人の行動や意見は、自分の固定観念に気づくためのヒントになります。 上司や同僚からのフィードバックに耳を傾けるのはもちろん、普段とは異なる考え方の記事や書籍を読んだり、他者の仕事の進め方を観察したりすることで、新たな視点を得ることができます。
またアナグラムでは、社員全員が週に1回、担当案件のビジネスの成長について議論する「グロースハック」という文化があり、他者の視点を取り入れ、知識をアップデートする習慣を大切にしています。
小さく行動し、変化を起こそう
新たな気づきを得たら、実際に試してみることが何よりも重要です。 なぜなら、人間の脳は頭で理解しただけでは変わらず、つい過去の考えに固執してしまうからです。
例えば、「価格が安ければ安いほど売れるとは限らない」と頭では理解したとしても、「でも、やっぱり値上げは怖いから、今まで通り安く売ろう」と考えてしまうのが、人間の性というものです。 実際に値上げに挑戦し、その結果を体験して初めて、考え方が変わることもあるのです。
そこで大事なのが小さく行動することです。資材の高騰などやむを得ない事情がありながら、商品を値上げするのが怖い場合、まずは一部の商品や地域限定で試験的に値上げを実施してみるなど、行動のハードルを下げることが有効です。
もし、その結果、売上が増える経験をすれば、「価格を上げると売上が下がる」という思い込みが、必ずしも正しくなかったことに気づき、利益を改善する機会が得られます。
また仮に「値上げで売上が大きく下がってしまった」という体験になったとしても、「自身の体験が他の人にも当てはまるとは限らない」という学びを得ることができます。リスクを限定していれば、失敗から得られる学びの価値の方が、損失を上回ることもあります。
手放した知識と、新たに得た知識を繋げよう
知識を手放した際にも、過去の知識を完全否定してしまっては本末転倒です。 どんな知識にも、絶対に正しいということはないからです。
重要なのは、一度手放した知識を完全に捨てるのではなく、新しい知識と組み合わせることで、より深い学びを得ることです。
例えば、「どんな連絡にも即レスが重要だ」という考え方を手放し、状況に応じて、必要な情報を整理し、丁寧に返信することで、かえってコミュニケーションが円滑に進むようになったとします。 その際には、即レス"か"丁寧な返信"か"という二択で考えて、「即レスは必要ない」と決めつけるのでなく、相手の状況や連絡の内容に応じて、最適な方法を選択するのが大事という、より高次の視点を持つことが重要なのです。
このように、一見矛盾する2つの要素のいいとこどりを行って、新たなアイデアを生み出す方法として、止揚という考え方もあるので、こちらも参考にしてください。
まとめ
知識や経験が増えても、時間と意識は有限であるため、1つの考えに固執せずに、知識のアップデートを続けることが大事です。
そのためには、何か大きなことを行うのでなく、日々思い込みから脱し、新しいことに挑戦していく習慣を作ることが鍵になります。
アンラーニングは簡単ではなく、脳の仕組み的に誰もが通る道なので、早い段階で気付けたら一生成長し続けるチャンスになります。ぜひ今日からアンラーニングの習慣をつけるために取り組んでみてください。実践していただければと思います。顧客理解が深まることで、きっと新たな気付きが生まれ、マーケティングや広告運用がより楽しく、より成果につながるようになるでしょう。