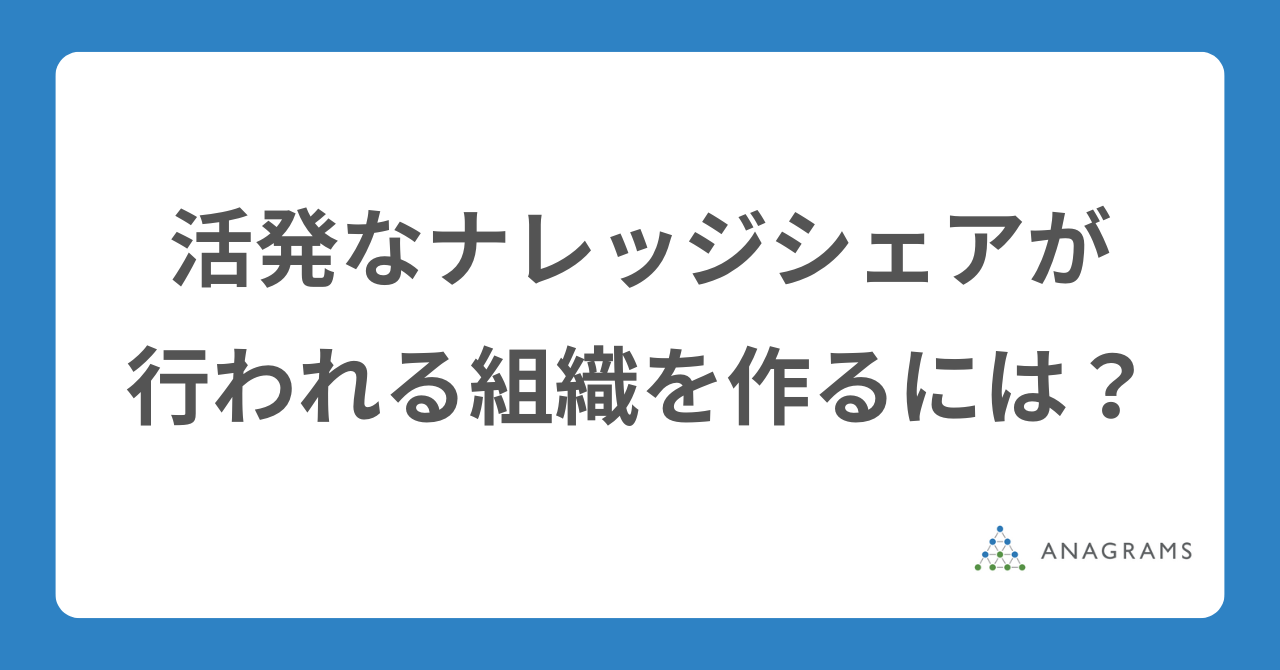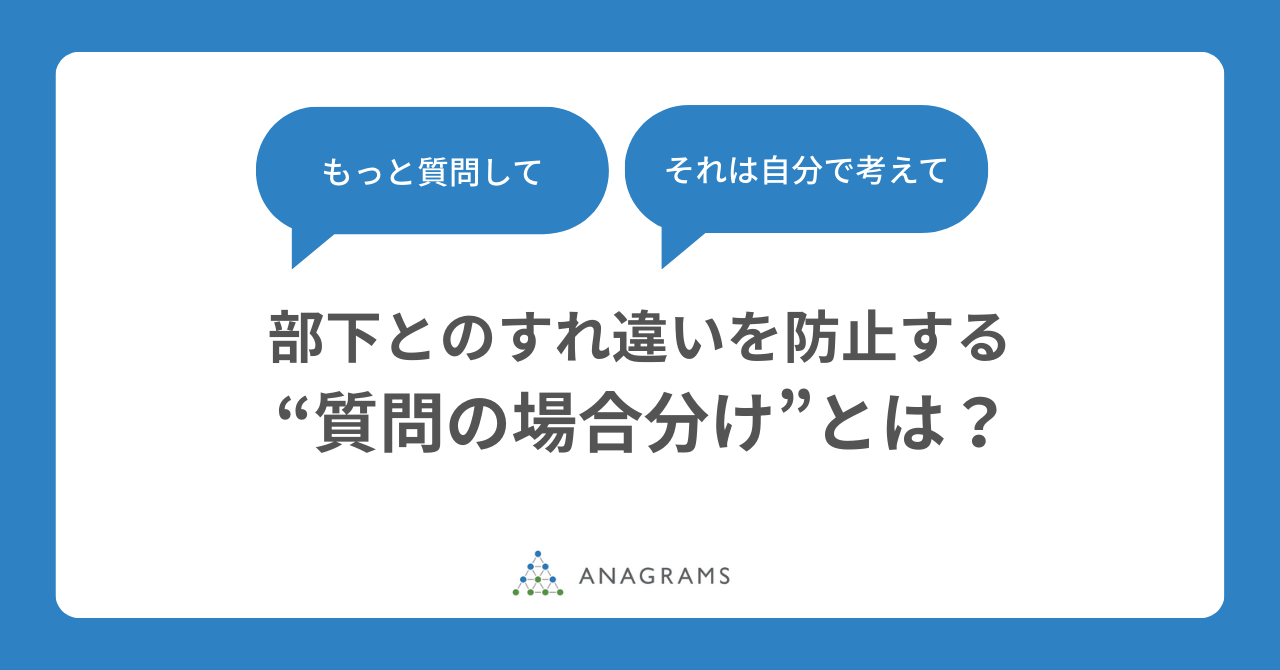
「たくさん質問する人は成長しやすい」とよく言われます。
基本的には先人の知恵を借りながら進んでいった方が早く目的地にたどり着けますし、質問をする過程で自分の理解度が明確になり、状況を整理しやすくなるなど、たくさんのメリットがあるからです。
質問によって得をするのは質問者だけではありません。
たとえば上司の立場であれば、部下から質問を受けることで「Aが分かっていないならBも分からないだろうから教えよう」という発想をしやすくなりますし、早めに質問してもらうことで適切なフォローをしやすくなる、言語化して伝えることで他のメンバーに聞かれた際に同じ内容を伝えやすくなる、など様々な効果を得られます。
ただ、マネジメントにおいて「質問」が有効であると言われたとき、こう思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「遠慮なく質問してね、と言ってもなかなか質問してくれないんだよなぁ」
「何でも質問すればよいというものではない。少しは自分で考えてほしい」
今回は、上司の立場として「質問」というものをどう捉え、マネジメントに活用していくべきなのかを考えていきます。


質問に関するすれ違い
質問してほしいことを質問してくれない、自分で考えてほしいことを質問される。これらの問題は、「質問」に対して両者がイメージしているものが異なることに起因すると考えています。
<質問してほしいことを質問してくれないケース(例)>
部下「Aさん(上司)は忙しそうだし、自分で考えられないヤツだと思われるかもしれないから、とりあえず進めてからあとで質問しよう」
上司「方向性がズレていたら修正に時間がかかるから、前提や基準がクリアではないならば早めに質問してほしい」
<自分で考えてほしいことを質問されるケース(例)>
部下「●●の使い方がわからないな。このあいだ質問を溜め込んで失敗したから、今度は早めにAさん(上司)に聞こう!」
上司「仕様書をせっかく作ったんだから、まずはそれを見てから質問してほしい」
こんなすれ違い、起こっていないでしょうか?
質問を場合分けしよう
「何でも質問してね」は実際には「何でも」ではない。「自分で調べてから質問して」と言っていたとしても「何時間も一人で悩んで仕事が止まってしまう」ことを望んでいるわけではない。
一言に「質問」とまとめてしまうと、こういったニュアンスはなかなか伝わりません。
そこで、質問を場合分けし、ふわっとしたものから具体的なものまで以下のように順に並べてみましょう。
- 何がわからないかわからない
- 前提や基準を確かめたい
- 理由に納得したい
- やり方や答えがわからない
- 他者の視点がほしい
- 前に聞いた内容をもう一度聞きたい
何がわからないかわからない
「何がわからないかわからない」というケースは、質問まで至らなかったり、質問されたところで「要領を得ないけれど、何を聞きたいんだろう?」と上司が困ってしまうことも多いです。
こういったとき、上司側はつい「もっと質問をまとめてから持ってきてほしい」と言ってしまいがちですが、何がわからないかわからないのに質問をまとめることは出来ません。
では質問を受けなくていいのかというとそんなはずはなく、部下をその状態のまま放置すると、霧の中を歩いているような感覚のまま悩みはどんどん深くなっていってしまいます。
まずは、質問がまとまっていなくてもよいから声をかけてほしい、と伝えましょう。
さらに、上司側が「何がわからないかわからない状態なのだ」と理解するために、「頭が整理できていないので、整理の部分から手伝ってもらいたいのですが…」「分からないことが分からなくてぼんやりと不安なので、話しながらクリアにしたいのですが…」などの前置きをしたうえで聞いてね、と伝えるとよいでしょう。
そのうえで、上司は質問に対して受け身の姿勢をとるのではなく「何がわからないのか」を探し出せるよう、現状を丁寧にヒアリングしていく必要があります。
前提や基準を確かめたい
前提や基準を確かめたいという意図の質問は、上司は「してほしい」と思っていて、部下は「しないほうがよい」と思っているケースがあります。
たとえば、提案資料を作る仕事を任せられたとして、前提となるクライアントの課題がズレている状態で完成させてしまうと、提案ギリギリでイチからやり直しになる可能性もあります。
上司側は「今回の提案を作る上で、クライアントが最も重視している課題はこの認識で合っていますか?」といった前提を確かめる質問を事前にしてもらい、そのようなリスクをなくしたいと考えますよね。
一方で部下は「資料を作っておいて」と言われたのだから、作り終えるまでは質問してはいけないのだ、と理解していることもあります。上司が忙しそうにしていたらなおさらかもしれません。
まずは、前提や基準に不安がある場合は、仕事を先に進める前に質問してほしい、と伝えましょう。
そのうえで、仕事を任せるときに一工夫することも意識できるとよさそうです。方針を自分の口から説明してもらい、理解度をある程度はかったうえで任せられれば、どの状態でチェックに回してもらうべきなのか、自分で進められそうかの判断がつくからです。
理由に納得したい
「この方針で進めるのはなぜなのか?」「この作業が必要な理由は何なのか?」など、根本的な部分を考えることは重要です。なぜならば、前提や現状を疑うことで、今の延長線上にはない大きな成果を生み出すことにつながる可能性があるからです。
たとえば、「大量生産をすることでコストを抑える」という前提を疑えば、「必要なときに必要なものを作ることで在庫管理コストを最小限に抑える」という新しいやり方に気付くことができるかもしれません。
また、仕事の進め方においても、なんとなく慣習で行っていた月に1回1時間の定例ミーティングを隔週30分のミーティングに変えたら、クイックに確認事項をクリアにすることができて仕事の進捗がはやくなった、みたいなこともありますよね。これは「なぜ月に1回、1時間のミーティングをしているのだろう?」と現状を疑った結果です。
このように、ものごとの理由を問うことは、大きな成果につながる第1歩となり得ます。
一方で、経験のある上司からしたら「なぜ必要なのか?なんて聞かずに、言われたことはとっととやればいいのに」と感じるかもしれません。
たしかに、世の中「やってみないと分からない」こともたくさんありますし、長く続いているものにはそれなりの理由があったりもしますよね。
まずは、理由への質問は成果を出すうえで大きな価値があることを伝えましょう。そのうえで、コストが高くないのであれば、納得できなくても一度やってみる柔軟さも大事にしたいということも伝えられるとよさそうです。
やり方や答えがわからない
やり方や答えがわからないケースは、まず「正解があるものなのか」を見極めてもらいましょう。
正解がないものに関しては、上司が意見を伝えることで思考が固定化し「やり方や答えを聞かなければ出たかもしれないアイディア」が出なくなる可能性があるため、一旦自分で考えるように伝えるとよさそうです。
逆に正解があるものに関しては、基本的には先人の知恵を借りたほうがよいケースが多いですが、その際「正解を導き出すのにかかる時間」を考慮しましょう。
自分で調べてすぐに回答にたどり着けるのであれば、上司・部下お互いの時間を節約するためにも自分で調べたほうがよさそうです。
一方で、たとえ回答に自力でたどり着けたとしても、上司に聞いたら5分で解決するものを何時間も延々と考え続けるのはもったいないですよね。
事前に上司と「10分調べて分からなかったら、分かっているところまで提示したうえで遠慮なく聞く」などの基準を設けることをおすすめします。
他者の視点がほしい
一般的に、認知的な多様性をもつことは、盲点を少なくし、よりよい決断へと導く可能性が高いため、他者の視点は積極的にもらいにいったほうがよいでしょう。
そもそも「人に頼る」というのは、自分ひとりの力の限界を正しく認知することでもあります。人間だれしも、ひとりの視点や出来ることには限界があるので、「部下だから他者の意見をもらったほうがよい」という話ではなく、経験が長いメンバーや上司の側も等しく意識すべきことだと思います。
まず部下に対しては、他者の視点は積極的にもらいにいこう、と伝えましょう。そのうえで、上司も「○○さん(部下)の意見を聞かせてほしいんだけど…」というように、他者の視点を積極的に聞きに行く姿勢を示せるとよいですね。
1つ注意したいのは、他人に意見をもらうこと=他人に決めてもらうこと(もしくは全員の意見の中間をとること)だと考えてしまいかねないことです。意見をもらったうえで、決断は自分で責任をもって行うことを意識しないと、上手くいかなかったときに「●●さんにこう言われたから」という気持ちが生まれてしまい、なかなか成長につながりません。
意見に振り回されてしまっていないか、自分で決断するということを避けていないか、上司は意識して見つつ、適宜アドバイスできるとよさそうです。
※アナグラムでは「挙手制(自分で担当したい仕事に挙手をする)」「逆ピラミッド(現場のメンバーが最終的な意思決定を行う)」といった制度を導入しており、周りの人に意見をもらったり質問することは推奨しつつ、決断は自分で行うということを徹底しています。仕事への臨場感を持ちやすかったり、うまくいかなかったときに立ち上がりやすいという意味で、うまく機能している制度です。
前に聞いた内容をもう一度聞きたい
知識というのを「知と知の織物である」と捉えるならば、まったく知らない分野のことを一度聞いて理解できるほうが稀でしょう。
だからこそ、上司は「それ前にも言ったよね?」とイライラするのではなく、「何度も質問するということは、それだけ難しいということだから、伝わったら価値のある内容なんだな」と捉えられるような心持ちが必要だと思います。一度質問に対してネガティブな反応をしてしまえば、ゆくゆく重要な質問事項が出てきたとしても、部下から質問しにくくなってしまう可能性があるからです。
まずは、質問する際に一度で覚えられないならばメモを取ろう、と伝えましょう。
そのうえで、どうしても忘れてしまったのならば、そう伝えてくれればOK、そもそも理解できていないのであれば、分かるまで聞いてほしいという旨を伝えるとよさそうです。
まとめ
ここまでの内容をまとめると、以下のように場合分けできます。
このように分けて考えると、「質問」というざっくりとした括りだと伝わりにくかった、求める振る舞いが明確にできるのではないでしょうか。
事前に基準を明確にすることで、部下側も「忙しそうだし質問しないほうがいいかな」「こんなこと聞いたら怒られるんじゃないか」など不要な不安を抱かずに、必要なタイミングで質問をすることができます。
上司側はもちろんこの基準に沿って、「早く質問してほしい」と伝えたことは真摯に答え、「これは10分調べてほしい」と伝えたのに調べていない場合は、その旨を指摘する必要があります。
よい問いは、部下自身の成長にも、チーム全体としての成果にも影響をもたらします。
認識のすれ違いをなくし、適切に質問が飛び交う環境を目指しましょう。