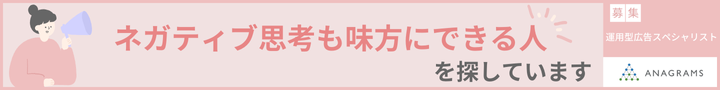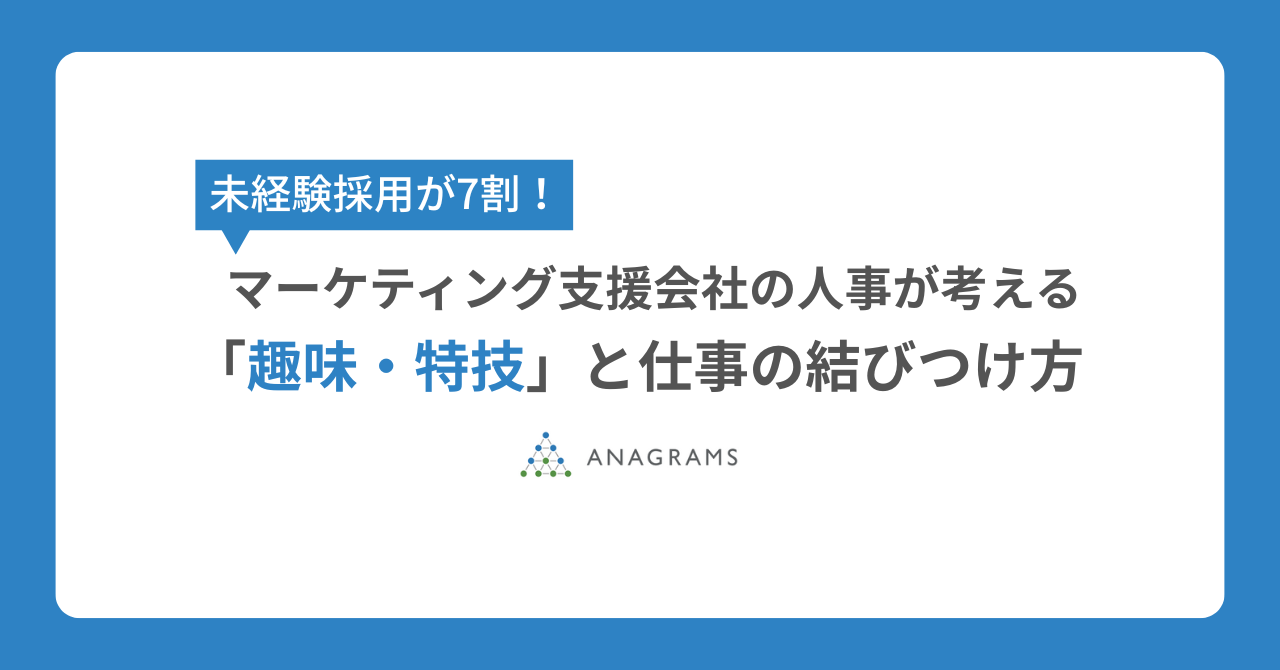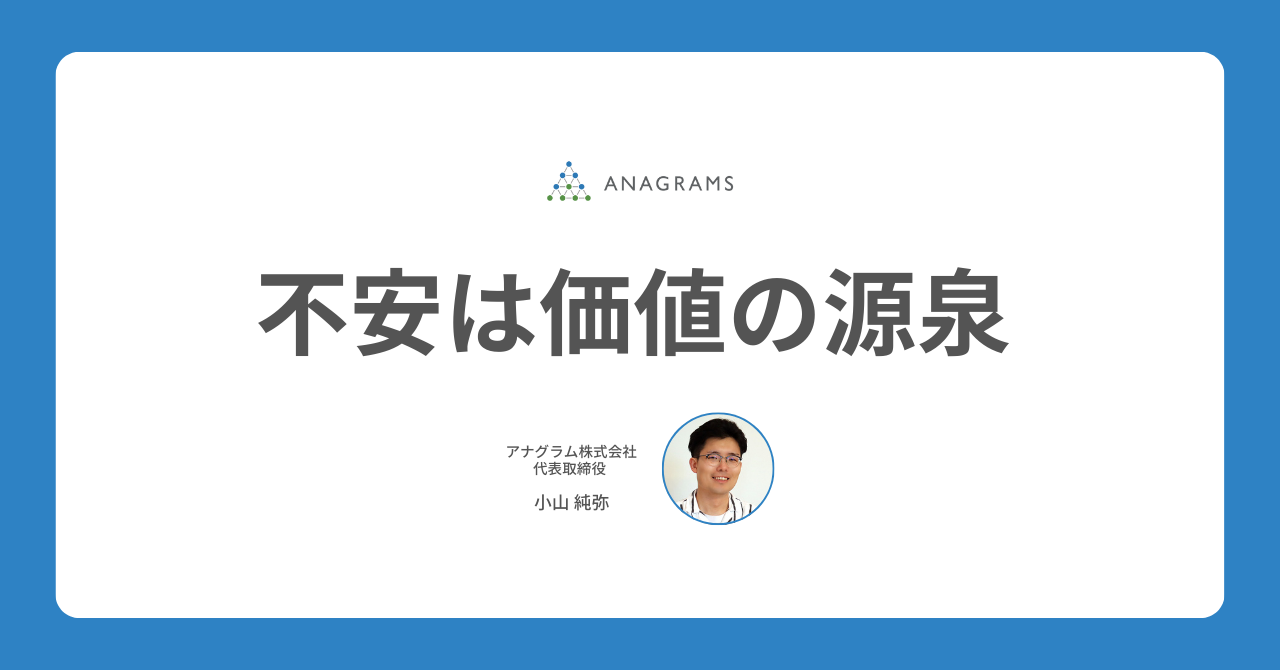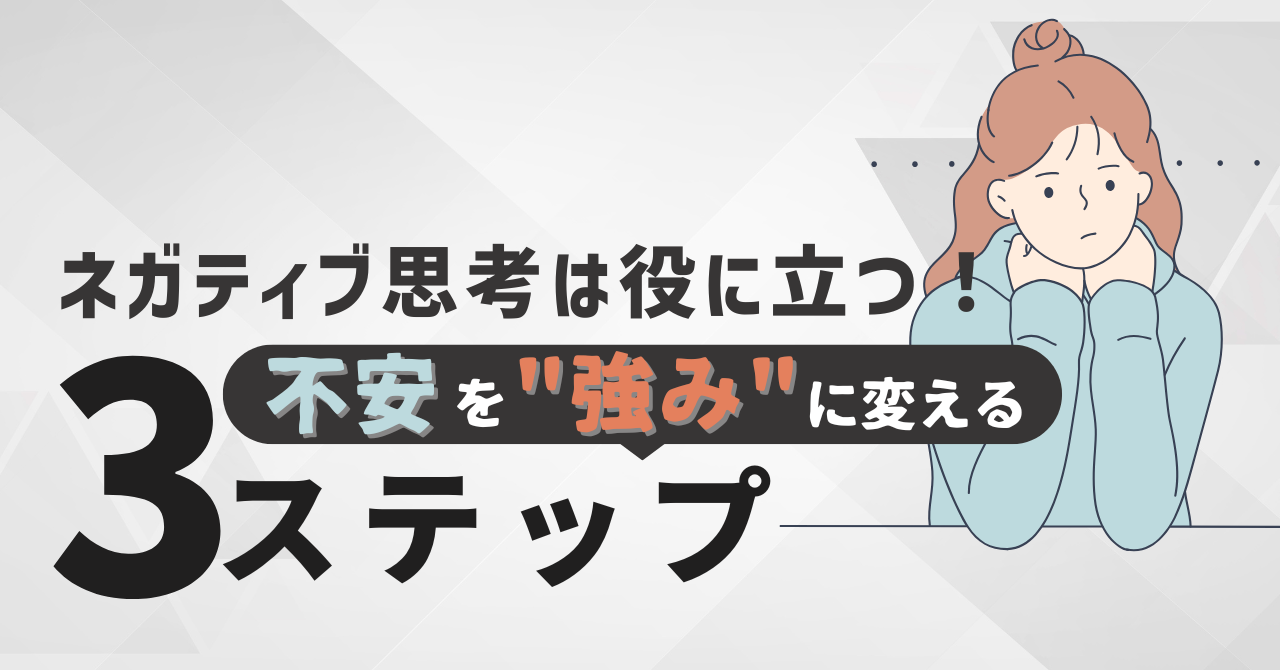
「あの発言は良くなかったな」
「うまくいかなかったらどうしよう」
一度そのような考えが浮かぶと、なかなか別の考えに切り替えられない。この記事を読んでくださっている方の中には、そんな人が多いのかなと思っています。かつては私もその一人でした。
ネガティブ思考とは、物事を悲観的、否定的、または消極的に捉える思考のことです。
以前、私は心理カウンセリングで「ネガティブな感情を抱くことを避けようとしていませんか?」と指摘されたことがあります。このとき私は『ネガティブ思考をなくしたい』と思い込んでいることを自覚し、それをやめることにしました。
自然と湧いてくる思考や感情そのものを「こう思っちゃいけない」と否定して、ネガティブ思考が連鎖している状態はとても息苦しいですよね。
しかし、実はネガティブ思考は悪いものではなく、むしろ仕事や生活に役立てることができます。今回は、せっかくネガティブ思考になるなら、自分の強みに変えてやりませんか!という話をします。


目次
ネガティブ思考は本当に悪いこと?
SNSや自己啓発本では「前向きでいよう」「ポジティブな言葉を使おう」といったメッセージがあふれています。そのため、ネガティブ思考の私たちは「良くないことだ」「やめないと」と思い込んでしまいがちです。しかし、「ネガティブ思考=悪」というのは誤解です。
人はネガティブな感情に直面すると、脳が「問題を解決しよう」と活性化する傾向があるという心理学の研究もあるほど、落ち込んだり不安になったりすることは、生き延びるための適応力として働くのです。
もちろん、ポジティブ思考にも多くのメリットがあります。しかし、無理にポジティブであろうとすると、かえってパフォーマンスが下がることも。実際、「常にポジティブでいるべき」という考えが、人を苦しめることもあります。
ネガティブ思考は決して悪いものではなく、上手く活用すれば仕事の成果を上げたり、人生を前に進める力になります。今回は、ネガティブ思考のメリットと、それを強みに変える具体的な方法をご紹介します。
ネガティブ思考がもたらす意外なメリット
ネガティブな思考は、自分を守ったり、より良い選択をするための役割があります。
例えば、
- 事前準備・リスク管理ができる
- 課題を解決に導ける
- 経験を活かし、改善できる
これらはすべて、仕事において重要な能力です。
例えば、「この施策がうまくいかなかったらどうしよう」と不安に思える人は、撤退条件を設定し、失敗時の対応策を事前に準備できるため、最悪の事態を想定してリスクを減らす行動が取れます。
また、「今週は売上が少なかったけれど大丈夫かな」と心配する人は、楽観する人よりも原因を調査し、改善策を考えることで、早めの対策が可能になります。
さらに、「Aさん、怒っていたかも…あの発言が良くなかったかな」と反省する人は、次から同じ失敗をしないように気をつけられ、改善を重ねながら成長していくのです。
ネガティブ思考を強みに変える3ステップ
ネガティブ思考を強みとして仕事や生活に活かすには、ちょっとした工夫が必要です。そこで、強みに変えるための3ステップを紹介します。
- ネガティブ思考を”客観視”する
- ネガティブ思考の”質”を変える
- ネガティブ思考は”行動”までをセットに
1.ネガティブ思考を”客観視”して「事実」と「思い込み」を分ける
思考は「そう考えているだけ」であり、必ずしも事実とは限りません。ネガティブ思考が悪い方向に働くのは、「思い込み」が原因のことが多いのです。
例えば、以下のような思考パターンがありませんか?
| パターン | 極端な例 |
|---|---|
| ネガティブフィルター | 「きっと社交辞令だろうな」 「運がよかっただけで実力じゃない」 →悪い側面は気にするが、良い側面には気づかない(気づこうとしない) |
| 認知の歪み(偏り) | 「満点とれなければ意味がない」 「ここでミスしたら人生終わり」 「私はいつも上手くできない」 「あの人は私を嫌っているにちがいない」 |
| 自己評価の歪み(自分の価値を不当に低く見積もる) | 「あの人はすごいのに、自分はダメだ」 「私はもっと努力しなければいけない人間だ」 |
私自身も、どれも身に覚えがあります。友人が同じことを言っていたら「そんなことないよ」と心から励ませるのに、自分のこととなると、言動のほんの一部の反省点ばかりに意識が向き、「自分はダメな人間だ」と極端な結論に飛躍してしまうことがあります。
ネガティブ思考が悪い方向に働くのは、事実とかけ離れた極端な解釈をしているときです。その思考に固執すると、自分も周りも幸せになれません。
ネガティブな考えが浮かんだときは、「もし友人が同じことを言っていたら、自分はどう答えるだろう?」と立ち止まって考えてみてください。そうすることで、不要なネガティブを減らすことにも繋がります。
2.ネガティブ思考を「リスク分析&対策」に変換し、”質”を変える
自分のネガティブ思考を客観視できたら、さらに分解し深堀っていきましょう。ネガティブな考えが浮かんだら、まず以下の3ステップで思考を整理し、思考の”質”を変えていきます。
- ネガティブ思考の中から「事実」だけ抜き出す
- 事実から「自分にできる行動」を考える
- ネガティブ思考自体をポジティブに解釈する
例えば、「私ってケアレスミスが多くて、仕事ができないな…」と思ったとしても、「ケアレスミスが多い=仕事ができない」とは限りません。自分を否定するような考えが浮かんでも、それをそのまま自分の価値と決めつけず、一度冷静になって事実を見つめてみましょう。
思考
- 「私ってケアレスミスが多くて、仕事ができないな…」
事実
- ケアレスミスの頻度はデータや具体的な指摘がないと判断できない
- 仕事の成果はミスの回数だけで決まるものではない
自分にできる行動
- 過去のミスの傾向を振り返り、実際の回数を把握する
- ミスを防ぐ工夫(チェックリストを作る・見直しの時間を増やす)を取り入れる
ポジティブ解釈
- ミスを気にしたからこそ、ミスを防ぐ方法を考えられた
このように思考を整理することで、単なる不安を建設的なアクションにつなげることができます。
もう1つ例をあげましょう。
私たちは、対人関係においてネガティブ思考に陥ることがよくあります。心理学者のアルフレッド・アドラーも「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と述べているほどです。
例えば、「Aさんの笑顔を見たことがない。もしかして私のことが嫌いなのかも…」と思ってしまうことがあるかもしれません。しかし、本当に嫌われているかどうかはAさんにしか分からず、単なる思い込みでショックを受けるのはもったいないことです。こうしたネガティブな考えが浮かんだときこそ、「事実」と「自分にできる行動」に目を向けることが大切です。
思考
- 「Aさんの笑顔を見たことがない。私のことが嫌いなのかも…」
事実
- Aさんが笑顔を見せない理由は他にも考えられる(仕事に集中している、もともと笑顔が少ない性格など)
- Aさんの気持ちは本人にしか分からない
自分にできる行動
- Aさんとの過去のやりとりを振り返り、事実ベースで関係性を考える
- Aさんに明るく接してみる、相手の態度が変わるか様子を見る
ポジティブ解釈
- 人の表情や声色をよく見て気づくから、改善に向けて行動できるんだ
ネガティブな思考が浮かんだときは、それを事実として決めつけるのではなく、「本当にそうなのか?」「なぜそう思ったのか?」と自問してみましょう。思考を分解することで、新たな気づきを得られるだけでなく、なぜネガティブな感情が生じたのかも明確になります。
さらに、状況を改善するための行動まで考えられたら、その時点でネガティブ思考は自分にとって決して悪いものではなくなっているはずです。
3.ネガティブ思考は”行動”までをセットにする
これまでの2つが実践できていれば、すでにネガティブ思考はあなたの味方になっています。せっかくなら、自分の強みとして活かせるよう、最後のステップまで挑戦してみましょう。
ネガティブな考えが浮かんだときは、現実を今より少しでも良くする「行動」をセットにする習慣をつけることが大切です。そうすることで、状況が実際に好転するだけでなく、ネガティブ思考を「あってよかった」と前向きに捉えられるようになります。
また、自分の思考パターンによって現実が良くなった経験を積むことで、自分自身や言動を肯定できるようになり、仕事や生活において再現性のある「勝ちパターン」を築くことにもつながります。
あなたがネガティブ思考だからこそ気づけることはたくさんあります。それは、現実をより良くするチャンスでもあります。
まとめ
ネガティブ思考は決して悪いものではありません。むしろ、仕事や生活をより良くするための武器にもなります。大切なのは、「ポジティブでなければならない」と無理をするのではなく、「ネガティブな気づきを成長のチャンスにする」ことです。
この記事を書こうと思ったきっかけは、ある人から「ネガティブだね」と言われたことでした(悪意のないツッコミです)。その言葉に引っかかりながらも、「ということは、ネガティブ思考の扱いに慣れているのでは?」とポジティブに解釈し、本記事を書くことにしました。まさに、ネガティブ思考の賜物です。
自分のネガティブ思考に悩んでいる方が、それを仕事や生活に役立てるきっかけになりますように。