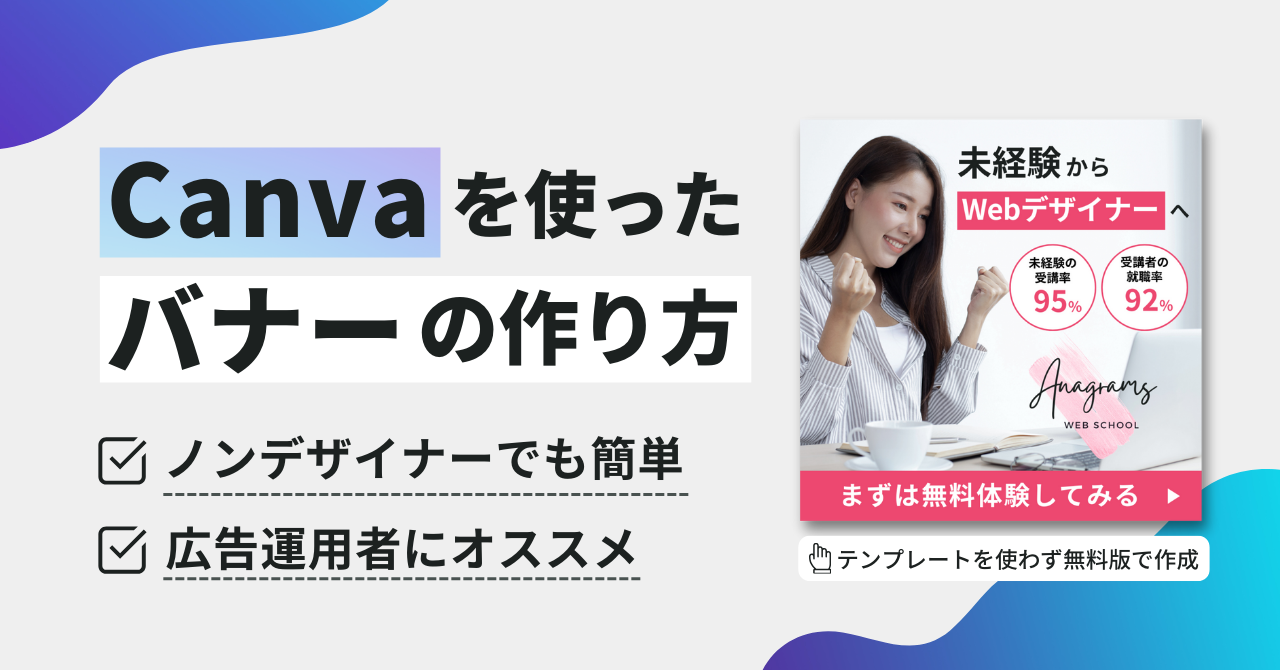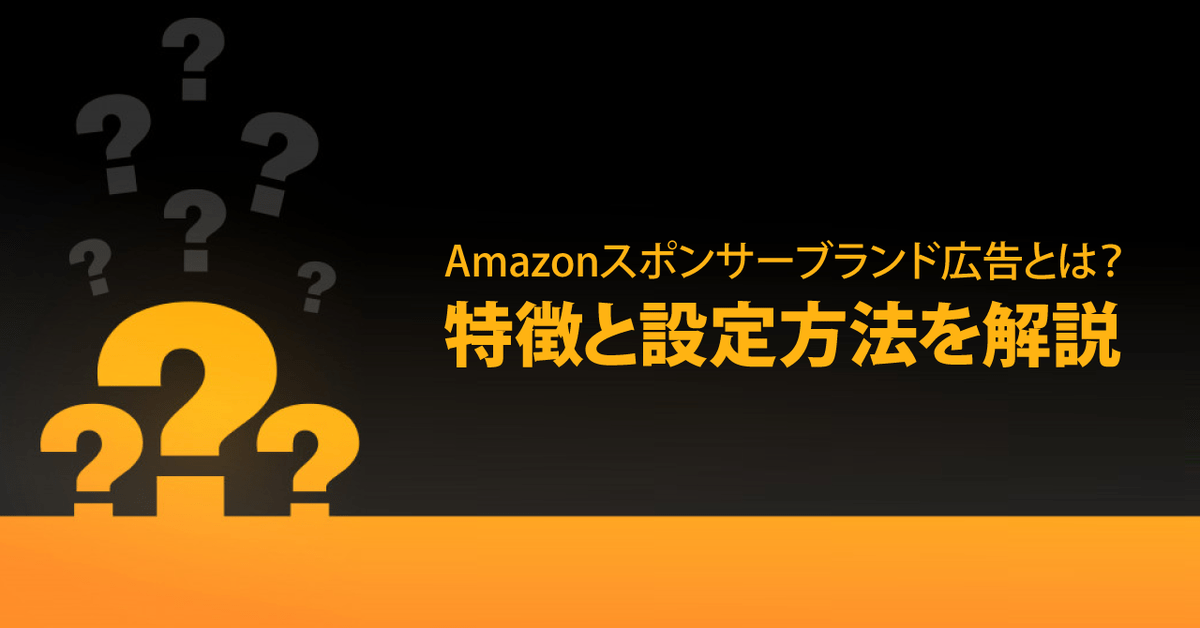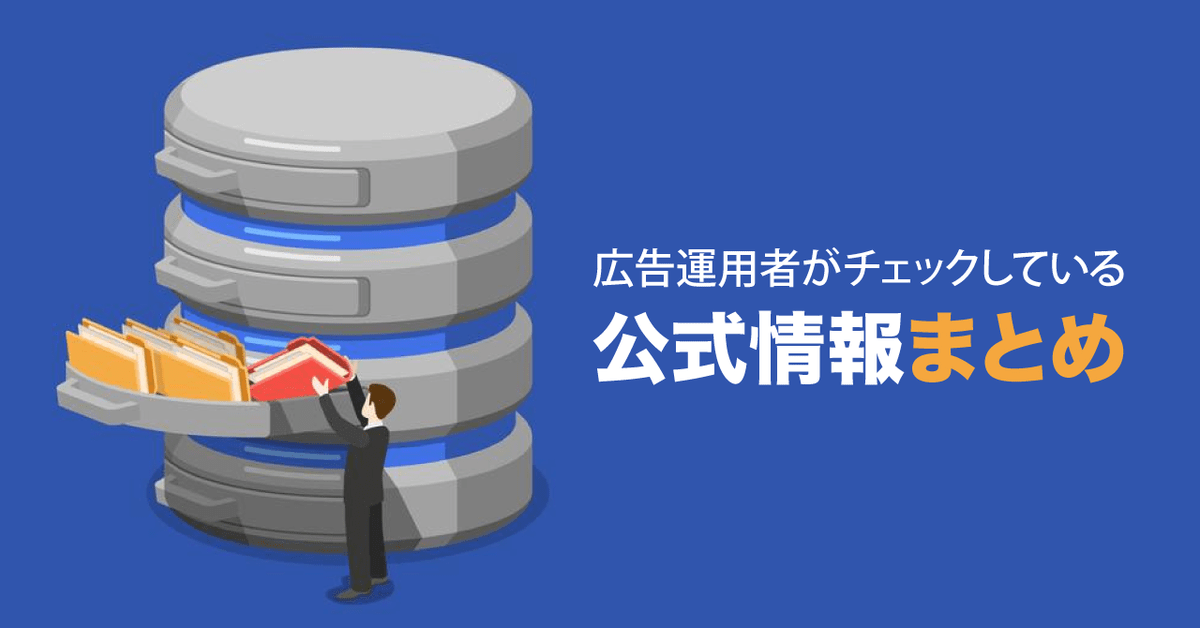Googleは2015年7月21日に、製造業や自社ブランド製品を販売するブランドメーカー(以下、メーカー)に向けてManufacturer Centerを公開したことを公式ブログで発表いたしました。
その原文訳(一部意訳)と筆者の補足など交えて内容をご紹介いたします。
以下は、Inside AdWordsの記事
"Introducing Manufacturer Center - a tool to help brand manufacturers provide authoritative product information to online shoppers"
http://adwords.blogspot.jp/2015/07/introducing-manufacturer-center-tool-to.html
を和訳したものになります。


Manufacturer Centerの紹介 - オンラインで買物をする買い物客に正しい製品情報を提供をするための支援ツール
Googleは商品や商品に関連する検索クエリに対して回答をしており、その数は全世界で月間100億回を超える規模です。故に、オンラインで買い物をする買い物客は、商品画像、商品説明、商品仕様の差異などの商品情報は、正確であり、リッチであり、一貫性を持っている事を期待しています。メーカーの商品情報はこのエクスペリエンス(体験)を買い物客に届けるために重要です。
今日、Google Manufacturer Centerをローンチしました:このツールはメーカーがgoogle.com、Google ショッピングやその他のGoogleサービスに渡り、買い物客へ正確な自社商品の情報を提供するのに役立ちます。買い物客の購入意思決定を促進するために、Manufacturer Centerに正確な商品データをアップロードすることでGoogle全体でメーカーの商品のリストを充実させます。
 Google全体でどのように表示されるかはManufacturer Centerに送信された商品データに影響されます。
Google全体でどのように表示されるかはManufacturer Centerに送信された商品データに影響されます。
メーカーは正確な商品情報を確実に買い物客に届けられるだけでなく、提供した商品データに対して高度な分析をすることも出来ます。例えば、とある製品が指定の期間内でどの程度Googleに表示されたか、買い物客が同じカテゴリに属する競合商品と比べて自社商品をどの程度クリックしてくれたかなどを知ることが出来ます。"Manufacturer Centerで得られるレポートによって、買い物客が自社ブランドとどのように関わったをかを把握することができるので、商品データを最適化してインプレッションのボリューム並びにエンゲージメントを高める事に役立ちます"と、ボッシュ電動工具(Bosch Power Tools)のデジタルディレクターであるSonesh Shahは話します。
 Manufacturer Centerのアナリティクスダッシュボードでは、パフォーマンス向上に役立つヒントを提供します。
Manufacturer Centerのアナリティクスダッシュボードでは、パフォーマンス向上に役立つヒントを提供します。
メーカーは商品情報の管理方法として、自社でManufacturer Centerに直接アップロードした商品情報を利用するか、承認されたGoogle ショッピングのパートナーの情報を利用するか選ぶことが可能です。ここで言うGoogle ショッピングのパートナーとは、商品データを整理してまとめて配信を行うSalsifyやShotfarmといった業界リーダーの企業を指します。
日本での対応は?
現時点では米国内のみが対象かつ招待制となっており、こちらの登録フォームから問い合わせる必要があります。
また、Manufacturer Centerのヘルプセンターも存在しますが、まだ日本語には未対応のようですので、Manufacturer Centerの日本対応を待ちましょう!
訳者の補足と考えられる今後の展望
これまでは、特にメーカーが製造する家電や消費財などの分野では、商品情報はMerchant(出店者側)の対応に依存しており、日本ではMerchantによって情報がまちまち、下手をすれば誤記述などによって誤った情報が記載されていることもしばしばでした。上記のリリースにもある通り、Manufacturer Centerの登場によって、メーカー側が正確な商品情報を直接提供できるようになるので、買い物客を悩ませる心配はなくなります。また、同じ商品カテゴリで競合する競合商品とのベンチマークデータなどもManufacturer Centerのレポートによって見られるようになるので、メーカー側のマーケターにも有意義ですね。
そのほか訳者が考えるメリットやデメリットは以下だと考えています(一部上記と重複しますが…)。
メリット
- メーカーが正確な商品情報を提供できる
- 同じカテゴリで競合する商品とGoogle上での影響度をベンチマークできる
- Merchant Centerのデータが紐づけられるようになる
メーカーが正確な標品情報を提供できる
提供できる商品情報は下記に渡ります。
- ID(フィード上で商品を識別するもの)
- 製品のブランド名
- 商品のタイトル(正式な商品名である必要はなし)
- GTIN、MPN(日本ではJANコード及びメーカー製品番号)
- データ公開日
- 商品発売日
- 希望小売価格
- 製品の正式名称
- 製品ライン(サブブランド名など)
- googleプロダクトカテゴリ
- メーカーの定めるプロダクトカテゴリ
この中で特筆すべきは「7.希望小売価格」でしょうか、ここを定めることでメーカー希望小売価格に対してMerchantはどのくらい安く購入できるか、例えば「20%OFF」みたいな表示ができるようになることを示唆してます。日本ではメーカー希望小売価格を設定しないオープン価格で提供される商品もあるので、すべての商品でそのような表示がされることはないのでしょうが…。
同じカテゴリで競合する商品とGoogle上での影響度をベンチマークできる
こちらは先にも述べましたが、アナリティクスダッシュボード機能によって分析をしたり、最適化のためのヒントを得ることができるので、メーカ側のマーケターにも有益な情報が得られそうですね。
Merchant Centerのデータが紐づけられるようになる
メーカー側からGTIN(日本で言うJANコードやISBN)が提供されるので、同じGTINを持つ商品は共通の商品として認識できるようになりますので、より一般的な検索クエリで表示される商品では特定のメーカばかりの物に偏ることなく、同じカテゴリで競合する別の商品が複数種類表示されるようになるのではないかと考えられます。商品名ではバリエーションごとに集約されるなども考えられますね。
デメリット
- Merchant側の商品フィードに"正確なGTIN"の記述が必要
- 日本での実装が現時点では未定
Merchant側の商品フィードに"正確なGTIN"の記述が必要
メリットでも触れましたが、前述の理由からMerchant側にも正確なGTINの記述が求められる事になりそうです。2015年9月15日より、一部の指定ブランドメーカーの商品を掲載する場合はGTINの入力が必須になります。これは訳者の体感値ですが、正確なGTINを入力せずとも商品フィードの審査に通ってしまっている現状も見受けられるので、このあたりのルールがどのように変わっていくかは注視する必要がありますね。いずれにしても、必要な情報は正確に詰め込めということに変わりはありません。
日本での実装が現時点では未定
こちらはそのままの意味合いになりますが、Google ショッピングの商品フィードにおけるポリシーが、短いスパンで大きな改定を行っている現状から察するに、想像よりも早いタイミングでManufacturer Centerは利用可能になってくるのではないでしょうか。
ちなみに、Manufacturer CenterアカウントはGoogle アカウントに紐付ける形で提供されるのですが、当該のGoogle アカウントで既にMerchant Centerを利用している場合は同じアカウントでManufacturer Centerを利用することが出来ないようですので、自社ブランド商品の製造と販売を行っているメーカーの場合は、それぞれ別のアカウントをもつ必要があるようです。
※09月12日(土)、「リスティング広告運用者の為のスキルアップセミナー Vol.2」の中で、データフィードについてお話する機会があるので、興味がある方はこちらからどうぞ!