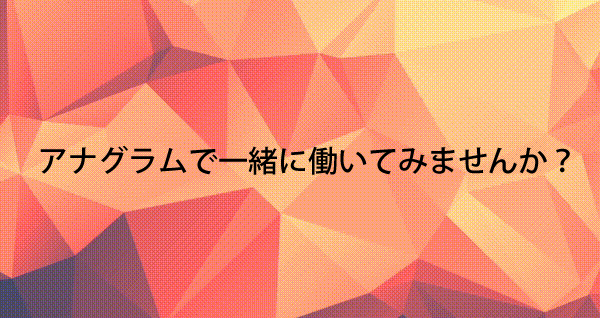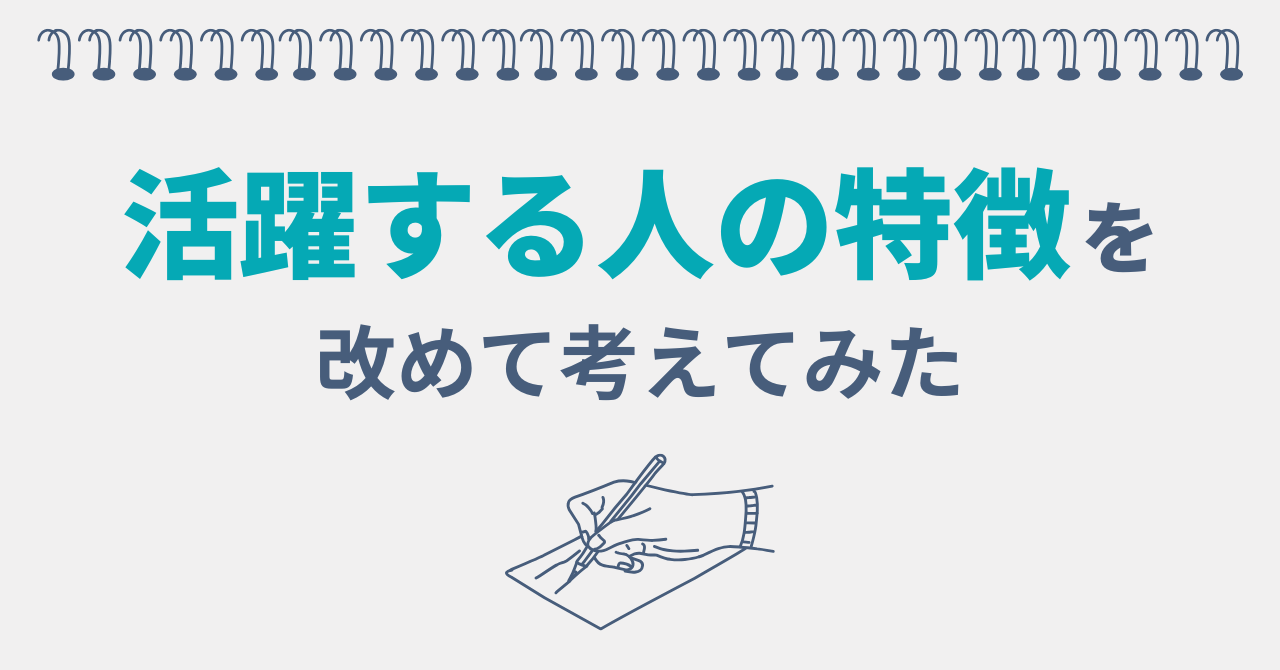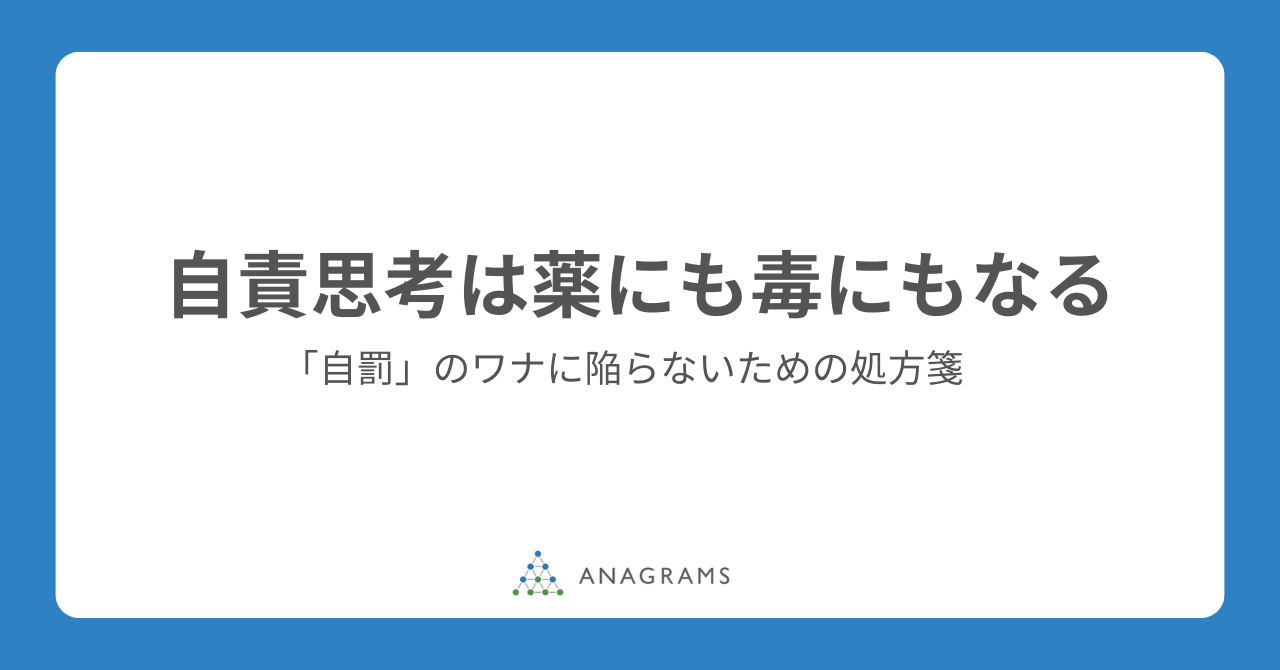
責任を自分に求める自責思考は、一般的に他責思考よりも良いものとして語られます。
たしかに誰かのせいにして「自分は悪くない」と開き直ってばかりでは成長するのは難しいでしょう。仮に本当に他の誰かが責任を負うのが妥当な場面だったとしても、関係者である以上は自分にも改善できる点があるかもしれません。
自責思考は、自らの成長を通して現状をより良くしていくためには欠かせない、現実との向き合い方といえます。
一見、その正しさに疑いがないように思える「自責思考」。ですがだからこそ、ワナの存在も認識したうえで、取り扱いに注意する必要があるのではないでしょうか?
いつどんなときでも「自分に原因がある」と捉えるのは、つらいようでいて実はラクです。なぜなら本来複雑なはずの原因を単純化することで、手っ取り早く向き合った感覚が得られてしまいやすいからですが、その姿勢はときに本当の問題から目を逸らすことにつながります。これが自責思考のワナです。
正しく状況を見極められなければ、問題の解決も難しいでしょう。改善に向かわず停滞する状態が続けば、そのうち無力感に打ちひしがれて病んでしまうかもしれませんよね。
すべてのものは毒であり、毒でないものはない。用量だけが毒でないことを決める。
16世紀ヨーロッパの医師であり科学者のパラケルススの言葉です。
どんなに優れた薬でも、ひとたび用法用量を間違えれば逆効果になる。つまり問題を解決する手段である「自責思考」も、薬として役立てるためには取り扱いに注意が必要なのです。
この記事では、陥りやすい「自罰」のワナを克服しつつ、その対処法―視点の方向性、責任のバランス―を知り、自責思考を味方につけて課題に向き合うための処方箋を提案します。


自責思考が毒に変わる「自罰思考」
突然ですが、もしあなたがうっかり擦り傷を負ったとして、どんな対処をしますか?
薬を使う、自然に治るのを待つ、次回は怪我をしないように同じ行動は避ける、などいくつか選択肢が頭に浮かぶかもしれません。ですがどんなに慌てふためいたとしても、傷口にわざわざ塩や毒を塗り込むことはないはずです。そんなことをしたら、傷が治るまでに余計な時間がかかってしまいますよね。
怪我の話であれば、これは言うまでもなく当たり前のことに思えます。では「怪我」を「仕事上やプライベートでのあれこれ」に置き換えてみるとどうでしょうか?
- ミスの再発防止策を考える(薬)より先に、自分を責め続けてしまう(毒)
- 家事の外注や分担を検討(薬)せずに、1人でこなそうとして行き詰まる(毒)
- 自身の成長を長い時間軸で捉えず(薬)短期で評価し落ち込んでしまう(毒)
当初は建設的な態度で問題解決に臨んでいたつもりが、気づけば思考の迷路にはまり、思い込みでがんじがらめになって、最終的に意図と反して事態を悪化させてしまった…なんて苦い思い出に覚えがある方もいるのではないでしょうか?筆者にはあります。
問題を解決することよりも、まるで罰を与えるかのように自分を責めることが優先されたとき、自責思考は毒になってしまうのです。
個人や組織をよりよい状態に導くために、「自ら責を負い」問題に対処すること。自責思考は本来そのための手段のはずです。ところが「自らを罰する」ことに目的がすり替わってしまえば、何も生まないどころか、疲弊だけをもたらす逆効果になりかねません。自分に責任を求めることと、自分を罰することは、似て非なるものなのです。
自罰思考に陥らないための考え方
ですが実は、自責思考の最も根深い”ワナ”は、自分を罰するあまり潰れてしまうこと、の他にあります。それは「本当のボトルネックに蓋をしてしまうこと」です。
いつどんな状況かにかかわらず常に「責任は自分にある」と捉える姿勢は、一見すると勇敢で誠実に思えるかもしれません。しかし自罰に陥って「私の能力が足りないのがダメなんだ」をすべての解にしてしまったら、現状を改善するための建設的な手だてに辿り着く前に、思考が止まってしまいますよね。
であれば有効な自責思考とは何なのか。筆者は「建設的かつ具体的なアクションを導いてはじめて成立するもの」だと考えます。
薬としての効き目を最大化するためには、目の前の課題を半ば思考停止ですべて引き受けるのではなく、自らが対処できる部分とできない部分を明らかにする必要があります。その上で、一方では力を尽くしつつ、他方では必要に応じて潔く諦めて進むのです。
ここからは、気づかないうちにハマりがちな2つのワナと、その対処法を見ていきます。
過去を責めずに、未来を攻める
視点が“過去”に囚われる—これが、自責思考に潜む最初のワナです。ここから抜け出すヒントは「原因」と「対処」を切り分ける視点にあると考えます。
”自分原因論”という考え方を耳にしたことはあるでしょうか?読んで字のごとく、すべてのことは自分が原因、つまり「今目の前で起きていることはすべて過去の自分の選択の結果」と受け止めるスタンスのことです。
「自分(が)原因(と考える)論(理)」という言葉は、その組み合わせが発する強いメッセージ性ゆえに、どうしても人の目線や思考を「原因」つまり「過去の自分」に向かわせがちです。一方で本来この言葉が”自ら責任を持つべき対象”として強調したいのは、むしろ「未来への対処」のほうではないでしょうか。
そこで役立つのが、「原因」と「対処」を分けて考えるという視点です。この考え方は、ネガティブな出来事に限らず、さまざまな場面に応用できます。
- 原因×対処
- 自分×自分
- 先週休んだ分の遅れ(自分の原因)を、今週取り戻した(自分の対処)
- 自分×他者
- 不注意によるミス(自分の原因)を、上長にカバーしてもらった(他者の対処)
- 他者×自分
- クライアントの社内稟議の遅れ(他者の原因)を受けて、進行スケジュールを調整した(自分の対処)
- 他者×他者①(本人の対処)
- 部下がプレゼン資料で行き詰まった(他者の原因)が、自分は最低限の助言にとどめ、本人がやりきった(他者の対処)
- 他者×他者②(第三者の対処)
- チームメンバーが新しいツールの使い方に戸惑っていた(他者の原因)ので、詳しい同僚がフォローしてくれた(別の他者の対処)
- 自分×自分
たとえ自分に非がない出来事であっても、対応や再発防止を自分が担わなければならない場面は少なくありませんし、逆に自分に原因があったとしても、対処を他者に委ねたほうがよい場面もあります。
人が自責思考のワナに陥るときというのは、往々にして”もう変えることのできない過去”にだけ目が向いているものです。
大切なのは、自分の力が及ばない「原因」を問うより、いまの自分が手を伸ばせる「対処」に集中すること。人を健やかに育む自責思考に必要なのは「過去の自分に何が欠けていたか」よりも、「未来の自分に何ができるか」を考えることではないでしょうか。
境界線を攻めて、半分手放す
未来に目を向けたら、次に見直したいのが「責任のバランス」です。2つ目のワナは、「ボトルネックの100%が自分にある」と錯覚してしまうこと。グラデーションで捉えずにいると、あらゆる問題を“自分の責任”フォルダに自動保存することになり、パンクしてしまいます。
そんなときはまずは「自分が責任を取るべき範囲と、そうでない範囲を丁寧に仕分け直すこと」から始めましょう。境界線を引いたら、自分の範囲以外は潔く手放す。ときに「誰かに迷惑をかけたくない」もしくは「他責に逃げたくない」といった想いが足を引っ張るかもしれませんが、他責思考と「境界をはっきりさせて自分の範囲に集中すること」は大きく異なります。
それでもハードルを感じる場合は、強制的に責任の比率を“6対4”や“5対5”などに仮置きしてみるのも一つの手です。
- 身近な誰かの不機嫌に巻き込まれた場合(自分:相手=4:6)
- 万が一自分の言動に引き金があったとしても、その感情の処理は相手の課題と捉えられるので、“少なくとも6は相手の責任”と設定することで、必要以上に責任を感じずに済む
- 他者に依頼した仕事の進捗が芳しくないとき(自分:相手=5:5)
- 依頼の仕方やサポート体制など、半分は自分にも責任があるかもしれないので、“5対5”で捉え直すことで、冷静に改善のヒントを探せる
- 自分がケアレスミスをしたら(自分:相手=6:4)
- 原因が明らかに自分にあっても、“残りの4は仕組みや環境にも原因があるのではないか”と捉えることで、過剰な自責(自罰)を避けつつ再発防止できる
こうして線引きを行えば、自分の責任範囲に集中しやすくなるのはもちろん、信頼感を持って周囲を頼ることに役立ち、過度な背負い込みも防ぎやすくなります。
不機嫌の例のように他者の責任の比率が高い場合はなおさら、むやみに受け取ることを控えることで、相手をしかるべき自責に導けるかもしれません。適切に自分の負担感を減らそうとすることは、他者の課題解決や成長の機会を奪わないことにもつながるのです。
ここで紹介した境界線を引くという考え方は、突き放すことでも、冷徹になることでもありません。むしろ、線を引くことで責任の輪郭が明確になり、自分が引き受けるべきことと、他者に任せるべきことのバランスが見えてきます。そうしてはじめて、各々が本来向き合うべき課題に集中しやすくなるのです。
大切なのは、罰することではなく課題に向き合うこと
この記事では自責思考を良薬として機能させるちょうどよい距離感を探ってきました。一見すると健全に見える「自責思考」が、いつの間にか「自罰思考」として毒をもたらすメカニズムは、まるで自ら免疫を下げて風邪を引いてしまうかのようです。
冒頭では”自責思考”を”他責思考”と対比しました。けれど正反対に見えて、どちらも“思考停止”によって改善から遠ざかってしまう点では、実は同じだともいえます。また、自分に厳しすぎる人は、ときに他者にもそのまなざしを向けてしまうことがあるのではないでしょうか。本当の意味で他人にやさしくなれる人は、まず自分のことを罰さず正しく育てられる人なのかもしれません。
アナグラムで大切にしている考え方に「人を責めずに仕組みを責める」があります。攻めるべきは「自分の動かし方」や「身を置く環境」などを含めた広い意味での”仕組み”です。他者と同様に自分自身も”人”であることを忘れてはいけませんよね。これに気が付く前の筆者は危うく自責思考の化け物になるところでした。”人”の道を踏み外さなくてよかったです。
受け手の準備が整うまで咀嚼できないのは、どんな学びにもいえることでしょう。きっとこの記事の内容も、よくて少し気がまぎれるくらいにしかならないかもしれません。
誰かがくれた希望も、ときに「あえて」踏みにじってみないと、本当に自分の手触りにはならないことがあります。 糧になる学びは、経験から自分の言葉で拾い直したものだけのようにも思えます。
ですがどうか、(過去の筆者がそうだったように)自分を律するつもりで意図に反して問題を見る目を曇らせてしまう、そんな“形だけの自責思考”で終わらせてほしくないのです。ここまでに紹介した考え方は、そのための"攻める矛先を操る技術”です。責任を“放棄する”ためのものではなく、自分が引き受けるべき責任に”ちょうどよく”応えるための視点なのです。
この記事が、自責思考に食いつぶされそうになっている誰かに届くことを願って。用法用量を守って、健やかな自責思考ライフを!