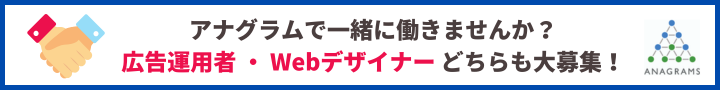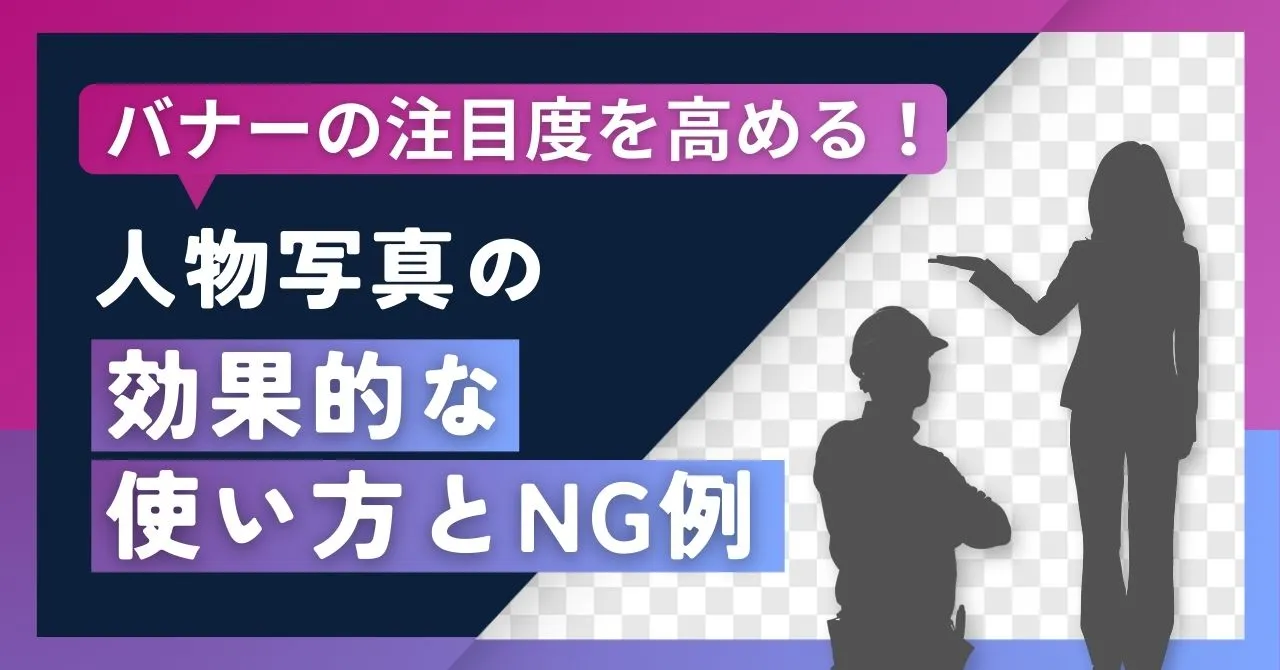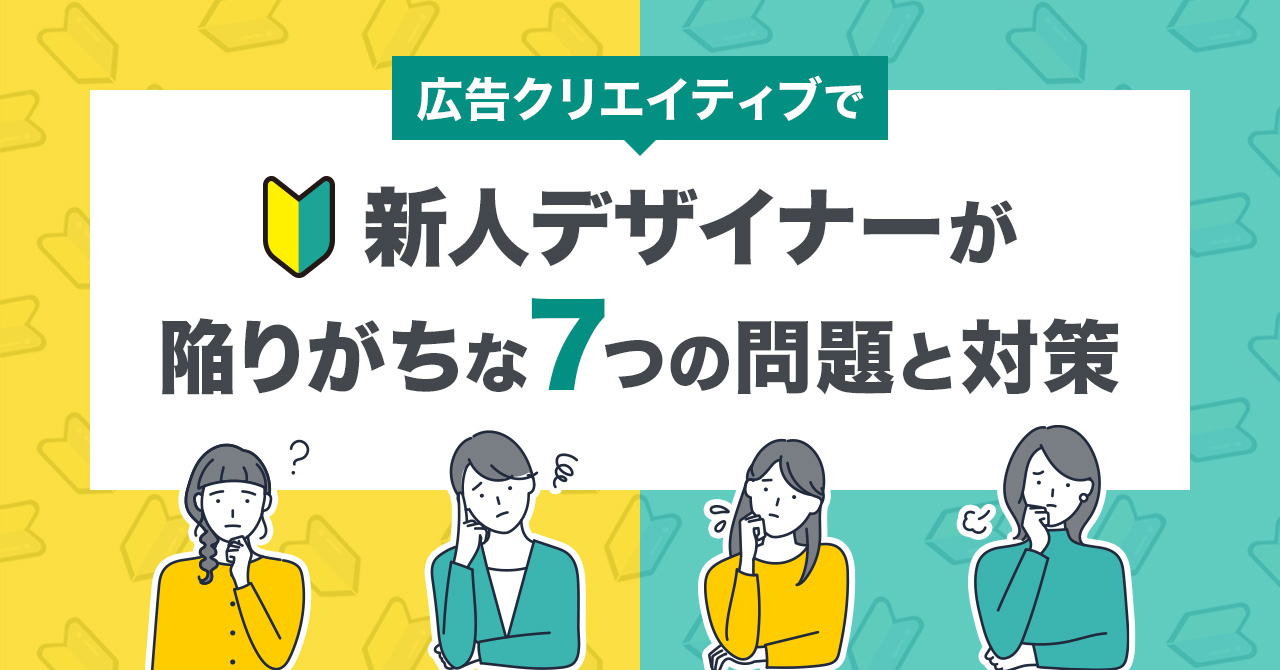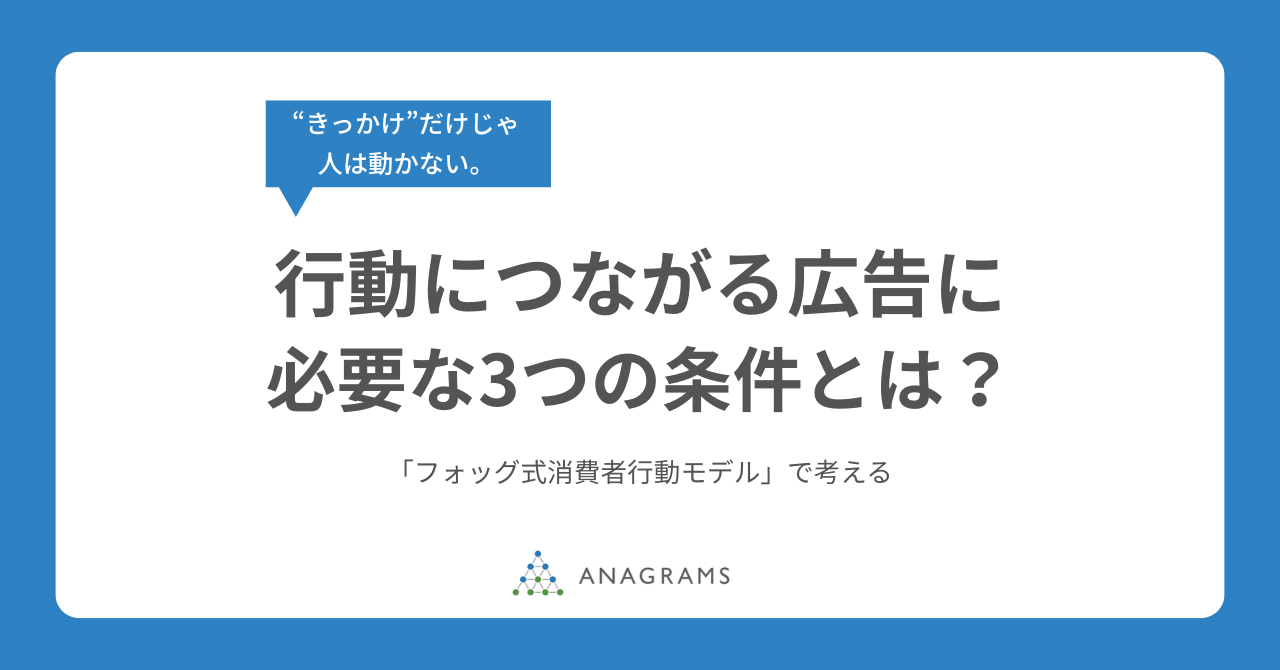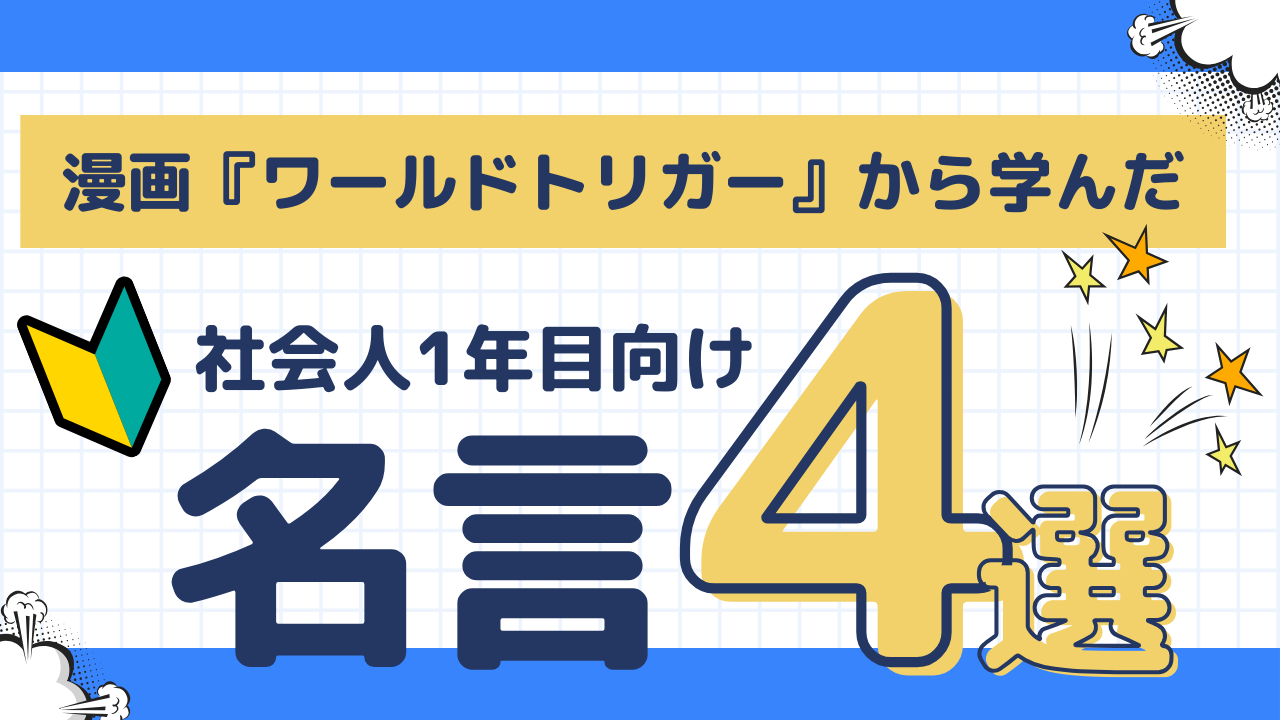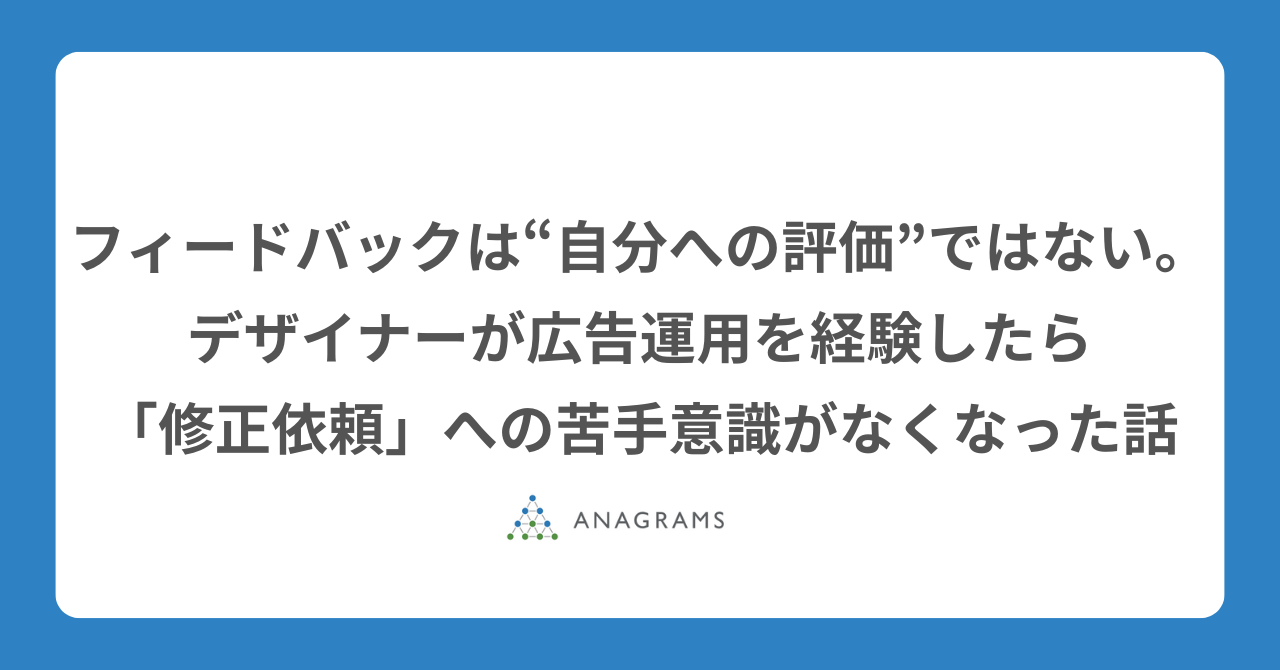
デザイナーとしてクライアントと向き合う中で、こんな風に感じたことはありませんか?
「デザインへの修正依頼や質問が来ると、自分を否定されているような気がして落ち込んでしまう」
私自身も、かつては同じ悩みを抱えていました。「いいものを作りたい」という一心でデザインに向き合っているのに、フィードバックをいただくたびに、自分の力不足を感じて自信をなくし、視野が狭くなってしまう時期がありました。
しかし、“広告運用”という専門外の領域に一歩踏み出した経験が、私のフィードバックに対する考え方を180度変えてくれたのです。
この記事では、フィードバックの受け止め方に課題を感じていた私が、広告運用を通じてどのように視点を変えていったのか、そこからどのようにクライアントへの向き合い方が変わったのかをお伝えします。


目次
フィードバックを「自分へのダメ出し」だと思い込んでいた
以前の私は、クライアントからのフィードバックを自分へのダメ出しのように感じていました。
例えば、構成案を事前に共有し、方向性の合意を得てから時間をかけて仕上げたデザインに、土台から見直すようなご意見をいただく。また、自分では「これだ!」と自信のあったデザインでも、「もっとこうした方がいいのでは?」と、フィードバックを受けて修正することも。
今思えば、いただいたご意見をそのまま反映することが、必ずしも成果に直結するわけではなかったのですが、当時は「どうして一回でクライアントの期待に応えられないんだろう」と、もどかしさを感じていました。
そんな時、上司から「自分もサポートするから、広告運用をやってみないか?」と声をかけられました。
当時の自分は、専門領域であるデザインですら自信をなくしている状態。そんな中で「数値管理や媒体設定、入札調整といった大変そうな広告運用なんて、自分にできるのか?」「クライアントの期待に応えられるのか?」と、不安な気持ちはありました。
それでも、「成長できる機会かもしれない!」と思い、挑戦することにしました。
広告運用を通じて気づいた2つのこと
広告運用という挑戦は、正直プレッシャーの連続でした。しかし、数字と向き合い、プロジェクト全体に責任を持つ経験は、私に2つの大きな気づきを与えてくれました。
デザインは成果を出すための「手段」のひとつにすぎない
これまでは広告運用者と連携し、デザインの企画制作やクライアントへの提案を行ってきました。しかし、デザインの企画制作はもちろん、配信設計全体の提案、広告クリエイティブの入稿、日々の入札調整やABテストまで、そのすべてを一人で担当しました。
特にクリエイティブはクライアントからほとんどを一任いただいていたため、自分の判断が成果に直結するという責任を、これまでよりも強く意識するようになりました。
特に責任を強く感じたのは、定例会の準備でした。
自分で予算やターゲティングを決めて入稿した広告が、「どんな人に届き、どう見られているのか」をデータから読み解き、次のアクションを自分の言葉で提案する。仮説と違う結果が出れば、その要因を考察し、次の一手を説明する。
最初は管理画面の数値をどう解釈していいか分からず、上司にアドバイスをもらいながら何度も資料を作り直しました。
その経験の中で気づいたのは、「デザインは成果を出すための手段のひとつにすぎない」ということでした。
広告の成果は、デザインだけでなく、ターゲティング、配信先、入札設定など様々な要素によって決まります。例えば、同じクリエイティブでも、ターゲティングや入札を変えるだけで成果が大きく変わることもありました。
この経験から、デザインという一つの手段に固執するのではなく、より広い視野で「どうすればプロジェクト全体の成果に貢献できるか」を考えられるようになったのです。
クライアントは「評価者」ではなく「パートナー」だった
初めて広告運用者として話す定例会では、とても緊張していました。
自分が新しく提案したクリエイティブよりも、上司が作成した既存のクリエイティブの方が好調だったため、厳しいフィードバックが来るのではないかと身構えていました。
しかし、実際のクライアントの反応は私の予想とは全く違いました。
「なぜこのバナーの方が成果が良いのでしょうか?」
「どういったデザインが獲得に繋がりやすいのか、もう少し詳しく傾向を教えてください」
といった、一緒に問題解決をしようとする質問が中心だったのです。私はデータから読み取れる仮説を伝え、クライアントと議論を深めていきました。
そうしたやり取りを通じてクライアントの成果への熱意に触れたことで、共通の目標に向かって伴走しているような感覚が芽生えました。その結果、これまで否定的に捉えていた質問も、「改善のヒント」として前向きに受け止められるようになったのです。
そこから、施策を繰り返す中で、上司の経験に自分の視点を加える形で改善を積み重ね、以前よりも高い成果を出すことができました。「引き続きお願いしたい」と言っていただけたときは、大きな達成感を感じました。
フィードバックが“成果を生むコミュニケーション”に変わった
広告運用を経験して実感したのは、クライアントからのフィードバックは「デザインの優劣」を問うものではなく、「成果を出すためのコミュニケーション」だということです。
これは、アナグラムの社内でも大切にされている「君は君の作ったアカウントではない」という考え方にも通じるものでした。
指摘する側は決してあなた自身を否定しているのではないのです。より成果を確度の高いものへと補正しようとしているだけであって、多くの場合は建設的な議論を望んでいます。その意識を忘れないで欲しいのです。
引用元:
この考え方が腑に落ちたことで、フィードバックを「自分を否定するもの」ではなく、「成果を高めるための対話」として受け止められるようになったのです。
以前は、フィードバックへの苦手意識が強く「ここは違うんじゃないか」と思う箇所でも、指摘をそのまま受け入れて修正し、なぜ自分がそう判断したのかを整理しないまま進めてしまうこともありました。
しかし今では、クライアントの指摘に対し、もし自分の考えと異なれば、デザインの意図や修正による懸念点を伝えて議論を深める。もし意図が掴めなければ、安易に修正するのではなく、まず対話を通してその背景を理解するようにしています。
このように、常に「どうすれば成果を出せるか」を起点として、「それなら、こうするのはどうでしょう?」と主体的に提案できるようになったのです。
クライアントと同じゴールを見据えることから始めよう
広告運用という新しい視点を得たことで、私はデザインの価値をより広く、深く捉えられるようになりました。そして何より、クライアントとのコミュニケーションが、ずっと前向きで実りあるものに変わったのです。
もし、かつての私のようにフィードバックが苦手だと感じるデザイナーの方がいれば、まずは「クライアントと共通の目標」を意識することから始めてみてください。
フィードバックを同じゴールを目指すパートナーからの「より良くするためのヒント」だと捉えるだけで、プロジェクトを前に進めるための建設的な対話に変わるはずです。
そして、今回の経験を通して私が強く実感したのが、「専門外の挑戦こそが、自分の専門性を深める」ということでした。
もしあなたの前にも新しい領域に挑戦する機会があれば、ぜひ一歩踏み出してみてください。きっと、それがあなたの専門性をより一層磨くきっかけになるはずです。