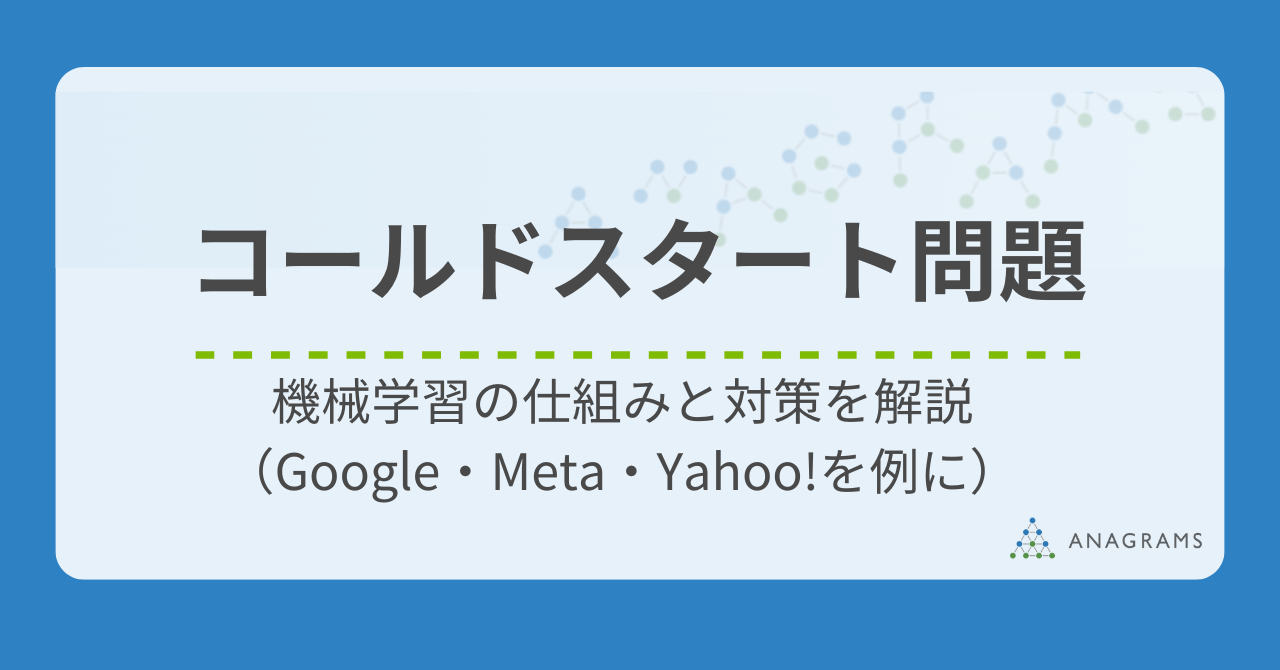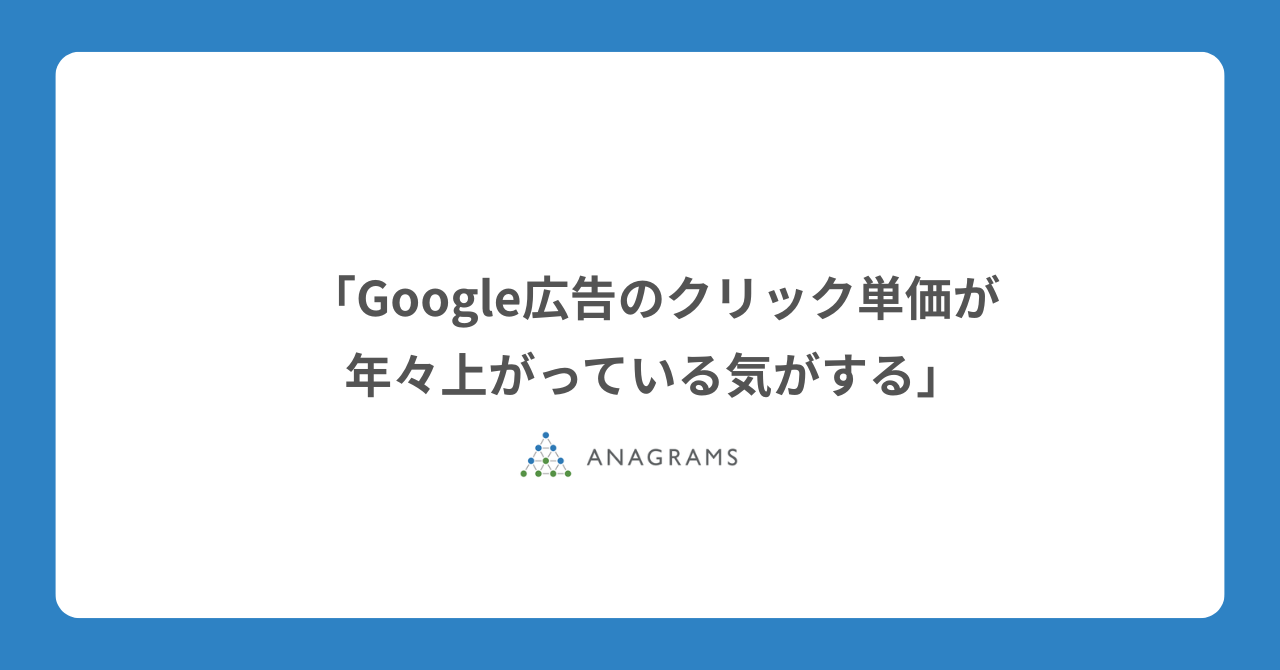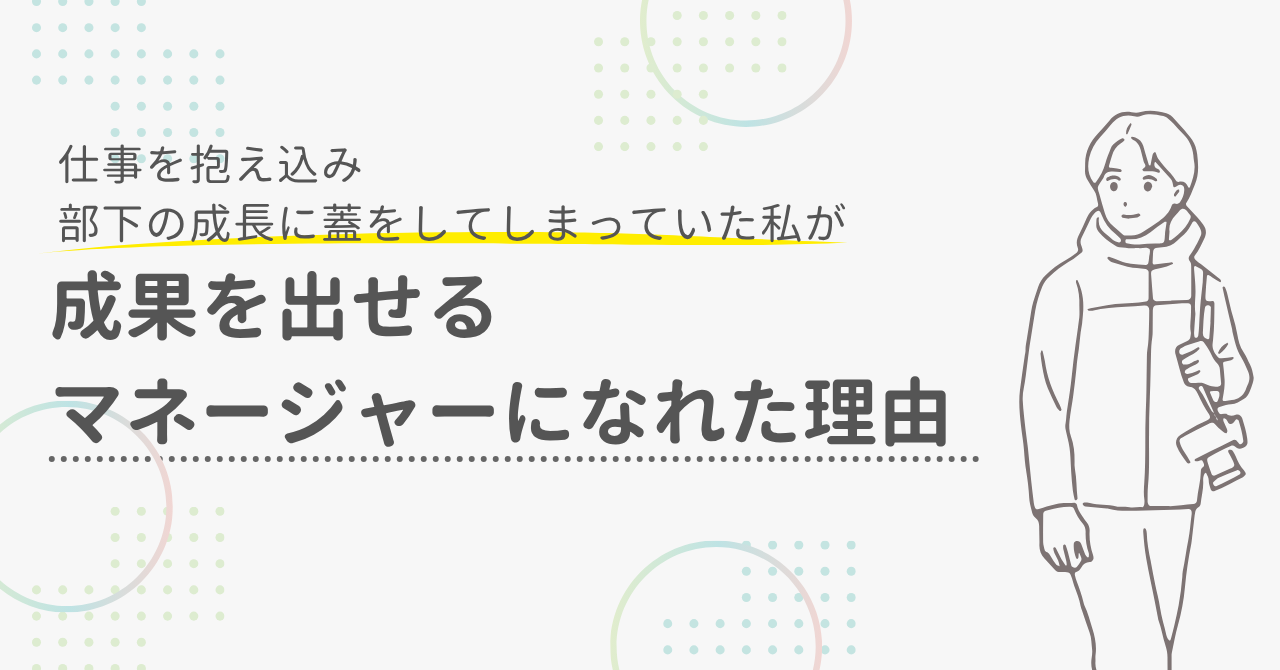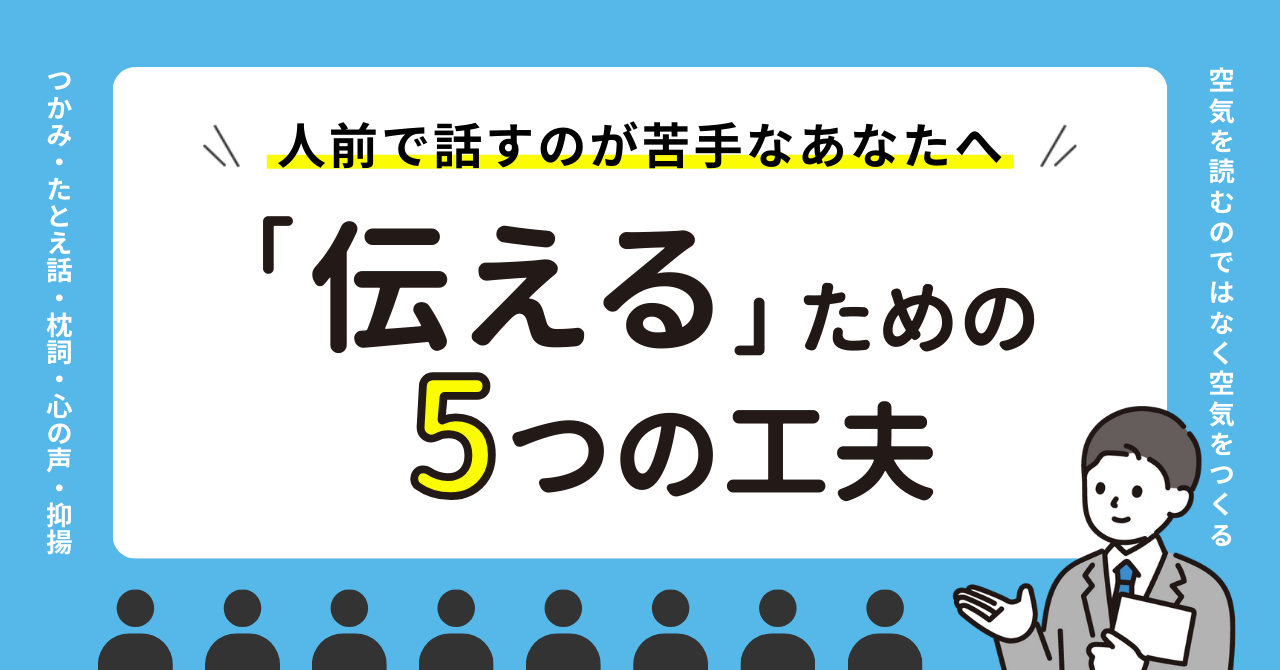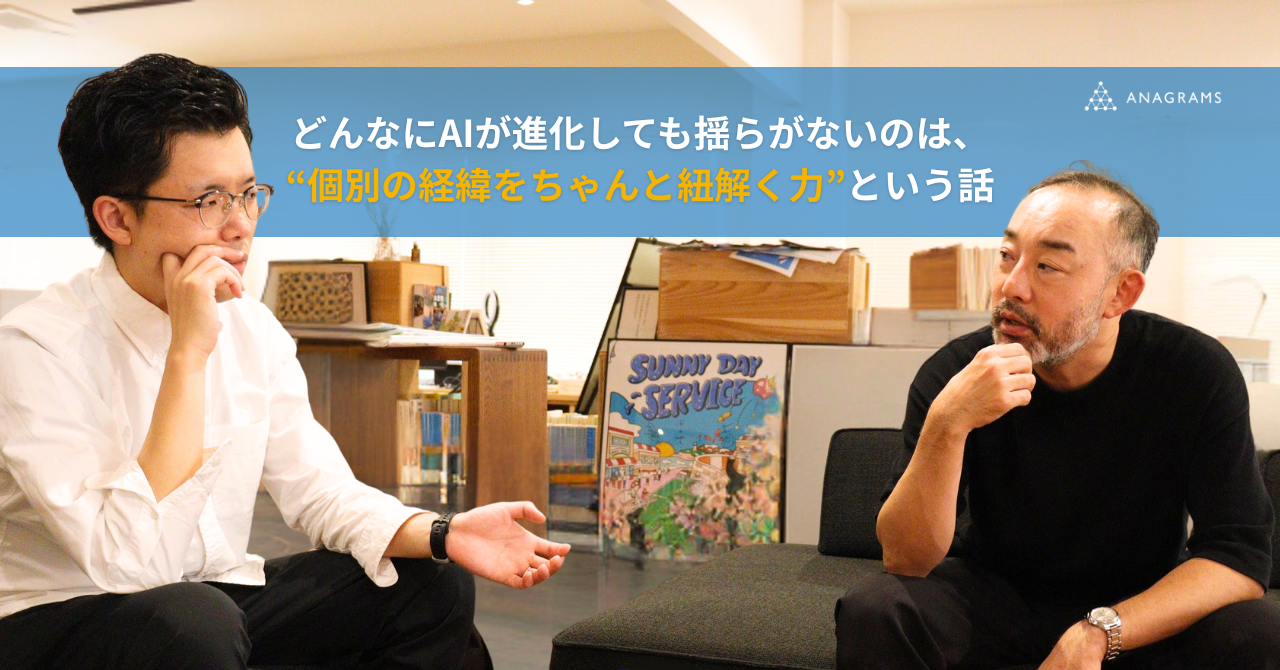
AIの進化によって、広告運用の多くが自動化されるようになりました。入札も配信も最適化も、昔に比べれば驚くほど手間が減っています。
そんな時代に「広告代理店の仕事って、これからどうなるんだろう?」という疑問を持つ人は少なくないでしょう。ただ、現場で働く人ほど感じているのは、単に“置き換えられるか・否か”ではなく、仕事の中身も変わりつつあるということです。
今回は、アナグラム代表の小山さんと、顧問であり金沢でマーケティング支援を行うLIFT代表の岡田さんに、AI時代の広告代理業の今とこれからについて語っていただきました。
※この対談は 2025 年 8 月に行われました
話し手:LIFT合同会社代表およびアナグラム株式会社 顧問
岡田 吉弘 さん
聞き手:アナグラム株式会社
代表取締役 小山 純弥
プロデューサー 西尾 美紗姫
目次
インターネット広告代理業は衰退する?

インターネット広告代理店の業界動向は、実は複雑な転機を迎えているんですよね。
ただ実際、インターネット広告市場は今も成長してるんです。電通の「日本の広告費」の統計を見ても、インターネット広告は2000年代から2020年代にかけて、ずっと成長してきた。広告費全体の半分近くがインターネット広告になり、多くの企業がこの成長に乗ってきました。
一方で、業界全体が成熟期に入ってきたシグナルも見えています。大手のネット広告代理店が大型広告グループに吸収されたり、あるいはインターネット広告事業の成長率が、かつてほどのペースでなくなったりしているところもある。これは必ずしも悪いことではなくて、業界が一定の成熟段階に達したことを示しているんだと思います。
SNS上でも「AIの導入があっても、検索広告がチャネルとして、このまま成長していくのか」という問い、あるいは「インハウス化が進んで代理店の役割が変わるのではないか」という議論が聞こえてくるようになりました。こうした問い自体が、業界全体で次の段階を模索し始めている証だと言えます。
新人研修(※)でも、AIの登場自体にはポジティブでありつつ、同じような問いを受けることがあります。「広告代理店の仕事って10年後も残ってますか?」などですね。今の世代は、最初から見えるところにAIが組み込まれた状態で仕事に入るから、肌で感じやすいというか、不安になりやすいんでしょう。
正直に言うと、私自身も広告運用を始めた2000年代前半は「今やってる仕事はそのうち自動化されてなくなるだろうな〜」と思っていました。当時はプラットフォーム側が今のように洗練されてはいなかったので、入札や設定の細かい部分で大きな差がつくという側面は確かにありました。だから仕組みが分かっていれば大抵の場合で他の人よりもうまくやれたんです。
でも、同時に「こんな状態が長く続くわけがない」という気持ちもあって、それから自動化だったりAIだったりが台頭し、結果そのとおりになったなあという印象を持っています。

※アナグラムは中途入社後に約1ヶ月の新人研修があり、岡田さんも一部のコマを担当されています

確かに大手の広告代理店の成長率が落ちたり、吸収・再編が起きたりしてるのは事実ですが、それは「市場全体の停滞」じゃなくて、「市場内での競争構造が変わった」ということだと思います。
市場全体を見ると、新しいプラットフォームやチャネルが次々と登場している。動画広告、SNS広告、生成AI関連の新しい広告フォーマット。こういった新しい領域が市場を広げています。
同時に進んでいるのが、セルフサーブ化です。昔は大型代理店に依存するしかなかった中小企業も、今は自社で直接インターネット広告を出稿できるようになった。敷居が低くなった分、参入企業が増えて、市場全体としては成長しています。
つまり「産業全体では成長してるけど、昔のような『運用スキルで差をつける代理店』という価値は通用しなくなった」ということだと理解しています。
そう。昔は、手動での細かい入札調整や、ターゲティングの工夫といったいわゆる職人芸だけで差がついていた時代がありました。でも今は、その作業はほぼ自動化されています。
だから表面的には「インターネット広告代理店の仕事が減った」ように見えます。ただ、同時に起きているのは複雑さの増加ではないかと。自動化されたツールが増えるほど、その中身はブラックボックス化され、より複雑になっていく。P-MAXにしても自動入札にしても、表面的には「ボタンを押すだけ」に見えるけど、もう複雑すぎてリバース・エンジニアリングしづらくなっています。そのため意図通りに適切に扱うことが 以前より遙かに難しくなっていると感じます。

「なにかを代理する」のはあらゆる商売の基礎

わかります。そういった流れを反映してなのか、実は、相談件数は増えてるんです。「P-MAXを回してるんだけど、CPAが悪化してる」「自動入札に切り替えたら逆に悪くなった」。こういう話が増えてきていますよね。
いま改めて、岡田さんは「インターネット広告代理店」という産業をどう感じているのか、率直に訊いてみたいなと。
うーん、確かにいろんなものがどんどん自動化されるし、使えるレバーも減ってはいるけれど、「なにかを代理する」のはあらゆる商売の基礎なので、広告運用も「運用」する必要があるかぎりは役割そのものはなくならないし、その役割の代理や代行には必ず需要がありつづけるだろうなと思っています。
あと、役割がある以上、AIには代替できないものが発生する。それは「責任」と「説明」の2つだと思います。「いや説明はできるじゃん」と思うかもしれないけど、その説明に責任がとれません。
外部のコンサルを雇う意味なんてほとんど責任の外部化ですしね。AIなら作業は代替してくれるし人間がやるよりも早いし、アイデアもたくさん出してくれるけど、その実行判断と責任は最終的には人間が負わないといけない。だから最終的な価値は「誰が」という部分に帰結するはず。誰がやるのか、誰が主体なのか。


P-MAXのような自動化されたツールが出てきても、結局、ボタンを押すのは人間で、その結果に対して責任を取るのも人間ですもんね。
事業会社の担当者からすれば、失敗したら自分のキャリアが終わるかもしれないという恐怖がある。「誰かに任せられる」「何かあったときに相談できる相手がいる」というのは、それ自体が大きな価値なんだと思います。
アメリカだとAIで作った履歴書で応募して、企業の採用担当がAIでレビューして合否判断するみたいな地獄がもう起きていますけど、それって参加者全員が無責任でしょう。別にAIを使うのは構わないんだけど、それだけで済ませちゃうと、企業の担当者は自分の所属する組織に、転職したい本人は自分自身の人生に、それぞれ責任を負った行動とはとても言えないですよね。
だから、どんなに自動化が進んでも、まともであろうとすれば、人が担うべき部分は確実に残るはずです。

難しくないロジックが組み合わさって想定外のことが起きる
アナグラムの新人研修で私が担当しているコマでは、最初にこう言います。「今から話すことは、ノウハウみたいなことは1つもない。でも、ゲームのルールみたいな話だから、ルールを知らないと勝負にならない」と。
たとえば入札の話。みんな「入札をポチポチ調整する」って揶揄するけど、そのポチをどうやって決めてるの? 100円を80円にするとして、その80円はどういう根拠で決めたんだ、っていう。ちゃんとやると論理的に説明が可能なんです。でも、みんな雰囲気でやりがちです。


そこですね。どういう根拠で判断するかが、実は最も重要な部分だと。
たとえば「広告の品質が上がれば平均CPCは下がる」というメカニズムになっているはずなのに、実際には上がっている。「なぜだ?」 って一生懸命考えたところで、そのロジックの中に答えはないでしょう。原理原則から外れた現象が現実に起こってるわけだから、それとは別のルールが絡み合ってそういうことが起きているんでしょ? って話をして。
だからそのルールを知らないと仕事にならない。 それを伝えるためにこの研修はあるんだ。ルールは公式のように覚えようとしたらつまらないんだけど、実は公式を実践にあてはめて応用問題を繰り返していく仕事なんだよと、そんなことをいつも言ってますね。


1個1個のロジックは何も難しくないけれど、組み合わさった瞬間に想定外のことが起きるんですよね。それはアカウントごと、すべてのタイミングによって、すべて違うことが起こってるから。入札を1つ変えるにしても、その背景にある「なぜ」を理解しているかどうかでまったく違う仕事になるんですよね。
個別の経緯を紐解いて、ちゃんと理由を見出していくことが、本当に大切なんだと思います。
大切ですよね。これが起きてるってことは、こういう事象が起こってるはずだから、つまりこういう機構になっているはずだ、っていうのをやっていく作業の繰り返しです。決して派手ではないけど、私はこれをとてもクリエイティブな営みだと思っています。

置かれた環境や選択肢を理解すると見えてくる
今言ってくれた「個別の経緯を読む」という考え方は、実は広告運用だけじゃなくて、マネジメント全般、採用、いろんなことに共通していると思っています。
たとえば以前、面接で応募者の評価が割れたことがありました。ある面接官が出身高校の偏差値に引っ張られた判断をしているように見えたので、「ちょっと待って。この人は何県のどこ出身なの?」と話を切り出して。


まさに個別の経緯を見ろということですよね。
そうです。調べてみたら、その人が生まれ育ったと思われる地域では、現実的に通える高校が3つしかなかった。その中で一番良い選択をして、そこで生徒会長もやっていた。
地方だと、学校の選択肢が少ない場合その地域の優秀な層が全員その高校に集まるから、偏差値で見ると平均的に見えても、実際には幅広い学力層が混在していたりするんです。


よくわかります。数字だけ見ると見えないものが、その人の置かれた環境や選択肢を理解すると見えてくるんですよね。
マクロのデータとして見たら、確かに統計的には一つの見方ができる。でも、個別の文脈を見たら全然違う背景が潜んでいることがよくあります。
うちは別に学歴で採用してるわけじゃなくて、その人がどういう環境で、どういう選択をしてきたのか、人生まで含めてちゃんと見ようとしているだけです。自分のバイアスに気づくためにもね。


これって、広告のCPAとか広告の品質とか、すべて同じ構造ですよね。数字だけ見て判断するんじゃなくて、その背景にある「なぜそうなったのか」を理解しなければ本質が見えてきません。
はい。一般解だけに頼らず、個別の経緯を見る。これは油断するとすぐ忘れるから、本当に繰り返し自分に言い聞かせるようにしています。

自動運転で増えるのは「直せる人」の仕事
あともう1つ、自動入札だと「車」の比喩をよく使います。
昔のまだマニュアル車で機構がシンプルだった時代は、一般人でもボンネットを開けて、ある程度直せました。でも、今はそんなことできる人はもう世の中ほとんどいないじゃないですか。中の機構を意識しなくても、命令だけすれば動く世界になっているから、全員がものすごく素人になっていく。一般技能だったものが特殊技能に変化していく。複雑になればなるほど、直せる人、修理工の価値は上がっていきます。


アナグラムに相談が来るのも、「直してほしい」っていうケースがほとんどです。「P-MAXを回してるんだけど、なぜかCPAが悪化してる」「自動入札に切り替えたら、逆に結果が悪くなった」。そういう時に、お客さんが困っていることが増えてますね。
順調だったら、既存の代理店を変えなくていいし、やり方も変える必要がない。必ず何か課題があって、簡単に答えられないから修理工に依頼が来るわけで。もはや運転の半分は自動なわけだから、自動でできることは当たり前すぎてソリューションにはならないんですよね。これが原因だろうと思える想像力と、直せる力が必要です。
これは広告に限らず、私が新卒で入ったSIerの世界でも全く同じでした。2000年代前半、就職氷河期のど真ん中で、どこも採用してくれなくて、ようやく潜り込めたのがSIerだった。
当時は、新しいシステムを作る仕事が花形で、みんなそっちを目指してたんだけど、実際に市場を見ると、保守の仕事の方が圧倒的に大きかった。新規構築の何倍もの予算が、既存システムの保守に使われていました。


なるほど。新規構築より保守の方がマーケットとして大きい。世の中にあるシステムの数と、新しく作られるシステムの数を比べたら、圧倒的に前者の方が多いわけですから。
確かに、考えてみれば当たり前ですが、そういうのは、人間がやる仕事なんですよね。
そう。これはITでも広告運用でも全く同じです。
自動化とAIが進んで、自称「運転がうまい人」は大量に発生するから、そんな渋滞しそうなポジションを目指すんじゃなくて、既存の広告アカウントで起きている問題を見抜いて「直せる人」になったほうが需要がある。


その「問題を見抜く」っていうのが、実は難しいんですよね。自動化が進むほど、何が起きているのか見えにくくなる。システムやツールに頼りすぎると、かえって問題に気づけなくなると感じるケースが増えています。
アナグラムでも、AIなど最新技術はアンテナを張って常に試し続けています。でもそのうえで、本質的に大事なのは、仕様の詳細まで把握して一気通貫で対応できる力。AI時代だからこそ、ロジックを徹底的に理解することが、問題解決の鍵になると考えてます。
「超強い1人」に依存するモデルは組織を脆くする
最近、ある会社で、システムの不具合に1週間気づけなかったっていう話を聞いて。それについて話したんですが、「気づけなかったことをシステムのせいにするな」って。
問題はシステムじゃない、姿勢の問題だと。こういう言い方すると根性論みたいになっちゃうけど、責任をシステムに転嫁したら、誰も責任を取れないじゃないですか。責任が不在だったらもうそこに人間は要らないでしょ。根性以前にあなたが要らなくなるよと。
あと、パッチワークが増えるほど人間は間違いに気づけなくなるので、システムで補完すればするほど、人間の感度は落ちていく。モニタリングそのものが壊れていることに気づけなくなるものなんです。広告業はサービス業だから、感度が鈍い人間がサービス業で活躍できるわけがない。


アラートをかけて終わり、みたいな仕事になってしまうと危険ですよね。
結局、そのアラートを見れるのが一部の優秀な人に偏ってしまって、組織として脆弱になる。「超強い1人」に依存するモデルは組織を脆くする。その人がいなくなったら終わりだから。


アラート依存は見る目を曇らせることもありますよね。「アラートが来てないから大丈夫」って思考停止してしまう。
でも、実際には、個別に見ていかないと分からないことがたくさんありますよね。
だから、戦略的に「無駄」を残しておかないといけないなと思います。一見無駄なようで、個別にちゃんと考えることが、実は一番大切だったりしますよね。
まさに。広告管理画面を見る時でも媒体の推奨設定をそのまま使うんじゃなくて「なぜこの推奨なのか」「このアカウントには本当にこの設定が適しているのか」を常に考えないといけないし、マネジメントでも一般解に頼らず、個別の経緯を見ることが大事。あらゆる仕事に共通する本質なんじゃないかと思います。

効率化と矛盾する「非効率を意図的に作る」理由
今言ってくれたように、意図的に「無駄」を残すようにするのは大事ですよね。
たとえば、請求書の処理。請求書が1万枚になったら、処理するだけで膨大なリソースがかかる。これを全部AIに任せれば、確かに効率は上がりますよね。
でも、そうすると何が起こるか。請求書作成を通じて担当者が取引を振り返ったり、それを送る際の先方とのコミュニケーションのきっかけ、そこから起こる機会の可能性すべてが効率化の陰でなくなってしまう。


会社って、効率だけで成り立つものじゃないなぁと経営に携わって実感しています。
だから、非効率を意図的に作るのは大事ですね。バランスは難しいけど。広告運用をコンサルティング業として考えると、過度な効率化にはどうしても矛盾が生まれます。コンサルって、高度な判断力がある人が必要な仕事なのに、どんどん自動化して、考えなくても済むようにしてしまったら、自分で考える力が育たない人間ができあがってしまう。そんな人ばかりが集まった会社に競争力があるわけないもんなあ。


求めている人材と、育てている人材が、真逆になってしまいますよね。
だから、どういうポリシーを持って会社を経営しているのかは重要ですよね。方法論は企業ごとに多少違っても、目指す方向と運営の方法論とがざっくり合ってる状態が、おそらく健全なんだと思います。


アナグラムの場合は、東京で130人以上の組織なので、岡田さんのところ(※)とは規模感が違いますが、基本的な考え方はどのサイズでも同じだと思ってます。効率と成長のバランス。これは経営における最大のテーマですね。
※岡田さんは、アナグラムの顧問のほかに金沢でLIFTというマーケティング支援の会社も営まれています

一般解だけに頼らず「なぜそうなったのか」を問い続ける

今日、岡田さんと話していて、「個別の経緯を見る」は、広告運用から、採用、組織運営、そして人のキャリア形成まで、すべてに通底していく考え方なんだなと気づきました。
そうですね。結局、一般解だけに頼っていたら、「あなたがそこにいる意味」がなくなっちゃうじゃないですか。広告の管理画面を見る時も、採用でレジュメを見る時も、システムのアラートを見る時も、その背景にある「なぜ」を理解しようと考えつづけないといけない。
これができる人とできない人とでは、最終的なアウトプットが全く違ってくる。入札の目標値をいくらにするかという行為は同じでも、そのアウトプットの差が仕事の質の差になって積み上がっていくのではないかと。


AIが進化すればするほど、「なぜそうなったのか」を説明できて、「どう直せばいいか」を提案できる人の価値は、どんどん上がっていくと思います。
結局、人にしかできないことって、減るどころか、むしろ重要性が増していくんだと確信しました。
「AIで仕事がなくなる」っていう不安は、ある意味で自然な感情だと思うんです。でも、その不安に飲まれて、表層的なスキルやトレンドだけを追いかけると、本当に代替されてしまいます。逆に、「なぜそうなったのか」を問い続ける姿勢や人にしかできない力を磨き続ければ、AI時代ほどチャンスが広がっていくんじゃないかな〜と、それくらい楽観的でいいような気もしますね。