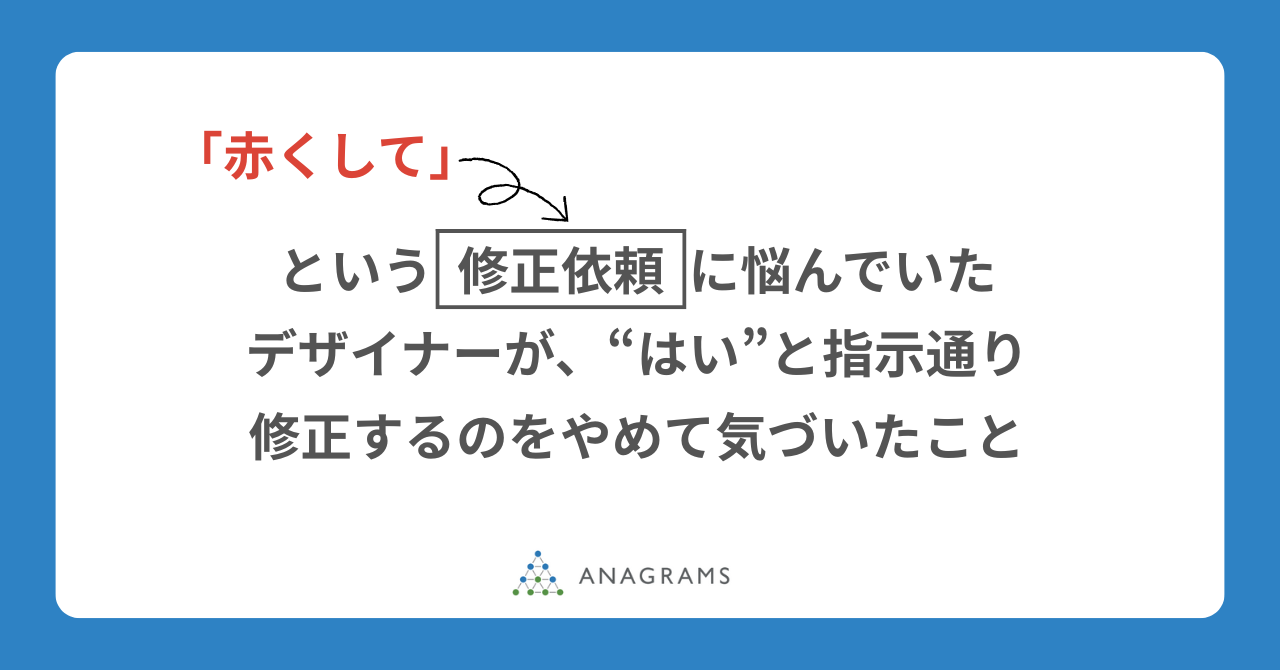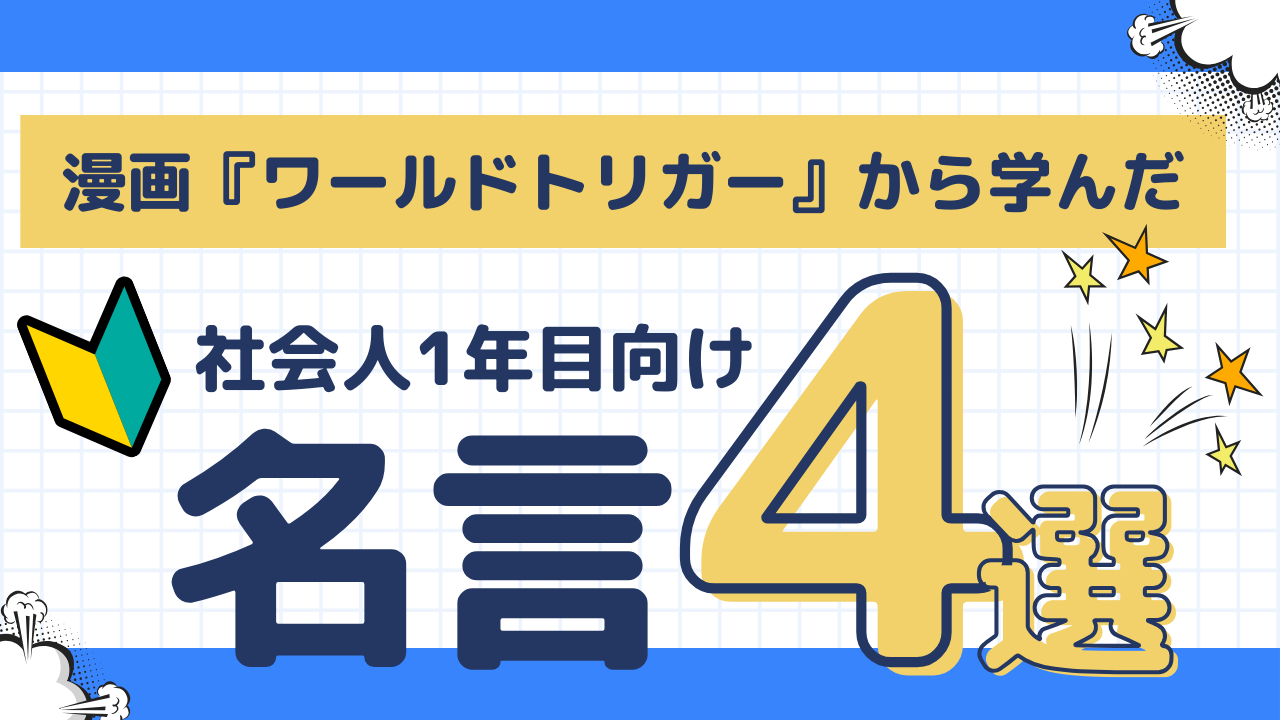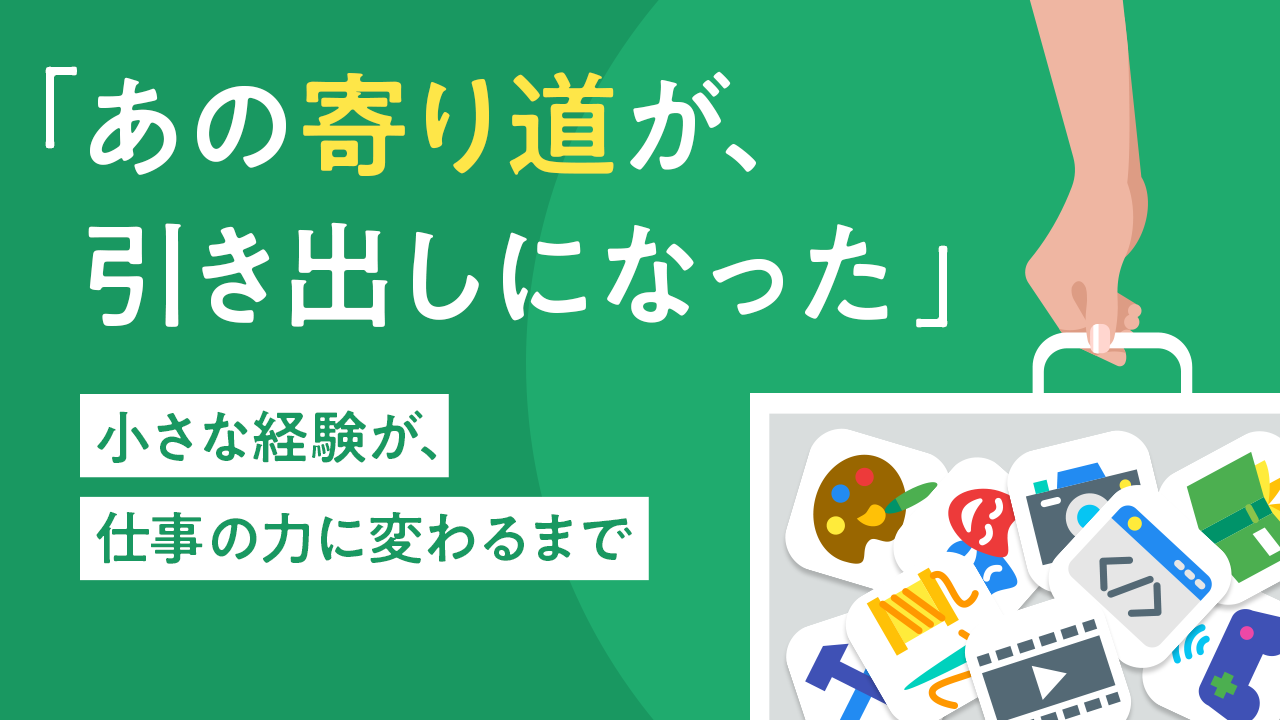
「どうせなら、仕事につながることをしたほうがいい」
そう考えて、“気になること”や“やってみたいこと”を後回しにしてしまう。学びや趣味にも“効率”を求めがちな人ほど、寄り道が怖く感じるものです。
でも、振り返ってみると遠回りの中でしか育たない力も、たしかにある。
本記事では、一見仕事とは関係なさそうに見える私自身の経験が、どのように新しい挑戦や成果につながっていったのかを振り返りながら、好奇心から生まれる“小さな挑戦”の価値について考えていきます。


一見無駄に思えた経験で引き出しが増えた
「気になったからやってみた」こと。その瞬間はただの思いつきでも、時間がたってから意外な形で役立つことがあります。
まずは、私の一見無駄に思えた経験が引き出しが増え自分の役に立ったエピソードを紹介していきます。
動画編集を趣味で始めたら、仕事で動画案件を任されるようになった
入社当初は、静止画の制作が中心で、動画制作にはまったく触れたことがありませんでした。
そんなある日、「自分の結婚式ムービーを自作してみたい」と思い立ったのがきっかけです。YouTubeでチュートリアルを見ながら、見よう見まねで動画編集を学習。最初はBGMと動きを合わせるのも難しく、ソフトの操作にも苦戦しました。それでも完成したときの達成感が楽しくて、気づけば夢中になっていました。
その経験が、後に仕事で活きることになります。動きやテンポの感覚が自然と身につき、静止画だけでは表現できなかった“動きのあるデザイン”を意識できるようになりました。
やがて動画案件の相談を受けるようになり、「趣味でやっていたことが、仕事の武器になるなんて」と驚いたのを覚えています。もしあのとき、興味を後回しにして“やらない”選択をしていたら、今も「動画は自分の担当外」と思い込んでいたかもしれません。
そんな小さな分岐が、いまの自分をつくっているのだと思います。
スクールで学んだコーディングが、ちょっとした修正で重宝された
入社前、デザインスクールでコーディングの基礎を学んでいましたが、実際に触ってみると想像以上に奥が深く、「これ一本を仕事にするのは自分には難しいかもしれない」と感じ、当時はデザイン主体の道を選びました。
現在、弊社ではコーディング作業は外部パートナーに依頼することがほとんどです。
それでも、自分でコードを“読める・少し触れる”だけで助かる場面は少なくありません。
たとえば、LPの文言修正や要素の位置調整など、軽微な変更をスピーディーに自分で対応できる。ちょっとした設定の確認や、レイアウト崩れの原因を特定する際にも、コードの理解が役立ちます。
得意ではないけれど、触れたことがあるだけで“できることの幅”が広がる。それもまた、実務の中で生きる“引き出し”のひとつです。
コスプレの経験が、ユーザー心理の理解に活きた
ある日、同僚に「一緒にコスプレしてみませんか?」と言われたのがきっかけでした。
それまでコスプレに興味はあったもののやる機会もなく、せっかく誘ってもらったので好奇心のまま挑戦してみることに。
実際にやってみると、想像以上にメイクに時間がかかることや、ウィッグの調整が大変なことなど、見るのとやるのではまったく違う世界が広がっていました。
後に、コスプレイヤー向けホテルプランの広告制作を担当する機会がありました。そのとき、あの体験を通して得た「準備の大変さ」が、自然とユーザーの気持ちを想像する助けになったのです。
広告制作は、常に“ターゲットの立場を想像する”ことが求められます。だからこそ、一見仕事とは関係なさそうなことでも、自分の中で実際に体験しておくことが、未来の引き出しにつながるのだと感じました。
経験して初めてわかる感覚がある。それを知っているかどうかが、表現の深さを変えていくのかもしれません。
引き出しが増えて得られた4つの力
一見無駄にも思えるような経験をいくつも重ねてきたけれど、振り返ると、それらは確かに自分の“引き出し”を増やしてくれていました。
引き出しの中身はスキルや知識だけではなく、「どう動けるか」「どう考えられるか」といった力の形で現れている気がします。
ここでは、その中でも特に実感している4つの力を整理してみます。
1. 対応力:小さな作業を自分で完結できる
引き出しが増えると、自分の中で完結できる範囲が広がります。誰かの手を借りずにちょっとした修正ができる、軽微な課題に即座に対応できる。それだけで、チーム全体の動きはぐっとスムーズになります。
「これ、自分でできるかも」と思える瞬間が増えると、自信と行動力も自然とついてくる。対応力とは、単に“作業できる力”ではなく、自ら動ける力でもあるのです。「待つ」から「動く」へ。その切り替えができる人は、どんな現場でも頼られます。
2. 判断力:目的に応じて最適な手段を選べるようになる
「思い描いたデザインを形にするには、どのツールを使えば一番早く、きれいに仕上がるか?」そうした判断は、実際にいくつかのツールを触ってみた経験からしか得られません。
PhotoshopやFigma、After Effectsなど、それぞれの得意・不得意を肌感覚で知っていれば、 「この演出ならAfter Effects」「このレイアウトはFigmaが早い」といったように、目的に応じて“最適な方法を選び取る判断力”を発揮できます。
3. 発想力:経験の幅がアイデアの源泉になる
新しい経験ほど、思わぬ発想のきっかけになります。異なる分野の要素を組み合わせたり、過去の体験からヒントを引き出したり。引き出しが多い人ほど、発想の切り口も豊かなのではないでしょうか。
たとえば、写真撮影で「光の入り方」を意識するようになってから、LPデザインで余白の取り方が変わったり、演出構成に注目しながらアニメを見ていたら、動画広告の“間”づくりに生きたり。
一見関係なさそうな経験同士が、ふとした瞬間に線でつながる。そんな“点と点の発想”こそ、独自のクリエイティブを生み出す源になります。
4. 共感力:異なる立場や気持ちを想像できる
多様な経験を重ねるほど、他者の立場や感情を想像する力が育ちます。それは、広告やデザインにおいて非常に大切な“視点の柔軟さ”です。
たとえば、自分がユーザーとして体験した不便さ、嬉しさ、驚き。そうした実感を持っていると、ターゲットの気持ちをよりリアルに描くことができます。
共感力は、経験の幅から生まれる。だからこそ、いろんな世界をのぞいておくことが、結果的に“伝わる表現”につながっていくのです。
引き出しが増えるというのは、単に知識が増えることではなく、いろんな角度から世界を見られるようになることだと実感しています。
引き出しを増やす3つの習慣
無駄だと思っていた経験が、あとで力に変わる。そう頭ではわかっていても、いざ日常に戻ると「やってみる」より「考えて終わる」ことの方が多いかもしれません。
では、そんな引き出しを増やしていくために、どんな行動から始めればよいのでしょうか。
ここでは、私が実際に意識している3つの習慣を紹介します。
まず触れてみる:興味がわいたら小さく試す
「気になる」「ちょっとやってみたい」その直感を軽く扱わないこと。最初から完璧を目指す必要はありません。たとえば「動画を触ってみたい」ならスマホで簡単な編集から、「デザインを学びたい」ならCanvaでテンプレートをいじってみるくらいで十分。
重要なのは、“とりあえず触ってみる”という一歩を踏み出すことです。完璧じゃなくても動いてみた経験は、後で確実に自分の糧になります。
経験を言語化する:「どんな場面で使えたか」をメモに残す
せっかく得た経験も、そのまま流してしまえば“ただの思い出”で終わってしまいます。「どんな場面で役に立ったか」「どんな工夫が効果的だったか」など、小さな気づきでも言語化して残すことで、“経験”が”知恵”へと変わる”瞬間が訪れます。
弊社では、日々の実践から得た学びや気づきを共有できる知見共有の仕組みが整えられています。自分の経験が誰かの課題解決につながったり、逆に誰かの共有が自分の引き出しを広げてくれたり。そうした循環があることで、「経験を残す」ことがチーム全体の成長にもつながっていきます。
メモアプリやNotionに残すだけでも構いません。過去の自分の記録を見返したとき、「あのときの試行錯誤が今につながっている」と気づけると、挑戦を続けるモチベーションにもなります。
掛け合わせてみる:異なる経験をつなげてみる
ひとつの経験だけを見ると凡庸に思えることも、、ふたつ以上の経験を掛け合わせることで一気に“自分らしい強み”になります。
たとえば「動画×デザイン」でSNS広告に強くなったり、「趣味×仕事」で他の人にはない視点を発揮できたり。
特別なスキルを新たに身につけるよりも、“今ある引き出し同士をつなぐ”ほうが、 オリジナリティのある成果につながりやすい。その積み重ねが、他にはない発想や価値を生み出していきます。
寄り道の中にしかないものを大切に
引き出しは、一気に増えるものではありません。日々の「気になる」「やってみたい」という小さな挑戦の積み重ねでできあがります。
当時は“寄り道”に見えても、未来ではきっと武器になっている。だからこそ、遠回りを恐れず、好奇心に正直でいましょう。
次に気になったことをひとつ、小さく触れてみてください。それが、未来のあなたを支える新しい引き出しになるはずです。