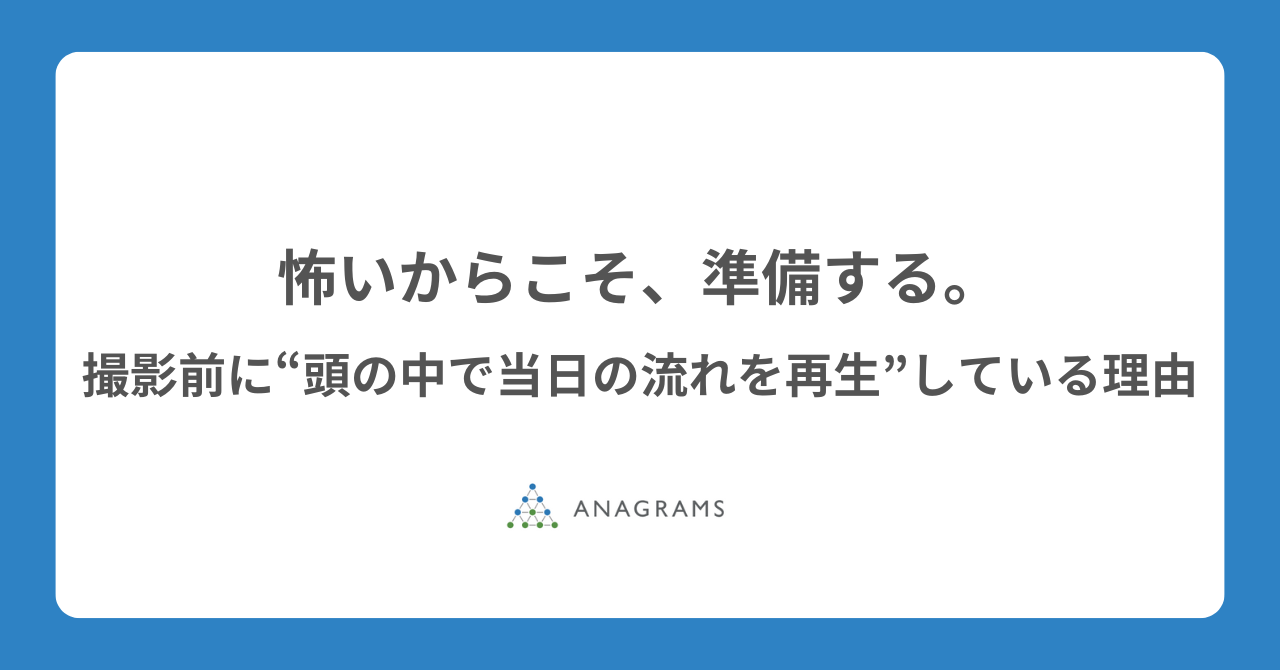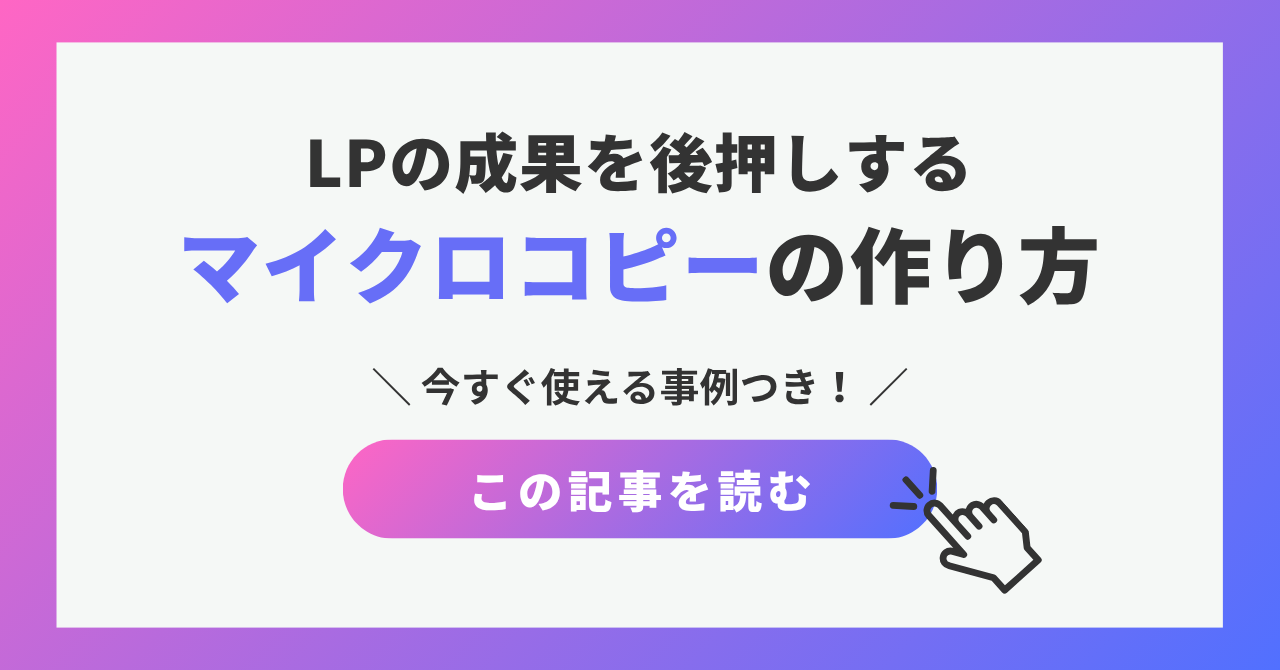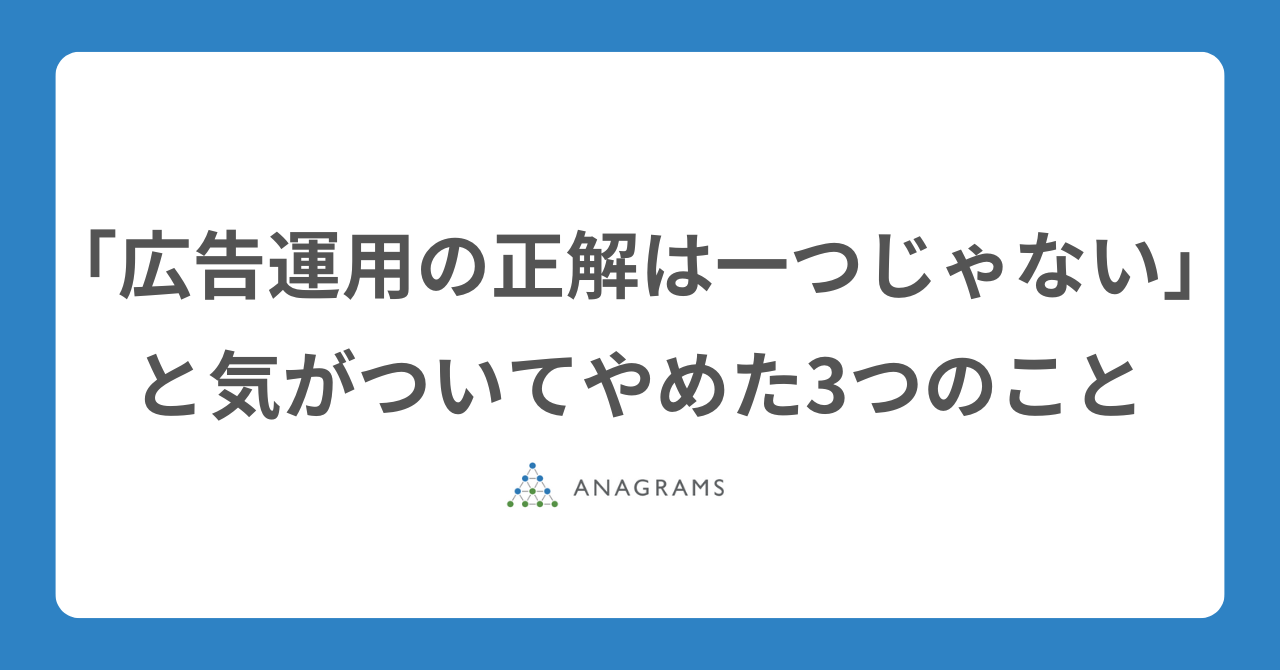
広告運用をしていると、次のように感じたことはありませんか?
- 「失敗したらどうしよう」と不安で施策を打ち出せない
- 提案しても上司やクライアントの反応が怖くて、自信を持てない
- 一度成果が出ないだけで「このやり方はダメだった」と思考が止まってしまう
私自身もかつて同じ状況に陥っていました。その背景には、広告運用という仕事ならではの特性があります。
広告運用は、CPAやROAS、CTRといった数値目標が明確に設定される仕事です。成果が数字で直ちに可視化されるため、「この数値を達成する=正解」と考えてしまいやすい。さらに、施策を打てば翌日には数字に表れる環境があり、短期的な上下に振り回されて「成功/失敗」をすぐに決めつけてしまいがちです。
こうした特性に加え、人間はそもそも「間違いたくない」「損を避けたい」という心理を持っています。結果として「唯一の正解があるはずだ」と思い込み、施策を一か八かの賭けのように捉えてしまいがちです。
しかし、私はある経験を通じて「広告運用に正解は一つじゃない」と気づきました。その気づきとともに、3つの“やめたこと”があります。本記事ではその体験をお話しします。


目次
広告運用の正解は一つだと思い込んでいた
私が広告運用に携わり始めた頃、頭の中には常に「正解があるはずだ」という前提がありました。学校で学んだ算数のように、「1+1=2」 のように一つの答えにたどり着くのが当たり前だと考えていたのです。
ところが広告運用では、その発想がかえって自分を苦しめる原因になりました。
施策を検討するとき、あらゆるリスクが頭をよぎります。
- 「この施策は本当に正しいのか?」
- 「もし成果が悪化したら、どう説明すればいいのか?」
このように、考えすぎて決断できず、時間だけが過ぎていきました。
ようやく実行に踏み切っても、一度成果が思うように出なければ「このやり方は間違っていた」と思い込み、思考が止まってしまう。 「成功」か「失敗」かの二択でしか自分を評価できず、失敗すれば自分を責め、成功しても「次も結果を出さなければ」とプレッシャーを抱え込みました。
その結果、私は挑戦よりも「間違えないこと」に意識が偏り、施策の幅を狭め、スピードも失っていました。まるで「1+1=2」しか答えのない世界を探し求めるように、広告運用に存在しない“唯一の正解”を追いかけていたのです。
広告運用の正解は一つじゃないと気づいた2つの出来事
当時の私は、広告運用にも唯一の正解があると信じ込んでいました。だからこそ、成果が出ないたびに「やり方を間違えた」と思い込み、ますます迷いが深まっていったのです。
そんな考えが少しずつ変わっていったのは、二つの出来事がきっかけでした。
二人の上司から受けた真逆のフィードバック
ある案件で、既存の検索広告に加えて新たにMeta広告を試そうと提案したときのことです。
一人の上司は「面白いね、挑戦してみよう」と後押ししてくれました。ところが、その上司の上司は「その商材でMetaは厳しい。まずは検索広告を深めるべきだ」と真逆の意見を返してきました。
当時の私は「一体どちらが正解なんだ?」と完全に混乱しました。しかし最終的にMeta広告を実施した結果、成果は想定以上に良好でした。一見すると「挑戦を支持した上司が正解」だったように見えます。ですが、もしCPAが高騰していれば、慎重な判断を示した上司が正解になっていたかもしれません。
結局はどちらの方法であろうと成果につながれば、両方とも価値のある施策です。この経験を通じて、私は「どちらが正しいか」ではなく「どちらの可能性を試すか」が重要なのだと気づきました。広告運用に唯一の正解は存在しないのを実感した瞬間でした。
上司が“失敗”を“検証結果”に変えた一言
別の案件では、立て続けに施策の成果が振るわず、私はすっかり落ち込んでいました。アカウント全体は悪くないのに、目の前の施策が思うようにいかないことばかりに気を取られ、クライアントへの報告でも自信を持てなくなっていたのです。
そんなとき上司に相談すると、私が「失敗」と受け止めていた結果を「これは貴重な検証の一つだね」と返してくれました。さらに「この結果をもとに、次の可能性を試せる」とごく自然に次の一手へとつなげてくれたのです。
このやり取りをきっかけに、私の中で「施策は成功か失敗かの二択ではない」という見方が少しずつ定着していきました。施策とはあくまで仮説に基づいた検証であり、そのどんな結果も次の一歩を考えるための材料になる。そう考えることで、重くのしかかっていた「失敗」という言葉が、前に進むためのヒントへと変わっていきました。
広告運用に“正解”がないと気づいてからやめた3つのこと
「広告運用に正解は一つではない」と気づいてから、私は意識して三つのことをやめました。どれも小さな切り替えでしたが、結果として施策のスピードや幅が広がり、クライアントとの関わり方も変わっていきました。
1. 「一発で成果を出さなきゃ」という思考をやめた
以前の私は、施策ごとに「これで成功しなければ」と強く思い込み、慎重になりすぎて動けなくなることがありました。しかし「まずは小さく試そう」と考えるようになってからは、思い立った施策をすぐにテストできるようになりました。
例えば、あるクライアントのMeta広告で達成したい目的があったときのことです。以前の私なら、一つのクリエイティブを制作するために、過度に時間をかけていました。しかし今では、目的達成のために考えられる仮説を複数立て、優先順位をつけながら、より多くのクリエイティブを試すようになりました。
もちろん、制作するパターンが増えれば、成果が振るわないものも出てきます。ですが、一つの施策を吟味しすぎるよりも、多くの仮説を素早く検証していくほうが、結果的に得られる知見も増え、次の施策に活かすことができます。
このように改善のサイクルを速めることで、最終的な成果にたどり着くまでのスピードも格段に速まりました。
2. 成功か失敗かで結果を評価するのをやめた
かつては、施策の結果を「成功」か「失敗」でしか判断できず、一度成果が出なければそれで終わってしまうことも少なくありませんでした。ところが、どんな結果も「検証結果」として捉えるようにしてからは、次につながる学びを得やすくなりました。
以前、ある案件でそれまでターゲットとしていた層とは大きく異なる層の獲得を目指した広告配信に挑戦したことがありました。結果だけを見るとCPAが目標に届かず、数値上は「失敗」と判断できるものでした。ところが、その結果となった要因を詳しく分析すると、配信面ごとに獲得状況が異なり、ある配信面においては獲得のチャンスが感じられたのです。
この発見を踏まえ、次の施策では注力する配信面を狙って、クリエイティブや広告文を調整し、配信しました。結果、CPAを改善しつつ、それまでは接点を持てていなかったであろうユーザーの獲得に繋げることができました。今ではこの施策が案件全体にポジティブなインパクトを与えるほどの規模になっています。
一見「失敗」に見える施策も、見方を変えれば次の打ち手を考えるための重要なヒントになる。そのことを改めて実感した経験でした。
3. 一人で完璧な答えを探すのをやめた
以前は、広告運用のプロとして「正解を示さなければ信頼されない」と思い込んでいました。すべての成果の理由を明確に示し、ロジカルな提案をすることが重要だと考えていたのです。その結果、定例会での会話が一方通行になってしまうこともありました。
しかし、「正解は一つではない」という前提に立ってからは、クライアントに積極的に質問し、意見を求めることが増えました。すると、Web広告以外の施策の状況や、社内のリアルな事情、エンドユーザーの声など、貴重な一次情報を共有してもらえるように。自分だけの視点では得られない発見が増えていきました。
もちろん、広告運用のプロとしての意見やスタンスは持つべきです。ただ、クライアントにはクライアントにしか見えない景色があり、どちらか一方の視点だけが正しいわけではないと気づきました。
そうした多様な視点を取り入れながら、「一緒に目的を達成する」という意識で向き合うようになってから、提案の幅が広がり、関係性もより深くなっていきました。
広告運用の正解は、いくつもある
ここまで紹介した三つのことをやめたことで、「正解を出さなければ」という思い込みから解放されました。代わりに、「仮説を立てて、試し、そこから学ぶ」というプロセスに集中できるようになりました。
広告運用は、常に変化する市場やユーザーの行動と向き合う仕事です。昨日の最適解が今日も通用するとは限りません。広告コピーやクリエイティブ、ランディングページ、媒体のアルゴリズムなど、成果を左右する要素は無数にあり、その組み合わせ次第で結果も大きく変わります。
もしあなたが「失敗が怖くて動けない」「反応が怖くて自信が持てない」と感じているなら、広告運用に正解は一つじゃないことを思い出してください。大切なのは、その場その場で最善だと思うアプローチを選び、素早く試し、学びを積み重ねていくことです。
そう捉えることで施策の幅は広がり、意思決定も軽やかになります。広告運用の醍醐味は、多様な正解を見つけ出していくプロセスにあると感じています。