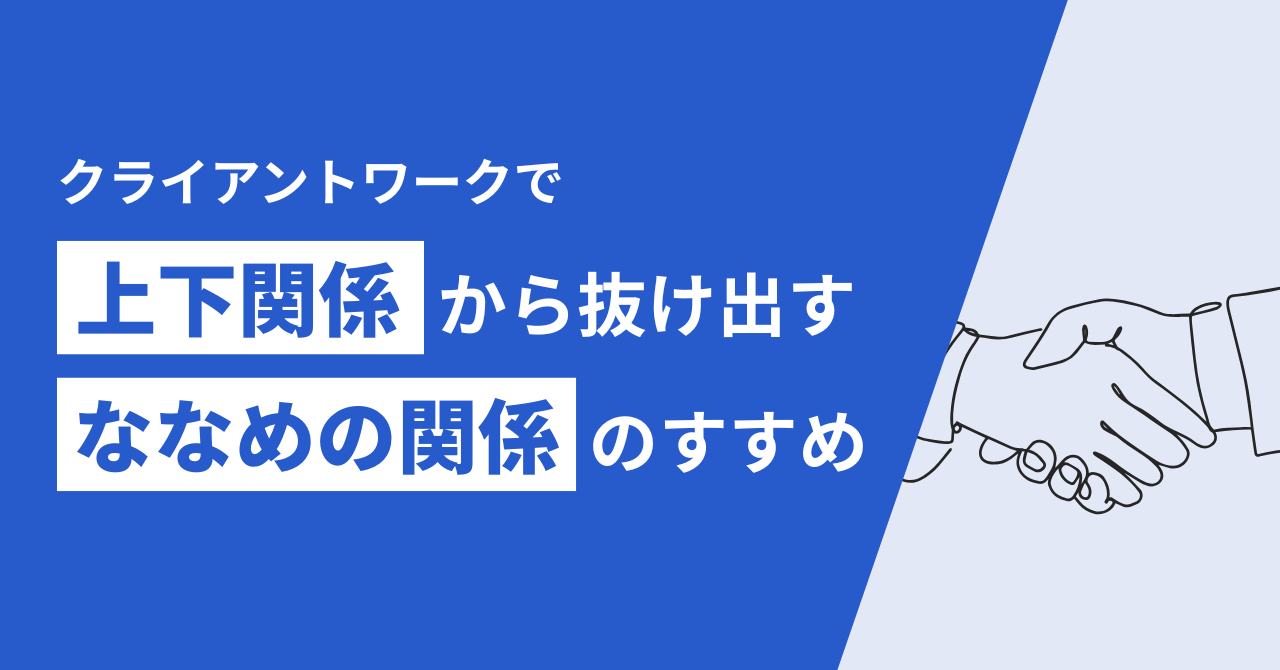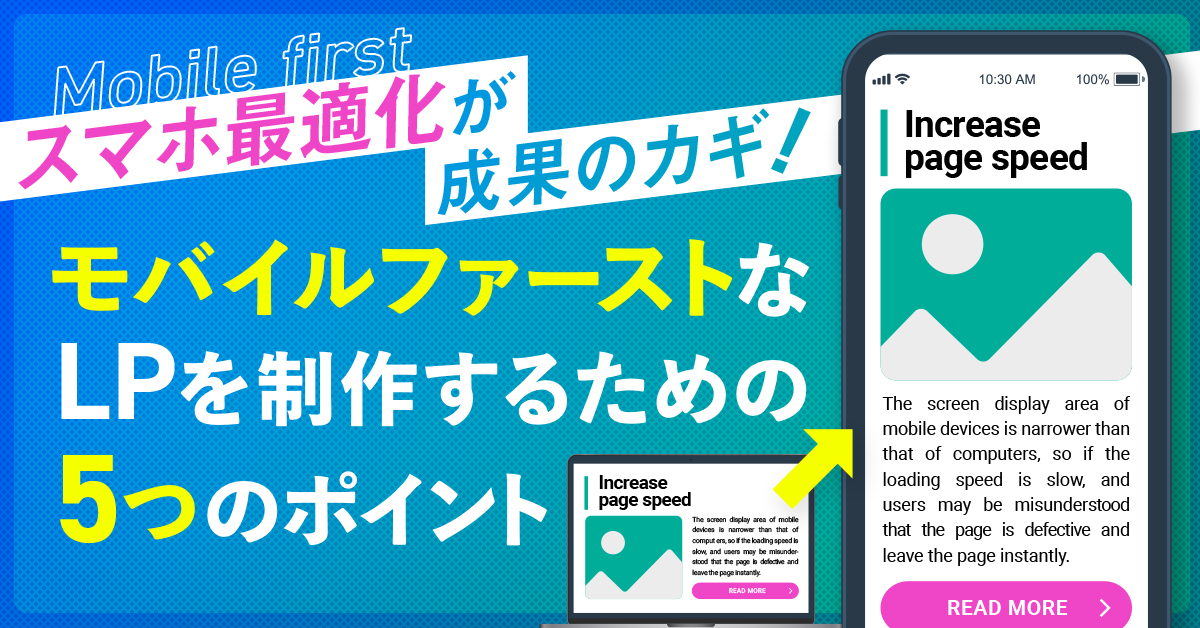広告バナーやWebサイトのデザインだけでなく、コピーを書いたり、撮影や進行管理を任されたり……。気づけばデザイン以外の業務にもどんどん関わっている、いわゆる“ジェネラリスト”な働き方をしているデザイナーは少なくありません。
現場の流れに応じて必要なことをこなしてきた結果、「色々やってるけど、これといった強みがないかも」「自分は結局、何を目指してるんだろう」と悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。
私自身、前職ではデザインだけでなく、ライティング・コーディング・撮影・SNSマーケティングなど、さまざまな業務に携わってきました。当時は「デザイナーとしてちゃんと成長できているのかな」と不安に思うこともありましたが、今ではその経験の広さこそが自分らしい強みになっていると感じます。
今回は、ジェネラリストなデザイナーの強みと、不安を抱く状態から一歩前進するために何をすればいいのか考えてみました。


目次
ジェネラリストなデザイナーの強み
一つのスキルに特化していないことに不安を感じることもあるジェネラリストなデザイナー。でも実は、その幅広さがあるからこそ発揮できる強みがたくさんあります。
ここでは、そんなジェネラリストならではの魅力を4つの視点からご紹介します。
手段に縛られず、目的から考えられる
ジェネラリストなデザイナーの大きな強みのひとつが、手段にとらわれず、目的から考えられる柔軟さです。
プロジェクトごとに求められることは違い、「正解」も毎回同じとは限りません。 だからこそ、今できる手段に固執せず、「この目的ならどんな形が最適か?」と考えられる姿勢が大切になります。
たとえば、動画広告の方が相性の良い商材があるにもかかわらず、「静止画しか作れないから」という理由で静止画だけを提案してしまう──。それは、成果のチャンスを逃すだけでなく、自分自身のスキルの可能性にも蓋をしてしまっている状態かもしれません。
“目的に合わせて最適な手段を柔軟に選べる”視点は、プロジェクトにおいて大きな価値になります。
プロジェクト全体を俯瞰してチームを前に進められる
ジェネラリストなデザイナーのもうひとつの強みは、プロジェクト全体を俯瞰して、流れを把握できることです。
日々いろいろな業務に関わる中で、自然と「この工程の後には何が起きるか」「他の担当者は何に困っているか」といった視点が身についていきます。その結果、部分最適ではなく全体を見据えた判断や提案ができるようになるのです。
また、関わる範囲が広いからこそ、チーム内の動きにもアンテナが立ちやすくなります。「今この人に声をかけておこう」「そろそろ○○の準備を進めないと」といった、小さな先回りがプロジェクト全体のスピードやスムーズさに貢献していきます。
こうした俯瞰力とチームとの橋渡しができるポジションは、ジェネラリストだからこそ担える価値のひとつです。
自分で考え、自分の手で実行できるため、スピーディに業務を進められる
「この案でいこう」と決めたあとに、他の誰かに制作をお願いして戻ってきたものを確認して……。そんなやりとりの中で、「あれ、ちょっと意図とズレてるかも」「ここもう一回お願いしてもいいですか?」と、手戻りが発生した経験はありませんか?
ジェネラリストなデザイナーは、自分で考えたことを、そのまま自分の手で形にできるのが強みです。誰かに伝えるプロセスを省けるため、判断から実行までのスピードが早く、ちょっとした修正もその場で完結できます。
もし他のメンバーにお願いする場合でも、自分で手を動かした経験があるからこそ、相手にとって分かりやすい依頼ができます。
“考えること”と“つくること”の両方に関われるからこそ、スピード感と現場理解のある動きができる。この連携の良さも、ジェネラリストならではの強みのひとつです。
広く関わるから、自然と頼られる存在になっていく
ジェネラリストなデザイナーは、デザイン以外の領域にも関わっているからこそ、いろんな人の立場や考え方に触れる機会が多くなります。
その中で、たとえば「エンジニアはこういう観点で動いてるんだな」とか、「クライアントはこういうところに不安を感じるんだな」といった視点が少しずつ身についていきます。
すると自然と、それぞれの立場の“言葉”や“前提”を、別の相手にも伝えやすくなる。“通訳”のように、役割や視点をつなぐ存在として動けるようになるでしょう。
実際にアナグラムでも、クライアントとのやりとりの中で、「デザインの知識はないけど、成果を出すためにどこに注力すればいいか言語化してくれて助かりました」と言っていただけることがあります。
広く関わっているからこそ、相手の視点に寄り添える。その姿勢が、チームやクライアントからの信頼につながっていきます。
“何者でもない気がする”不安と、そこから一歩進むために
ここまでジェネラリストなデザイナーの強みを話してきましたが、それでも自分がどこに向かっているのか不安が拭えないこともありますよね。
「強みを作らなきゃ」「何かに特化しなきゃ」と無理に肩ひじを張る必要はありません。むしろ、専門性は「手段」ではなく、「どんな場面で、どう貢献できるか」で定義されるものです。
たとえば、「Figmaが得意」より、「他職種との橋渡しが得意」「混沌とした情報を整理して形にするのが得意」といった、“動詞”で語れる力こそ、あなただけの専門性かもしれません。
とはいえ、最初からその「動詞」が明確な人はほとんどいません。価値の出し方は、ちょっとした好奇心や手応えの積み重ねで育っていくものです。そこで、おすすめしたいのが“少しだけ深掘ってみること”。
日々の業務の中で、「こういうの好き/得意かもしれない」と思える瞬間があったら、ほんの少しだけ踏み込んでみましょう。
たとえば──
- 会社の中に近しい業務があれば、「やってみたい」と声をあげてみる
- 「こういう業務をやってるときが楽しい」と社内チャットやSNSで発信してみる
- 少しでも知見を深めたいと思ったら、本を読んだり、セミナーやコミュニティに参加してみる
そうした小さな行動が、自分らしい強みを育ててくれるはずです。ジェネラリストとして、業務の幅広さや他職種との関わりの中で得てきた視点は、それを形にする大きな支えになります。
最後に
これからの時代、AIの進化によってバナー制作やライティング、コーディングなどのデザイン業務は、ますます自動化が進んでいくでしょう。
一方で、「誰に何を届けるべきか?」「そもそもこの課題は何なのか?」といった曖昧で複雑な問いに向き合い、全体をつないでいく力がより一層求められるようになります。
目的を見失わずに、チームの間を橋渡しし、必要に応じて自分の手で動いて形にする。そうしたジェネラリストならではの柔軟さと推進力は、どんな時代でも必要とされ続けるはずです。
本記事が、ジェネラリストであることに悩んでいる方にとって、自分の経験や働き方に自信を持ち、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。