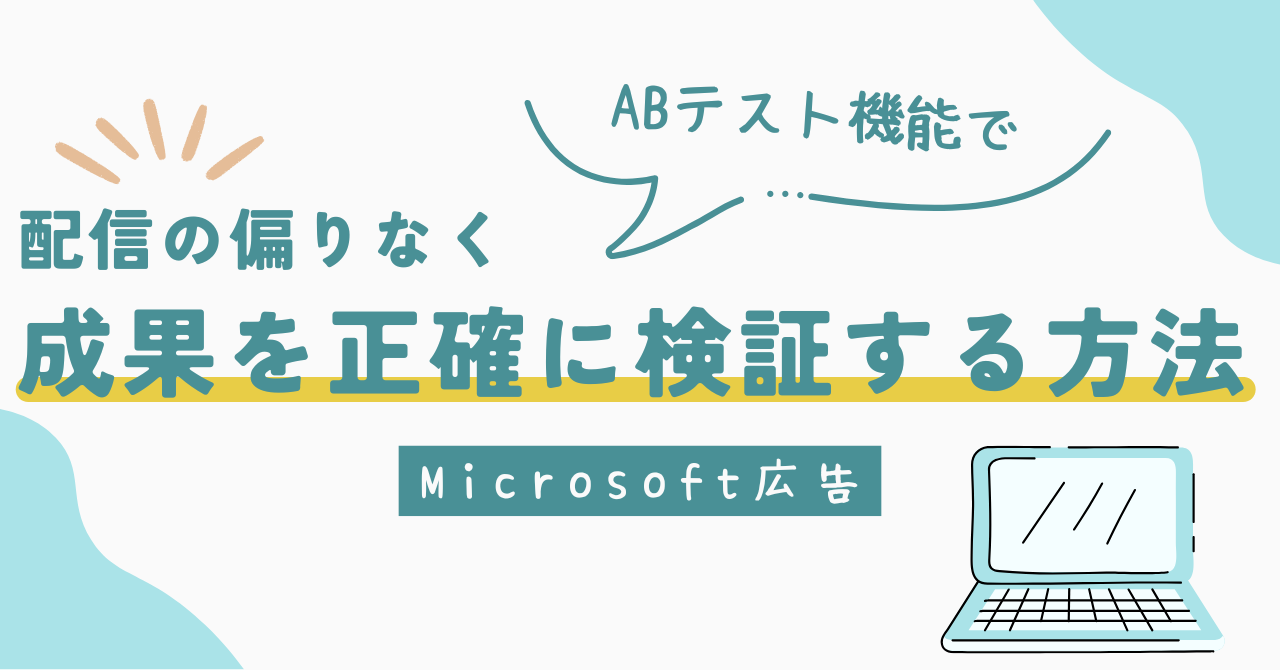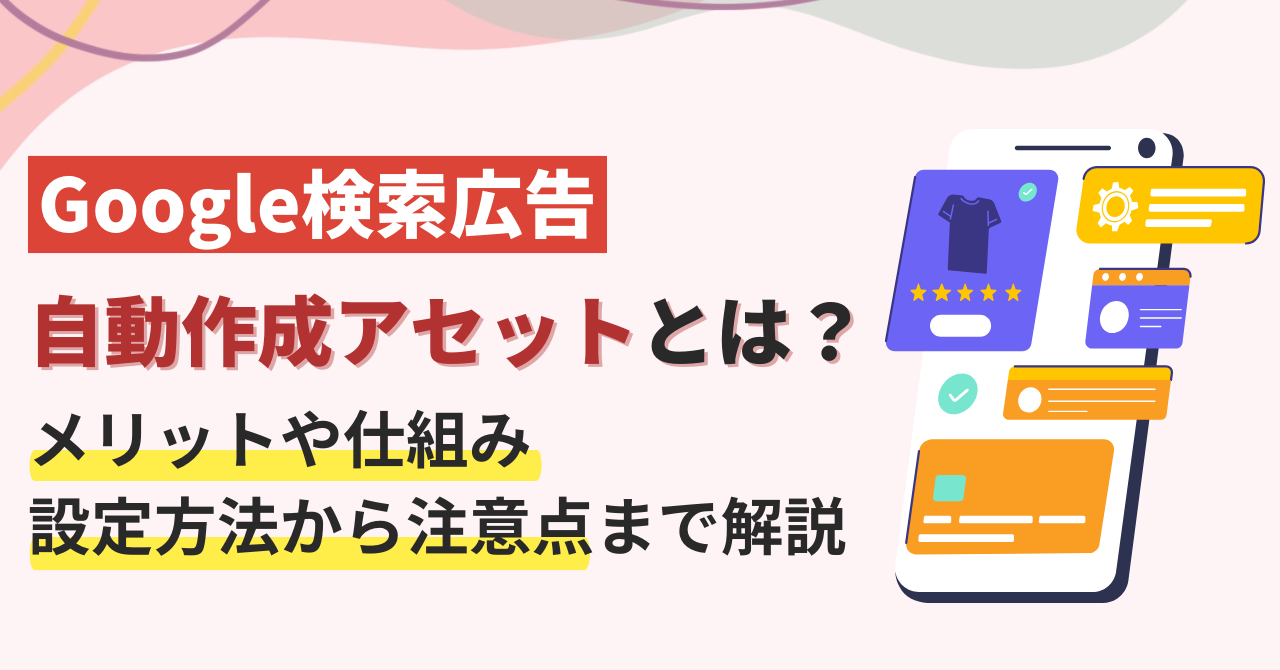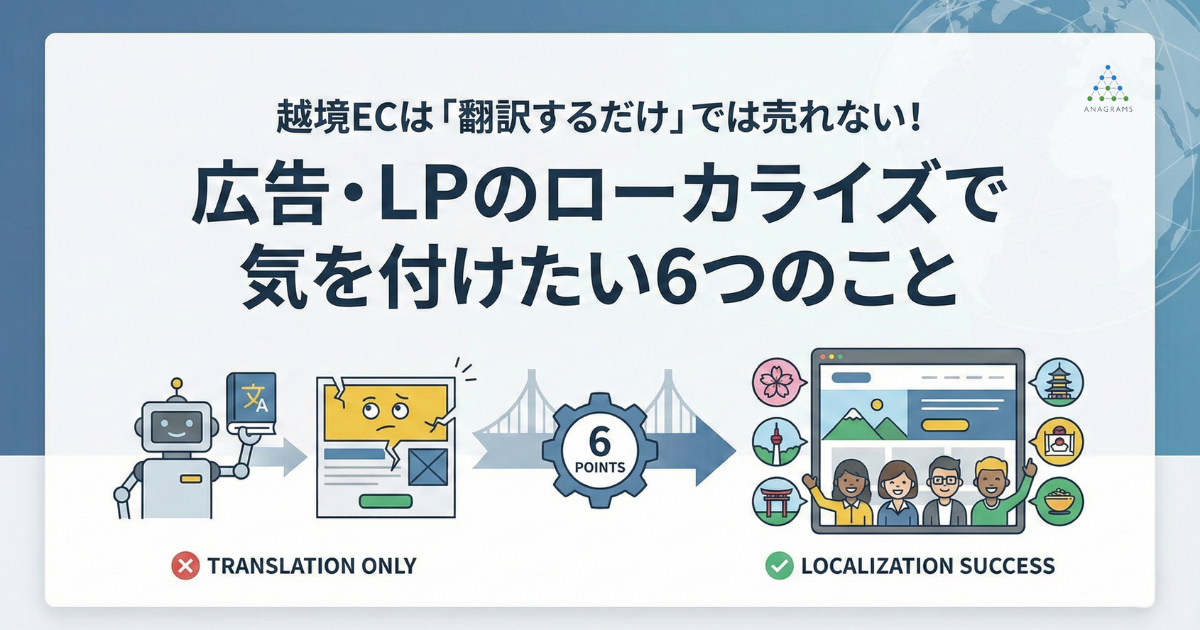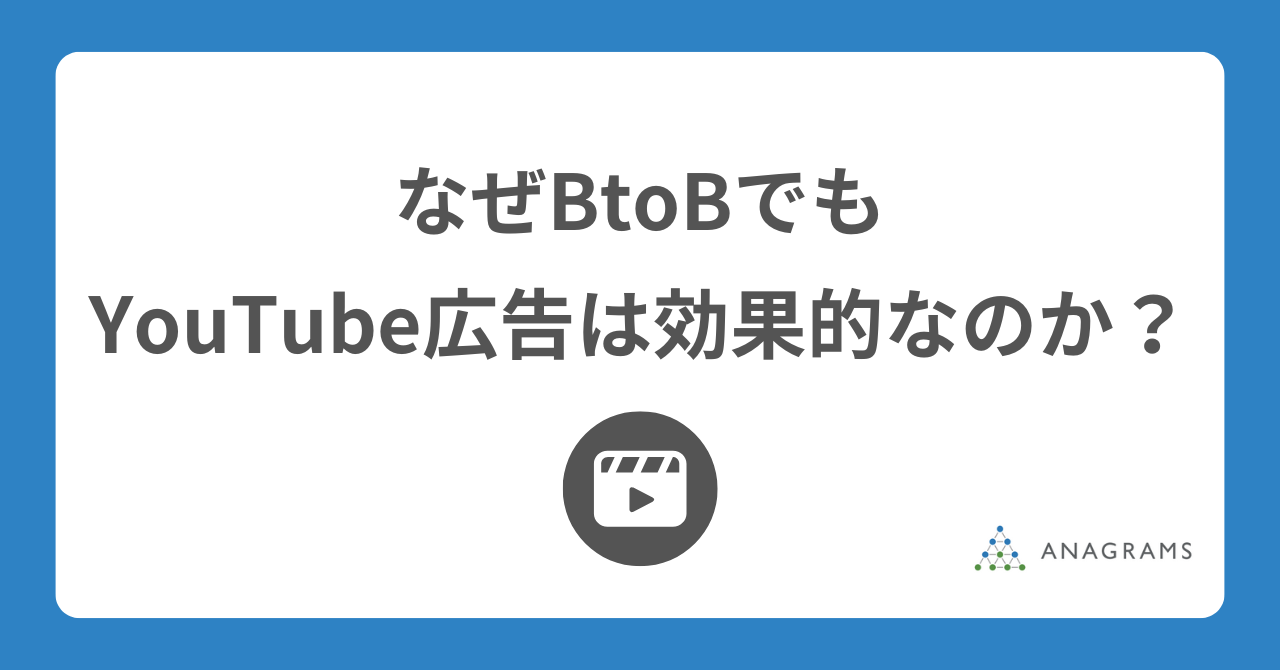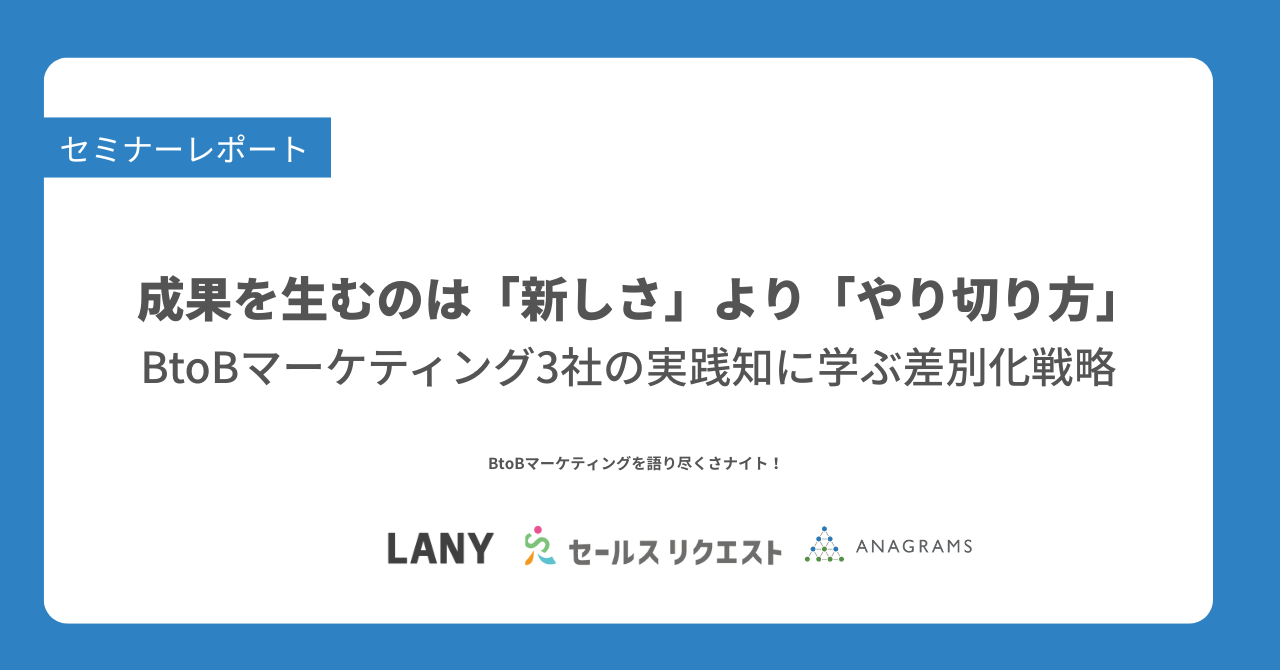
新しいマーケティング手法に次々と挑戦してはみたものの、「成果につながらなかった」「継続できなかった」と感じたことはないでしょうか?
BtoBマーケティングの現場では、AIやインテントセールス、SNS動画施策など、新たな打ち手が次々と現れる中で、"できること"が増え続けています。
しかし、実際に成果を出している企業に話を聞くと、彼らが口をそろえて語るのは、「どんな施策か」よりも「どこまでやり切ったか」の重要性でした。
本レポートでは、BtoB支援に豊富な実績を持つ3社(LANY、セールスリクエスト、アナグラム)が登壇したイベントを通して、成果を出す企業が実践する“やり切る力”の正体を紐解いていきます。
イベント概要
- BtoBマーケテイングを語り尽くさナイト!|LANY×セールスリクエスト×アナグラム
- 開催日時:2025/03/13 (木) 19:00 - 21:00
- 場所:アナグラム株式会社
- 登壇:株式会社LANY、株式会社セールスリクエスト、アナグラム株式会社


目次
新しいことより「やり切ること」が成果につながる
ーーBtoBマーケティングでは、SEOやブログ、YouTube、広告など、どの企業も幅広くオンライン施策に取り組んでいて、差別化が難しい印象です。そうした中で、2025年以降、他社と差別化しながら成果を出していくには、どのような取り組みが効果的だと思われますか?
従来の施策も見せ方を変えるだけで差がつく

新しいプラットフォームへの挑戦も大事ですが、従来の施策の中でも“見せ方”や“届け方”を工夫することで、十分差別化は可能だと思っています。

株式会社LANY 代表取締役 竹内 渓太
株式会社リクルートホールディングスにデジタルマーケティング職で新卒入社。3年間デジタルマーケティングに従事。大規模サイトのSEOを中心に、デジタル広告運用やB2Bマーケティングなど多種多様な業務を経験。その後、株式会社LANYを創業し、Webメディア・サービスサイト・データベース型サイトなど幅広いモデルのSEO改善をプレイヤーとしてサポート。現在もプレイヤーとして多くの企業のSEOコンサルティングに取り組んでいる。著書『強いSEO』(エムディエヌコーポレーション)を出版。
YouTubeの講義形式の動画だと既に他社も取り組んでおり、以前ほど再生数が伸びづらかったり、問い合わせにつながりづらくなってきたりしているといいます。そこでLANYさんでは、単なる講義形式ではなく、“朝のニュース番組風”の形式でSEO情報の配信をはじめたそうです。

15分程度の動画で、SEOの最新情報をわかりやすく伝える構成にしているんです。片手間でも見てもらえる内容にすることで、他社とは異なるスタイルを打ち出し、実際に反応も良くなっています。
YouTubeも競合が増えている中で、あえて情報番組風のトーンに変えることで、「既視感のない」体験を届けている点が印象的です。
さらに、セールスリクエストの原さんは、「経営者の思想」を取り入れた発信を行っているそうです。
経営者自身の思想や価値観の発信が個性になる

支援会社はどうしても提供する情報や手法が似通いやすく、他社との差別化が難しい側面があります。
そこで私たちは、サービス内容に加えて経営者自身の思想や価値観を発信することで、他にはない個性を打ち出す取り組みを進めています。
他社が簡単には模倣できない「人」や「哲学」の部分にこそ、ブランドの芯が宿ると考えています。重要なのは、飾らず、等身大の言葉で、自分自身の考えを率直に伝えていくことです。

株式会社セールスリクエスト 代表取締役 原 秀一
2012年にインテリジェンス、2015年に弁護士ドットコムでキャリアを積み、2019年スマートキャンプにて営業・営業企画・Bales営業責任者を経てスタートアップ企業の成長に特化したセールスリクエストを設立。2023年7月、株式会社セールスリクエストとともにAll's Groupに参画し取締役に就任。
確かにBtoBのサービス選定において、提供価値や実績はもちろん重要ですが、最終的な決め手になるのは「誰と一緒に走るか」だったりします。そのときに見える経営者自身の思想や価値観は、他にはない指針になりますよね。
特に支援会社のようにサービス内容が似てくる領域では、「この人の考え方に共感できるか」「この価値観なら安心して任せられるか」といった視点が、判断軸としてますます大きくなっていると実感します。
一方アナグラムの二平さんは、BtoCではいまや一般的な手法となったYouTube広告が、実はBtoBでも活用でき、実際に成果を伸ばしているといいます。
BtoB企業での利用が少ないYouTube広告もシナリオ次第で成果につながる

BtoBのYouTube広告では、1~2分でサービス紹介をする認知系の動画は飽和してきている実感があります。ただ、獲得を狙った広告に取り組んでいる企業は少ない印象です。

アナグラム株式会社 マネージャー 二平 燎平
BtoB中心に数十社以上の広告運用やコンサルティングを経験。前職にて中小企業向けERPのセールスやCS、マーケティングなどTheModelの全工程に従事した経験と運用型広告の知見を合わせた売上を伸ばすBtoBマーケティングコンサルティングに定評がある。アナグラム社では主にBtoB向けの支援や情報発信を担当。2024年3月に新刊「BtoBマーケティング“打ち手”大全 広告運用で受注を勝ち取る 最強の戦略 88 (できるMarketing Bible)」を出版。
既に課題を認識しており、サービスの検討をしている顕在層には短い動画でも十分にサービスの特徴を伝えて、リードを獲得できると言います。ただ、課題を認識していないユーザーに対しては、情報量が足りず、態度変容を促すには不十分で成果は期待しづらいそうです。

弊社だと5~6分の長尺の動画を使うケースが増えてきています。ユーザーが感じる悩みのシーンを提示して共感を呼び、理想の姿を見せてサービスの検討意欲を高めるなど、シナリオをしっかりと設計することで、安価にリードが取れている事例もあります。
動画のシナリオを作る前の準備段階で、アンケートやインタビューを行い、ユーザーを深く理解した上で、構成を作り込むことを徹底しているそうです。
1本の広告を作る際にも「やり切る」意識を持ち実践することが、成果を出すコツだと実感しました。

「古典的な手法」もまだまだ効果的。ただし、やり方には工夫も必要
一方で、従来から用いられている「古典的な手法」であっても、各社の工夫がみられます。
ーーBtoBマーケティングの一貫として、書籍を出版している企業も多いですよね。
認知度の向上に加えて、体系的なノウハウを持っている根拠となる効果も期待できると思いますが、出版から1年が経過したアナグラムの二平さんは、効果を実感されていますでしょうか?
前提知識がそろい、商談がスムーズに進む

書籍を出版したことで、Facebook経由でご相談がくることもあり、お問い合わせいただく機会も増えて非常にありがたいです。
ただ、リードにつながるだけではなく、商談の場面でも書籍の効果を実感しています。書籍で惜しみなくノウハウを提供していますので、商談前に情報提供が完了している状態のイメージです。ですので、商談当日は議論が活発になりやすく、受注につながりやすい傾向があると感じています。
単なる会社紹介やヒアリングで終わるのではなく、初回の商談からディスカッションが進み、一気にクライアントの期待が高まることも多いそうです。
さらに、セールスリクエストの原さんの場合は、書籍をプレゼントすることによって、商談や受注率を高められているそうです。
セールスレターに書籍を同封。受注率の向上も

通常のセールスレターを送るだけではなかなか反応を取れない企業にも、書籍を同封したレターを送ると反応率が上がったりします。
また、受注のフェーズでは、商談の最終局面では訪問商談を行い、書籍をプレゼントすると、良い反応が得られ、受注率も上がっています。
書籍の執筆リソースや出版の費用を加味しても、十分に費用対効果が合うぐらい有効活用できているそうです。
ーー古典的な手法ですと、展示会を利用している企業も多いですよね。
営業支援を行っているセールスリクエストさまは展示会の知見も豊富かと思いますが、成果を上げるために意識しているポイントはありますか?
展示会施策は即日アプローチで差をつける

展示会の施策も、当日どういう動きをして、どういう準備をするかで成果が大きく変わりますね。
従来のやり方では、多くの企業と名刺交換をするというリードをとにかくたくさん取る動きをする企業が多いですが、弊社では当日アポイントの取得に全集中しています。
展示会後に名刺を整理して、後日メールや架電でフォローしている企業が多いですが、後日になると既に他社もアプローチをしていて、競合が増えているので、反応率が悪くなるそうです。

やはり、自社が見込み顧客だと考えている顧客は、他社も同様に見込み顧客と考えている。だから、他社が入り込む前に、即日アプローチをする必要があるんです。
当日全メンバーが日程調整ツールをその場で開けるように準備して、少し会話をして、ターゲットだとわかれば深掘りのヒアリングをせずに、まずは日程調整を打診するようにしています。この方法で圧倒的にアポイントの獲得率を高めることができましたね。
他社も狙っているであろう見込み顧客に、いかに先手で入り込めるか。「日程調整ツールをその場で開けるようにしておく」というのは一見地味ですが、泥臭いことを“やり切る”ことが、古典的と言われる手法でも大きな差別化や実際の効果に貢献していることがわかります。

新しいテクノロジーは、活用場面の見極めが鍵
ーーテクノロジーの発展や新たなサービスの登場により、他社と差別化する施策もあると思いますが、直近活用している新しい施策はありますか?
ニッチなニーズを狙う「インテントセールス」

近年だと、インテントセールス(※)が流行っていますね。
※インテントセールスとは、顧客の購買意欲や関心を示す「インテントデータ」を活用し、購買意欲が高まったタイミングを捉えてアプローチする営業手法

インテントデータをうまく活用できているケースだと、狭いニーズ、狭いワードを狙っているサービスですね。
例えば、「オフィス移転」というワードを使っている企業は、十中八九オフィス移転を検討している企業ですよね。ワードから特定のニーズを絞り込めるサービスだとピンポイントに顕在層にリーチできて、相性が良い傾向です。
流行している手法だからといって、むやみに取り入れてもうまく機能しないことも少なくありませんよね。重要なのは、「自社のサービスとその手法がなぜ相性が良いのか」を見極めたうえで活用すること。
インテントセールスも同様で、特定のワードがそのままニーズに直結するようなサービスであれば、ピンポイントに顕在層へリーチでき、大きな効果が期待できます。
AI活用による業務効率化
また、新しい技術では外せないAIの活用にも各社の工夫がみられました。
ーー近年のトレンドですと、ChatGPTをはじめとしたAI関連のプロダクトが増えている印象です。現場ではどのようにAI活用を行っていますか?
複数人で分担していた作業が一人でできるように

ある程度型のある業務はAIで自動化することで、昔はプロジェクト単位でやっていたことが、個人単位でもできるようになりましたね。
例えば、CXOレター作成の場面で役立っているそうです。従来は、競合のサービス洗い出して、ユーザーインタビューやアンケートを実施して、レター作成を行うという作業を複数人で分担して、各フェーズに時間をかけたそうです。

今では、AIで競合のサービス洗い出して、インタビューのスクリプト作成やレターの作成まで自動化できています。人が行う作業はインタビューの実施とレターの推敲くらいです。
圧倒的に作業が効率化しましたね。
データの処理や分析、定型作業などAIの得意分野を見極めて、人力による作業の効率化を実現されていると言います。

弊社でもAIを活用して、リサーチが早くなりましたね。
広告代理店などの支援業の場合、色々な案件を担当するケースが多いですが、最初のキャッチアップのスピードは各段に早くなりました。
リサーチの効率化によって空いた時間で、アイディアを考える時間を増やせたり、クライアントと週次で定例を行い議論を深めて、施策を素早く回す体制を作れています。
現場のメンバーの中にもAIを使いこなせているメンバーとそうでないメンバーがいるそうです。実際にどういった作業をAIに任せられるのかを伝えて、メンバーがメリットや使い方を理解することで、現場でも徐々に浸透してきていると言います。

まとめ
これまで私は、「他社と差別化するには、いち早く新しい施策を取り入れることが重要だ」と思い込んでいました。ですが今回のイベントで印象に残ったのは、むしろ既存の施策をどこまでやり切れているか”が成果を左右するという現場のリアルでした。
SEOや広告、展示会、書籍、動画など、一見ありふれた施策でも、届け方や設計を工夫し、愚直にやり抜くことで、他社と大きく差がつく。 その姿勢こそが、BtoBマーケティングの本質なのだと気づかされました。
一方で、インテントデータやAI活用のような新しいアプローチも、流行に乗るのではなく、“自社にとっての意味”を見極めたうえで使いこなす姿勢が必要です。
「新しさ」よりも「やり切り方」この視点を持つことで、日々のマーケティング活動がもっと骨太なものになるはずです。
イベントで得た示唆を活かし、自身の関わる案件でも改めて“やり切れているか”見直していこうと思います。
今後、開催予定のセミナーはこちら