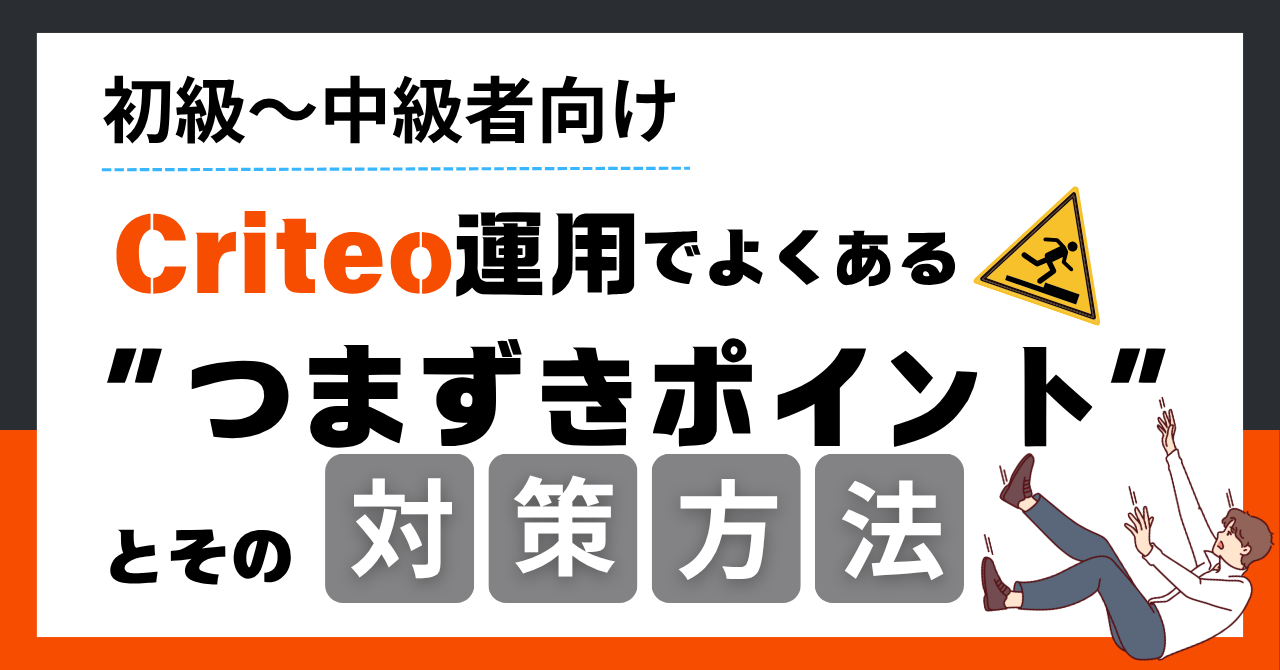みなさんはCriteo配信開始してから、定期的にデータフィードの中身を見直ししていますか?配信開始したら運用調整がメインで、データフィードの変更は場合によっては費用もかかり、なかなか改修が難しいというケースも多いと思います。
Criteoをはじめとするデータフィード広告は、データフィードを基にクリエイティブが自動で生成されるのでクリエイティブ検証が不要と思われがちです。しかしながら、一般的なディスプレイ広告と同じように、データフィードの中身を変更しクリエイティブに表示される要素の検証が効果改善には非常に有効です。
この記事では、Criteoのデータフィード改修におけるポイントと、具体的に見直していただきたいポイントをご紹介します。Criteo配信中であれば、ぜひCriteoフィードをお手元にご準備いただきチェックしてみてください。


目次
Criteoのデータフィードとクリエイティブの仕組みを理解しよう
Criteoデータフィードを見直ししていく上で、まず覚えておいていただきたいポイントについて解説していきます。
各データフィード項目が何に使われているか把握しよう
Criteoデータフィードの各項目は大きく2つの役割に分かれます。
- クリエイティブの表示に利用する項目
- エンジンの学習に利用する項目
※big_image・image_linkはadditional_image_linkを利用する場合のみエンジン学習に利用されます。
クリエイティブの表示に利用する項目は、クリエイティブが生成される際に表示に利用されます。ここで注意したいのがデータフィードの仕様と表示される文字数は同じではないという点です。文字数以外にも表示してみると意外と小さかった、重要な情報が途切れて表示されているということもありますので、定期的にクリエイティブの表示内容は確認しておきたいですね。
エンジンの学習に利用する項目は、どのユーザーへ高く入札するかや、どの商品をクリエイティブでレコメンドするかを判断する、重要な役割を果たしています。そのため、できる限り多くの情報を入れておくことがCriteoで効果を最大化していく上で非常に重要です。特に「商品のカテゴリ」関連の情報は抜けがちなため、必ず設定しておきたいポイントです。
実際のクリエイティブで表示される範囲を知ろう
実際のクリエイティブを見てみると、データフィードの規定に対して表示される文字数が少なくて驚きますよね。そのため、最終的なクリエイティブの表示文字数を認識した上で、データフィードを構築することは抜けがちなポイントです。
title(商品名):18文字程度
discription(説明文):24文字程度
※表示サイズやレイアウトにより異なります。
※主要サイズやネイティブ枠を参考にカウントしたものとなります。
表示頻度も考慮して構成を決めよう
Criteoのフィード項目のすべてがクリエイティブに表示されるわけではなく、掲載される場所やフォーマットによって表示される頻度が項目ごとに異なります。
たとえば「discription」は省略されやすい項目のひとつです。そのため、ユーザーに見てほしい情報をdiscriptionだけに入れてしまうと、表示の機会自体が得られない可能性があります。
一方でバッジエリアは表示頻度の高い「画像」とセットで表示される機会が多い傾向です。そのため、重要な情報を含めるのに向いている項目のひとつです。
このように、ユーザーに必ず見て欲しい情報は、省略されずらく表示頻度の高い項目に含めるのが大切です。
Criteoのデータフィード見直しにおける4つのポイント
Criteoのデータフィードは項目も多いため、どこから見直しすべきか迷ってしまいますよね。今回はCriteoのアップデートも加味し、4つのポイントに絞ってご紹介しますので、まずはこの項目だけでもチェックをしてみてください。
①カテゴリの見直し
データフィードにおいて、カテゴリ情報を詳細に設定することはとても重要です。詳細に設定することでユーザーがどのような商品に関心が高いか、学習可能な情報の粒度がより詳細になります。それによって、入札ではCTR・CVRの高いカテゴリをより詳細に捉えられ入札調整に活かしたり、レコメンドではユーザーの詳細な興味関心を反映した商品をバナーで表示することが可能となります。
カテゴリ情報はデータフィードの中で設定することができ、1商品に対して3カテゴリまで指定可能です。最大3カテゴリまで指定可能ですが、1カテゴリまでしか設定されていないケースや、3カテゴリまで指定されていてもユーザーの興味関心を捉えられるカテゴリ構成となっていないケースがあるため、是非見直してほしいポイントです。
例えばECアカウントの場合1カテゴリしか設定していない場合、ユーザーはどのカテゴリに関心があるかまでしか情報を得ることが出来ません。しかしカテゴリ3つ全て設定することで商品カテゴリ以外のユーザーの関心をカテゴリから読み取ることが可能です。
見直し方法はECとそれ以外の業種で異なるので各業種に合わせてご確認ください。
- ECの場合
「product_type」のカラムの内容の見直しを実施してみてください。3カテゴリ記載する際は「>」の記号で区切る対応が必要となります。
例:メンズ > ブランドA > トップス
- EC以外の場合
「categoryid1~3」のそれぞれのカラムの内容の見直しを実施してみてください。
②additional_image_linkの活用
additional_image_linkはデータフィードに追加可能な項目で、メイン画像以外にも複数の画像データを持っている場合に利用可能です。最大10枚まで設定可能で、画像URLを,(カンマ)で区切って記載します。
additional_image_linkを追加することで以下の2機能を利用することが可能となります。
- Image Optimization機能
- 広告フォーマット“Collection”が利用可能
Image Optimization機能はadditional_image_linkとメイン画像の中から、ユーザーの関心に合わせてより最適な画像を自動で選定してくれる機能です。この機能はadditional_image_linkを設定するだけでなく、CRITEO社へ利用開始の依頼が必要です。この機能はadditional_image_linkがすべての商品に入っていなくても利用が可能です。メイン画像以外に設定した画像を、配信に利用しても問題ない場合は是非こちらの機能をONにしてみてください。
広告フォーマット“Collection”は、1つの広告フォーマットでメイン画像とadditional_image_linkに設定した、上位3つの画像を表示できる広告フォーマットです。この広告フォーマットは全ての商品でメイン画像とadditional_image_linkが3つ以上記載されている必要があります。広告フォーマット追加にはCRITEO社への依頼が必要なので、条件を満たしている場合は是非検証してみてください。
③バッジエリアの活用
title・discriptionに入らないが、表示頻度の高いエリアで訴求したい内容はバッジエリアの利用がおすすめです。バッジは大きく分けてエクストラバッジとディスカウントバッジの2種があります。
エクストラバッジは作成した画像をデータフィードに画像URL形式で記載し、バナーへ表示させる機能です。こちらの機能は比較的多くのアカウントで実装されていますがディスカウントバッジは割引率を表示するアカウントでは利用率が高いですが、それ以外のアカウントではあまり利用されていないエリアです。
実はディスカウントバッジエリアは全角2文字程度のテキストを表示することが可能です。しかもデータフィードにテキストを記載するのみで、全角2文字でも「人気」「NEW」「新着」「注目」など記載できる情報が多くあります。是非ディスカウントバッジエリアを利用していない場合は活用してみてください。
④エクストラテキストの活用
文字数が多くあったり、パターン数が多く画像を用意できない訴求がある場合は、エクストラテキストエリアの活用がおすすめです。
こちらはデータフィードの仕様書の下部にしか記載がなくあまり広く知られていないデータフィード項目ですが、表示頻度の高いエリアへのテキストの表示が可能です。特におすすめなのは赤枠のデータフィード項目です。例えばECであれば口コミ件数・お気に入り件数・ポイント還元内容を記載するのに最適です。
最後に
Criteoに限らずデータフィード広告の改善において、データフィードの見直しは非常に重要です。また検証する上では、変数を出来る限り少なくし、期間を空けて進めていくことも重要なので、頻繁なデータフィードの見直しができる環境が理想的です。
また、現在のデータフィードに記載されている内容が全てとも限りません。実は開発すればマスターデータ(データフィード成型前のデータ)に出力できる情報がある可能性もあります。データフィードは商品数を多く扱うWebサイトにおいては大きなデータの財産です。是非この機会に最大限データフィードに出したい情報と、マスターデータの記載内容も見直ししてみてください。