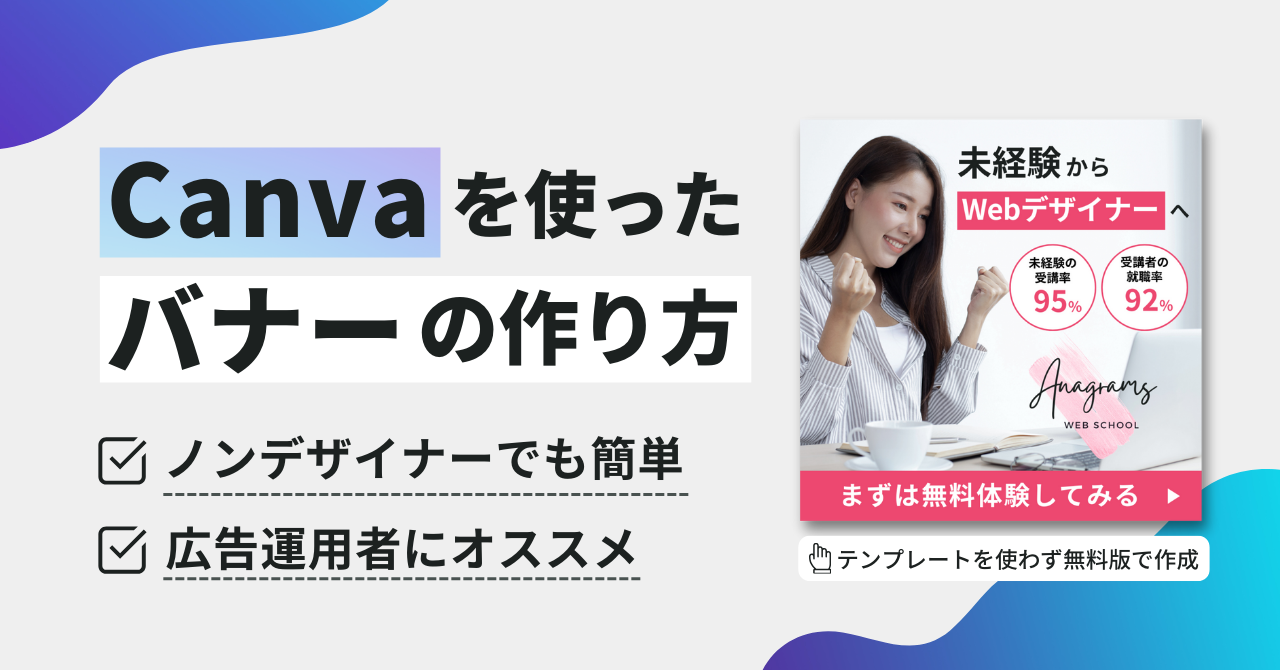アナグラムでは限りなく本質的な仕事のみにエネルギーを集中するために、現場から排除すべき事象はなるべく排除するように心がけています。それが小さな組織が限られたリソースで持続的成長を続けられる最低条件とも思っております。
少々手前味噌ではございますが、タイトルの「小さな組織、限られたリソース、それでも持続的成長が可能な強い組織」を「アナグラム」に置き換えて執筆しています。少人数組織・中小企業に関わる方にとって少しでも参考になれば幸いです。
 |
 |
|---|---|
 |
目次
アナグラムにないもの
朝礼・終礼・必要のない会議
会議は必要なときに最短の時間で行います。アナグラムの現在のオフィスはドアや壁で閉ざされた会議室がないワンフロアです。そのため、中央のスタンディングテーブルで立ちながら5分だけ話す・デスクで数分だけ話すなどオープンでスピーディなディスカッションが目立ちます。
また、出社時間をある程度選べる少しだけフレックス制を導入していることにより朝礼は困難です。これは夜型のメンバーや、幼稚園の送迎などに始まるさまざまなライフスタイルを持ったクルーが集まっているために始まった制度です。
更に、ほとんどの案件を常に2名以上のチーム体制で動いていたりするので、チーム間でのコミュニケーションは常に取れています。そして、この人数で組織のミッション・ビジョン・バリューなどは共有できていると考えているので毎日の朝礼・終礼を現時点では必要としていません。
組織の許容を超えた無理な採用活動
組織の急拡大が必要なケースでは、やむを得ず採用活動を中心に動かないといけないこともあるでしょう。しかしながら、自らの許容を超えた無理な採用活動は、現場に不要な歪を与え、結果的にクルーらにストレスを与えてしまうことがあります。結果的に周りからの見た目よりも激しく戦力を蝕むトリガーになりかねません。
※意図しない不要なコンフリクトは必要ない、というのが私達の今の時点での経営判断です。恐らくそれは近いうちに必要不可欠になるかもしれませんけれども。
いつも、「ちょっと足りてなくて、新しい仲間が欲しいな」と現場のメンバーが思っているくらいがきっとちょうどいいのです。※よく新卒採用支援の営業電話をいただきますが、上記の理由から現状では表立った新卒採用の実施は時期尚早という判断を下しております。
個々人へのノルマ、キャパオーバーな仕事、利益相反
アナグラムには個々人に対する営業・売上に関するノルマが一切ありません。個々人のノルマがあると、どうしてもその達成に躍起になり、結果的にクライアントを幸せにしない選択肢を選んでしまうメンバーを生み出しかねません。そういった構造・状況を絶対に作らないためにも個々人への売上ノルマ設定や、特定のメンバーに仕事が集中することを意識的に避けています。
※もちろん、向上心のあるメンバーは個々人で、半年でここまでクライアントのビジネスを伸ばそう!だとか、運用できる数を増やしたい!・提案の幅を広げたい!という目標を持ちながら働いています。経営指標として重要なKPI・数字は財務責任者や成長のための統括責任者が見て管理していくべきものと考えています。さらに言えば、個々人の営業利益は評価軸のたったひとつの要素でしかありません。
休めない空気・帰れない空気・付加価値のない残業・定例飲み会
これらはなかなか難しいかもしれませんが、本質的ではない疲労をクルーに蓄積する原因になりかねません。古参のクルーから率先して「文化」を醸成していくことが重要です。皆さんそれぞれの人生・家庭・夢があります。夜はカフェで勉強したい人も、お子さんと食卓を囲みたいお父さん・お母さんもいるでしょうからその気持ち・時間を大切にしてほしいと思います。
そして、会社(オフィス)に居ない時間帯こそが、その人のユニークかつ新しい「ボキャブラリー」を得るチャンスであり、そのボキャブラリーの豊かさを我々は非常に大事にしています。これが広告・マーケティングの成功につながることが少なくないからです。
※もちろん、クルー同士のコミュニケーションも大切だと考えているので、お昼はなるべく2人以上で外で食べることが多いですし、勉強会がある毎週木曜日には社内全員でお弁当(福利厚生)を食べてコミュニケーションをとっています。
アタマを使わない作業・時間
クライアントのミッションを達成し続けるための本質的な活動に、可能な限り最大の時間と体力を割きたいものです。誰がやっても解けない問題・Excelとの格闘に多くの時間を費やすのは褒められたことではありません。
- レポートや繰り返しの作業などはフォーマット化を進める
- もっと良い方法がないか?を常に考える
- 有益なインプットを怠らない
これらをチーム単位・クルー個々人単位で意識しています。フォーマット化やプログラミング技術に長けたクルー・パートナー企業が「自分のアタマを自由に使える時間」を増やしてくれていることに感謝しなければなりません。
アナグラムにあるユニークなものは?
全員参加の週1グロースハック(勉強会)でのオープンなノウハウ共有
週に1度、最先端のノウハウを共有するグロースハックという名の勉強会を全社で行っています。
古参クルーはファシリテーション・プレゼンテーションといった学びを提供するアウトプットの機会を。入社から浅いクルーは多くのインプットと多様な業種・ビジネスモデルに触れる機会を仕組化し、半強制的に導入・運用しています。
「グロースハック」は世間一般的にはビジネスやサービスの成長のための試行錯誤と捉えられています。
「ビジネスの継続的な成長(グロース)×IT、WEBにおける高い技術力による仕組化(ハック)」
※とても好きな表現でしたので引用させていただきました。((出典)http://exidea.co.jp/growth-hack/
我々の組織では、題材となるクライアントのビジネス(サービス)・そして我々組織(クルー)の成長を意図しているので、やや広義な「グロースハック」です。組織内での情報非対称性(ノウハウの差)を少なくし、自身の所属するチーム以外の成功体験に限らず、失敗体験をも知ることで自分ごと化することにより、限られたリソースの中で最高のサービスが提供できると確信しています。
全員合意の採用制度
なるべく社内全員で採用活動に関わっていこう!というのが「持続的成長」を支える考え方です。面接には現場のクルーも多く同席しますし、最終面接を通過した方とは入社前に複数名のクルーと食事会をしたりしてお互いに気持ちよく働くことができるか?どういった役割・働き方をされたいか?を確認します。ミスマッチを可能な限りゼロに近づけるための取組です。
また、一般的な新卒採用を行わずに長期インターン制度を導入しているのもここに通じる信念があります。新卒入社希望の方(そう言っていただけると本当に嬉しいです)もまずはインターン生として勤務していただき、仕事内容や組織のスタンスを理解・納得した上で正社員として入社することを選択できる環境であれば、私たちも学生の皆さんも必ず幸せになれると考えています。
レベルの高い作業環境・早く仕事が終わる工夫
疲れにくい椅子、ハイスペックなノートPC(VAIO ZやVAIO Pro)マルチモニターを積極的に導入し、多くのスタッフが3画面で仕事しています。多くのツールを並行してログイン・使用するシーンで役立ちます。座り仕事が大半を締めるため、腰にかかる負担は可能な限り避けなければなりませんし、PCのスペックによるストレスはほぼありません。
休みたいときに休める!各種福利厚生制度・半フレックスな出社時刻
- 各種福利厚生制度
- バースデイ休暇
- パートナーバースデー休暇
- お子様バースデイ休暇
など、きちんと休める文化を作るための休暇制度を作っています。※上記に含まれていない福利厚生制度も数多くご用意しています。
- 出社時間をある程度選べる少しだけフレックス制な出社時刻
- 9時-18時
- 10時-19時
勤務時刻もライフスタイルや公共の交通機関の混雑状況を加味して出勤が可能で、現時点では上記2パターンの勤務帯が存在します。これは、子供の幼稚園の送迎を行いたい、という要望から生まれた制度で、今後もこの選択肢を積極的に増やしていきたいと考えています。
基本的に2人以上の体制でクライアントをサポートする仕組みもあるので、お休みは柔軟にとれるようになっています。当然ですけど有休取得も、いつとるのかも個人の自由です。平日どちらかが急に休んでいても滞りなく進みます。それが最低限の仕事ですからね。
その他、あらゆる変化への許容
さまざまな面で変化の激しいこれからの時代は、変化できるものが生き残ると信じています。制度やシステムは厳格に決めるよりも、変えるべきときに変えることを受け入れるべき、つまりしっかりと”運用”することの方が重要だといえます。
まとめ
1日のうち、判断・意思決定に使うエネルギーは限られていると思うのです。
FacebookのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏は以前、「なぜザッカーバーグ氏は、毎日同じTシャツを着ているのか」という質問に対して、毎日着るものについて「エネルギーを使うのは無駄」と回答しています。ザッカーバーグ氏は普段、グレーのTシャツや黒のトレーナーを着ており、過去には、「全く同じTシャツを20枚も持っている」と明かしています。米国のオバマ大統領、スティーブ・ジョブズも同様の信念を貫いています。
参考:The Huffington Post 「Facebook CEOのマーク・ザッカーバーグ、「なぜ毎日同じTシャツを着ているのか」に答える」
メンバーに「毎日同じ服を着よう!」とは言いませんが、この「意思決定エネルギー」の考え方は組織運営にも活きる部分があると思っています。余計なルールや定例会議を作りすぎないこと、迷ったらなるべくシンプルにすること。頭を使うべきポイントで頭を使えるような働きやすい環境を作り続けることをモットーにしています。