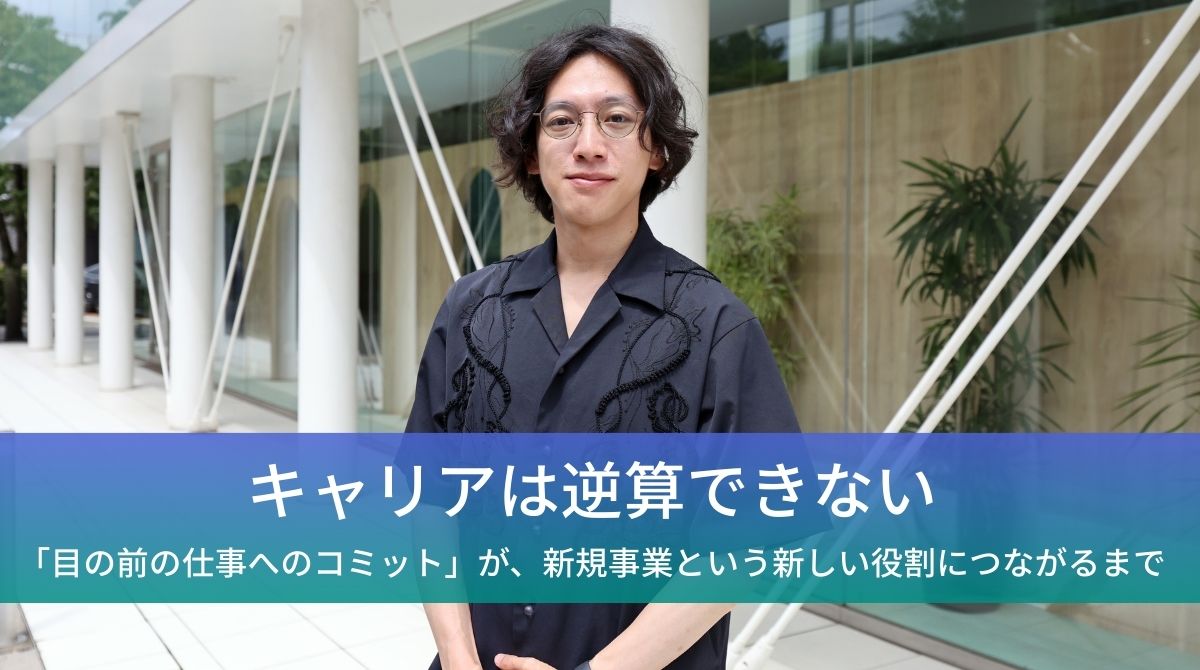”負け盤面”ほど燃える!?ネガティブな状態=チャンスだと思うようになった原体験
ーーー入社当時、嵯峨山さんは未経験者としての入社でしたよね。前職までは営業・マーケティング支援を経験されてきたそうですが、当時の仕事内容について詳しくうかがえますか?
1社目ではMR(医師や薬剤師の方々に医薬品情報を提供する営業職)として、薬の提案営業をしていました。他社と同じ薬を扱っているので、選んでいただくためには営業の仕方で差を出すしかなくて、とにかく泥臭く行動した記憶があります。
そもそも製薬業界には「薬の説明資料は勝手に抜粋したり順番を入れ替えたりしてはいけない」みたいな特有のルールや制約も少なくないんですよね。工夫することがタブーになってしまいかねない環境で、自分なりの工夫をどう発揮するか最初は苦労しました。
ただ、「決済者が誰か」とか、「その人は何に心を動かされて最終決定するのか」とか、そういうことに考えを巡らせて戦略的に行動するようになってからは、仕事がすごく面白くなったんです。

アナグラムに入社してから「メンタルが強い」と言われることがあるんですけど、たしかに自分は上手くいかない時期も「落ち込まない」どころか、むしろ「燃える」タイプかもしれません。最近過去を振り返ってみて、この1社目のころの経験が「負け盤面ほど燃える」と思うようになった原体験になっている、と気づきました。
ーーー原体験、ですか?
はい、当時自分が前任から担当を引き継いだタイミングでは成果が出ていなくて、まさに逆境というか、マイナスからのスタートでした。医者の先生と話をしに病院まで行ったところで、最初は話すら聞いてもらえないのが普通だったんです。
そこでまずは、毎日病院に通って受付の方と仲良くなることにしました。受付の方に顔を覚えてもらえれば、口利きしてもらえるだろうと考えてのことだったんですが、実際、格段にスムーズに話が進むようになって。先生が講演会へ移動する新幹線で隣の席に座ってコミュニケーションを取り、まるで秘書のように立ち回っていた時期もあります(笑)

先生本人でなく、あえてご家族のニーズに応える働きかけをした結果「家庭内で立ち回りやすくなって助かる」と喜ばれ、それまで忙しくて話せないと断られていた先生と面談できるようになったこともありました。
先生の研究領域を調べて海外の最新論文を取り寄せ、学術的な観点から情報提供をしたこともあります。意外と他のMRがやっていない切り口だったこともあって、とても喜んでもらえたんです。
手応えがある度に、与えられた状況の中で最大限工夫して成果につなげることの面白さを感じましたね。
最終的に成果が社内でも表彰されて、気が付いたら「ネガティブな状態こそチャンスなんじゃないか?」と捉えるようになっていました。”まぐれ”じゃなくて”自分の行動が引き寄せた”と実感するために「逆境はむしろ都合が良い」とまで思うようになったんです。
ーーーピンチも楽しめるマインドはそのころから変わらないのですね。では、そこからどのような経緯でアナグラムへの入社に至ったのでしょうか?
その後アナグラムに入社するまでの2社では、それぞれ未経験の領域に挑戦しました。当時は経験を活かしながらも専門範囲を広げたかったんです。
営業から少し軸をずらし、2社目では店舗ビジネスのプロモーションを担当したり、3社目で新規事業の立ち上げやECのコンサルを経験したりもしました。実はこの頃、広告運用にも触れる機会があって、アナグラムのことも知っていたんですよね。
当時は新しい学びがある度に関連する別の領域に興味を持ち、それをメインに深ぼるために転職を続けていました。ただ、分業だとどうしても最後まで伴走できないことがモヤモヤしていて。それでいつからか「まるっと自分の裁量で、クライアントのビジネスを伸ばせる場所に身を置きたい」と強く思うようになりました。
その後、アナグラムを「営業から運用まで、一気通貫で担える”絶好の場所”だ」と認識してから、実際に応募するまでは早かったですね。

「自分は無知」ならば、打席に立たないことは損でしかない
ーーー入社時点で社会人としての実績があると「いち早く成果を出さなければ」と気負ってしまうところもありそうです。何か嵯峨山さんが意識してきたことはありますか?
入社前から「1年は上手くいかないだろう」とか、「アナグラムで活躍するには数年かかるだろう」とか、ある程度の負荷がかかる心の準備はしていたつもりでした。それでも想定以上に周りに圧倒されて、自分をちっぽけにしか思えない時期もありましたね。
だけど完全に折れることはなかったんです。前職までに未経験領域でも成果を出してこられた自負があったし、「愚直にやっていればきっとできるようになる」という自分への信頼はあったので。
あとなにより「自分は無知だ」と思ってやってきたことが、かえってエネルギーの源になってますね。
ーーー「無知」という自己認識が、エネルギー源になる…というと?
これは仕事に限らずですけど、世の中にはまだ自分が知らないものがいっぱいあって、それを知っていくのが純粋に楽しいんです。もちろん成果にこだわるのは大前提ですが、自分はその過程で「出来ない」が「出来る」に変わっていくことも楽しめるタイプというか。
でも「自信がない」のとは違います。これまでに積み重ねてきた自負と同時に、まだまだ成長できるぞという伸びしろの感覚も常にあるというスタンスです。無知だからこそ「どうやったら失敗するのか、どんな施策なら成功するのか」といったデータを十分に集める必要があるし、そのためには相応の時間がかかるだろう、と割り切っていたんですよね。
入社前から「早くチームリーダーになって、その景色をみたい」とは思っていたので、当然そのためには現場で着実に成果を出さなければならないと覚悟を決めてました。

ーーーなるほど、最初から長い時間軸を見込んでいたんですね。嵯峨山さんはあらゆる経験やフィードバックをレベルアップの材料にしているのが印象的です。現在のように道を切り拓けるようになったきっかけや指針があれば教えてください。
経験を積むうちに自然とそうなったところもありますが、象徴的だったのは、前職の3社目の時に上司からもらった「仕事をRPGのように楽しめ」というアドバイスかもしれません。「自分が社長だと思って、他の人を動かせ」と言われたんです。
RPGには0からレベルを上げていく要素や、”この人に話をきかないとストーリーが進まない”などのギミックがありますよね。それで振り返ってみると、1社目の製薬業界という制約の多い環境の中でも、あの手この手で状況を変えようと立ち回って成功体験を得た経験と、この言葉がつながる感覚があったんです。
図らずも「当時から自分はRPGさながらに状況を切り拓いていたんだ」と気づいたら、この言葉がスッと自分の腹に落ちた気がします。そう思えるようになると、悔しさや多少の理不尽、意見の食い違いなどは全部、よりよい関係値のための必要なイベントやレベルアップの材料でしかないんですよね。
ーーーそのマインドは、アナグラムでは実際にどのようなアクションに落とし込んできましたか?
まずは、深く理解するためにたくさん質問することですね。上司の考え方を学びトレースするために質問は欠かせないですし、クライアントに対しても必要に応じて質問を重ねなければ、相手の意図を正確に汲み取った“よい支援”はできないと考えたからです。
迷わず手を挙げ続けることも徹底しました。アナグラムは挑戦を歓迎してくれる環境で、当時の上司の方針もあり、失敗も許容しながら信頼して任せてもらえたんです。だからこそ、やれることはすべて試してみようと思えました。
上司とも相談して入社から1年以内に全媒体の提案や運用を経験すると決め、4か月ごとにマイルストーンも置きましたね。選り好みやこだわりを持つよりも、とにかく機会を引き受けることを第一にしてきたんです。

「他の人と同じことをやっても差はつかない。クライアントには成果や貢献で返さなければ意味がない」とは1社目のころから思っていたので、社内で失敗談として共有された施策も含め、誰かが試したことは一通り自分でも実践するようにしてきました。
もちろん案件ごとの状況を考慮した上でですが、”無知”の前提で考えたら「自分の案件ならむしろ上手くいくかもしれないし、やってみないとわからない」ですからね。何よりも避けたいのは、やらずに見過ごす機会損失のほうなので。
自分で自分の可能性を閉じ込めない人は、何度でも再スタートできる
ーーーアナグラムは自社売り上げのノルマを設けていない分、クライアント目標の達成や成果を出すことへのコミットが強い環境ですよね。自分なりのKPIとして、クライアントの売り上げ拡大はもちろん「先方担当者の出世」などを置いている人もいますが、嵯峨山さんにとってのKPIはありますか?
担当開始から1,2ヵ月以内で新たな案件の紹介をもらえるようになろうと思っています。
アナグラムには、半期に一度お客さんにお願いしている「顧客満足度調査」がありますよね。あのアンケートに回答いただける、というのもある種の肯定的なアクションですが、紹介はさらにその上を行く、信頼関係の最高到達点だと思うんです。
自分が複数の案件を続々と紹介してもらえたのも、2年目に3~4社を一気に担当して成果が出せた時期だったので、とても印象に残っています。
ーーーグンと伸びる人はブレークスルーポイントを経験することが多いですが、嵯峨山さんにとってはまさに当時がその時期だったのでしょうか?
はい。やはり、新規で3〜4社を同時に担当し、一気に成果を出せたことが大きな転機でしたね。とにかく数多くトライして、上手くいく条件や失敗につながりやすい状態などのデータを蓄積していくなかで、「こうするとこうなる」という感覚が掴めてきたんです。その土台があったからこそ、機会を最大限に活かせたんだと思います。

周囲の人から学ぶことも多かったですね。自分の思考や視野の外にある選択肢は、チームリーダーやマネージャーから学びましたし、部下を持った今は、部下の考え方からも気づかされることがあります。
特に実感しているのは、「適した寄り添い方は人によって違う」ということです。たとえば自分は大きな方向性だけ示されるほうが進めやすいタイプですが、人によってはもう少し細かなステップや具体的なイメージを伝えた方がかえって動きやすい場面もある。
ある部下に「想像で答えるクセ」を感じたときは、「思い込みが可能性に蓋をすることもある」と納得しやすいように、実際に起きた「想定と現実のズレ」をチームで共有し合う時間を週1で設けました。
複数の視点から振り返ることで本人にとっても気づきにつながりますし、自分にとっても部下の考え方をより深く知る助けになっています。
ーーーどの時期のエピソードからも、人に興味を持って働きかけてきたのが伝わってきます。最後に、嵯峨山さんは「どんな人と働きたい」と思いますか?
やっぱり、“頭でっかちにならず行動できる人”、ですね。
変に「〇〇だから上手くいかないのでは」と前もって賢く考えて、やらない理由を探してしまうのではなく、まずはやってみる人。やってみなければ分からないし、やった結果「思っていたのと違う」ということもある。だからこそ、自分で自分の可能性を閉じ込めない人と一緒に働けたら、とても楽しいと思います。

アナグラムは自分で工夫できる人にとってはとてもよい環境です。かつてMRをしていた頃の自分のように、規制の強い営業職で裁量不足を感じていて「自分の提案で最後までやり切りたい」と思っているような方も、きっと満足できるんじゃないでしょうか。
大切なのは、素直さと馬力ですね。端から経験豊富に見える経歴であっても、プライドを捨てて若い上司の下で吸収できるタイプの人は、のびのびと力を発揮できると思います。