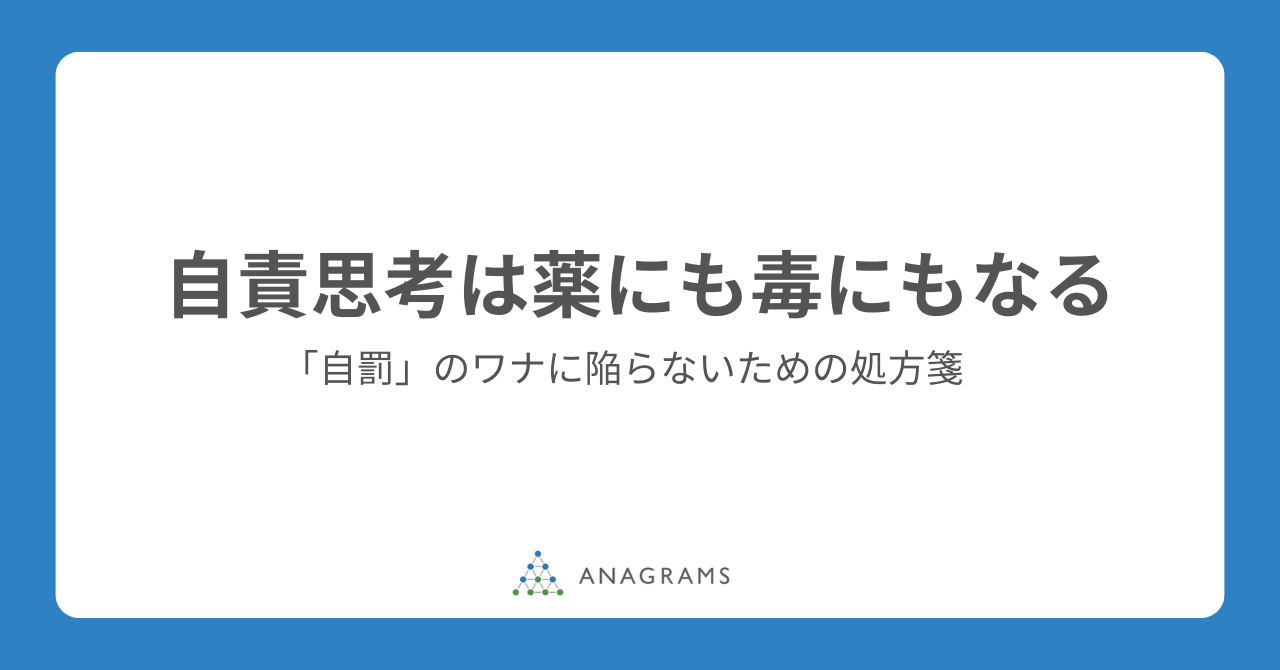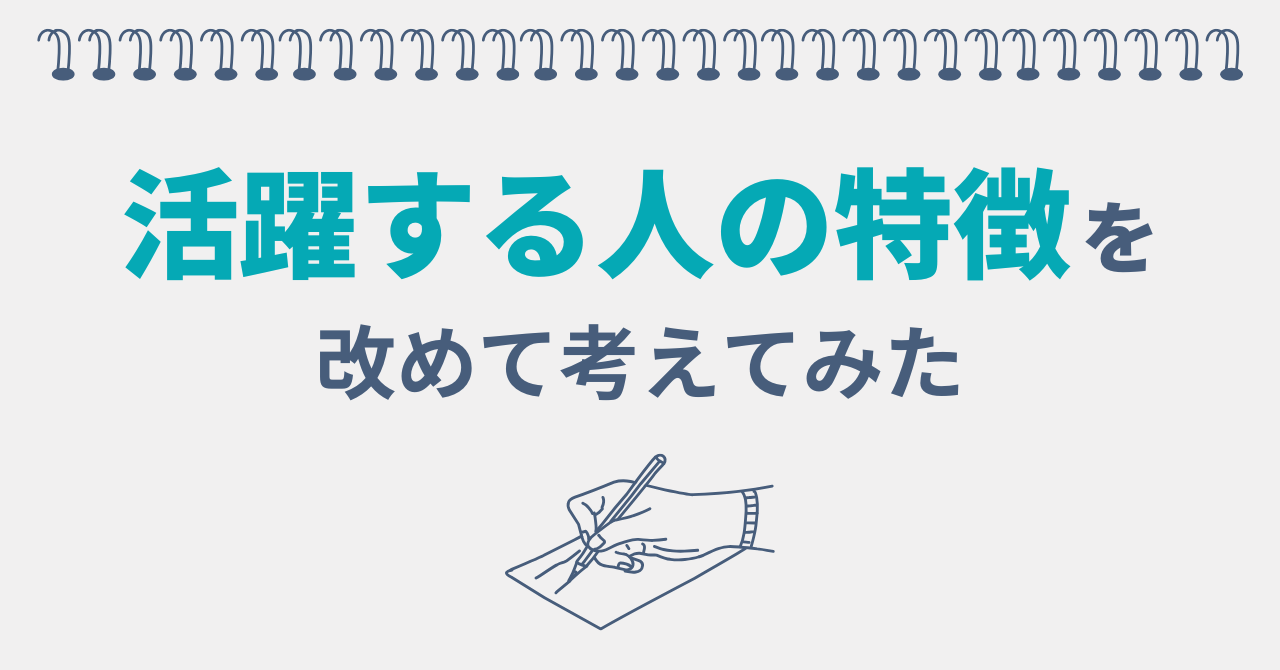
「活躍する人の特徴って、どんなものでしょう?」
採用面接や説明会では、よくこんな質問をいただきます。
転職先で成果を出すには、どんなスキルやスタンスが求められるのか。会社選びの判断軸としても、納得のいく答えがほしいところですよね。
けれど正直に言うと、この質問に端的に答えることは実はとても難しいことだと感じます。
そもそも、「論理的思考力」「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」といった「特徴」を表す言葉には、どこか静的で、ラベルのような響きがあります。一方で、これまで社内で見てきた「活躍」の実態は、もっと地道で、もっと動的なものでした。
目の前の仕事に丁寧に向き合い、周囲からの信頼を少しずつ積み重ねていく。そうして変化しながら、気づけば役割を広げている。
そんな道筋を辿る可能性は、特別な資質を持った一部の人に限られたものではなく、本来、誰にでも開かれているのではないかと思うのです。
このような前提にたったとき、冒頭の問いに対する真摯な回答というのは、特徴のラベルを提示するものではなく、「どういう成長プロセスを辿れば、成果を出せるようになるのか」というプロセスを提示するものなのではないかと考えました。
本記事では、社内での観察を通して見えてきた共通項を手がかりに、活躍のプロセスを紐解いてみたいと思います。


目次
活躍とは「早く成熟期に入り、長く維持すること」
「活躍する人はどのようなプロセスを辿っているのか」
この問いに向き合うにあたり、まず必要なのは「活躍者」の定義です。でもこれが意外と難しい。なぜなら、人によって思い浮かべる姿がまちまちだからです。
たとえば、大きなプロジェクトを成功に導いた人。常に新しいことにトライしている人。平均的なパフォーマンスを安定して発揮する人。あるいは何度失敗しても立ち上がる人。
どれも「活躍」の一つのかたちに違いありません。でも、あらゆるケースをも「これだ!」と完全に掬い取れるような答えとは、どうも言えない気がします。
ですが唯一、「早く」成果を出す、そして「長く」成果を出し続ける、この両輪が揃う状態の人であれば、胸を張って「活躍者」と呼べるのではないでしょうか。
わたしたちのキャリアは「プロダクトライフサイクル」の曲線に似ているところがあります。
プロダクトライフサイクルとは、製品が市場に出てからどんな曲線を描くかを、以下の4つのフェーズに分けて示した理論です。
- 製品が市場に認知されるまでの「導入期」
- ぐっと売上を伸ばし、人気が加速する「成長期」
- 安定した人気と売上を誇るトップランナーとしての「成熟期」
- そして、やがて新しい製品にその役目を譲る「衰退期」
これをわたしたちのキャリアに当てはめると、新しい環境でがむしゃらに学ぶ導入期・手応えを感じ始める成長期・周囲から信頼され、任される成熟期・そして、これまでのやり方が通じなくなって戸惑う衰退期、といったところでしょうか。
この視点を前提にするなら、「活躍」はさらにこう捉え直すことができそうです。
──価値が最大化される”成熟期”に「早く」到達し、その状態を「長く」維持できること。
つまり、継続的に成果を出す人は、この「早く」到達するための「縦の推進力」と、「長く」維持するための「横への射程」を持っていると言うこともできそうです。
早く成熟期に到達するには?
では、成熟期にいち早く到達するための「縦の推進力」は、どうすれば育つのでしょうか?
社内で成熟期にいち早く到達したメンバーの例を観察すると、成熟期にたどり着く前の「導入期」や「成長期」を実りあるフェーズにすることが、一番の近道であるとわかってきました。
ここからは、各プロセスを充実させるアクションについて、より詳しくご紹介していきます。
導入期:信頼を”貯める”
キャリアの初期段階、あるいは新しい環境での最初のミッションは、今後仕事を任せてもらうための土台となる「信頼」や「期待」を育むことです。
仕事において結果はとても重要です。しかし、だからといって過程が無駄であるということは意味しません。
むしろ過程を軽視しない姿勢こそが、周囲からの信頼や期待、ひいては成長を勢いづける機会を呼び寄せ、結果的に早く成長期に移行することにつながります。
社内で見られたいくつかのケースを整理してみると、活躍する人の導入期に共通する要素は、あまりにもシンプルな2点に集約されました。
1つ目は、素直な姿勢で学びに臨むこと。2つ目は、学んだことを即実践しながら軌道修正していくこと。
この時期に達成したいことは、このサイクルを回すことで、よい行動習慣を定着させること。いわば成長の基礎体力をつけていくことです。
「素直に聞き入れる」── 学びの姿勢
活躍する人は、自分の意見や過去の成功体験を持ちつつも、新しい環境では一度それを脇に置き、素直にアドバイスを聞き入れる姿勢を持っています。
前職でのやり方が通用しない可能性を理解し、意識的に「新人」となってアンラーニングしていく準備があるのです。
活躍者の上司にも訊いてみたところ、安定した学びへの向き合い方は「この人は時間の問題で伸びていくに違いない」と安心して伴走できる、大切な要素のようでした。
「とにかく動いてみる」── 行動量と粘り強さ
彼らは「自信がないからやらない」のではなく、「自信がないからこそ、まず動いて学ぶ」という行動第一の姿勢を貫きます。成長を加速させるためには、たとえつまづいたとしても行動量を積み上げることに勝る方法はないと、肌で知っているからです。
また、一度の失敗で諦めず、「できるまでやってみよう」と粘り強く挑戦し続ける姿は、自然と周囲の「応援したい」「なにかあればフォローしよう」という気持ちを集めます。結果としてポジティブな循環に入りやすいように見受けられました。
こうした思考や行動の習慣をつくっていく上で欠かせないと思われるのは、客観的かつ正確な自己理解です。
「今の自分はなにが得意で、反対にどこに課題があるのか」といった現在地の把握や、「特定の条件下で自分がどのようなパフォーマンスを発揮できるか」といったパターンの把握によって、失敗から過度に落ち込むことを避けながら、効果的に学習を進めることができるのです。
このように、導入期においては、成果そのものよりも、未来の成果に繋がる「信頼の貯蓄」が重要になります。
教わったことを地道に実践し、徐々に自分なりの工夫も加えられるようになってくる。
そうした行動が自然と積み上がることで、上司からも「多少背伸びした仕事を任せても大丈夫そうだ」と思われるようになれば、成長期への移行が見えてきます。
成長期:挑戦の機会を”引き受ける”
導入期で築いた信頼を元手に、より大きな成長を遂げる段階です。今の自分にできる仕事だけを続けていても、能力のキャパシティは広がりません。
この時期に共通していたのは、導入期で得た「この人なら大丈夫だろう」という周囲からの信頼を元手に、自ら少し背伸びした挑戦的な仕事に手を挙げていることでした。
もちろん、最初から完璧にこなせるわけではありません。しかし、周囲のサポートを得ながらその壁を乗り越えた時、一つの成功体験が大きな自信を生み出します。
こうした挑戦と成功の積み重ねによって、「困ったときは周囲に頼ってもいい」「自分なりのやり方で成果を出していい」という感覚が育っていきます。
その結果として、過剰に理想を追いすぎたり、弱みを隠そうとしたりすることが減り、ありのままの自分を受け入れたうえで力を発揮できるようになる―—いわば自己受容の段階に至るのです。
この「挑戦→成功→自信→自己受容」というポジティブなスパイラルこそが、成長期のエンジンです。導入期から続く「学びと実践のサイクル」はさらに加速し、状況がどう変わっても成果を出せるような、自己効力感も培われていきます。
経験を重ねるうちに、最初は背伸びだった案件でも、安定してPDCAを回せるようになるでしょう。その過程で、マネジメントへの関心が芽生えたり、専門性を磨くことや他領域への挑戦に意欲を持つなど、“射程の拡張”が自然と起こっていくのです。
上司の目から見ても、そうした変化が無理なく進んでいると感じられたとき、人は「成熟期」へと移行する段階に差しかかります。
長く成熟期を維持するには?
プロダクトライフサイクルになぞらえるなら、どんなに優れたプロダクトも「成熟期」を経ていつかは「衰退期」を迎えます。
キャリアも同じで、現状維持は緩やかな後退にほかなりません。昇進とともにパフォーマンスが停滞する「ピーターの法則※」が示すように、意図的に手を打たなければ、誰もが「過去の人」になるリスクを孕んでいます。
※ピーターの法則:人は能力を認められて昇進を繰り返すが、やがて「その人の能力の限界を超える役職」に到達し、そこで能力不足によって成果が出せなくなる、といった組織構造に関する指摘。
では、そうした停滞を乗り越え、長く活躍する人は何が違うのでしょうか?
その鍵となる「横の射程」を保つ力は、大きく2つの要素に集約されます。
ゴールや原動力がずっと先の未来にある
ひとつは、視線が常に、目先の成果や評価の、さらに先にある景色を捉えていることです。
例えば、年収や職位といった、いわば「キャリアの標識」も大切でしょう。けれどそれ以上に以下のような、より遠く、そして本質的なものを目標や原動力にしていると思われるケースが多く見られます。
- 「この仕事を通じて、社会のどんな課題を解決したいのか」という信念
- 「クライアントや組織の成長に貢献したい」という他者への想い
- 「自分自身のこの弱点を、必ず克服したい」という内なる課題
遠くのゴールを見据えているからこそ、現状の成功に満足しません。一つの中間目標の達成は、通過点に過ぎないのです。
だからこそ、常に「もっと良い方法はないか」とベターを追求し続けることができ、結果として成熟期が長く続くのだと考えられます。
新しい導入期を自ら始められる
そしてもう一つの、より決定的な秘訣。それは、一つの山の頂上に安住せず、自ら次の新しい山に登り始める力です。
「それでは”長く”保つとは言えないのでは?」と感じるかもしれません。たしかに文字通りの意味にはあてはまらないかもしれませんが、衰退期を遠ざける策としては、有効な選択肢の一つといえるでしょう。
活躍し続ける人は、自分のやり方が陳腐化する前に、「1年生」の環境へと自らを置き直しているのです。
例えば、それは以下のようなアクションとして現れます。
- マネジメントへの挑戦や、未経験の役割を引き受けること
- 専門性を活かしつつも、これまでとは違う分野で職種変更を行うこと
- 周囲との協力が不可欠な、より高難易度の案件に自らトライすること
こうした行動が新たな「導入期」を生み、影響範囲や周囲との交流も広げながら、再び成長や成熟へとつながっていきます。その繰り返しの中で、やがて人は複数の“プロダクトライフサイクル”を並行して抱えるようになっていくのです。
ある領域では成熟したプロフェッショナルとして信頼されながら、別の領域では謙虚な学び手として成長を続ける。そうした複数の立場を柔軟に行き来できることこそが、「活躍し続ける力」なのではないでしょうか。
この成長プロセスがアナグラムで再現性を持つ理由とは?
ここまでは、どんな職場でも通用する「活躍する人の成長プロセス」について述べてきました。
ここからは、このプロセスがアナグラムという組織の中で、なぜ高い再現性を持って機能しているのか、アナグラムに長く根付いてきた「一気通貫」「挙手制」「売上ノルマなし」といった仕組みに紐づけつつ、掘り下げてみたいと思います。
一気通貫制においては”素直であること”が必要条件
アナグラムの大きな特徴の一つに、一人のコンサルタントが顧客への提案から広告運用、レポーティングまでを一気通貫で担当する業務体制があります。
これは、誰しもが自分の得意な領域だけでなく、不得意な分野や未経験の業務に直面することを意味します。最初から最後までを完璧に一人でこなすのは、不可能ではありませんが、非常に難易度が高いといえるのです。
だからこそ、この環境では、自分の限界を素直に認め、臆せずに人に頼れること、そして他者の知識や経験を素直に吸収し、まず実行できることが、極めて重要になります。
一気通貫の環境は「素直な姿勢で学びに臨む姿勢」や「即実行してみること」といった行動を、もはや導入期において欠かせないものにしているのです。
自ら機会を得ないと始まらない”挙手制”
アナグラムでは、案件へのアサインやメンバーの受け入れ(配属)といった社内での役割は、基本的に「挙手制」をベースとしています。
これは単に「やりたい人がやる」という話ではありません。「自らの意思と責任で、自身のキャリアをデザインすべきだ」という、会社からのメッセージです。
この環境では、導入期で信頼を得るというステップを踏んだうえで、少しストレッチした仕事や課題に「やらせてください」と自ら手を挙げることができます。
また、「自信がないからこそ足踏みせず、自らをさらなる挑戦の機会にさらす」という選択も、社内ではよく目にします。
そして、その挑戦する姿勢は、周囲からさらなる信頼と応援を集め、次のより大きな機会を引き寄せることに繋がっているケースも多いです。
売上ノルマがないからこそ、鍛えられる
アナグラムにおいては、個人に課される売上ノルマがありません。
これは、「他者から決められた、分かりやすい数字を達成すれば良い」という働き方ではない、ということを意味します。
その分、一人ひとりが「顧客にとって、そして会社にとって、本質的な成果とは何か?」という問いに、早期から向き合わなくてはなりません。
短期的な数字ではなく、長期的な顧客の成功や、チームへの貢献を自ら考え、定義し、実行する。
決められたゴールを目指すのではなく、自らゴールを設定し、その境地への道筋を描く。
この環境こそが、「成熟期」に求められる、広い視野と自律的なマインドを早くから自然と育んでいるのかもしれません。
このような視座の高さは、自然と個人を「組織」や「チーム」といった、より大きな主語で物事を考えるように促します。
部下や後輩の成長に合わせた機会を創出したり、チーム全体の成果を最大化しようと試みたり。その「貢献」への意識が、結果として個人の活躍をもう一段階、深いものにしていると思えてなりません。
アナグラムのプロダクトは、やっぱり”人”
アナグラムは、人の可能性を信じ、「人こそがプロダクト」だと考えている会社です。
この記事では、「活躍する人」の成長プロセスを紐解く中で、この理念と、プロダクトライフサイクルというフレームが、思いのほか自然に呼応する場面がいくつもありました。“人というプロダクト”の成長が、その構造の中にすっと溶け込んでいくように感じられたのです。
活躍を目指すなら、「自分というプロダクトをどう設計し、育てていくか?」という問いは避けて通れません。 そこには、私たちが日々顧客のプロダクトに向き合うときと同じように、仮説と検証、試行錯誤のプロセスがあります。
その成長曲線は、なだらかに続く1本の坂道とは限らず、以下の図で示すような紆余曲折や、回り道を伴うかもしれません。
ときに停滞し、自信を失い、「今、自分はどのフェーズにいるのか」と迷う瞬間もあるけれど、そんな揺らぎも含めて人の成長なのだと、社内を見てきて感じます。
アナグラムは、それぞれが自らの「特徴」を活かしながら、のびのびと力を発揮してくれることを願っています。一方で、持ち合わせた「特徴」が様々であることを肯定しているからこそ、共通する「成長の過程」を意識し、実行していくことの意義が際立つと感じます。
ご自身のキャリアという壮大なプロダクトを、より長く、より輝かせるための一助として、紹介した考え方が何らかのヒントになれば幸いです。