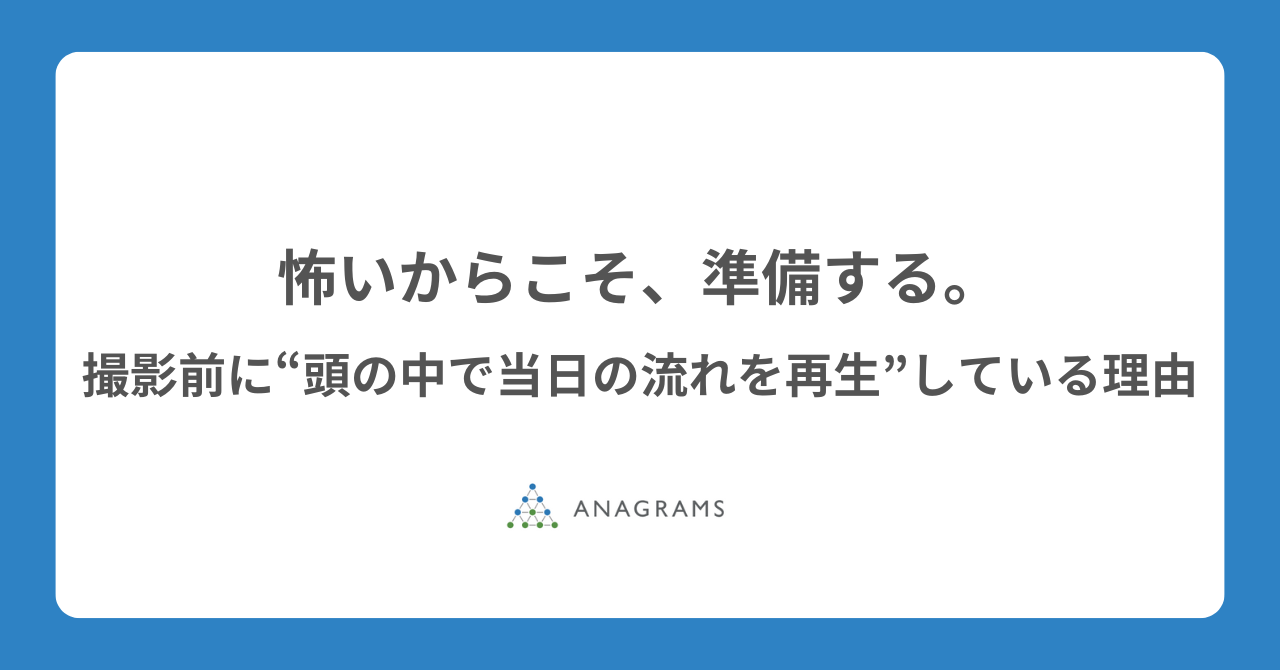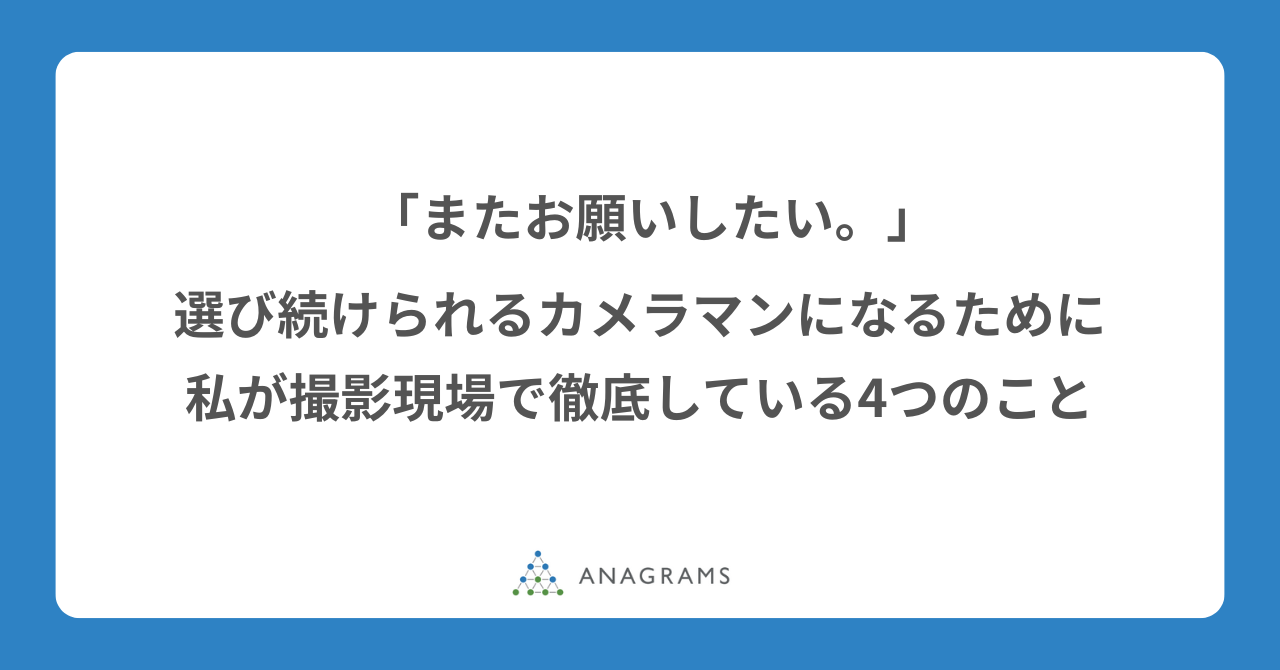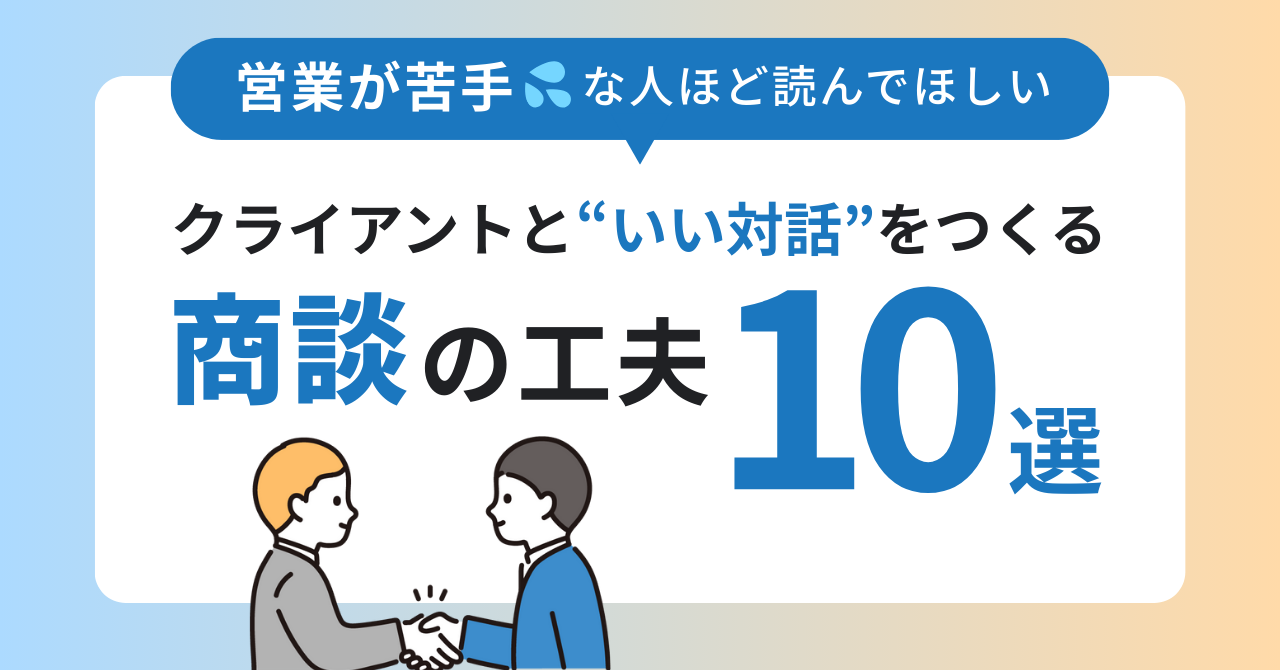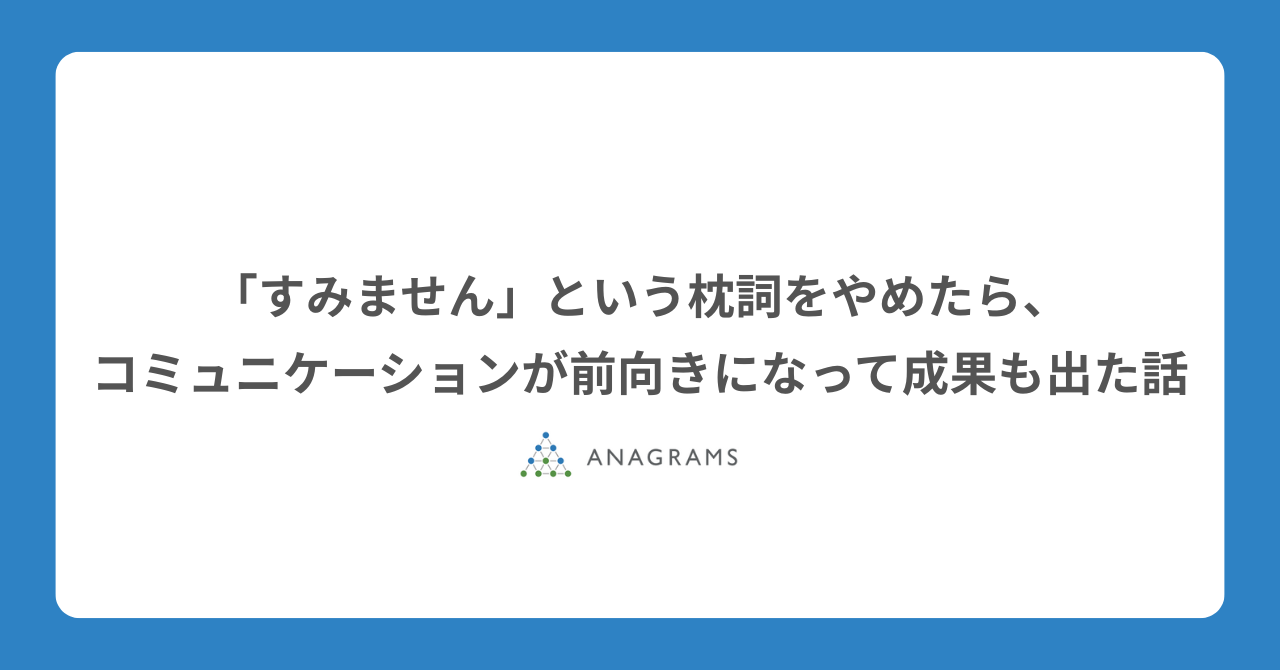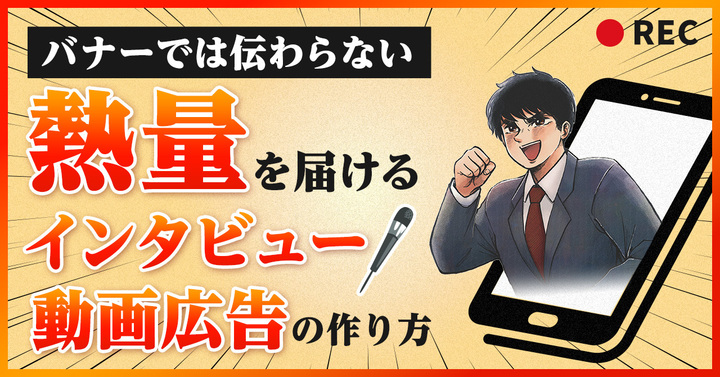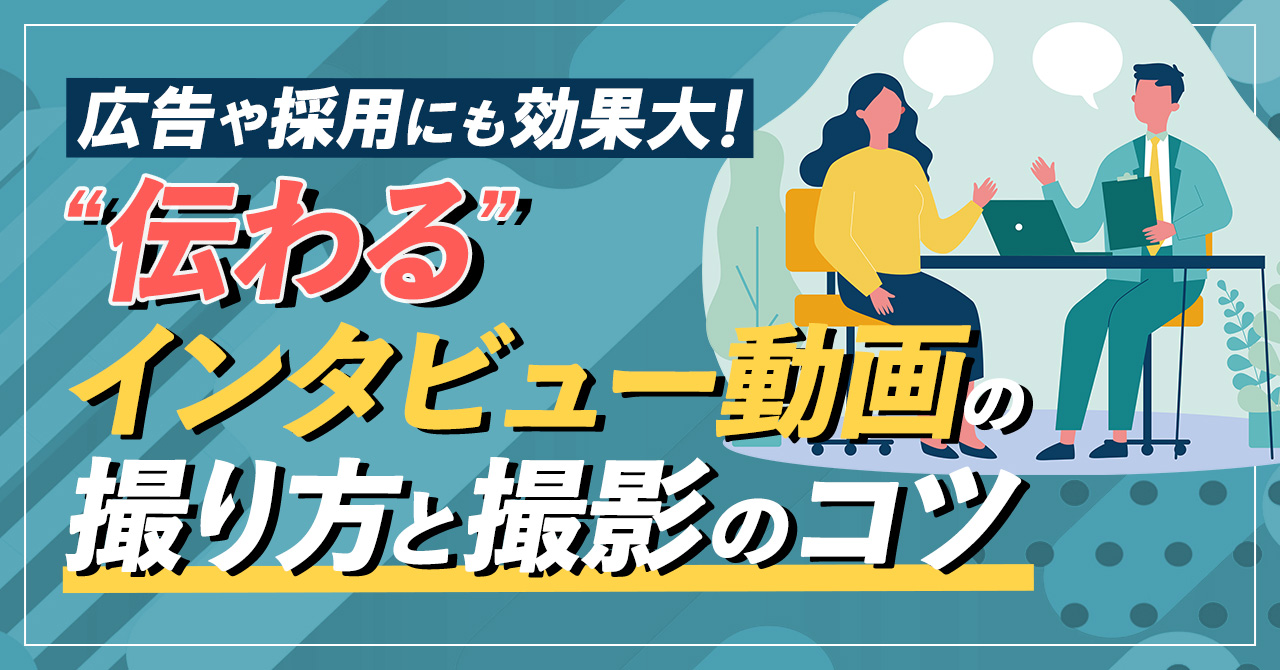
インタビュー動画は、採用やWeb広告、SNSなど幅広いシーンで活用できるコンテンツです。社員や経営者、お客様の声を“映像でそのまま伝える”ことで、テキストや画像以上にリアルな熱量や信頼感を届けられます。
アナグラムでも、YouTubeチャンネルで会長・阿部のインタビュー動画を定期的に掲載しており、既存のお客さまや採用候補者の方から「会社の雰囲気がよくわかった」という声を多くいただいています。
そんな魅力的なインタビュー動画ですが、“なんとなく撮る”だけでは良いコンテンツに仕上がりません。魅力をしっかり伝えるには、撮影前の準備や当日の進行にコツがあります。
今回は、インタビュー動画制作の中でも「撮影」に焦点をあてて、事前準備・撮影中・撮影後、それぞれのフェーズで押さえておくべきポイントを詳しく解説します。


目次
インタビュー動画制作の流れ
インタビュー動画を制作する上で、まずは全体の流れを押さえておきましょう。
①企画
インタビューの目的やテーマを明確にし、誰にどんなメッセージを伝えるかを決めます。大まかな進行スケジュールを示したガントチャートを用意すると、複数人での進行管理がスムーズになります。
②手配
インタビュー対象者への出演依頼、撮影場所の確保、スケジュール調整を行います。撮影班は機材の準備やロケハン(場所の下見)を実施します。ロケハンが難しい場合は、画像や動画などでインタビューに適した場所か確認しましょう。
③質問事項の作成
当日の質問事項を作成します。事前にインタビュー対象の経歴やSNSでの発信を調べることで質問の内容も考えやすくなります。
④撮影
撮影当日は、カメラ・音声・照明を整え、スムーズに進められる環境を整備します。
⑤編集
撮影した動画の編集を行います。編集ソフトを立ち上げる前に、インタビューの内容を一度文字起こしして、使用するシーンを選定するとスムーズです。その後Adobe Premiere Proなどの編集ソフトを使用してシーンの調整を行い、テロップやBGMを追加して動画の完成です。
このように、インタビュー動画の制作は「企画」から「編集」まで複数のステップを踏んで進めていきますが、中でも「撮影」がスムーズに進むかどうかは、事前準備にかかっていると言っても過言ではありません。
ここからは、撮影を成功に導くための「事前準備」「撮影中」「撮影後」それぞれのポイントについて、時系列で整理していきます。
インタビュー動画の撮影は事前準備が9割
インタビュー動画は、基本的に被写体が座ったまま話す形式が多く、カメラや音声機材も固定で撮影することが一般的です。
そのため、撮影当日の対応力よりも、事前にどれだけ丁寧に準備できているかが動画の完成度を大きく左右します。
事前準備のポイントを時系列順に見ていきましょう。
事前準備|撮影場所の選び方
インタビュー動画の撮影に向いている場所の条件は「静かであること」「適度に明るいこと」です。
撮影環境によって編集の負担が全く変わってくるため、条件の良い場所を選ぶことができればその分調整にかかる時間も少なくなります。
撮影に向いている場所の例
- 音:室内で出入りの少ない静かな部屋
- 光:文字が読めるレベルの明るさ
避けたい場所の例
- 音:人の声、電車や車の音が響く場所
- 音:屋外などの風が強く吹く場所
- 光:インタビュアーの配置が逆光になってしまう場所
- 光:直射日光が差すなど明暗差が大きい場所
スタジオを借りたりクライアント先で撮影したりする場合は、実際に見られそうであれば下見に行ってみることをおすすめします。実際に見ることで、希望の画は撮れそうか、撮影当日どの位置に何を配置していけばスムーズに進められるかなど、イメージしやすくなります。
なお、空調音などの軽微で規則的な音(ホワイトノイズ)であれば、編集である程度改善することも可能です。
対応方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
事前準備|用意しておきたい撮影機材
インタビュー動画の撮影には、必ずしも高価な機材が必要というわけではありません。
ここでは、基本的な撮影環境を整えるために用意しておきたい機材をご紹介します。
カメラ or スマートフォン
動画撮影に対応したカメラ、またはスマートフォンを用意します。人物が座って話すだけのシンプルなインタビュー動画であれば、スマートフォンでも十分対応可能です。
カメラを選ぶ際は、連続撮影可能時間もチェックしておきましょう。一部のカメラでは、30分程度で自動的に録画が停止される場合があります。長時間の撮影が予想される場合は、途中で録画を一時停止するタイミングを事前に決めておくと安心です。
三脚
撮影機材を固定するために必須のアイテムです。手持ちだとどうしてもブレてしまったり、重さで撮影者に負担がかかったりすることがあります。
カメラを使う場合は、対応するカメラ三脚を。スマートフォンの場合は、スマホスタンドやフレキシブル三脚などでもOKです。いずれの場合も、ぐらつかず、倒れにくい安定感のあるものを選びましょう。
ワイヤレスマイク
音声のクオリティを高めるために、外部マイクはぜひ用意したい機材です。カメラやスマートフォンに内蔵されているマイクは広く周囲の音を拾ってしまうため、インタビュアーの口元の近くにつけられるワイヤレスマイクを用意することをおすすめします。
リングライト
室内が十分に明るい場合は出番が少ないですが、思ったより部屋が暗い/逆光しか撮影ポジションが取れないといった状況では活躍します。持ち運びもしやすいので、用意しておくといざという時に便利です。
インタビュー当日|機材や人物の配置
撮影当日は、機材や人物の配置によって動画の印象が大きく変わります。
ここでは、スマートフォンやカメラ・簡易照明など、一般的な機材を使った際の基本的な配置例をご紹介します。
カメラ、照明機材の位置
カメラはインタビュアーのすぐ隣で、インタビュイーの正面から少しずれた位置に設置しましょう。インタビュイーを正面からとらえてしまうと、目線がカメラ目線に見えてしまいインタビュアーに受け答えしているのに視聴者に話しかけているかのような違和感が生まれてしまいます。
照明はカメラのうしろに置き、インタビュイーの顔に強い影や白飛びが起こらないよう光を調整します。
インタビュアー、インタビュイーの位置
インタビュアーとインタビュイーは対面で座るのが基本ですが、カメラに干渉しない距離感を意識しましょう。
近すぎると、インタビュアーの体や手の動きが画角に入り込んでしまったり、圧迫感のある映像になってしまうことも。テーブルを挟んで、やや余裕のある距離感を保つのがおすすめです。
インタビュー当日|機材の事前確認
撮影トラブルは、ちょっとした確認不足から起こることがほとんどです。撮影開始前に、以下のポイントをしっかりチェックしておくことで、安心して本番に臨むことができます。
カメラの画角に映るものが適切か
撮影前には必ず入念に画角の確認を行いましょう。
- インタビュイーが画面の中心、引きの画角に位置しているか
- 背景がゴチャゴチャしていないか
- 画角内に必要のないものやカンペが映りこんでいないか
SDカードやデバイスの保存容量に空きがあるか
空き容量が不足すると、撮影が途中で止まります。あらかじめ容量をチェックし、不必要なデータを整理したり、予備のSDカードを用意しておきましょう。
録音機器の接続確認
音声のトラブルは編集で修正しづらいため、接続状態を事前にテストします。実際に声を出して録音し、ノイズや音割れがないかチェックしましょう。
インタビュー当日|参加者への注意点の周知
撮影時の注意事項を撮影前にインタビュイーやインタビュアー、見学しているゲストに周知します。以下の注意事項をスタート前に伝えるだけでもリテイクを減らせるので、必ず共有しておきましょう。
撮影用のテーブルに物を置かない
インタビュー動画では人物が主役です。机の上に置かれた飲み物・スマホ・PC・名刺入れなどが視覚的なノイズになり、集中を妨げることがあります。カンペを使う場合はインタビュアー側に置くなどして、画角に入らないようにしましょう。
電子機器はサイレントモードにする
PCやスマートフォンの通知音が鳴ってしまった場合、リテイクとなってしまいます。バイブレーション機能でも振動音を拾ってしまう可能性があるので、必ず「サイレントモード(音&振動OFF)」に設定します。
インタビュアーの相槌はなるべく声を出さない
「はい」「うん」といった声の相槌やリアクションがインタビュイーの発言と被ってしまった場合、編集時にノイズになる可能性があります。笑顔やうなずきだけで反応することを事前に共有しておくと安心ですね。
データ整理が終わるまでが“撮影”
インタビュー動画の撮影は、カメラを止めた瞬間に終わりではありません。映像や音声のチェック、データの整理まで終えて、はじめて“撮影完了”と言えます。
撮影直後|取れ高の確認をすぐに行う
一度機材を片づけてしまうと再撮影が難しくなるため、撤収前に以下を確認する時間をあらかじめ設けておきましょう。
- 必要なシーンがきちんと撮れているか
- 音声が問題なく収録されているか
- 画質や構図に乱れがないか
とくに音声の録り漏れやノイズ混入は、編集での修正が難しいため、現場での確認が必須です。
撮影後|データ管理が編集のしやすさに直結する
インタビュー動画は、素材の整理がそのまま編集のスピードに直結します。「あとでやろう」と思って溜めてしまうと、何がどのデータか分からなくなりがちなので、なるべく当日中に以下のような整理をしておくのがおすすめです。
- 質問ごとに撮影を分けておくと、編集時にカット・構成しやすい
- ファイル名は「撮影日+内容」(例:20250328_Q2_製品の感想)などで統一
- フォルダも「日付>人物名>質問番号」など、階層をわかりやすく整理
気軽にインタビュー動画撮影にチャレンジしてみよう
テキスト記事と違い、映像では語り手の“声・表情・間”など、文字では伝わりにくい情報まで届けることができます。その結果、エピソードに説得力が増すだけでなく、語り手の人柄や空気感までも視聴者に伝わりやすくなるのが、インタビュー動画ならではの魅力です。
また、インタビュー動画はひとつ作っておけばさまざまな場面で“何度も使える”コンテンツになります。
<活用例>
- 社内の文化や価値観の紹介
- 採用広報やSNSでの発信
- 商品・サービスのプロモーション
最低限スマートフォンとマイクの用意だけでも気軽に取り組めるので、本記事を参考にしながらぜひチャレンジしてみてくださいね。