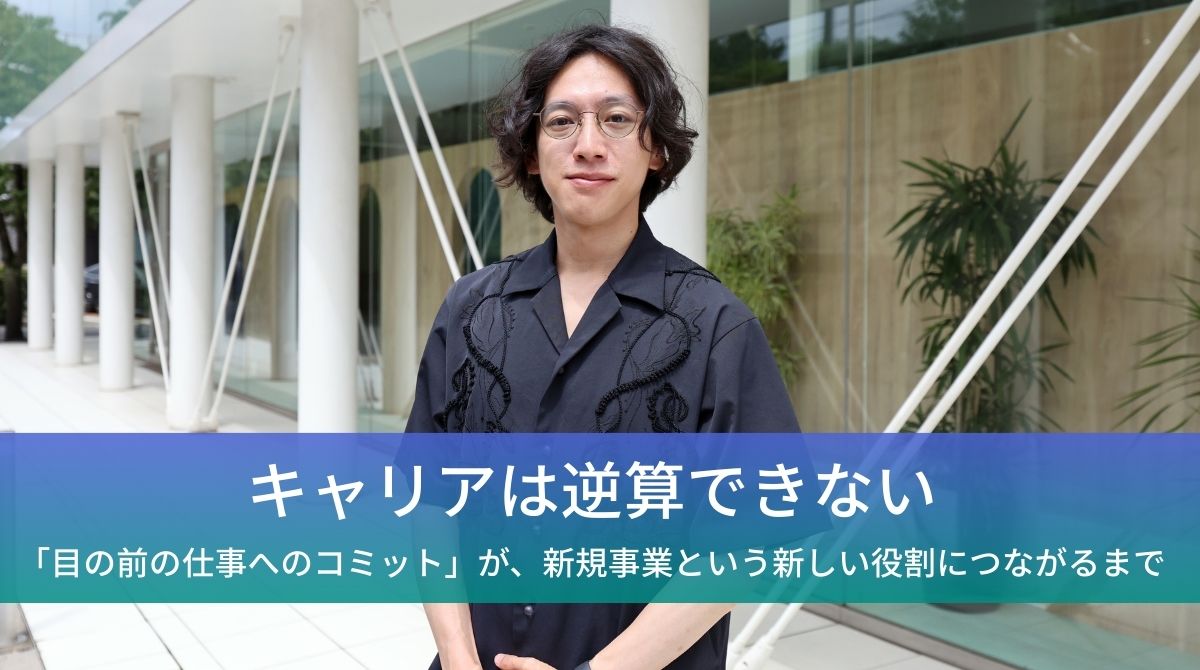“クリエイターとして求められる姿”と“自分らしさ”の間で、答えを探し続けた日々
ーーー平野さんは大学生のころから、現在に至るまでTikTokやYouTubeで動画クリエイターとしての活動を継続されています。どのようなところに力を入れてきたか教えてください。
たとえばゲーム実況やASMRのようなジャンルなら、顔を写さずとも声や音だけで動画が成立しますよね。そうではなく、一般的には演者のビジュアルがウリになりやすいジャンルで、”あえて顔を出さない”戦略をとっています。良くも悪くもタレント性が意識されがちな土俵だからこそ、純粋に“コンテンツの面白さ”を際立たせられれば差別化できると考えたからです。
普段の投稿でも、見る人にいかに楽しんでもらうか?を大切に、あくまで「エンタメ作品」を届ける意識を持って活動してきました。SNSは個人の一部分を切り取ったものに過ぎませんが、その断片と自分を比較して落ち込んだり、批判的な視点で捉えてしまいがちです。自分としては、視聴者に対してそういった刺激を与えるのではなく、単純に娯楽として面白く見てもらえるように意識しています。
だからこそ好意的なコメントを残してくれる視聴者が多く、平和に運営できていてありがたい限りですね。

ーーー学生時代から活動されていたのであれば、就活はしなかったのでしょうか?
いえ、その頃はまだ現在のような成果が出る前の時期だったので、流れに身を任せて就活して、銀行に就職しました。ですが自分には会社勤めが合わないという感覚を強く抱くようになって…絶望のあまり、トイレでご飯を食べたこともあります。
今振り返れば、単に環境が合わなかっただけなのですが、当時の自分は「自分がダメだからだ」と思い込んでいました。特に、業界の特性もあり、「会社とは個性を押し殺して働く場所」という意識が強くなってしまったんです。
そうして1社目を退職しましたが、その後も”就職”という選択肢を意識しては「クリエイター活動をする身として、企業に就職することは”負け”を意味するのではないか」「(クリエイター活動を)”降りた”ことになるのでは」と何度も思い悩みました。
ーーーそこから再び就職しようと思うまでに、どんな心境の変化があったのでしょうか?
きっかけの一つは、支持してくれる視聴者が増えるにつれて「”求められている姿”と”自分らしさ”のバランス」に葛藤するようになったことでした。
フォロワーが増えるのはもちろんうれしいですが、その反面「どうしたらフォロワーが増えるか?」という思考が強くなりすぎてしまうと、発信内容がどうしても本来の自分から遠ざかってしまいます。
この悩みはクリエイターとして成果が出てきたからこそ直面したジレンマでした。逆説的ですが、個人で一定以上の実績を作れたからこそ、会社員時代と似たような釈然としない思いを抱えるようになったんです。

それを自覚するようになってからは「会社」をひとくくりに考えるのをやめました。今度は「自分に合った組織かどうか?」を軸に、クリエイター活動と両立できる会社を探すことにしたんです。
組織に入ることは、自分らしさを失うどころか、確かめることにつながった
ーーー背景をふまえると、会社選びにはなおさら慎重だったかと思います。アナグラムを選んだ決め手は何でしたか?
選考を通して「”人”を見るカルチャー」を感じられたことです。
特に面接の場では、求職者というよりは1人の人間として対話できたのが印象的でした。当時抱えていた葛藤を受け入れてもらった上で、人生へのエールをもらった気がしたのを覚えています。ダメだと思っていたありのままの自分らしさが、この場所でなら活きるのかもしれないと思えました。会社勤めへの恐れや覚悟など、当時ガチガチに張りつめていたものがふっと緩んだ瞬間でしたね。
面接の場でここまで深く人となりを見てもらえるのであれば、実際の仕事も誠実かつ真っ当な環境で出来る会社だろう、と倫理観の高さを信じられたことも大きかったです。
ーーー実際に入社していかがでしたか?会社という組織への印象は変わったのでしょうか。
変わりましたね。組織でも成果を出せたことで、「自分らしく働く上で、会社員か個人かという区別は必要ない」と気づけたのは大きかったです。組織=個性を殺される場所という感覚もいつしか消えていました。
むしろ「自分は何が得意なのか」を確かめられる機会は、組織のほうが多いかもしれません。動画の制作について頼ってもらえたり、自分も他の人の視点に触れられたり、といった経験を通して、「自分ってこれがすごいんだ」「自信を持っていいんだ」と自分らしさをより客観的に肯定しながら捉えられるようになりました。

個人でも、組織でも。大切なのは“人の心を前に動かす”こと
ーーー広告業界で動画の重要性が日に日に増していくなか、自身のクライアントへの貢献はもちろん、社内のメンバーから平野さんに相談が寄せられているのをよく目にします。現在に至るまでに意識してきたことはありますか?
入社当初から「素直に目の前のことに向き合うこと」を徹底してきました。原動力になっているのはずっと、過去の自分に恥じない自分でありたい、その一心なんです。
個人で活動していたときもはじめから上手く行ったわけではありません。それでもひたすら動画を作り続けて少しずつ成果が出てきました。「目の前のことを積み重ねた先にしか成果がない」のは、個人であろうが会社であろうが全く同じです。
一気通貫の仕事には初めての経験も多いですが、入社前の経験が活きる場面も少なくありません。自分にとってはそれが動画の領域ですし、各々の担当領域が広い分、これまでに経験してきたことを活かしやすい環境ともいえるのではないでしょうか。
ーーーアナグラムでは運用型広告を未経験で入社する人が8割を占めますが、「これまでの人生で、何かを突き詰めて考えた経験がある人」が多い印象です。平野さんはアナグラムの仕事のどんな部分にやりがいや面白さを感じていますか?
“人の心を前に動かせた”と実感できる瞬間です。
ここでいう「人」は、以前は「コンテンツを見る人」のことでしたが、今では「手がけた広告を見る人」に限らず、「関わるクライアント側の担当者さん」や「社内で一緒に働くメンバー」にまで対象が広がっています。
頼ってもらう度に、これまでやってきた動画周りの知見を言語化する機会にも恵まれました。アナグラムには書籍購入費用を全額負担してもらえる福利厚生があるので、さまざまなコンテンツに触れることができ、それも広告やクライアント、社内など仕事の多方面に還元できていますね。

たとえば先日読んだスタジオジブリの書籍には「飛行機を描くときに、あえて現実にはあり得ない大きさにしている。それは視聴者がより臨場感を持ちやすくするためだ」と記載されていたんです。
この「相手の立場や見る世界を想像して寄り添うスタンス」に触れたことで、ずっと温めてきた「面白いコンテンツとは」という自分なりの仮説がまとまったような感覚になりました。
具体的には「映像や言葉などの単なる情報の提示を超えて、見る人の頭の中にどれだけ“関連する個人的な体験や記憶”を呼び起こせるか。それがコンテンツの魅力を決める」というものです。
見る人のことを想像して想いやることは、個人で活動していたころから大切にしてきました。アナグラムに入社してからは、動画制作のみならず、「どう信頼いただくか?」という視点となってクライアントワークにも通じています。
ーーー最後に、今似た境遇にある方や、葛藤を乗り越えようとしている方に対してメッセージをお願いします。
個人での活動も会社員も両方経験したからこそ、結局は目の前のことにどう取り組むかに尽きると感じます。どこにいるかよりも、どう動くか。自分にどう向き合って個性を発揮するか、でしかありません。
そう気づけたからこそ、いまでは当時の自分にも「お前は元から負けていない」といってやることができます。
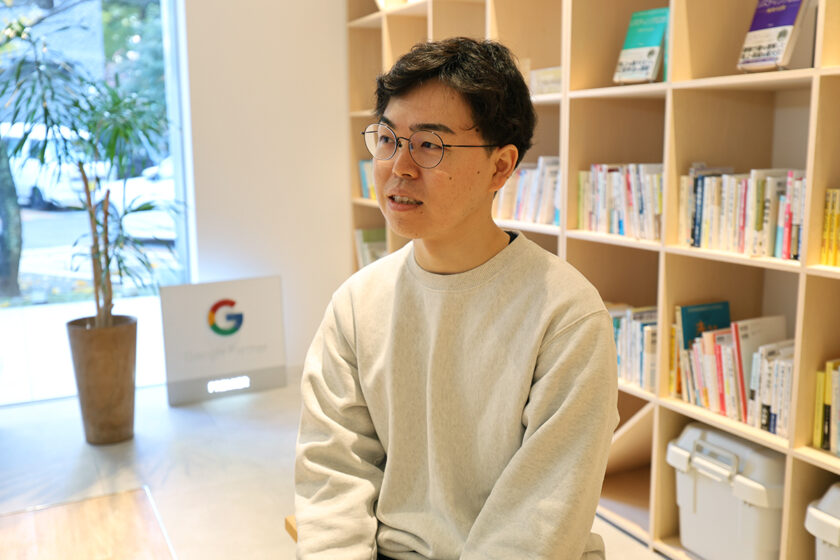
成果を出すことの大切さはどの場所を選んでも変わりません。ですがたとえば元芸人が営業会社で活躍するように、本気で取り組んだ経験は意外な場面で活かせることがあります。いざというときは会社勤めという選択肢もある、と知っておけるといいんじゃないでしょうか。もし環境を変えたいなら、それは「負け」どころか「価値」のある選択になるかもしれません。
「クリエイター気質を活かしたい」「個性と組織のバランスを模索している」人に、そのときの場所としてアナグラムはおすすめできますし、そういう人と一緒に働けたらきっと楽しいですね。