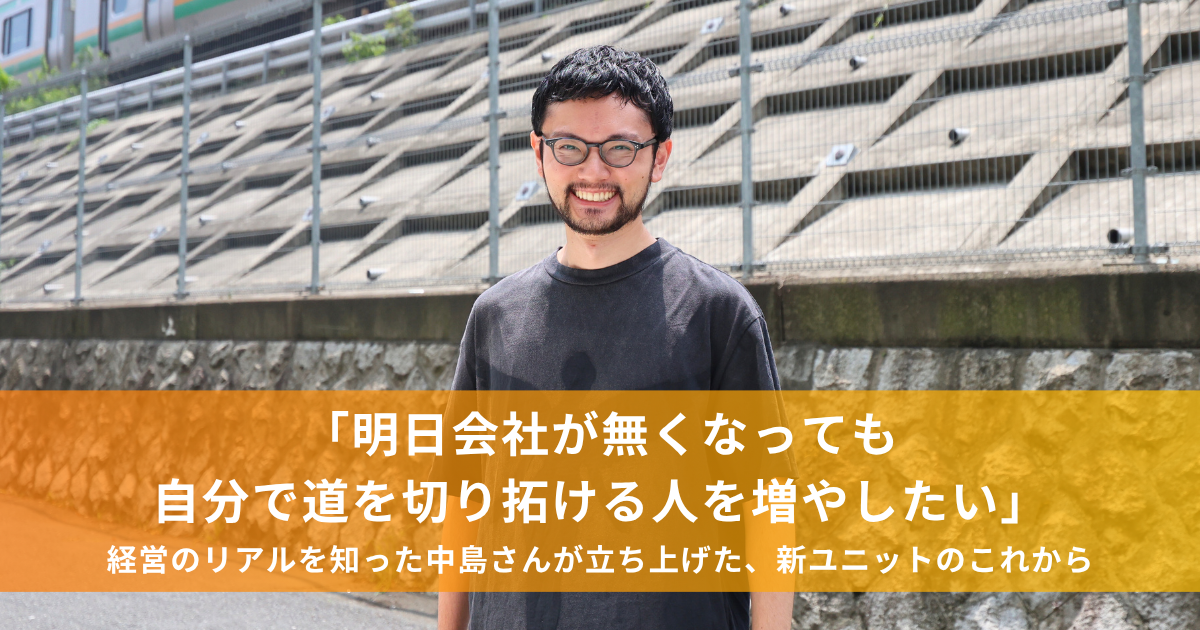
出戻り後に突然任された仕事は、グループ会社の「代表取締役社長」だった
ーーーまずはこれまでの経歴を教えてください。
大学4年生のときにインターンとしてアナグラムに入社し、2019年4月からは新卒として正社員になりました。新卒2年目になった頃にチームリーダー昇格の話が出ましたが、そのタイミングでyutoriという会社に1人目のマーケティング担当者として誘われ、転職をしました。
yutoriでは1年ほど働いて、2021年7月にアナグラムに戻ってきました。このとき一度インタビューを受けています。
ーーーということは、今回のインタビューはこの記事の続編になるのですね。
はい。アナグラムに出戻った…はずでしたが、2022年4月にはフィードフォースグループ(※1)のM&A先であるシッピーノ株式会社に、代表取締役という形で出向しました。
さらに、2024年1月からはアナグラムと兼務する形で、同じくM&A先である株式会社フラクタ(※2)で経営に携わりました。
そして、フラクタで任されていた仕事にめどが立った2024年6月ごろから、アナグラムで生成AIの推進や、新規事業の検討、YouTubeチャンネルの立ち上げ・運営といった、メイン事業(運用型広告を主軸としたマーケティング支援)からは少し離れた仕事に携わり、いまに至ります。
※1)2020年1月からアナグラムは株式会社フィードフォースの連結子会社となっています。
※2)2025年6月に株式会社フィードフォースを存続会社とする吸収合併を行っています。
ーーー4年間の出来事とは思えないほど様々な経験をされていますね…!改めて、一度アナグラムを離れてから、また戻られた理由について教えてください。
転職を決めたとき、アナグラムに対しての不満は何もありませんでした。ただ、当時まだまだ事業が定まっていないスタートアップだったyutoriに飛び込むのに「今しかない」というタイミングだと感じたんです。20代前半で身軽でしたし、体力があるうちに挑戦したいという気持ちでした。
当初から、もしyutoriを辞めることがあったら、またアナグラムで働きたいと思っていました。育ててもらった当時のメンター、秋山さんへの義理もあります。辞めるときにも戻ってきやすいように計らってくれましたし、ちゃんと恩返ししたいなと。クライアントにも良くしていただいていたので、ありがたみみたいなものも感じていましたね。

ーーーシッピーノの代表取締役社長に就任されたと聞いたときは、突然のことに驚きました。どのような経緯でグループ会社の経営に携わることになったのでしょうか?
代表(当時)の阿部さんから、急に言われました。「提携して一緒に取り組んでいく会社が出てくるから、そこでちょっと中島くんに手伝ってほしいんだよね。リソース空けておいてね」と。M&Aについて、関わる予定の人を含めてあまり話せない状況だったのだろうと思いますが、具体的に「社長になってもらいたい」と話があったのは動き出す1週間前でした。驚きましたし、しびれましたね。「なるほど。阿部さんの『リソース空けておいてね』は『社長やれ』ってことだったのか……。いや、なんでやねん」と。
おそらく、気合があって、前職でもアパレル業界で有名な人と一緒にブランドを作ったり、スタートアップで抽象度の高い仕事を経験したことから、度胸があると思われていたんだろうな、と思います。
抽象度の高い仕事は、喜んで引き受ける。やったことは「会社が生き残っていくための全て」
ーーー突然決まったうえに大きなプレッシャーがのしかかるオファーだと思いますが、中島さんはなぜ受けたのでしょうか?
抽象度が高かったり、特殊な経験が積めたりする仕事は、基本的に引き受けるようにしているんですよね。というのも、僕は将来「面白い話ができるおじさん」になりたいと常々考えていて……。
プライベートでは、一人で海外旅行をするのが好きなんですが、一人旅が好きだっていうことと、抽象度の高い仕事を引き受けるってことは、僕の中では理由が一致しています。
しょうもない話から深い話までしてくれる面白いおじさんになるための方法として、海外旅行もするし、一見ハードな仕事もやる。「うわー!」とか言いながらも、そういうのも含めて人生なので、なんだかんだ喜んでやっています。

ーーーグループ会社2社の経営では、それぞれどのようなことを求められましたか?
1社目のシッピーノでは、最低限の使命として事業を黒字で安定させること。そして、できれば再成長を目指したいというものでした。具体的には、マーケティング、セールス、マネジメント、採用、プロダクト…会社が生き残っていくための全てですね。
2社目のフラクタでは、シッピーノより短期間での事業分析を求められました。まずは売上のサイクルや、誰が何をやっているのか、などの状況理解からでしたね。自分で今は何をしないといけないのか考えながら、事業を整理していく必要がありました。いつまでにお金がなくなるのかシミュレーションを立てて、これを避けるためにはどうしようという話をして、事業縮小までのリードを行いましたね。
ーーー2社とも「なんでもやる」という感じですね…!1社目のシッピーノで代表を経験したことが、2社目のフラクタの仕事にも活きたのでしょうか?
そうですね。シッピーノを経験していなかったら、フラクタはもっと分からなかったと思います。
ーーーグループ会社の経営に携わって、大変だったことはありますか?
めちゃくちゃありました。1番に思いつくのは、シッピーノ時代の社員との関係構築ですね。シッピーノ社員にとっては、M&Aを経ての社長交代だったこともあり、新しい社長が突然やってきたという状況でした。そうなると当然、「誰やねん」となりますよね。最初は他人行儀だからこそ仲良くやれるんですが、だんだんお互いのことが分かってきたときに、すれ違いが起きるんです。立場やカルチャーの違いもありますし、創業社長から2代目社長になって、社員と自分が互いに選びあって築いた関係ではないというのは大きかったと思います。
もう1つは、フラクタ社員への事業縮小の通達です。最終的に事業縮小をすることに決まったタイミングで、僕から全社員に現状と今後について話すことになりました。どうやったら社員に一番負担なく、次に繋がるようにできるのか、というのはよく考えましたね。伝えるのが早すぎると進行中のプロジェクトが立ち行かなくなるし、遅すぎると十分な転職活動ができないので。

生き残れる会社と個を育てるために。目指すのは「自律分散型の組織」
ーーーさまざまな経験を経て、新たに得た気づきや考え方の変化はありますか?
自分たちが強みだと思っていたものに、首を絞められるケースがあることに気づきました。強みとしているものを盲信した結果、別のことに少しも種を蒔くことができていないケースってよくあるんですよね。
たとえば、受注しやすい企業だけに寄り添った結果、チャーンしやすい企業が多く、LTVが低くなってしまうとか、デザイン力が強みの制作会社において、強みに特化した人材ばかりを採用した結果、技術的な課題に対しての期待に応えられなかったりとか……。
弱みに首を絞められても、弱みだと分かっているからみんな「なんとかしなきゃ」と思えるんですが、強みに首を絞められても、中々これが強みであるという考え方を変えられないんですよね。それが怖いところだなと思います。
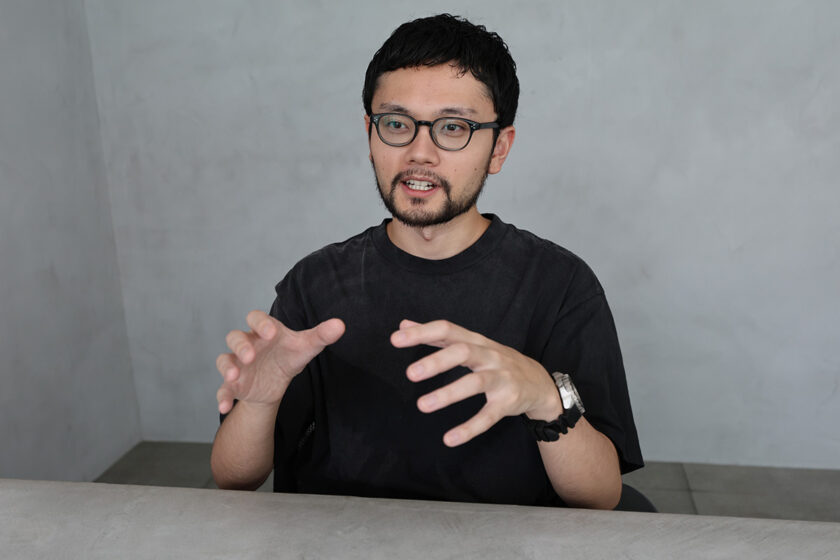
あとは、「会社が潰れるのって嫌だな」と強く嚙みしめましたね。そういう意味でも、少しでも強みと逆のこと、会社の多数派と逆のことをやる人がいないとな、と思います。アナグラムだと、ブログからインバウンドで集客ができていることは強みですが、盲信して書き続けることには意味がないですよね。たまにアウトバウンドの集客をやってみたり、ブログでは届かない層への発信としてセミナーやYouTubeをやってみたりするのがいいんじゃないかと。そんな考えもあって、アナグラムのYouTubeチャンネルの立ち上げにも関わりました。
ーーーたしかに強みの盲信が自分たちの首を絞めているかもとは、なかなか思えないですね…!中島さんは、今後どのようなユニットにしていきたいと考えているのでしょうか?
自律分散型の組織というのを、アナグラムでやりたいとずっと考えていました。ユニットを小さな会社のようにできたらいいなと思っていて。
ーーー組織全体が同じ強みだけをもっている状態ではなく、各ユニットがそれぞれの方法で、クライアント支援や集客ができる状態、ということでしょうか?
はい。個人事業と会社のよいところをそれぞれ採用して、自らの個性を活かしつつ、コミュニティの恩恵にもあずかれる体制が理想ですね。
たとえば、自社のマーケティングはユニット単位で戦略を立てるべきだと思っています。各ユニットにはそれぞれ得意なことや経験したことが異なるメンバーがそろっているので、各人の個性を理解して、育成して、それをブログやセミナーで発信して集客につなげるところまでを、ユニットとして戦略的に行うイメージですね。代表の小山ともその思いは一致して、具体的な取り組みにもなっています。(※)
※今期よりアナグラム全体で、プロデューサー制というユニットにマーケティング機能をもたせる取り組みを開始しました。
あとは、チームリーダーの力をもっと信じていきたいですね。現状もチームにおいてクルーたちの広告運用の師匠であることは間違いないですが、それだけではなく、組織全体の課題に対しても一人ひとりが解決のアイデアを持ち、チームを巻き込んで実行していける人材になってほしいです。
アナグラムは逆ピラミッドの体制をとっているので、案件の最終意思決定は現場のメンバーが担っています。そのため、会社がいくら方針を示したとしても、実行するかどうかは現場次第です。そういった意味でも、現場のメンバーをしっかり見ているチームリーダーが、課題に対してのアンテナを立て、それをただ「課題がある」と主張するだけでなく、巻き込んで解決していくものだという認識を持つのは非常に大事だと思っています。

僕自身は、新しいユニットでチームリーダーを積極的に巻き込みながら、課題解決を一緒に議論して実行までサポートしていきたいです。たとえ明日会社が無くなっても、自分自身で道を切り拓いていけるメンバーが増えていくと良いですね。
ーーー最後に、中島さんはアナグラムでどんな人と働きたいですか?
当事者意識が強い方と一緒に働きたいですね。自律分散型の組織でありたいという考えとつながっているのですが、こういう案件がやりたいとか、組織の課題が気になるとか…そういう思いに対して、達成するために自ら動こうとする人が合うんじゃないかなと思います。また、アナグラムに限らず、広告業界全体が変化が激しく、常に分からないことがたくさん起きている環境なので、自分でキャッチアップして動いていく姿勢は大切ですね。
僕自身、さまざまな環境を経たことで、改めて広告代理店っていいなと思っています。社外の人間として事業にかかわるからこそ、商品やサービスのマーケティングを純粋に、とことんやれる側面があるからです。
アナグラムではしっかり知識や技術を学べる体制を用意していますが、それは運用型広告を「設定できて、配信できる」だけでなく、未経験であってもビジネス全体をドライブしていけるような気骨のある人と働きたいということの裏返しでもあります。なので、広告に興味があって、とことんやりたい!というガッツのある人は、未経験であってもぜひアナグラムの門をたたいてほしいです。




