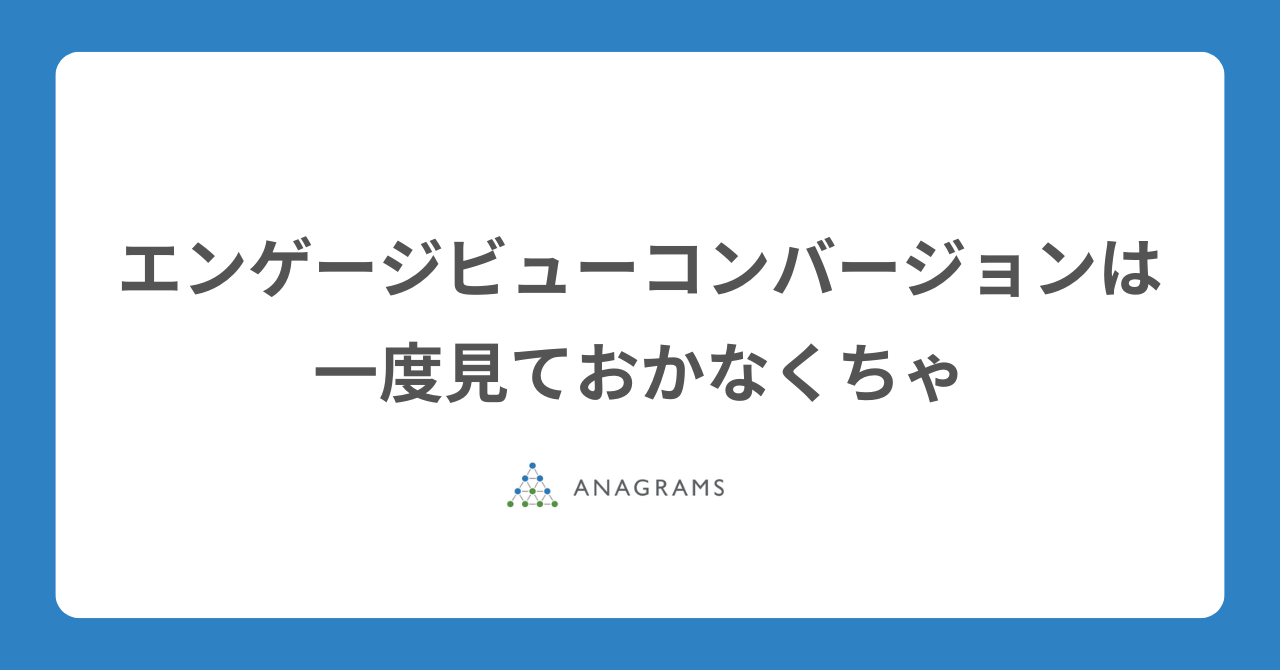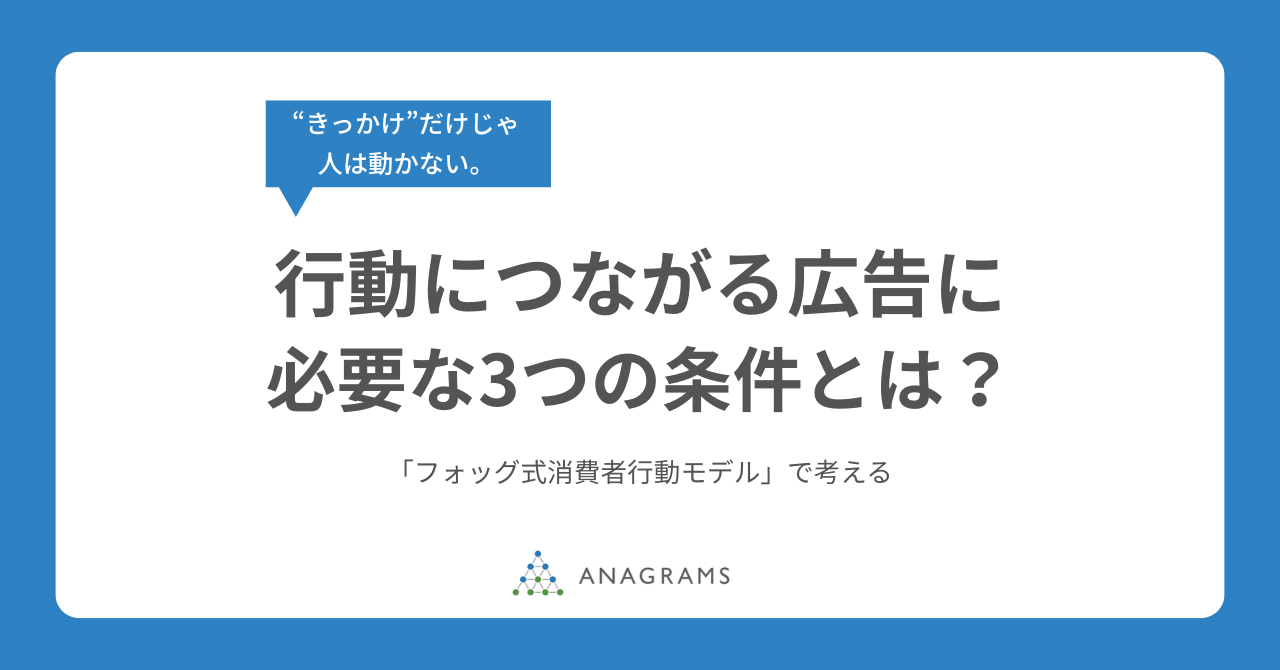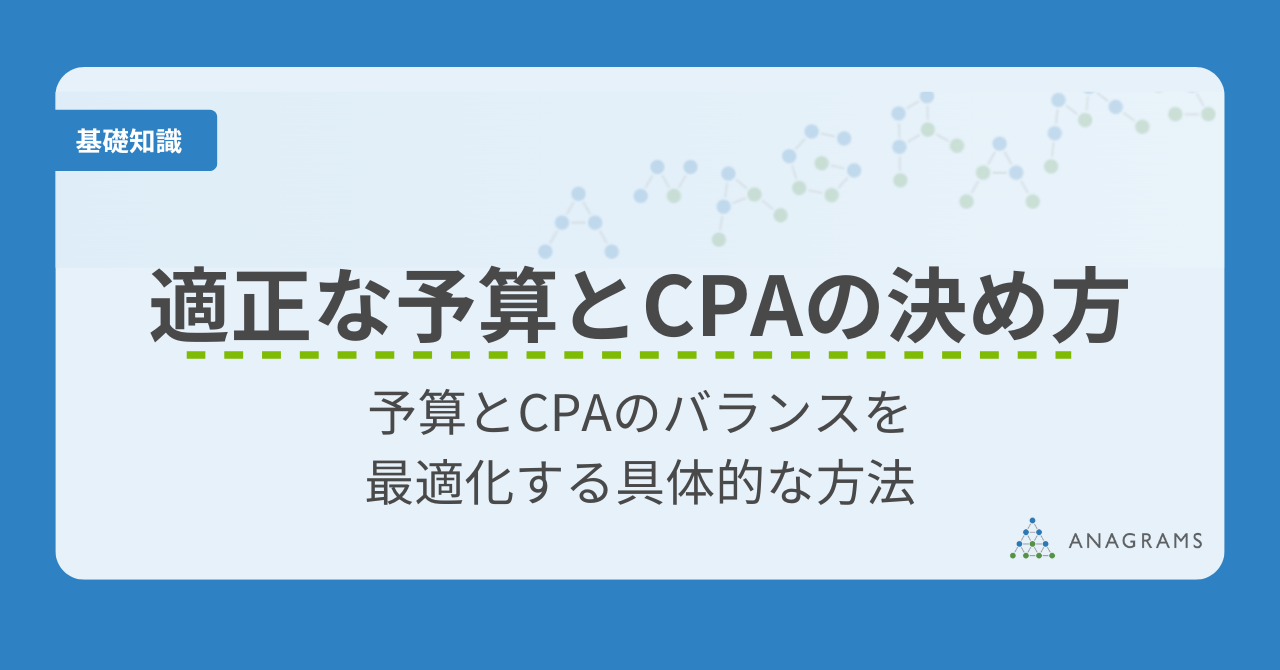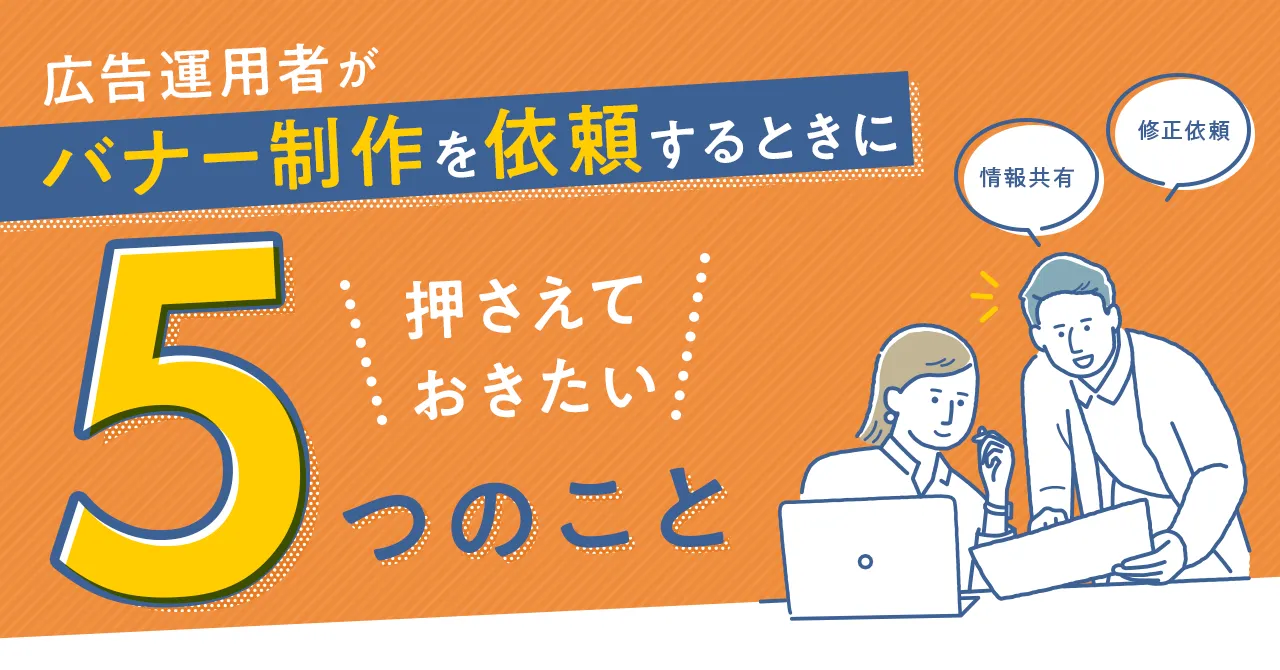物事をどう見るかで、世界の景色はガラッと変わります。仕事でもプライベートでも、「ちょっと視点を変えたら、解決の糸口が見えた」という経験はありませんか?
たとえば、小規模チームでリソースが限られている状況。これは「マンパワーが少なくできることに限りがある」と捉えることもできますが、一方で「意思決定が早く、柔軟に動ける強み」と見ることもできます。弱点だと思っていたポイントが、独自の強みや特徴に変わるのです。視点の切り替えで、新たな解釈や気付きを得る、そんな思考の”枠組みの切り替え”がリフレーミングです。
今回はリフレーミングをいろいろ拡大解釈しながら、ビジネスの現場でも日常生活でも役立つスキルとして紹介していきます。


目次
リフレーミングとは?
リフレーミングとはもともとはコミュニケーション心理学の用語で、物事の見方や枠組み(フレーム)を別の視点から捉え直すことで、新たな意味や肯定的な側面を見出す心理学的な思考法です。こうした堅苦しい説明もありますが、”違う視点で考えてみる”、”相手の気持ちになって考えてみる”と思えば、ビジネスや日常生活のいたるところで自然と使っていませんか?
たとえばメタ認知も、自分自身を一段階高次の視点から客観的に捉えること、つまり違う視点で自分自身をみることなのである意味リフレーミングとも言えます。同じ状況や事象でも、どの「枠組み」から眺めるかによって別の選択肢が見つかったり新たな気づきが得られます。
一方で、リフレーミングをせず、ただ主観だけで考えるとどうなるでしょうか。クライアントから指摘を「否定された」と決めつけたり、仮説が外れたことを「失敗した」と嘆いたり。ひとつの見方にとらわれてしまうため、選択肢も狭まりがちです。主観や直感などの単一のフレームのみで考えることに頼ると「現実の枠組み」を変えることができず、行動も思考も停滞してしまうのです。
だからこそ、意識的に枠組みを切り替えるリフレーミングが有効です。一見マイナスに見える出来事を別のフレームで捉えることで、問題解決の糸口や気持ちの余裕を得られます。心理学ではストレス対処法としても用いられますが、ビジネスにおいては意思決定や課題解決、チームマネジメントに広く応用できる実践的な思考法なのです。
リフレーミングの活用シーンと効用
「リフレーミングってどんな場面で使えばいいの?」と思う方も多いかもしれません。答えはシンプルで、いつでも使えます。ネガティブに見える事象も、視点や解釈を切り替えるだけで、別の意味を持ち始めるのです。ここでは4つの典型的なシーンを見ていきましょう。
コミュニケーションでも
人とのやりとりは、受け取り方ひとつで大きく変わります。たとえばメール。こちら目線で書けば「一方的に押しつけている」と感じられることもありますが、相手の立場で読み直せば「どうすれば読みやすいか?」「負担にならない伝え方か?」と工夫できます。リフレーミングすることで、相手を気遣った建設的なコミュニケーションが可能になり、結果的に関係性もスムーズになります。
意思決定でも
意思決定では、「短期」と「長期」など異なるフレームを切り替えることが効果的です。短期的には合理的に見える判断も、長期的には逆効果になることがあります。
たとえば、キャンペーンでの値引き。短期的には売上を押し上げられますが、繰り返せば「安くないと買わない顧客」を育ててしまい、結果的にブランド価値を損なうリスクがあります。
リフレーミングは、このように「今だけ効果的かどうか」ではなく、「未来にどう影響するか」という時間軸を変えた視点を与えてくれます。その結果、よりバランスの取れた判断が可能になるのです。
課題解決でも
仕事の課題解決にもリフレーミングは役立ちます。ビジネスのフレームワークが多数あるのも、有用性の証左かと思います。
たとえば広告のクリエイティブを考えるとき、自分目線だけで作ると「なんとなく良さそう」に終わりがちです。しかし「ターゲットの視点」にフレームを変えて見直せば、「このメッセージはターゲットにとって魅力的だろうか?」「ターゲットが理解しやすい語彙を使っているだろうか?」と新しい問いが立ち、改善点が見えてきます。
日常生活でも
日常でもリフレーミングは小さなストレスを和らげます。
たとえば、言動が粗雑で苦手な知り合い。正面から受け止めると嫌悪感しか残りませんが、「反面教師」というフレームに切り替えると「自分はああならないようにしよう」という学びに変わります。また、誰かの一言にイライラすることもありますが、「相手も余裕がなかったのだろう」とフレームを変えることで、気持ちが軽くなることもあります。
リフレーミングのコツ
リフレーミングは特別な才能が必要なスキルではなく、少し意識すれば誰でも取り入れられる思考法です。ただし闇雲にやろうとしてもうまくいかないことも多いので、いくつかのコツを押さえておくと実践しやすくなります。
別の問いをたてること
リフレーミングの第一歩は「問いを変えること」です。同じ出来事でも、問いを変えるだけで意味づけがガラッと変わります。
たとえば、失敗したときに「なぜうまくいかなかったのか?」と問うと原因探しに偏りますが、「この経験から学べることは何か?」と問えば次のアクションに直結します。アウトプットする前に一呼吸おき、別の問いを自分に投げかけるだけで、新しい解釈が生まれるのです。
型を持つこと
「違う見方をしよう」と思っても、ゼロから考えるのは難しいもの。そこで役立つのが「型」です。世の中の格言やビジネスのフレームワークは、そのままリフレーミングの型として活用できます。
たとえば「鳥の目・虫の目・魚の目」という比喩は、複数の視点を持つ型として活用できます。
- 鳥の目=全体を俯瞰するマクロ視点
- 虫の目=細部を観察するミクロ視点
- 魚の目=流れやトレンドを読む視点
さらに3C分析やファイブフォース分析などのフレームワークも、視点の切り替えを助ける「型」の一種です。こうした型をストックしておけば、状況に応じて即座に思考を展開できるようになります。
適切なフレームを選ぶこと
どんな場面にも万能なフレームがあるわけではありません。だからこそ、複数のフレームを当てはめてみて、その中から状況にしっくりくるものを選ぶことが大切です。
たとえば広告運用の分析。問題の原因が毎回同じ画面で見つかるとは限りません。管理画面で「あーでもない、こーでもない」と表示を切り替えながら、期間を変えたり、別のディメンションのレポートを出したりしながら原因を探していたりしませんでしょうか?こうした作業そのものが、フレームを切り替えていることにあたります。
課題解決は、一つの視点に固執するのではなく、複数のフレームを試しながら最適なものを選び取るプロセス。この柔軟さこそが、リフレーミングを実践的なスキルに変えていくのです。
マネジメントでの活用ケース
たとえばマネジメントでは、ちょっとした「見え方」や「フレーム」の違いがコミュニケーションのズレや成長機会の逸失につながることがあります。ここでは3つのシーンで、リフレーミングが有効に働く例を紹介します。
見えているものと枠組みの違いを意識する
現場のメンバーが見えているものと、マネジメント側が見えているものは往々にして異なります。
そのため、アウトプットに違和感があったとき、いきなり否定や指摘から入ると根本のズレが解消できなかったり、逆にマネジメント側の指摘が誤っていたりして信用を失ってしまう恐れがあります。
まずはお互いの視点や持っている情報を整理することから始めると、そうしたズレを解消することができます。メンバーは現場の情報を多くもっているので、そのアウトプットを出すに至った情報や背景をしっかり聞いてからアウトプットを判断していきましょう。またマネジメント側は複数の視点やフレームを持っている立場でもあるため、「どの視点でズレを感じているのか」を明示すると、齟齬の少ないフィードバックができることでしょう。
例:「この企画は、ターゲットユーザーの視点で見るとすごく面白いんだけど、継続率の観点で見ると少し弱いかもしれない」
→このようにフレームを明示すると、単なる「良い/悪い」ではなく具体的な対話が可能に
行動を構造化して考える
メンバーの行動になにか違和感を覚えたとき、それを単純に「行動ミス」として片付けるのは早計です。行動の裏には、認知や思考といったプロセスがあります。そのためバリューチェーンのように「認知 → 思考 → 行動」というフレームで分解してみると、ズレの発生箇所が見えやすくなります。
- 認知のズレ:必要な情報が共有されていなかった、前提が違っていた
- 思考のズレ:価値観の違いや、ロジックの食い違い
- 行動のズレ:他の手段を知らなかった、スキル不足
このようにリフレーミングで構造化して考えることで、メンバーの行動(アウトプット)だけを責めるのではなく「どこを補えば良いか」という建設的な対話が生まれます。
例:「この対応、判断がちょっとずれたのは、依頼の段階で前提情報の共有がちゃんとできてなかったからだね」
→問題を構造的に整理すると、対処療法的な対応を減らし、根本の問題解消に
“ちょうどいい”目標の枠組みを一緒に考えてあげる
目標設定は、あまりに現状と近い枠組みだと成長が鈍化し、逆に壮大すぎる目標を掲げるとメンバーが混乱したり萎縮したりします。キャリアや成長はオープンワールドのようなもので、可能性は無限にあります。
そのなかで、時間軸を整理してあげたり、能力・スキルマップといったフレームを使って「今このタイミングで、どこを目指すのがちょうど良いか」を一緒に考えることが重要です。
メンバーが現状の枠組みから一歩外に踏み出せるような良い枠組み≒“ストレッチゾーン”を見極めることが、マネジメントの腕の見せ所です。
例:「半年でこの数値目標はタイヘンに見えるかもしれないけど、月ベースで考えると頑張ればできそうじゃない?」
→適切な枠を提示することで、目標が現実的かつ前向きなものに
リフレーミングを鍛える方法
リフレーミングは、知識として知っているだけでは身につきません。日常の中で「別の見方」を増やす習慣を重ねていくことで、少しずつ思考の柔軟性が育っていきます。
フレームを持っていない状態は、ある意味「モノサシを持たずに測ろうとする」のに似ています。どんなに注意深く観察しても、比べる基準や視点がなければ「長いか短いか」「大きいか小さいか」を判断できません。思考も同じで、複数のフレーム(モノサシ)を持っているほど、状況を違う角度から捉え直すことができるのです。
では、どうすればフレームを増やせるのか?そのために有効なのが、日々の中でできるトレーニングです。ここでは4つの切り口で整理してみましょう。
①インプット(知識・情報)
新しい知識や物語に触れることは、未知のフレームを自分の中に取り込むことです。自分の頭の中だけで考えていると、どうしても限られたフレームに偏ってしまいます。だからこそ自分以外の人が整理した知識や概念と取り入れられるインプットが大切になります。
- たとえば
- 読書・勉強・記事を読む:理論や他人の視点に触れ、自分の解釈の幅を広げる
- ドキュメンタリー鑑賞:現実の多様なストーリーに触れ、固定観念をほぐす
- SNS観察:多様な価値観やトレンドを知り、違う切り口を持つ
②対話・他者からの気づき
自分と異なる人の思考や価値観に出会うことは、新しい視点をインストールする最も強力な方法のひとつです。とくに「自分が当たり前だと思っていた考え」を他者に揺さぶられることで、リフレーミングの回路が開きます。
- たとえば
- インタビュー・いろんな人と話す:異なる立場の人から新しい見方を得る
- 1on1・コーチング:他者に問いかけてもらうことで、自分の思考の枠に気づける
③経験・体験
新しい体験は、無意識に持っていた枠組みを揺さぶります。文字情報のインプットでは、ある意味言語化できるものが対象となります。しかし経験や体験では言語化しきれないものなどを含めて体験知として得ることができます。
- たとえば
- 旅に出る・出かける:環境を変えることで、物事の「当たり前」が揺らぐ
- 初めての経験をする:未知の体験が、新しい視点を強制的にインストールする
④内省・自己対話
外からの刺激を整理し、自分の中に定着させるプロセスです。自分で振り返ることは、別の時間軸で当時の自分の言動を客観視することであり、自然とリフレーミングができるのです。
- たとえば
- 内省:一歩引いて出来事を振り返り、別の意味を探す
- ジャーナリング:書き出すことで思考のパターンを可視化し、新しい解釈を生む
リフレーミングは一生使える普遍的なスキル
リフレーミングは、一時的なテクニックではなく、人生を通じて鍛えられる普遍的なスキルです。
筆者自身も、若い頃は些細なことでイライラしたり悩んだりすることが多かったのですが、歳を重ねるにつれて「そういう解釈もあるよね」「その立場なら見えていないこともあるよね」と受け止められる場面が増えてきました。同じ出来事でも年齢や立場によって多様な解釈ができるようになる、これこそがリフレーミングの本質です。
読書や勉強、人との対話、新しい体験、そして内省。これらの積み重ねが新たなフレーム(モノサシ)を増やし、物事を柔軟に捉え直す力を育てます。仕事でもプライベートでも他者と関わることは避けられず、いまは価値観の多様性がますます広がる時代です。だからこそ、自分だけのフレームに閉じず、他者のフレームをいかに取り入れられるかがとても重要です。
リフレーミングは、年齢やキャリアに関わらず磨き続けられる普遍的なスキルとして、多様性の時代を柔軟に生き抜くための強力な武器となるでしょう。