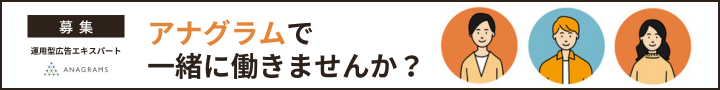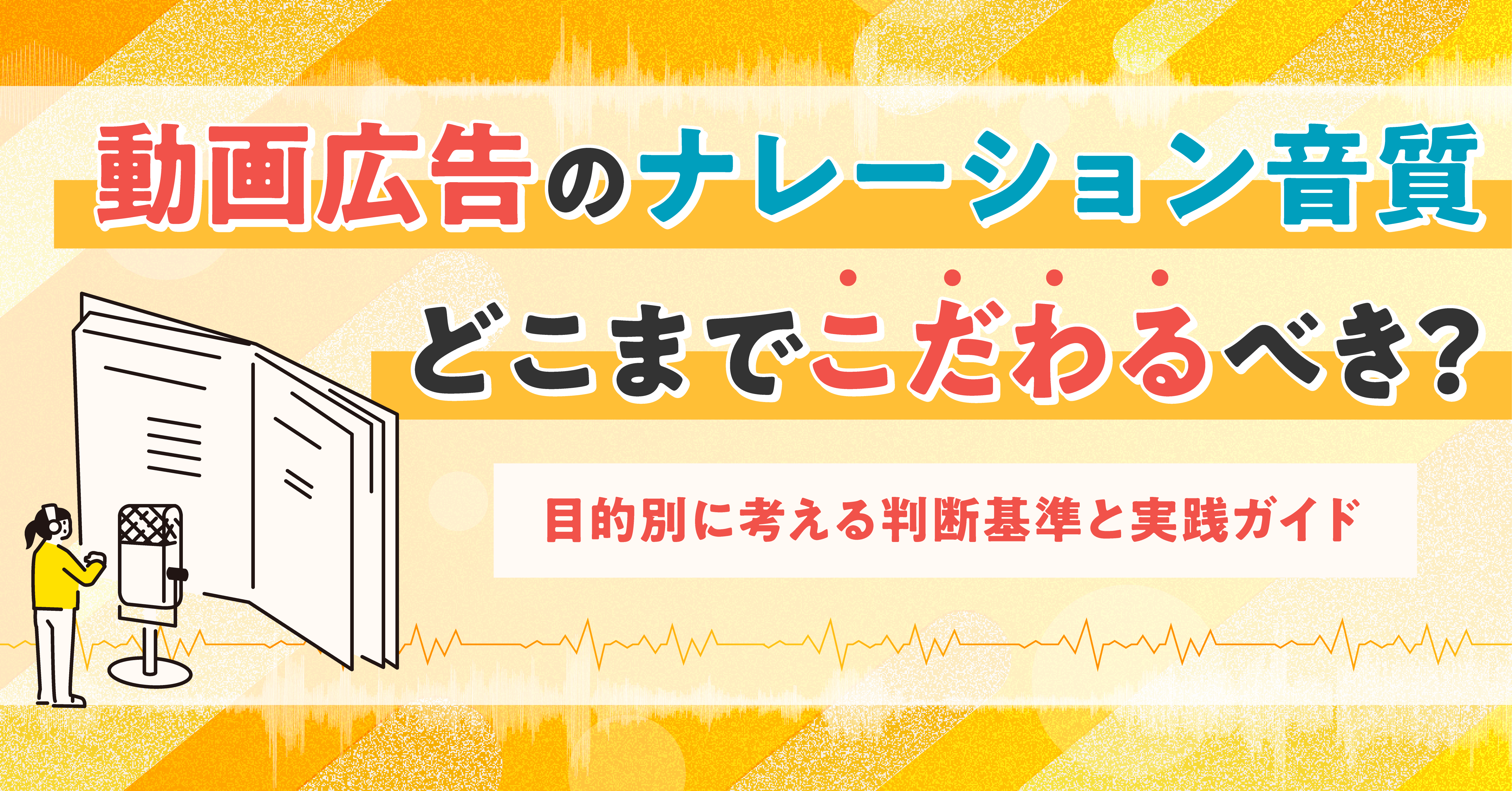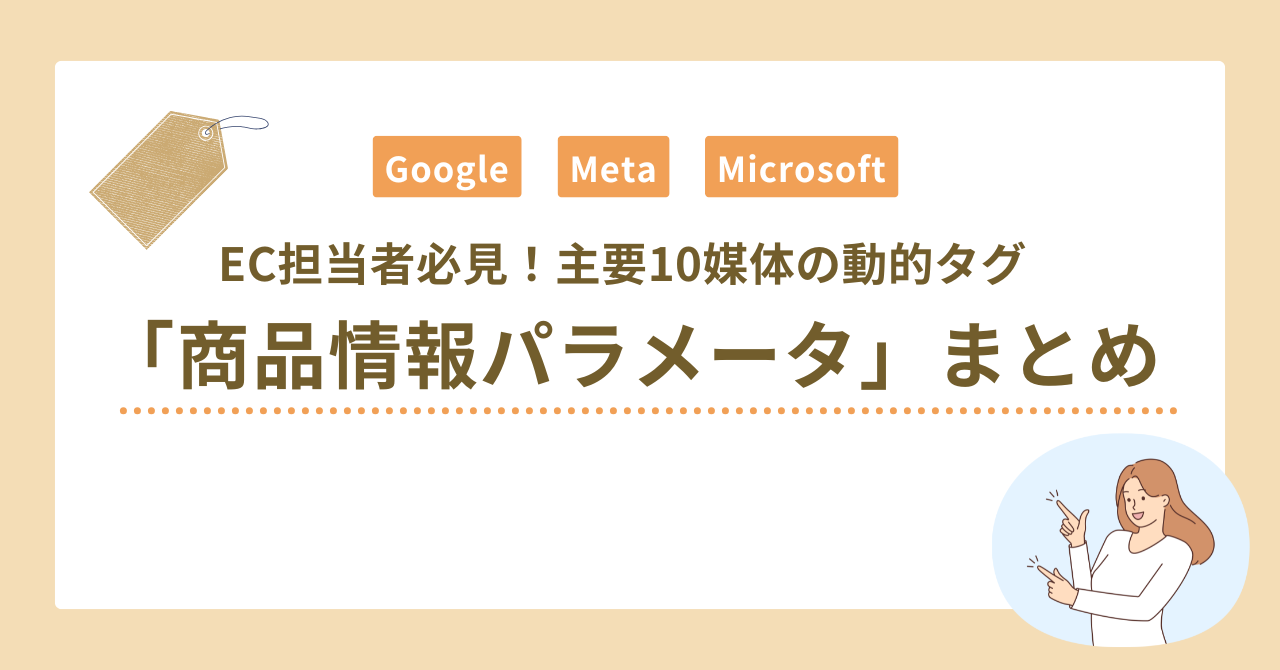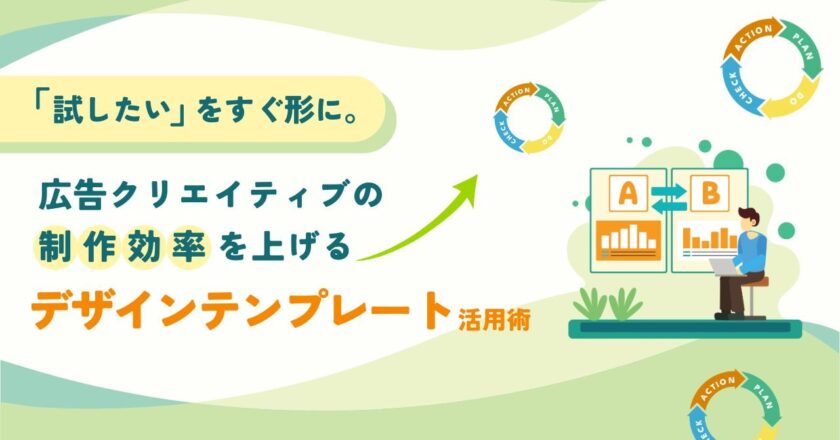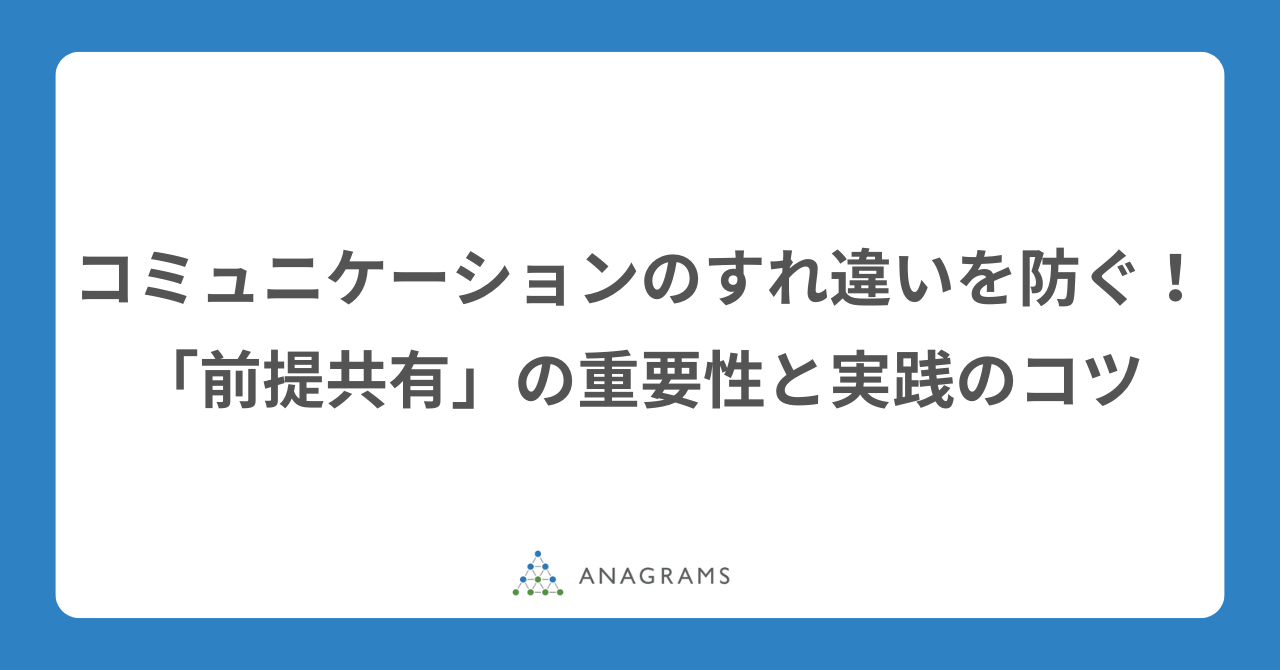
仕事でこんな経験はありませんか?
質問をしたのに、意図が伝わらず『もっと整理してから聞いて』と言われてしまう。
依頼通りに進めたつもりなのに、『違う』と指摘される。
実は、こうしたすれ違いの多くは 「前提の共有不足」 が原因です。
前提を共有できていないと、しっかりコミュニケーションをとったつもりでも、いつの間にかズレが生じてしまうことがあります。
本記事では、 コミュニケーションのズレを防ぎ、スムーズに仕事を進めるための「前提共有」のコツを紹介します。


目次
コミュニケーションのすれ違いは「前提共有の不足」から生まれる
人は誰でも、自分のこれまでの経験や立場から、それぞれの「前提」を持っています。
例えば、30代の中堅社員と、20代の新入社員とでは、仕事の進め方や社内の事情について持っている情報が異なります。しかし、中堅社員が暗黙的に「前提」として考えている情報に、多くの場合新入社員は気づくことができません。そもそも存在を知らないトピックに気づくことは難しいですよね。
これが30代中堅同士でも、中途社員同士などであれば、経験してきた業種や職種によって持っている「前提」が異なることは多々あります。この場合の「前提」は「常識」と言い換えてもいいでしょう。
自分ではコミュニケーションをしっかりとっているつもりでも、お互いの前提がズレると、いつの間にかすれ違ってしまうことがあります。
前提共有の不足によるすれ違い事例
たとえば、こんなシチュエーションに心当たりがないでしょうか?
例1:はりきって作った資料を却下されてしまったケース
シチュエーション:
「今度の定例会資料に入れるので、Meta広告の施策提案を作って」と上司に頼まれた。
結果:
はりきって詳細な10ページくらいの資料を作り提出したところ、読んだ上司からこんなものは使えないと言われる。一週間もかけたのに……
例2:GTMの設定確認で迷子になってしまったケース
シチュエーション:
「Google広告のCVタグが動作しないです。トリガーの設定はこれであっていますか?」という質問を後輩から受けた。
結果:
Googleタグマネージャーでトリガーの設定を見ても特に問題がなさそう。Googleタグマネージャーの管理画面とWebサイトをうろうろしたが、原因がわからないまま数時間が過ぎる……
どちらも本人はまじめに取り組んでいるのに、いまいち成果がでない結果となってしまいました。似たような経験は私も実務上であります。
では、いったい何が悪かったのでしょうか?
実は、どちらにも共通しているのは「前提共有」が足りていないことです。質問する人/される人、仕事を依頼する人/される人の間の頭の中にある前提が共有されずに、思い込みで作業を開始してしまうと、最終的に大きなズレが発生し、時間もロスしてしまうことが少なくありません。
前提共有を意識して取り組むと、同じケースでも結果が大きく変わります。
前提の共有による改善例
例1:はりきって作った資料を却下されてしまったケース
シチュエーション:
「今度の定例会資料に入れるので、Meta広告の施策提案を作って」と上司に頼まれた。
前提の確認:
「次回の定例会に久しぶりにいらっしゃる、WEBに詳しくない取締役に施策のOKをもらいたい。ほぼ信頼してお任せいただいているのでGOが出るようにしたい」という前提を共有してもらった。
結果:
専門用語は極力少なく、必要な用語には注釈をつけ、Meta広告が今回の提案に入っている理由と費用対効果を中心に、3ページ程度の簡潔な資料にまとめた。完成した資料で上司にOKをもらい、定例会でもスムーズに提案を了承していただくことができた。
例2:GTMの設定確認で迷子になってしまったケース
シチュエーション:
「Google広告のCVタグが動作しないです。トリガーの設定はこれであっていますか?」という質問を後輩から受けた。
前提の確認:
詳しく聞いてみると、「他の媒体のCVタグは正常に動作している」という前提を共有してもらうことができた。
結果:
同じトリガーを使用している他の媒体のタグが動作しているのだから、おそらくトリガーの問題ではないはず、と最初から確認する箇所を絞ることができた。GoogleのCVタグだけに間違いがあるかもしれないとあたりをつけて確認すると、GTM上のコードの記述に一部誤りがあった。修正すると正常に動作した。
このように、最初に前提を明確に共有すると、無用なコミュニケーションのすれ違いを防ぐことができます。会話や仕事のやり取りの中で、「今、この人はどういう前提で話しているだろうか」「私の前提は相手に伝わっているだろうか」と一度立ち止まり、すり合わせを行うことが、最終的には時間と労力のロスを減らすことにもなります。
前提共有を実践する5つのコツ
前提の共有が大切だとして、では、実際にしっかり前提を共有するためにはどうすれば良いでしょうか?
いくつかすぐにできるポイントがあるので見ていきましょう。
1.「目的」と「背景」を共有する
質問や相談の場合、自分が「ここが問題だ」と思っている点だけでなく、「目的」や「背景」を共有することで、問題設定があっているかを一緒に考えることができます。
質問を受ける側は共有をもとに「何を確認すればいいか」を考えることができ、問題設定のズレに気づきやすくなります。
資料作成や仕事の依頼でも、「目的」「背景」を共有することで自分が何をしたらよいか判断しやすくなります。
2.納期、優先度を確認する
質問や相談であれば、まず「これっていつまでに解決したいですか?」のような簡単な質問を挟むだけで、その後の手順が違ってきます。今日中に解決しないといけない場合と今月中でいい場合では、とれる手段が変わってくるからです。
資料作成などの作業でも、納期によっては省略しなくてはいけない箇所が出てくるので、取捨選択の相談をあらかじめしておいた方がスムーズです。
また、優先度を確認することも有効です。「不便だからできれば解決したい」と「今期の目標達成のために絶対必要」では、対応が変わってきます。
3.アウトプットのイメージを共有する
資料なら、どのくらいのボリュームが必要なのか? グラフを活用するか、テキストで説明するのか。あとでデータを活用できるようにExcelがいい。印刷して回覧するのでPDFがいい。など、アウトプットのイメージを最初に確認しておくと、最終成果物のずれが少なくなります。
4.テキストにこだわらず口頭も使い分ける
特に最近では、リモート勤務などでテキストコミュニケーションが主になっている職場も多いと思います。実際に目の前にいなくても、Webミーティングツールなどを使って口頭で話したほうが良い場合があります。
自分があまり詳しくない分野については、長時間かけてテキストで質問をまとめるより、5分間口頭でのMTGをお願いしたほうが有効なことが多いです。
口頭で相談したことや、回答してもらった内容については、ミーティングの後でslackやchatwork上にテキストでメモを残すようにすると、自分の認識のズレを相談相手に確認してもらいやすくなりますし、その場にいなかったメンバーにも相談内容を共有できるのでおすすめです。
5.最終結果ではなく中間でフィードバックを受ける
資料などは、最初に前提を確認し、少し着手してみて、「これでイメージ通りですか?」と依頼者に確認してみましょう。
作業前に確認できたと思っていた「前提」のズレが補正でき、致命的な失敗になりにくくなります。
前提共有がコミュニケーションの質を高める
仕事上のコミュニケーションのすれ違いは、「能力不足」ではなく「前提共有の不足」から生じることが多いものです。お互いの認識や情報、期待値などの前提を最初にきちんと共有することで、後々の大きなズレを未然に防ぐことができます。
ぜひ次の機会で、上記のポイントを意識するとともに、「この前提で相手に伝わるかな?」「相手の持つ前提は何だろう?」と一度立ち止まって考えてみてください。前提共有を中心としたコミュニケーション改善の意識と工夫で、職場の人間関係はより円滑になり、仕事の効率と質も向上するでしょう。
前提共有は、実はとてもシンプルなコミュニケーション技術です。しかし、その効果は絶大です。明日からでも実践できるこの方法で、あなたのビジネスコミュニケーションを変えてみませんか?