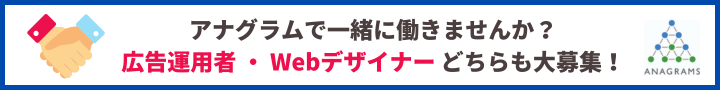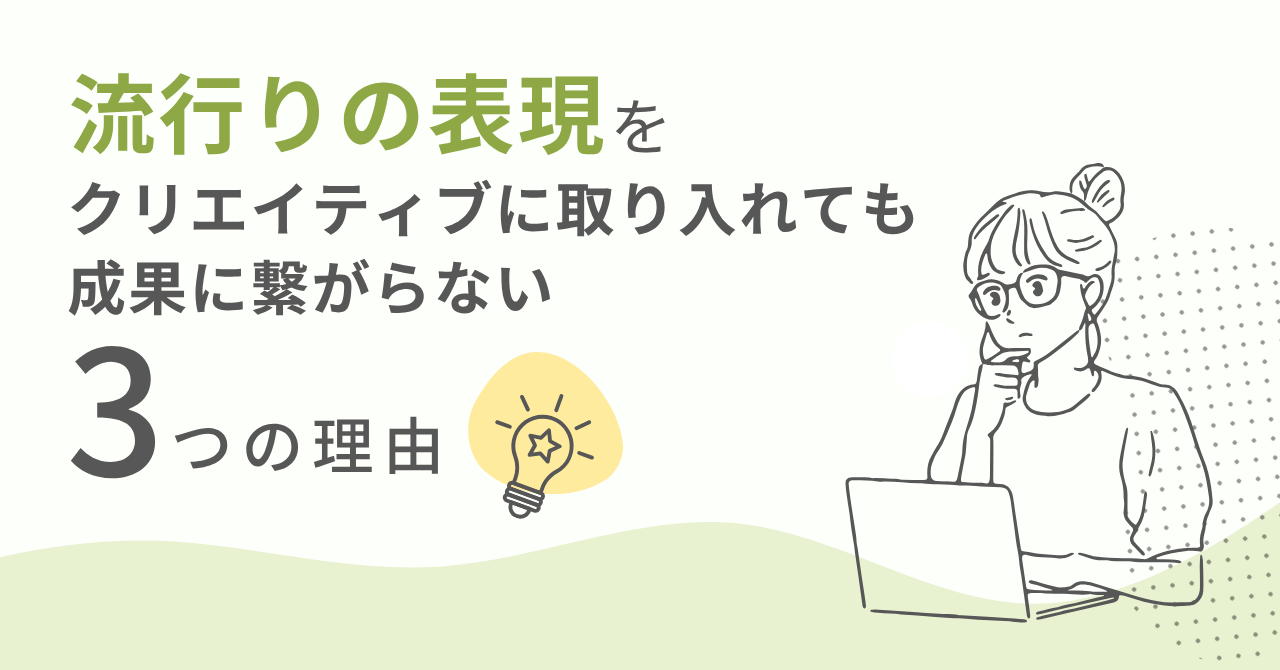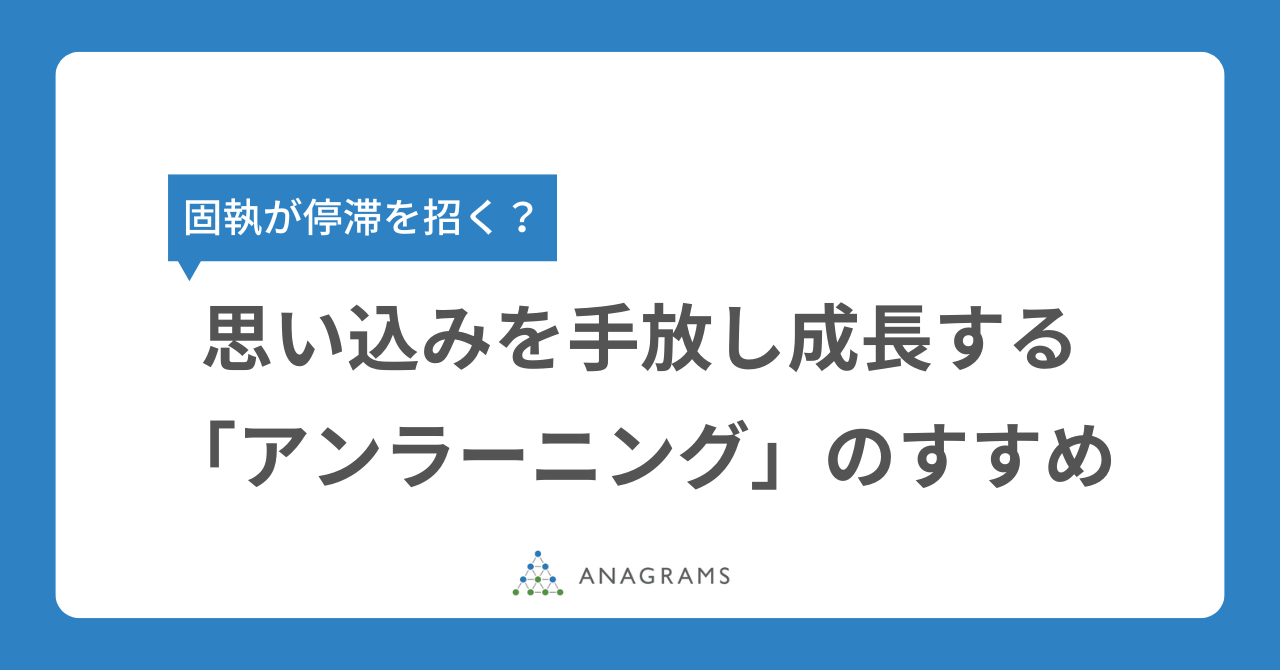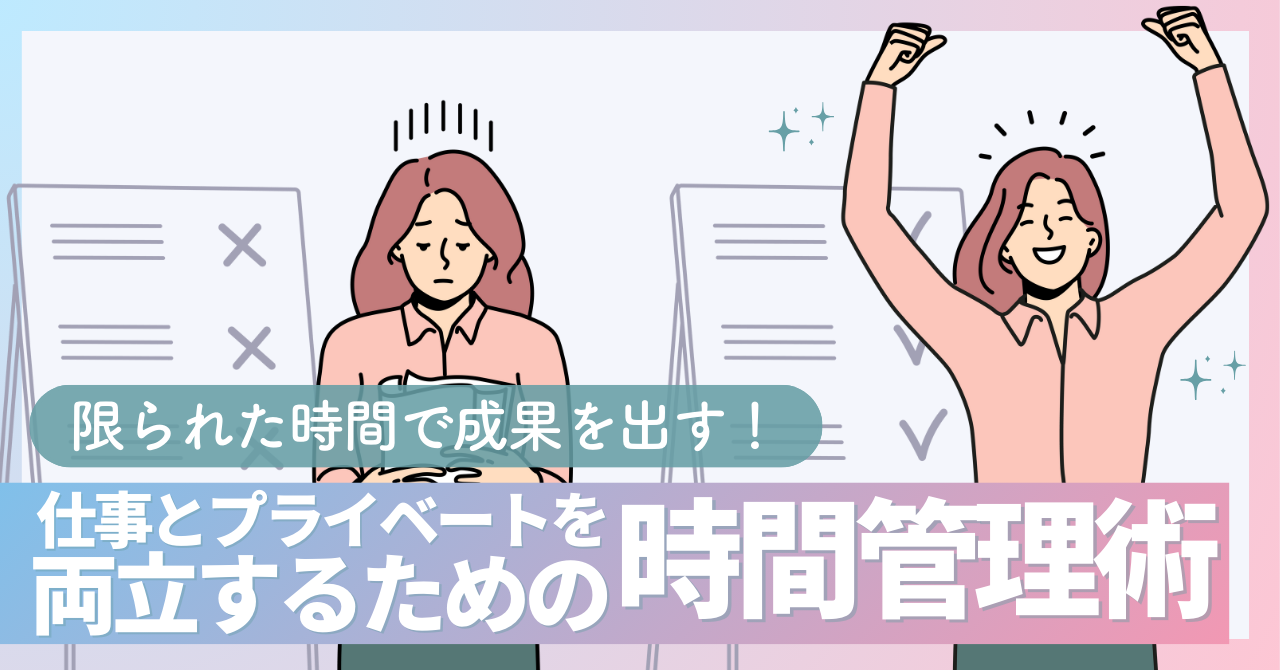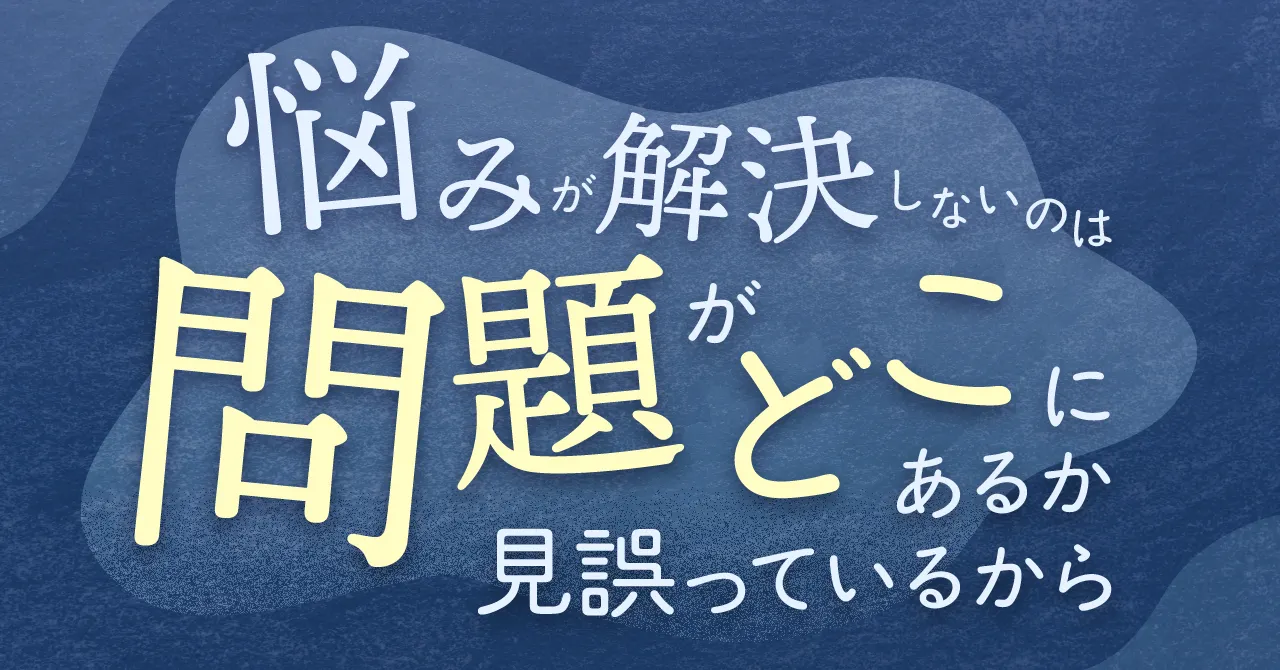
「一生懸命に取り組んでいるのに成果が出ない」
「努力しているのに悩みが解決しない」
そんな経験はありませんか?
その原因は、努力不足ではなく、“問題がどこにあるか”を正しく捉えられていないことにあるかもしれません。
私自身「会議で緊張してうまく話せない」という悩みを長い間抱えていました。声が震えたり、話したいことが飛ぶのは気持ちの問題だと思い込み、意識を変えようとしましたが、なかなか改善しませんでした。
思い切って専門家に相談したところ、「話しているとき、息が苦しそう」「息継ぎを意識してゆっくり話した方がいいかも」とアドバイスを受け、原因はメンタルではなく話し方にあることが判明したんです。実際に息継ぎを意識して話すようにしたところ、「今回はうまく伝えられたかも」と感じる瞬間が増えていきました。
長年の悩みは、第三者の視点により問題のありかを正しく捉えることができ、大きく改善しました。
「なぜうまくいかないのか?」を考えるとき、私たちはつい“見える場所”ばかりを探してしまいます。
しかし、本当の原因は“自分では見えにくい場所”にあることが少なくありません。ここからは、「なぜ自分では問題のありかを見つけにくいのか」そして「どうすれば正しく捉えられるのか」について、考えていきます。


目次
問題がどこにあるかは自分だと分かりにくい
悩みの原因を自分の力だけで正しく見つけるのは、実はとても難しいことです。つい自分の思考や感情の枠の中だけでものごとを見てしまいがちですよね。
たとえば「緊張して話せないのはメンタルの問題」と思い込んでいた私のように、目に見える“症状”ばかりに注目して、その下にある“前提”を見落としてしまうことがあります。
広告運用の現場でも同じようなことがよく起こります。たとえば、コンバージョン率が低いとき、本当の原因はフォームの項目の多さにある場合、ページの見た目ばかりを修正しても、成果にはなかなか繋がりません。
このように、問題の本質を見誤ると、どんなに施策を実行しても成果は得られないでしょう。“見えている部分”にばかり手を入れても、“本当の問題”は解決しませんよね。
しかも厄介なのは、本人にはその誤りが自覚しづらいという点です。長く関わるほど「このやり方が正しい」と信じてしまい、前提を疑う視点を失っていきます。
だからこそ、ときには自分の外に視点を置く必要があります。自分では気づけない前提を指摘してくれる存在、それが「第三者の視点」です。
なぜ第三者の視点だと本当の問題が見つかりやすいのか
自分と他者では、同じものを見てもいても、感じ方や注目するところが異なります。だからこそ、自分では気づけない違和感に気づけます。
では、なぜその差が生まれるのでしょうか。それは、「知識や経験」「感情」「前提」の3つの違いにあります。
経験や知識が異なるから
人それぞれ、持っている経験や知識は違います。そのため人は、自分の中にしか「普通」を持てません。
たとえば、ある業界のアカウントを長く担当していると、その相場や傾向が“常識”になります。しかし他の人から見れば、「このクリック単価は高すぎない?」「LPの構成が業界平均と違う」といった思いもよらない指摘が出てくることがあります。
このように、他者の自分とは異なる知識や経験を取り入れることで、思わぬ角度から自分の中では見えなかった問題が見えることがあります。
感情に引きずられないから
当事者であるほど、どうしても焦りや不安な気持ちが判断に影響してしまいます。「この施策は自分が立てたものだから」と思うと、結果が悪くても冷静に見直しづらいものですよね。
しかし、第三者はそうした感情に左右されず、客観的に状況を見ることができるので、より正確に問題を捉えられます。
たとえば会議で、発表者は緊張で自分の話し方のクセに気づきにくい一方、聞き手には「スライドをめくるのが速い」「この部分はもう少し補足した方が伝わる」などの改善点をすぐに見抜けます。
このように、冷静な視点を取り入れることで、見落としていた問題や違和感に気づきやすくなります。
1つの原因に固執しないから
自分一人で考えていると、「原因はこれだ」と思い込みに縛られてしまいがちです。一方、第三者はその前提を共有していないため、「なぜ?」「本当にそう?」と素朴な疑問を投げかけられます。
この“問い直し”が、思考の偏りをほぐし、新たな発見に気づかせてくれるきっかけになります。
たとえば、LP(ランディングページ)で業界用語を当たり前に使ってしまい、後から「ユーザーはその用語を知らないのでは?」と指摘を受けることはよくありますよね。
このように、情報を持っている側だからこそ気づけない落とし穴があります。特に担当期間が長くなるほど、こうした前提を見落としがちです。
だからこそ、定期的に自分とは違う視点を取り入れて、当たり前を疑ってみることが大切になります。
第三者の視点をどう取り入れるか
第三者の視点を取り入れる方法は、大きく分けて二つあります。
一つは他者の意見を取り入れる方法、もう一つは自分を客観的に観察する方法です。いずれも目的は同じで、「自分では気づけない前提や思い込みを可視化すること」です。
人に見てもらう
第三者の視点を取り入れる一番シンプルな方法は、誰かに見てもらうことです。上司・同僚・専門家など、他の人の目を通すことで、自分だけでは気づけなかった原因やヒントが見えてきます。
私自身「ひとりで答えを出したい」と思うことが多いですが、行き詰まったときは上司や同僚に相談します。相談を通じて自分にはなかった視点を得られ、「話してみてよかった」と感じる場面は少なくありません。
広告運用の現場でも、人に見てもらうことは有効です。アナグラムでは「グロースハック」という取り組みがあり、毎週約2時間、担当外のアカウントを分析し、改善策を共有します。異なる経験を持つメンバーの意見が交わることで、担当者には見えなかった問題や仮説が浮かび上がります。
ひとりで解決できないと感じたり、もっと良い方法があるのではと悩んでいるときは、第三者の視点を取り入れて仮説を広げ、解決の糸口を見つけてみましょう。
自分を客観視する
もう一つの方法は、自分自身を第三者のように観察できる仕組みをつくることです。
自分の思考や行動を外側から見ることで、新しい選択肢や改善のヒントを見つけやすくなります。
たとえば、急いで作った資料を翌朝に見直すと、「ここ直した方がいいかも」と気づくことはありませんか?これは、作成時の主観から離れ、冷静に第三者の視点で資料を見返せているからです。
常に他者に頼れるとは限らないからこそ、日常の中で「自分の外側」から見つめ、検証する習慣を持つことが大切です。
自分の考えや行動を見える化する
自分を客観的に見るためには、頭の中にある考えや日々の行動を“見える形”にすることが大切です。書き出したり、記録を残したりすることで、感情に流されず、冷静に自分を振り返ることができます。
たとえば、将来や仕事への漠然とした不安があるときは、ノートやメモアプリに「何が不安なのか」をそのまま書き出してみましょう。書き出しながら言語化することで、「事実」と「感情」を分けて考えやすくなるため、問題の所在がはっきりしてきます。
また、会議での話し方に課題を感じる場合は、録音や録画で振り返るのもおすすめです。話すスピードや間の取り方、「えっと」「その〜」といった口癖などを客観的に確認することで、無意識の癖に気づき、改善のヒントを得られます。
AIを活用して第三者の視点を得る
AIを活用することで、自分の考えや感情に対して、中立の立場からフィードバックをもらうことができます。
人に相談しづらい悩みを整理したいときや、自分の意見が偏っていないか確かめたいときに活用すると、新たな視点が得られるでしょう。
自分の考えを見える化したり、AIを活用したりすることで、気づけなかった前提や思い込みが見えてきます。その気づきが、問題のありかを見つける手がかりになります。
まとめ
努力しても成果が出ないとき、私たちはつい「もっと頑張る」ことに意識を向けがちです。
しかし、問題の本質が別の場所にある場合、努力の量を増やしても結果は変わりません。問題解決において成果を左右するのは、行動量ではなく、「正しい前提に立って意思決定できているかどうか」ではないでしょうか。
業務を進める中で、成果が伸び悩んだときや「努力しているのに成果が出ない」と感じたときこそ、まず「どんな前提でこの判断をしているか」を見直してみることをおすすめしたいと思います。