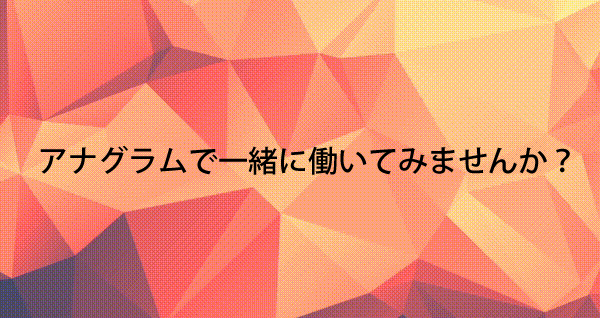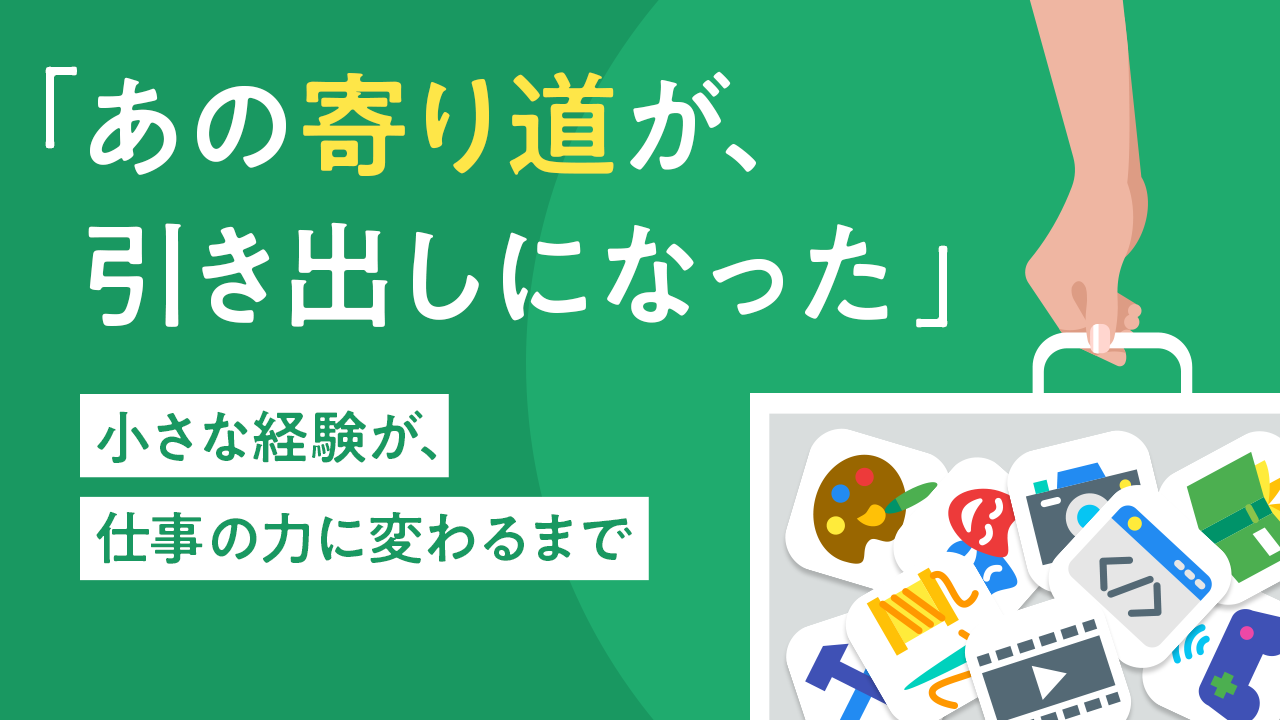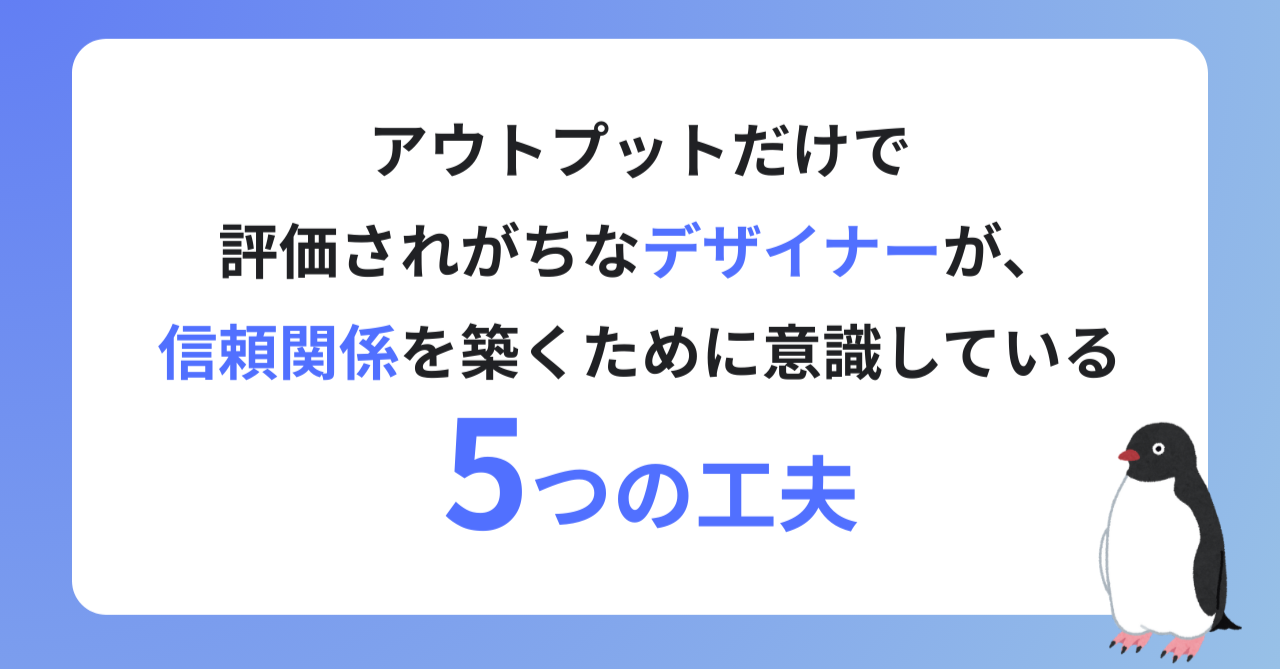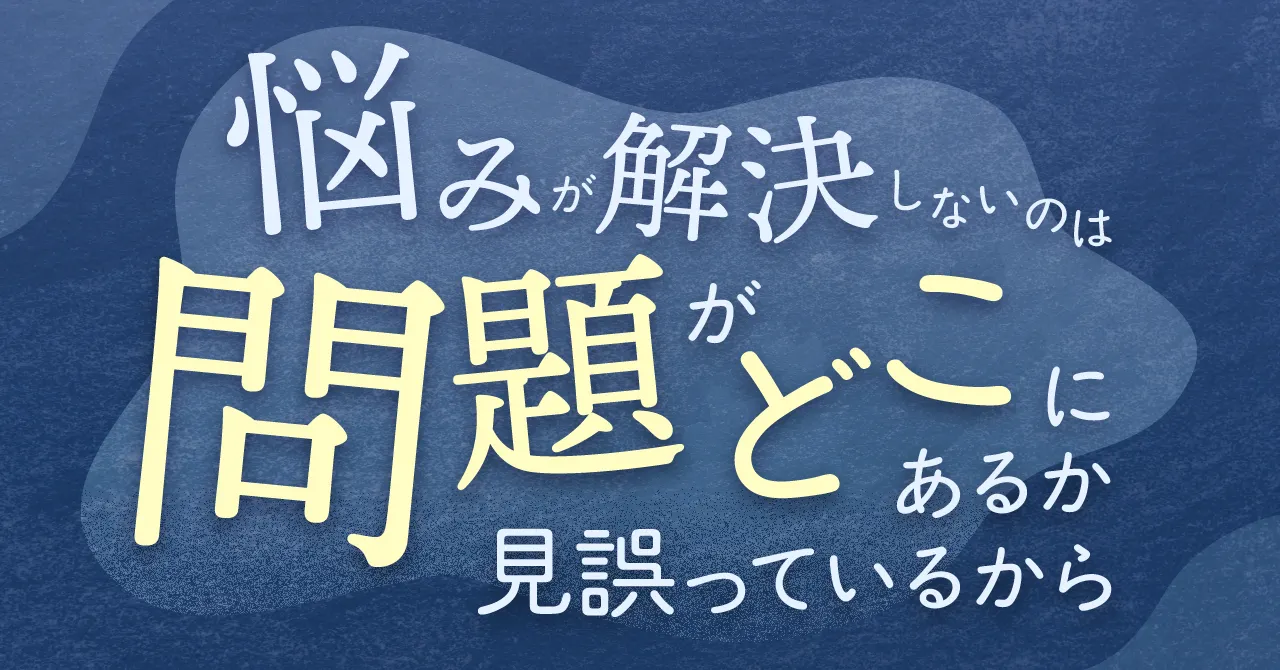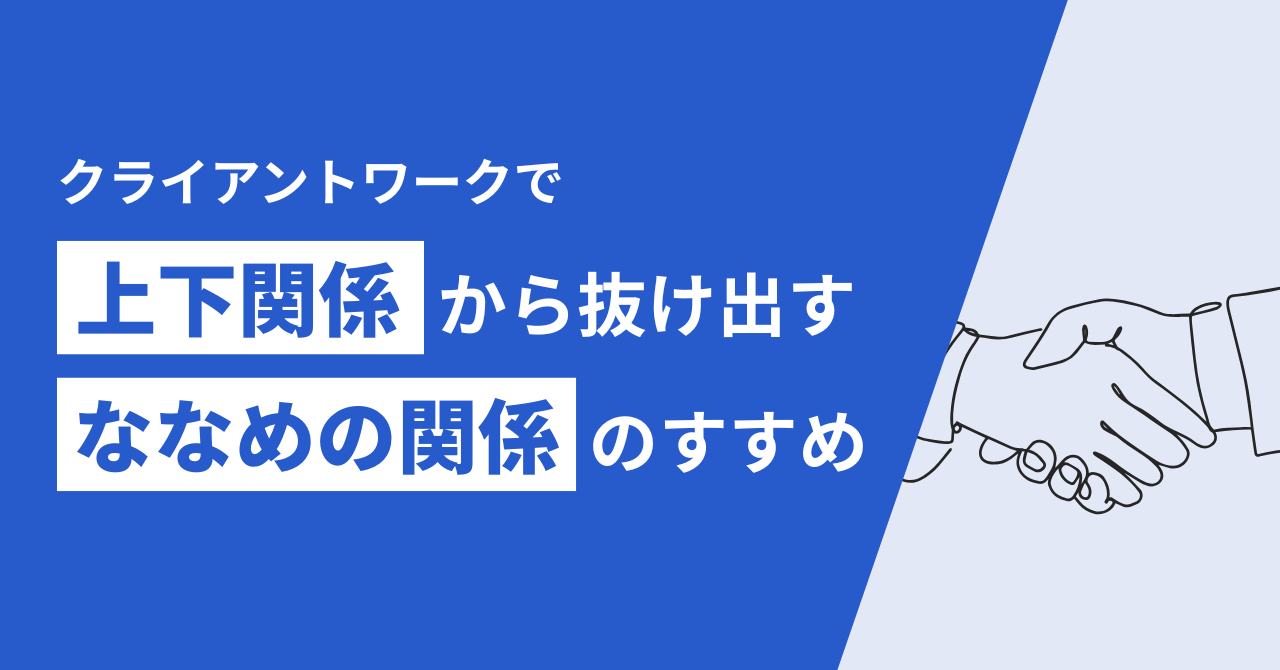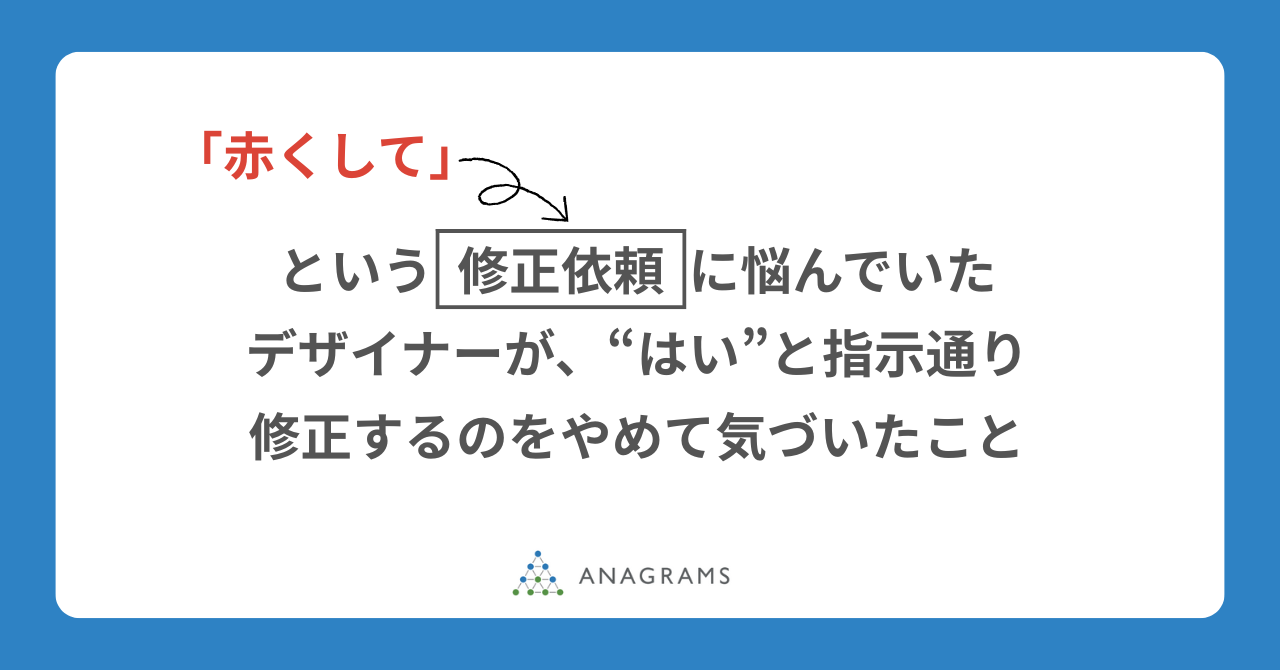
デザインの仕事をしていると、クライアントや社内の制作依頼者から「もう少し赤くしてほしい」「文字を大きくして」など修正依頼を受けるのは日常茶飯事です。
私自身、デザイナーとして駆け出しの頃は、「自分のデザインがまだ未熟だからだ」と多少の違和感を抱えながらも言われたとおりに直すことが「仕事の正解」だと思っていました。
しかし、ある案件で大きな壁にぶつかりました。何度も修正を重ねた結果、確かに依頼者の指示はすべて反映されていましたが、最終的に出来上がったものは「誰のためのデザインなのか」が分からない曖昧なものになってしまったのです。
そのとき初めて、「言われたとおりに直す」ことが必ずしも正解ではないと気づきました。修正依頼はただの作業指示ではなく、その裏に依頼者の意図や不安、あるいはユーザーへの思いが隠れている。そこに目を向けなければ、本当に意味のあるデザインにはならないのです。
本記事では、そんな失敗や気づきを踏まえながら、修正依頼を”消化すべきタスク”ではなく“考えるきっかけ”に変える方法を紹介します。


目次
修正依頼の「裏側」にある意図とは?
「赤くしてほしい」「文字を大きくしてほしい」などの修正依頼は、単なる作業指示のように見えます。しかし、その奥には依頼者の目的や感情が隠れているケースが多いものです。
「赤くして」
私が実際に担当したある案件では、「このテキストを赤くしてください」と依頼されたことがあります。当時の私はただ指示通りにテキストの色を赤く変更して再提出したのですが、その後「ちょっとイメージと違う」と差し戻しを受けました。なぜだろうとあらためて聞いてみると、本当の意図は「コピーをもう少し目立たせたい」でした。つまり、”赤に変更すること”が正解だったのではなく、「視認性を上げる」「重要度を強調する」ことが目的だったのです。
「もう少し大きくして」
別のケースではバナー制作で「サブコピーの文字を大きくして」という依頼を受けたことがあります。最初は、メインコピーとサブコピーが同じくらいのサイズになってしまうと視覚的な情報の優位性が崩れ、広告の意図が伝わりづらいのでは、と違和感を覚えました。
しかし話を聞いてみると、クライアントには過去の経験が背景にありました。以前、サブコピーに含まれる特定の単語を強調してみたところ成果が良かったため、その再現を意図して「サブコピーをもっと大きくして」という指示になっていたのです。つまり、単なる「サイズ調整」の話ではなく、「過去の成功体験を活かしたい」という目的が隠れていたわけです。
振り返ってみると、多くの修正依頼には共通点があります。それは「依頼者が言葉にできなかった課題や不安が、表面的な指示として現れる」ということです。依頼者自身もデザインの専門家ではないため、「なんとなくもっと目立たせたい」「ここが気になる」といった感覚を、色やサイズといった分かりやすい指示に置き換えて伝えているのです。
思考停止で修正する前に考えたい4つの視点
では、依頼を「作業」で終わらせないためにはどう考えればよいのでしょうか。ここでは4つの視点をご紹介します。
①なぜその指示が出たのか、目的を仮説立てる
修正依頼を受け取ったとき、まず大事なのは「言われたことをそのまま直す」のではなく、「なぜその指示が出たのか」を考えることです。
たとえばLP制作で「ボタンを緑にしてください」と言われたとします。指示通り色を変更して修正完了とするのは簡単ですが、「なぜ緑なのか?」と問いを立ててみましょう。もしかすると「他の要素と色変えてボタンであることをわかりやすくしたい」「ユーザーの目を引きたい」という狙いがあるのかもしれません。
私自身、かつては指示をそのまま反映するばかりで何度も何度も修正を繰り返したことがあります。そのときは正直「言われた通りにやっているのにどうしてこうなるんだろう」と苛立ちを感じることもありました。けれど今思えば、依頼者は最初から正解を持っていたわけではなく、デザイナーとして依頼者の意図を汲み取って対応するべきだったのだとわかります。
修正依頼を受けたらまず、その背景にある目的を仮説として立てる。仮説を立てれば、デザインの方向性を見失わずにすみますし、依頼者に確認する際も「こういう意図でよろしいですか?」と建設的な会話に発展させることができます。
依頼を“そのままの言葉”で受け止めるのではなく、“言葉の裏にある背景”を推測してみる。これだけで、修正依頼は「単なる作業」から「コミュニケーションを通じて成果を磨く場」に変わります。
②他の方法でもっとよい解決策はないかを探る
修正依頼を受けたとき、仮説を立てて意図を想像できたら、次にすべきことは「その指示をそのまま実行する以外に、もっと良い方法はないか?」と考えることです。
たとえば「文字を大きくして」と言われたとき。確かにテキストのサイズを大きくすれば、そのテキストの視認性は上がります。しかし、そのままだと全体のバランスが崩れてしまったり、余白がなく窮屈な印象になってしまうことも。
あるテキストの視認性を上げたいのであれば、テキストのサイズを変える以外にも
- 背景色を変える
- 下線を引く
- 他のテキストを相対的に小さくする
など他の方法もたくさんあります。
実際に私が経験したある案件でも、そのまま文字サイズを変えるのではなく、先頭にアイコンを追加することでテキストの視認性を上げ、同時に内容も汲み取りやすくなり依頼者からも「こちらの方がいいね」と納得してもらえたことがあります。
このように「依頼=解決方法」とは限りません。むしろ依頼者の指示は“課題のヒント”にすぎず、その課題をどう解決するかはデザイナー次第です。依頼者の意図に合わせてより適した解決策を提示できるかどうかが、デザイナーとしての成長速度に大きく関わってくるのではないでしょうか。
③クライアント視点だけでなく、ユーザー視点も忘れない
修正対応で最も陥りやすいのは、「依頼者の要望に100%寄り切ってしまう」ことです。もちろんクライアントや上司の意向を尊重するのは大切ですが、本来のゴールは“ユーザーにとって使いやすく、伝わりやすいデザイン”をつくることです。
たとえば、クライアントから「もっと目立たせたい」と言われて文字を大きくした結果、画面全体が窮屈になって他の要素が読みづらくなることがあります。あるいは「赤くして」という依頼をそのまま反映したら、ブランド全体のトーンから浮いてしまい、かえってユーザーの違和感を招くこともあるでしょう。
ここで必要なのは、「依頼者の視点」と「ユーザーの体験」を両方天秤にかける意識です。つまり、修正が依頼者の不安を解消する一方で、ユーザー体験を損なっていないかを常に確認する。デザインは部分最適ではなく全体最適が重要だからです。
実務的には、修正のたびに次のような問いを立てると効果的です。
- この変更でユーザーの行動はスムーズになるか?
- 一部を直したことで、全体の読みやすさや動線は崩れていないか?
- 依頼者が見たい「強調ポイント」と、ユーザーが知りたい「本質情報」は一致しているか?
この視点を持つと、ただ依頼者に従うだけのデザイナーから、「ユーザーにとって最適な形を提案できるパートナー」へとステップアップできます。結果的に、クライアントからの信頼も一層厚くなるはずです。
④修正後のデザインに「説明」を添える
修正に対応した後は、ただデータを渡すのではなく「なぜそう直したのか」を説明することも大切です。
例えば、
- 「ボタンを赤くすると全体のトーンが崩れるため、代わりに文字サイズを調整しつつアイコンを追加しました」
- 「目立たせたいという意図を汲み取り、単に文字を大きくするのではなく、余白を多めにとり視認性を高めました」
といった具合に、修正の裏にある考え方を伝えると、依頼者は「なるほど、そういう理由でこうなったのか」と納得できます。もし提案が受け入れられなかった場合でも、こちらの考えを伝えることで「実は目立たせたいわけではなく、ボタンらしくクリックできることを伝えたかった」など依頼者が言葉にできていなかった真の意図を引き出すことができるでしょう。
説明を添えることで、作業ベースの関係から「提案ベースの関係」にシフトしやすくなるのです。
「考える習慣」がもたらすもの
修正依頼をただ“言われた通りに直す作業”として片づけるのではなく、そこに「なぜ?」を問い、目的を考え、時には代替案を提案する。この習慣を身につけることで、次のような変化が訪れます。
- 依頼者からのデザイナーとしての信頼が深まる
- 単なる修正対応ではなく「意図を理解した上で提案してくれる人」と認識されることで、信頼度は格段に上がります。結果として、社内外で「安心して任せられるデザイナー」としてポジションが強化されます。
- 仕事の質が「作業」から「提案型」にシフトする
- 最初は「赤くして」「大きくして」といった単純な依頼が中心でも、考えて返す習慣を積み重ねることで、依頼内容が「どうすればもっと伝わるだろう?」という相談に変わっていきます。デザイナーの役割は“実行者”から“クリエイティブのパートナー”へ進化します。
- 自分自身のアウトプットへの満足感が増す
- 指示通りに修正しただけでは「これは本当に正しいのか」というモヤモヤが残りがちです。しかし、目的を踏まえて自ら考え抜いたアウトプットは、自分自身が胸を張って出せる成果物になります。
このプロセスを繰り返すことで、修正依頼はもはや“デザイナーを消耗させる雑務”ではなく、自分の成長とキャリア拡張につながる"成長の機会"へと変わっていきます。
すぐに「はい」と修正する前に考えてみよう
もしあなたが修正依頼に対してただ「はい」と返事をして、そのまますぐに手を動かしていたとしたら…実はそこで、大切なチャンスを逃しているかもしれません。もちろんスピード感も大事ですが、本当に必要なのは作業に入る前の時間です。
「なぜこの指示が出たのか?」
「本当に伝えたいことは何だろう?」
「他にもっと良い方法はないか?」
この問いを立てるわずかな時間が、デザインの質を変え、依頼者との関係を深め、そしてあなた自身の成長を加速させます。
修正依頼は、ただの“作業”ではありません。デザイナーに与えられた、思考と提案のチャンスです。次に「赤くして」「大きくして」という依頼が届いたら、まずは一度深呼吸してみてください。
“はい”と修正する前に、ほんの少し考える。その小さな習慣こそが、あなたを「作業者」から「信頼されるパートナー」へと変える第一歩になるでしょう。